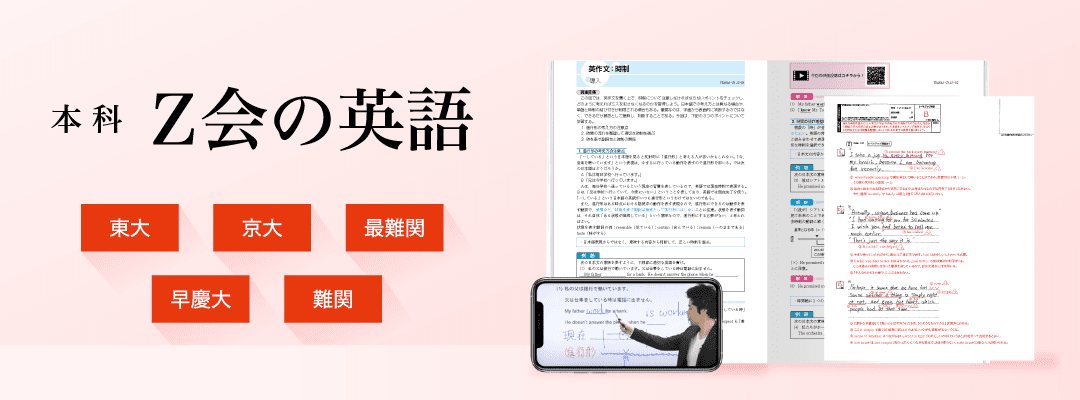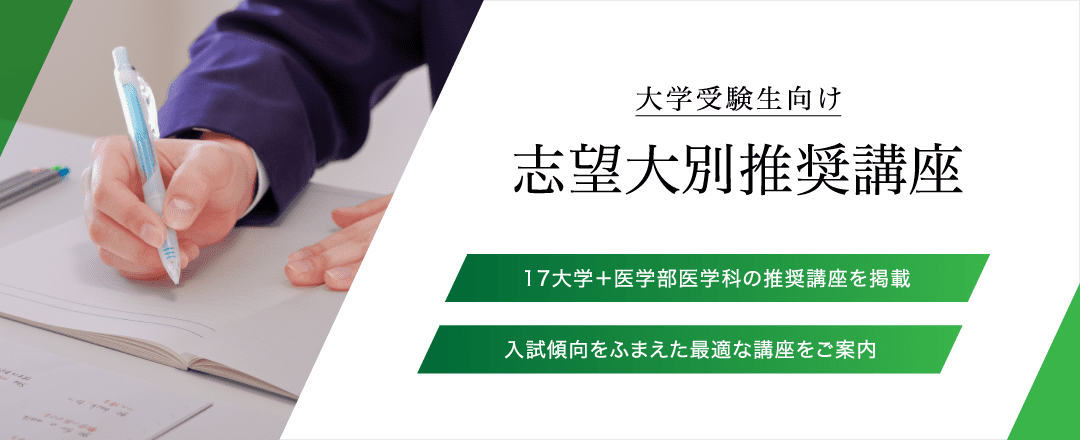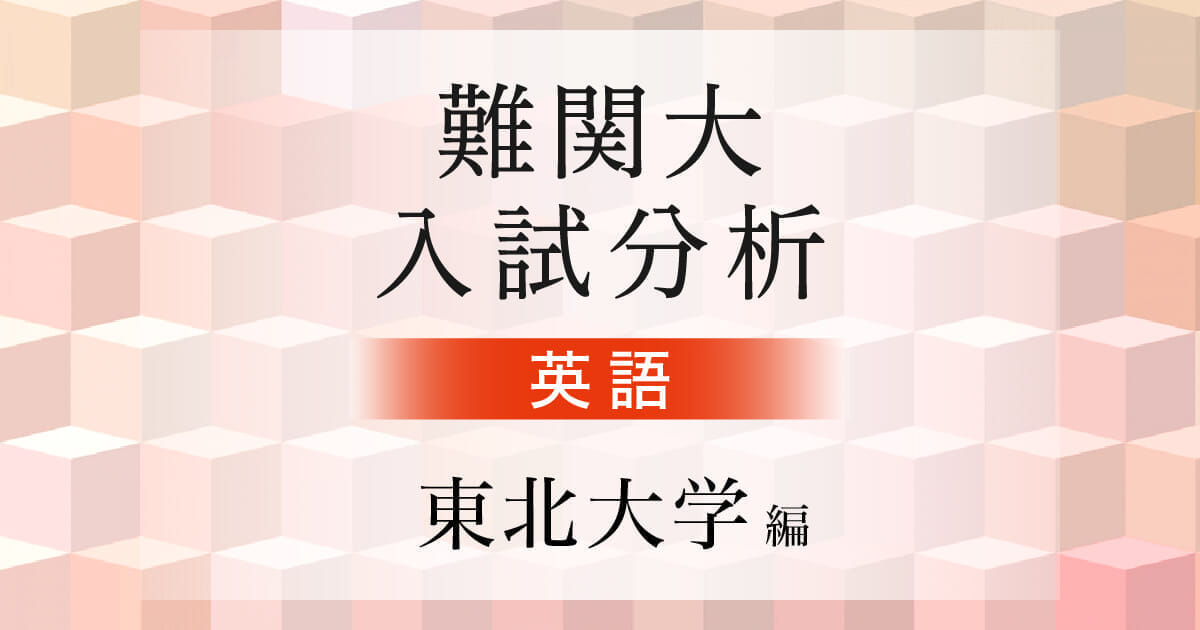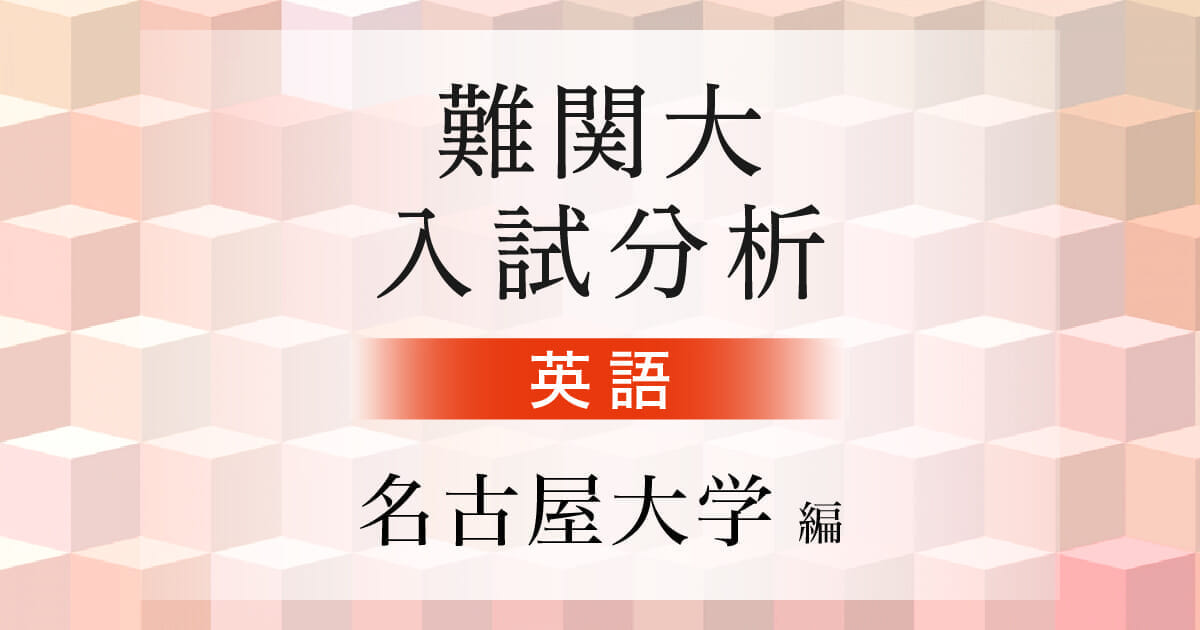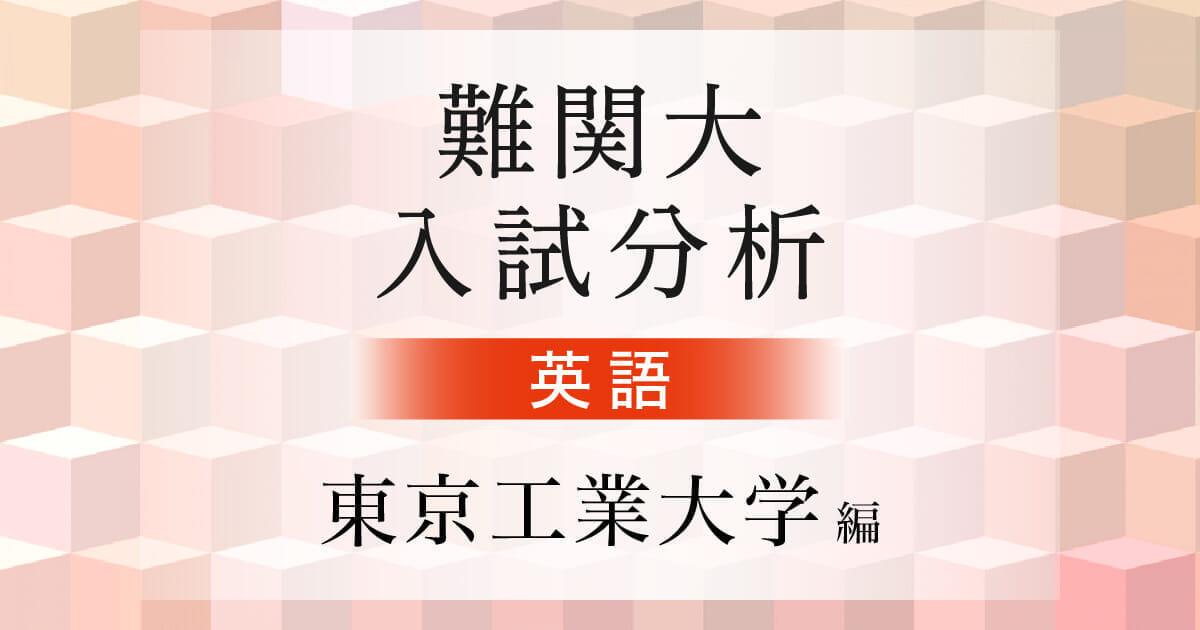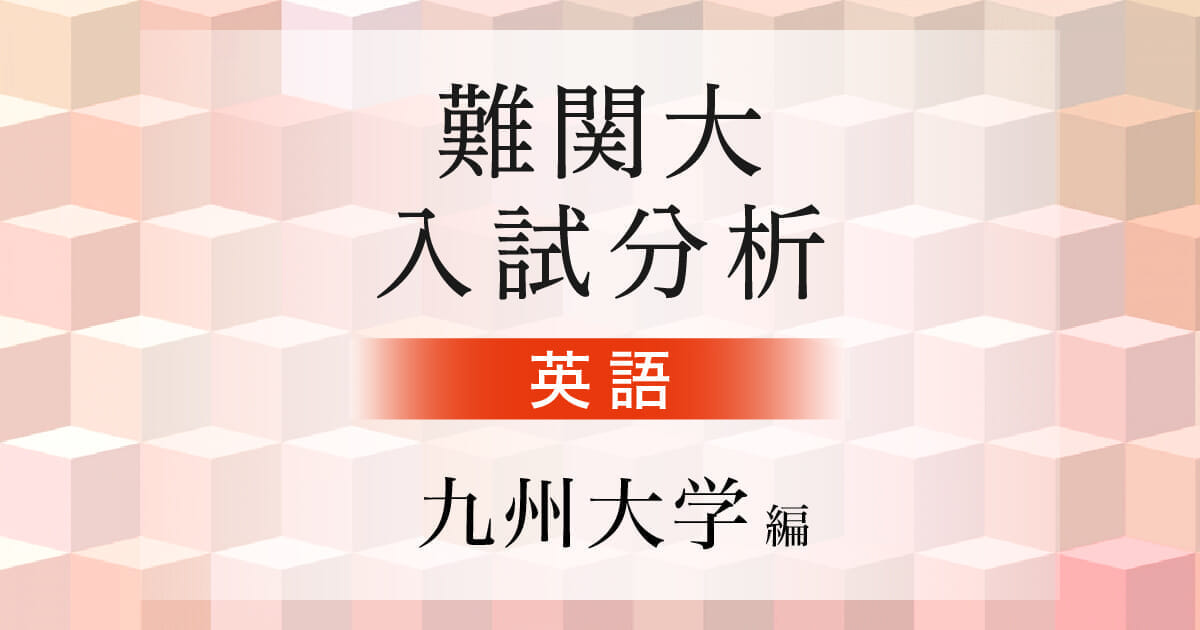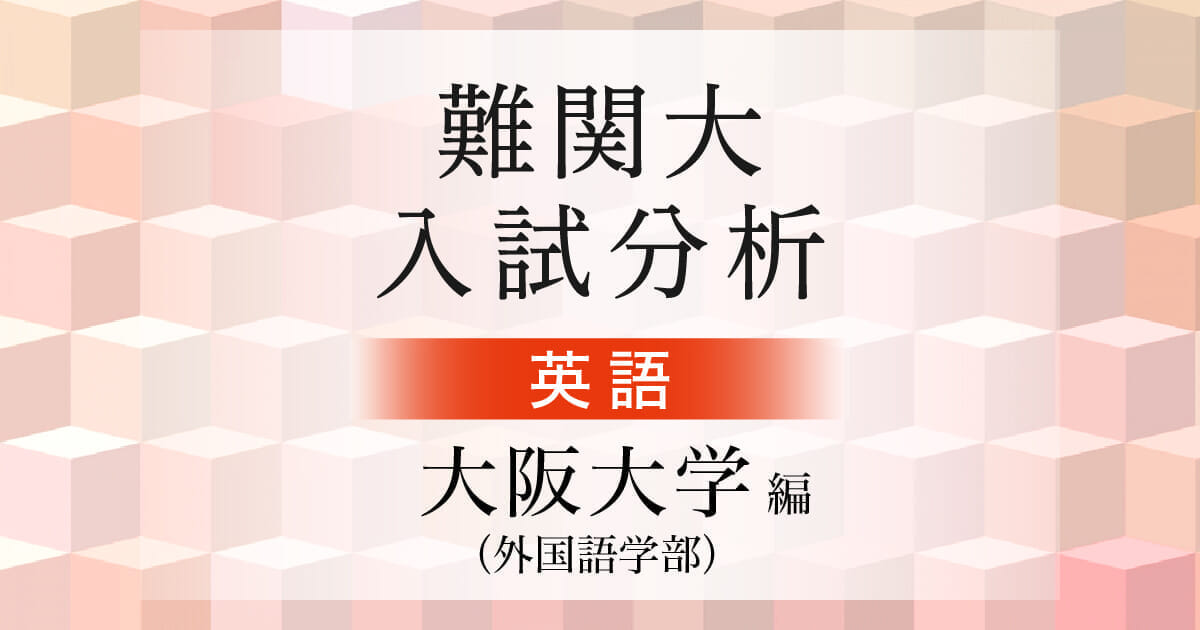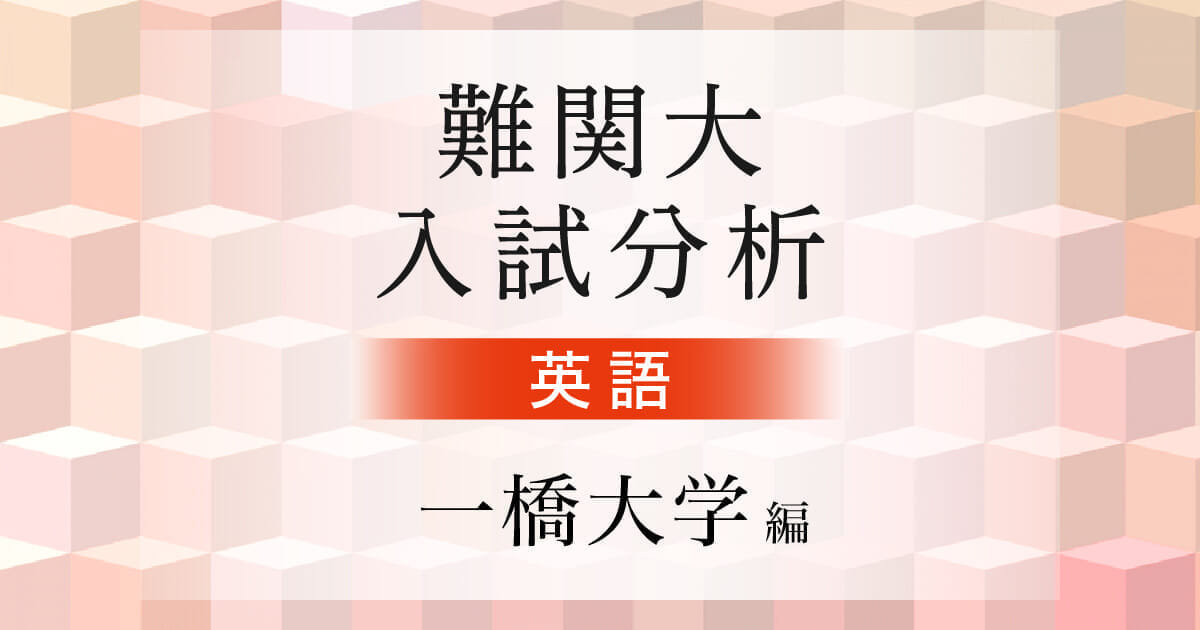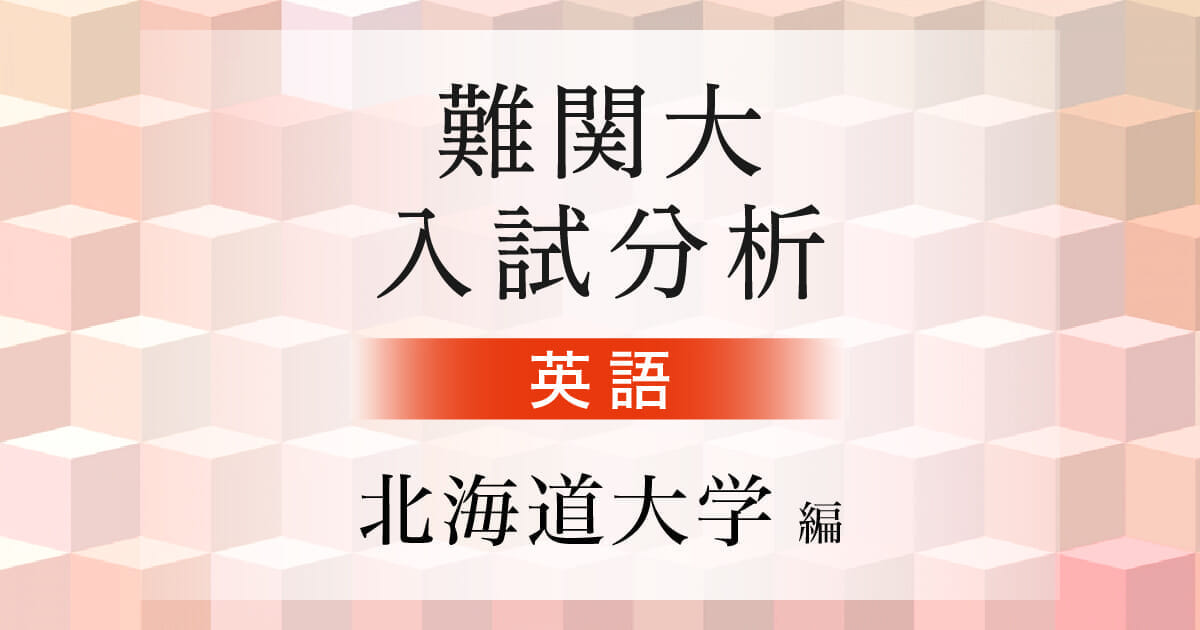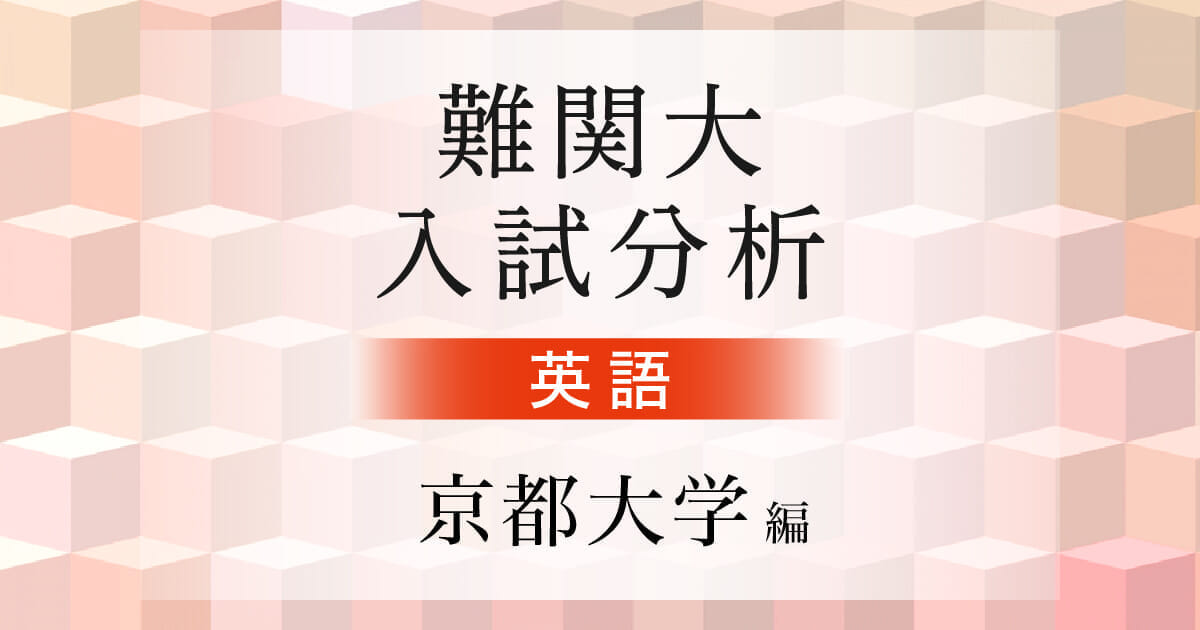2024年度 東京大学 英語
2024年4月24日
カテゴリー : 大学受験
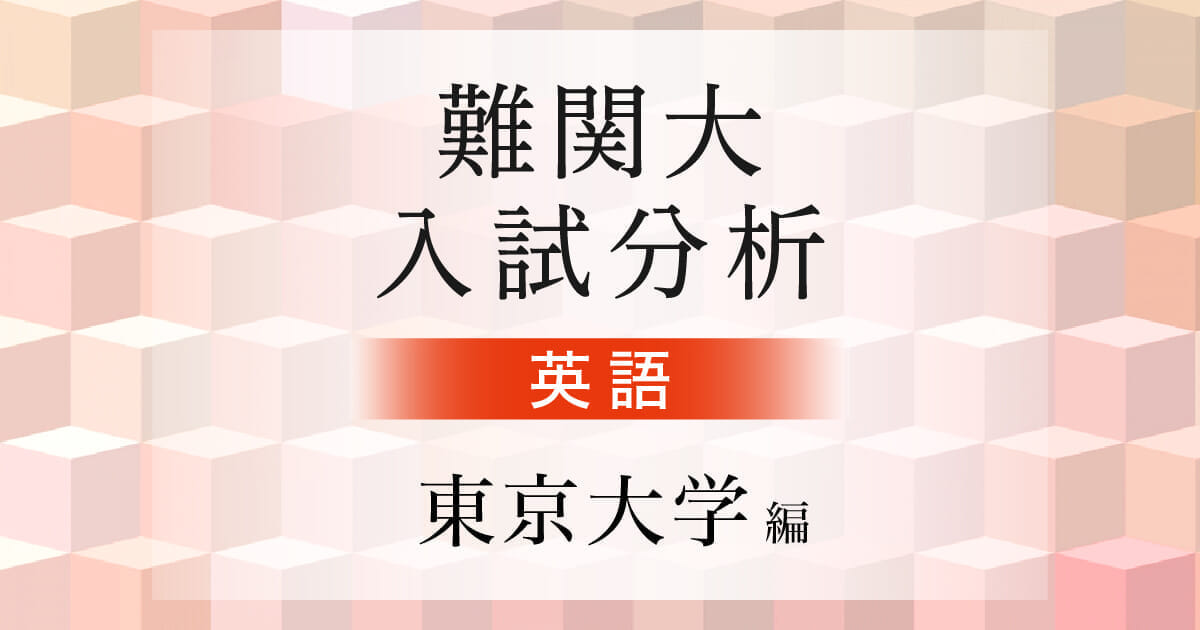
確実に内容を理解するだけでなく、
適切に表現する記述力もポイント。
一見すると読みやすく易しそうな問題なのに、いざ解答をまとめるとなると手強いのが東大英語。解答を作成するための日本語・英語での記述力こそがカギ。とにかく自分で書く演習を積むことが肝要である。
*分量:変化なし *難易度:標準(昨年度比)
■概要 (120分)
* 出題・解答の形式
- 記述式・客観式混合
* 特記事項
-
2(A) 2つの主張のうち1つを選び、それに対する自分の考えを述べる新傾向の問題が出題された。
-
2(B) 訳すべき和文の分量が増えた。
-
3 2023年度に引き続き、ダイアローグ形式の出題があった。
■各問の分析(難易度は東大受験生を母集団とする基準で判定しています)
| 1(A):要約(プロパガンダについて)[やや難] 英文の内容を70~80字の日本語で要約する問題。2022年度以降、英文の長さは400語程度となっている。英文では、宣伝活動について「プロパガンダ」という語自体の意味を絡めながら述べられている。例年通り、英文の内容としては決して理解しづらいものではないが、制限字数内に収めるためにポイントを取捨選択する作業は困難だっただろう。また「プロパガンダ」という表現の用い方や、最後の段落の内容の含め方に迷ったと思われる。 |
| 1(B):文補充、語句整序(新聞と雑誌の記事の書き方)[標準] 語数は選択肢を含めて約980語で、2023年度より減少した。文補充では、空所は例年同様5箇所であったが、不要な選択肢は2023年度から減り、1つとなった。不要な選択肢の数は、2020年度以降、増減を繰り返している。空所前後の流れと、空所を含む段落のトピックを把握するという、文補充の基本的な解き方に従えば、正解に辿り着くのはそれほど大変ではなかっただろう。 語句整序では、該当箇所の語数は14語であったが、並べ換える要素の数は12個であった。語数・要素の個数は、2022年度からおおむね増加傾向にある。難度は標準的であった。 |
| 2(A):自由英作文(「紙/自転車は人類の最も偉大な発明の一つである」という主張に対する考え)[標準] 与えられた2つの主張から1つを選び、理由を添えて考えを述べるという、初めて出題される形式の自由英作文。解答の語数は例年通り60~80語。「紙」と「自転車」のいずれも身近なものであり、難しい語句をあえて使わなくても書けるので、2つの主張のうち、どちらを選んでも取り組みやすかったと思われる。 |
| 2(B):和文英訳(クオータ制による不平等の解消)[標準] 例年通り下線部の日本語を英訳する問題。1文の英訳だった2023年度と異なり、2文の英訳が求められ、訳すべき和文の分量が増えた。「…されたあかつきには」「まさに…に照らして」など一部訳出しにくい箇所も見られたが、表現しやすい日本語に読み換えた上で英訳することができれば、大きな困難はなかっただろう。第1文が長く、文構造がやや複雑になりがちなため、冠詞や時制など細かい部分でのミスや修飾語句などの訳しもれに注意が必要であった。 |
| 3:リスニング((A)「スエズ運河の封鎖事故」について解説した記事、(B)「配送業が抱える問題」に関するラジオ番組、(C)「パプア・ニューギニアの言語的多様性」についての講義)[標準] 例年通り、設問文・選択肢ともにすべて英語の選択式で、中問(A)〜(C)は2022年度以降、すべてが独立した内容となっている。(B)はダイアローグ形式であった。 (A)は放送文中の表現の意図を問う問題があったが、全体的には、正解の根拠となる箇所を特定しやすく、選択肢でも放送される表現をわかりやすく言い換えているので取り組みやすかったと思われる。 (B)は紛らわしい選択肢が含まれており、放送文中の単語の意味を前後の文脈から正しく把握する必要があった。また、2023年度と同様に、放送された内容と一致しないものを選ぶ問題が出題された。 (C)は抽象度の高い内容だった2023年度と比べると、馴染みのあるテーマで、理解しやすかっただろう。数字の聞き取りが問われたほか、放送された内容を端的にまとめた選択肢を選ぶ必要のある問題が出題された。 |
| 4(A):正誤問題(心拍と時間の感覚との関係)[標準] 英文中の下線部から誤りを含むものを選ぶ正誤問題で、6年連続の出題。英文は5つの段落に分かれており、各段落に5つの下線が引かれている点も例年通り。語数は約440語で、2023年度から大きな変化はない。例年、文法・語法面からだけでなく内容面からも誤りの有無を判断する必要があるが、2024年度は設問文にも「文法上または内容上の誤りがある」と明記されていた。問われている文法・語法のレベルは例年通り基本的なものが大半だが、(24)は文法・語法上の誤りを含んでおらず、文脈を正確に把握していないと正解するのが難しかった。 |
| 4(B):下線部和訳(動物と人間に対する子供の頃の考え)[標準] 約320語の英文に対して、和訳する下線部は例年同様3箇所。内容を明示して和訳する問題はなかった。文構造はおおむね把握しやすかっただろう。修飾関係や代名詞、前置詞など、細かな部分まで正確に訳出したい。(ア)の rip handfuls out は単語自体の意味を知らなくても、文脈から推測して訳出できるとよかっただろう。 |
| 5:長文読解(黒人として街を歩くこと)[標準] 「歩くこと」を軸に母国ジャマイカとアメリカでの筆者の経験について書かれたエッセイ風の英文からの出題。語数は約960語で、2023年度より150語程度増加した。時系列に沿って話が展開されていて、エッセイや小説特有の省略や口語表現等も多くは見られなかったため、正しく内容を把握するのはそこまで難しくなかっただろう。分量・形式ともに2023年度から大きな変化はないが、2023年度に下線部の説明として適切なものを選ぶ問題が出題された(D)(ウ)が、例年通り、本文の内容と一致するものを選ぶ問題に戻った。 設問は比較的取り組みやすいものが多かったと思われ、特に(C)は例年に比べて書くべき内容が判断しやすく、該当箇所の訳出もしやすかっただろう。(D)(イ)は空所を含む文に否定語が複数含まれるため、文意の把握に注意が必要であった。 |
■合否の分かれ目
例年通り、英語の発信力・受信力・批判的な思考力を試す問題がバランスよく出題された。120分という限られた時間内でこれだけの問題をこなさなければいけないことを考えると、決して時間的余裕はなく、負担感の多い問題構成であることは例年と変わらない。取り組みやすい問題をできるだけスピーディーに処理し、確実に得点した上で、負担感の大きい問題にかける時間を確保したい。
■東大英語の要求
要求① 「基本=易しい」と甘く見てはいけない。
難易度が高い語句はあまり登場しないが、文脈の把握が難しい英文を題材にすることや、基本語の盲点となる用法を設問とすることがあり、基本事項の習得が疎かだと得点を伸ばすことができない。
要求② 高度なリスニング力を身に付けよう。
東大のリスニングは、放送時間が長いのに加え、聞き取り問題として扱うには高度な英文を題材にしており、解答には高度なリスニング力が求められる。差がつきやすい問題の1つなので、対策には十分時間をかけておく必要がある。
要求③ 時間管理力を付けよう。
東大英語の最大の壁は、与えられた試験時間内に膨大な量の問題に適切に解答できるかどうかである。まずは時間を意識して問題を解くこと。大意要約や自由英作文など記述に時間がかかる問題も含まれているので、日ごろから〈答案作成→第三者による添削→指摘された内容をふまえての答案改善〉のサイクルを築いて、質の高い答案を迅速に作成できるようになっておかなければならない。
■東大英語攻略のために
基礎力の完成
文法事項を網羅的に習得した上で、さまざまな英文を正確に読めるようにしておくこと。また、対策にあてた時間が得点に直結しやすい要約・自由英作文の記述対策にも早い段階から取り組んでおきたい。
精度の向上と時間管理
基礎力が身についたことを実感できるようになったら、答案の精度を上げていく一方で、時間管理力をつけるために時間を計って演習し、自分の課題を確実に消化しておこう。
過去問を使った演習
試験本番では必要以上に時間をかけてしまい、時間配分がうまくいかないこともあるだろう。ある程度余裕のある戦略を組み立てられるように、出題構成と問題量に十分慣れておくこと。過去問研究の差が明暗を分ける。
難関大入試の英語対策はZ会
難関大合格者に支持され続けているZ会の添削指導で難関大水準の英作文力を!
自己採点が難しい英作文を伸ばすには、第三者の良質なフィードバックが近道です。
Z会の英語では、毎月本番さながらの記述課題に挑戦。
プロの丁寧な指導で、難関大合格に必要な「自身の考えを英語で伝える力」が身につきます。
難関大合格に向け、Z会で英語対策をしませんか。
この記事に関連するおすすめ受験・学習情報
Z会でできる受験対策
- Z会では、志望校合格を実現する対策講座を多数開講中。Z会の良問&添削で、質の高い自宅学習を! ◆Z会の通信教育 高校生・大学受験生 中高一貫校に通う中学生 高校受験をする中学生 国私立中学受験をする小学生 公立中高一貫校受検をする小学生