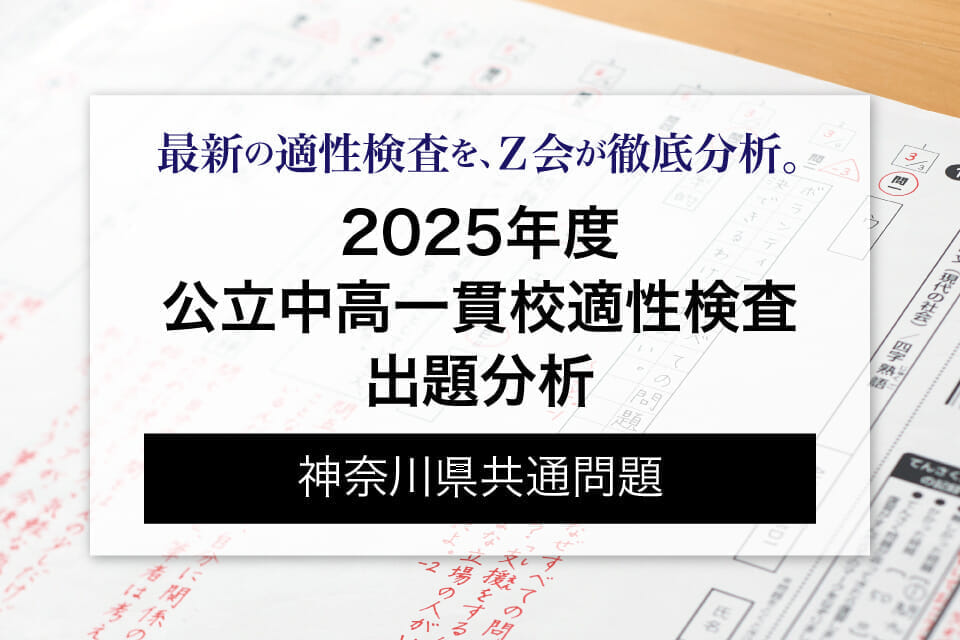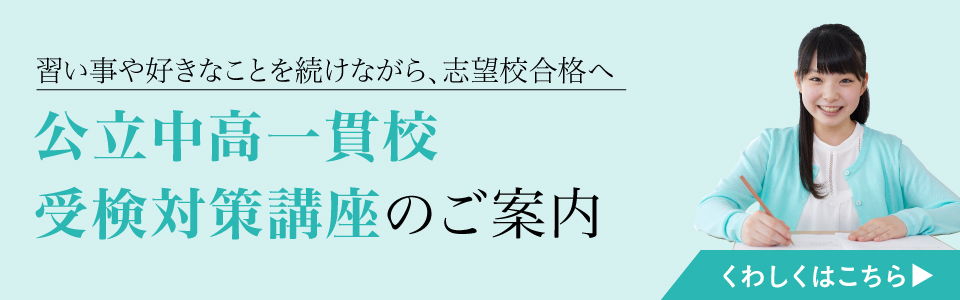出題校
神奈川県の中高一貫校では、神奈川県の共通問題を使用して、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共通=神奈川県共通問題、独自=学校独自の問題)
| 相模原中等教育学校 | ||
|---|---|---|
| 平塚中等教育学校 |
| 相模原中等教育学校 | ||
|---|---|---|
| 平塚中等教育学校 |
全体的な傾向
適性検査Ⅰ、Ⅱともに、大問・小問数が前年度とまったく同じでした。また、問題の傾向に大きな変化はありませんでした。
例年通り、マークシート方式による解答用紙が用いられ、マークシートで答える問題と語句や文章で記述する問題がありました。
適性検査Ⅰ、Ⅱはいずれも会話文や表・グラフなどの情報を読み取る問題で、あたえられた情報の中のどこに注目すればよいかを判断する必要がありました。
試験時間に対して問題量が多いため、問題文から情報を読み取る正確さだけでなくスピードも求められます。
問題ごとの分析
適性検査Ⅰ(45分)
共通問題
〇テーマ
農業用水の「分水」の仕組み
〇内容
農業用水の「分水」の仕組みを、図や文から読み取り、正しい文の選択や計算を行う。
◆概要
問題を解くためには、分水の仕組みについて、会話文や、図・文章の資料を読み取り、素早く理解する必要があります。
「円筒分水」という語や、それを使った分水の仕組みは、ほとんどの人にとって初めて知ることばかりだと思いますが、原理はそれほど難しくありませんので、あわてずに取り組めば、正解できます。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)
円筒分水の施設において、「久地堀に流れていく水の量が1分あたり104L」と仮定した場合、「1時間で根方堀に流れていく水の量」が何Lであるかを解答する問題です。
「1分」と「1時間」という時間のちがいに注意し、「久地堀」と「根方堀」に流れていく流量の比を文章・図から求めれば、解答できます。
落ち着いて計算し、確実に正解しておきたい問題です。
共通問題
〇テーマ
汗の主な成分、暑さ指数
〇内容
汗で失った成分をスポーツ飲料で補うのに必要な量を求める、暑さ指数を求める
◆概要
(1)
汗をかいたときに失われる水分量や、水以外の失った成分を補うために必要なスポーツ飲料の体積を求める問題です。
(2)
暑さ指数を乾球温度・湿球温度・黒球温度の値から求めたり、求めた暑さ指数が運動指数が運動が原則中止になるのかどうか検討する問題です。
いずれの問題も、初見の内容であっても会話文を読めば内容をすぐに理解できる問題であるため、必ず正解したい内容でした。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(1)イ
問題では汗700gについて問われているのに対して、〔調べたこと1〕では汗1000gについて示されていることに注意が必要です。
また会話文から、食塩相当量はナトリウムの量を2.5倍すればよいとあるので、ナトリウムの量は食塩相当量を2.5で割ればよいことがわかります。
以上のことから、ナトリウム、カリウム、カルシウムに関して失った量をスポーツ飲料で補うのに必要な量を求めます。
ミスなく短時間で解答するには、汗1000gと汗700gでは、ふくまれる成分の割合は一定なので、まずは汗1000gで失った成分の量を補うために必要なスポーツ飲料の量を成分ごとに求め、最後に汗700gに換算したときの値を解答するのがよいでしょう。
もちろん、〔調べたこと1〕であたえられた値を成分ごとに汗700gにふくまれる量に換算して計算する方法でも求められますが、限られた試験時間においては短時間で求める工夫も必要です。
共通問題
〇テーマ
運輸会社が荷物を輸送するときに行う工夫
〇内容
運輸会社が荷物を運ぶ際に行っている工夫について、荷物を運ぶ設定例をもとに考える。
◆概要
ある地点間の荷物の輸送について、あたえられた条件と「中継地の位置」、「運転手の人数」、「トラックや荷物の数」に注意して考える問題です。
(1)
中継地が荷物を輸送する地点間の中間の位置にある場合について考える問題です。
(1)アは、すべての荷物を目的地に最も速く輸送し終わる時刻について求める問題で、(1)イは、中継地を設けない場合における運転終了後の運転手の位置を求める問題です。
あたえられた条件のうち、運転手の「時速、連続で運転できる時間・合計で運転できる時間」に特に注意して計算する必要があります。
(2)
中継地が荷物を輸送する地点間の中間の位置にない場合について、すべての荷物を目的地に最も速く輸送し終わる時刻について求める問題です。
あたえられた全ての条件にくまなく注意しながら筋道を立てて考える力が必要です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)
(1)とは異なり、中継地が荷物を輸送する地点間の中間の位置にない場合について考える問題です。
この場合、運転手の連続で運転できる時間と休けい時間、トラックの乗り換えは中継地で行う必要があることに注意し、「何時間後にトラックを乗り換えれば最も早く荷物を輸送できるか」に焦点を当てて考える必要があります。
荷物を輸送する様子を、トラックを乗り換えるタイミングごとに図示して考えると分かりやすいです。
共通問題
〇テーマ
校外学習の行動計画について
〇内容
校外学習の行動計画をルールに従って立てる。
◆概要
動物園の園内マップをもとにルールに従って行動計画を立てる問題です。
(1)
ルールに従って計画を立てるとき、午前に観察カードをかくことができる動物は最大で何種類かを考えます。
(2)ア
ルールと会話文にある行動予定をもとに、出発した場所に再び集合する予定時刻について考えます。
(2)イ
ルールと会話文にある行動予定をもとに、かくことができない動物の観察カードは何かを考えます。
(1)、(2)ともに、問題であたえられている複数の情報をきちんと整理しながら順を追って考える必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)ア
問題であたえられているルールに加えて、会話文にかかれている行動予定もふまえながら、出発した場所に再び集合する予定時刻を求める問題です。
一見すると、午前から午後までの行動計画を一つずつ丁寧に順を追って考える必要がありそうな問題ですが、
ひかりさんの発言から「午前にライオンの観察カードをかくことができること」と「午後、ゾウのえさやり体験より前に、他の2つの体験をおえることができること」に気づくことができるかどうかがポイントです。
制限時間の限られている適性検査に対応するために、あたえられている複数の情報を手際よく読み取って問題を解く力をぜひ身につけておきましょう。
共通問題
〇テーマ
卒業に向けた活動の提案
〇内容
卒業に向けて自分たちができる活動を、70字以上80字以内で提案する。
◆概要
卒業に向けて自分たちができる活動についての話し合いを読み、「地域の人や在校生のために」どんな活動ができるかを提案します。
条件は2つ。「だれのためのどのような活動かを具体的に書く」「その活動の中でどのような役割を果たしたいかを具体的に書く」。
いずれも「具体的に」とあるのがポイントです。読み手が頭の中でリアルにイメージできるように書いてください。
字数が限られているので、その活動に決めた理由などは書かずに、活動の具体的な内容にしぼって書きましょう。
適性検査Ⅱ(45分)
共通問題
〇テーマ
日本語の「かな」について
〇出典:
【資料1】『学研ハイベスト教科事典 国語』金田一春彦監修より
※一部表記を改めたところがある。
【資料2】『玉川児童百科大辞典 国語』石黒修編より
※一部表記を改めたところがある。
【資料3】『日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白い ことばの世界』国立国語研究所編より
※一部表記を改めたところがある。
◆概要
(1)
3つの資料から読み取れることとして正しいものをすべて選ぶ選択問題です。
(2)
3つの資料をふまえて「万葉がなはどのようにして日本語を漢字で書き表したのか」「カタカナは万葉がなからどのようにしてつくられ、現代では主にどのような役割があるか」をまとめ、80字以上90字以内で説明する問題です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)
資料の内容をふまえ、問われていることに正しく対応するようまとめることが求められています。
字数が限られていますから、具体例などをふくめてしまうと字数オーバーしてしまうので気をつけてください。
求められている内容がどの資料に書かれているのかを適切に判断し、わかりやすい文章にまとめましょう。
共通問題
〇テーマ
日本の人工林と林業
〇内容
人工林の木は植えてから51年目に切り始めることを考慮し、人工林の面積の変化や、伐採する本数などについて考える。
◆概要
(1)
1966年度と2021年度の人工林の面積のグラフを読み取り、その変化について答えます。
(2)
あたえられた条件をすべて満たすように、木を切る本数を計算し、90年生以上の木の最終的な割合を求めます。
どちらの問題でも、それぞれの会話文や資料中にある情報・条件を考慮しながら、あてはまるものを考えていく必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(1)
アでは、あたえられた条件をしっかり確認し、解答すべき内容は何かを理解することが重要です。
1966年度から2021年度までは55年が経っていますので、1966年度に「1年生~5年生」だった人工林は、2021年度には「56年生~60年生」となっています。
前者が229万ha、後者が154万haなので、その差が答えとなります。
イでは、2021年度の51年生以上の人工林の面積を足し上げ、全体の面積1009万ha(会話文中に書いてある)で割れば、割合を求めることができます。
考え方としては難しくないので、計算ミスをしないようにすることが重要です。
共通問題
〇テーマ
調理実習で作る料理
〇内容
料理に使う材料の分量や費用を求める。票を1番多く集めた料理とその票数を求める。
◆概要
(1)ア
材料費をかえずに、ツナ1缶をベーコンで代用する場合の分量を求める問題です。
ツナ1缶あたりの金額とベーコン100gあたりの金額が問題文で示されているので、計算方法さえわかれば簡単に求めることができます。
(1)イ
4種類の料理の材料と分量をもとに、ジャーマンポテトを作るための費用を求める問題です。
にんじん、たまねぎ、じゃがいもの材料費は、ツナとベーコンの材料費、問題文中の4人分の費用、および、あたえられた資料をもとに計算して求めます。
(2)
4人それぞれが、4種類の料理に投票した票数の合計が10票になるように投票したとき、票を1番多く集めた料理の票数を求める問題です。
会話文から、4人それぞれがどのように投票したかの情報を読み取り、1つずつ表の中に票数を書いていくと解きやすいでしょう。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)
4人それぞれが、どの料理に何票投票したかを、1つずつ整理して考えていく必要があります。会話文の情報から、以下のことを読み解けるかがポイントです。
『4人とも、4種類の料理で同じ票数の料理はない。』
⇒たとえば、1つの料理に10票入れると、残り3つがすべて0票で同じ票数になってしまうので、このパターンはない。
同様に9票、8票入れるパターンもなく、考えられる票数の組み合わせは次の5通りである。
①:7,2,1,0、②:6,3,1,0、③:5,4,1,0、④:5,3,2,0、⑤:4,3,2,1
『それぞれの人が1番多く投票した票数は、4人ともちがう。また、その票数は「たろう>かなこ>じろう>ひかり」である』
⇒それぞれが投票した組み合わせは、たろう:①、かなこ:②、じろう:③または④、ひかり:⑤となる。
『じろうが1番多く投票した票数と2番目に多く投票した票数の差は1票である。』
⇒じろうが1番多く投票した票数は5なので、2番目に多く投票した票数は4だとわかる。よって、じろうの票数の組み合わせは③と決まる。
共通問題
〇テーマ
立方体の展開図の組み立て・配置
〇内容
立方体の展開図を題材に考える。
◆概要
(1)
立方体の展開図にかかれている矢印について考える問題です。
(2)
矢印や数字がかかれている立方体の展開図を組み立てて配置し、ルールに従って考察する問題です。
展開図を組み立てたときの立体をイメージしたり、その立体を配置したときの様子を正確にとらえたりする必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(1)ア
立方体の面にある矢印の向きを考える問題です。
(1)アを間違ってしまうと(1)イも間違ってしまうので、丁寧に取り組みましょう。
頭の中で組み立てて判断するのが難しい場合は、立方体と展開図を見比べながら「組み立てたときに重なる辺に着目して考える」と分かりやすいです。
展開図を組み立てたときに重なる辺や点に着目すれば、立方体の向きを正確にとらえることができるでしょう。
とくに伸ばしておきたい力
神奈川県では、より伸ばしておきたい力として、情報整理・運用力、論理的思考力が挙げられます。
あたえられた多くの情報の中から問題を解くために必要な情報を探し出したり、情報を読みかえたりする力が求められます。
・適性検査Ⅰ
【問1】
情報整理・運用力が必要な問題です。複数の資料を素早く読んで内容を理解し、解答に必要な情報を手際よく探し出せるようにしましょう。
【問2】
情報整理・運用力が必要な問題です。内容の理解はもちろん、素早く正確な計算力を身につけておくことが大切です。
【問3】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。問題全体の様子をとらえつつ、あたえられたルールをそれぞれの場合について適用して、答えにたどり着く力をつけておくことが大切です。
【問4】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。資料から必要な情報をぬき出すのはもちろんのこと、情報のあたえ方から問題のポイントを予想しないと時間が足りなくなるでしょう。
【問5】
課題解決力、表現力が必要な問題です。自分が考えた意見・提案について、他の人がわかるように適切な文章で表現する力をつけておきましょう。
・適性検査Ⅱ
【問1】
情報整理・運用力、表現力が必要です。限られた字数の中でわかりやすく伝えられるよう、書くべきことを整理する練習をしておきましょう。
【問2】
情報整理・運用力が必要な問題です。資料や文章から必要な情報を読み取り、順を追って考え、正確に計算する力が求められます。
【問3】
論理的思考力が必要な問題です。あたえられた条件を1つずつ整理して、順序立てて検討する力が必要です。
【問4】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。問題文の条件を整理して、順序立てながら考察する力をつけておきましょう。
おすすめの学習法
複数の資料の読み取りが必要なため、手がつけにくい印象を受けますが、比較的解きやすい問題もあります。
読み取った情報を文章や図などに整理する練習をしっかりしておくとよいでしょう。
問題ごとに、おすすめの学習法を紹介しますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査Ⅰ
【問1】
複数の資料から必要な情報を読み取る練習を行っておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生11月号では、長い文章や複数の資料から、問題のポイントを読み取り、記述を行う練習ができます。
【問2】
計算処理力を高めるのはもちろんのこと、計算の仕方を工夫することで短時間でミスなく正解を導き出すことも意識していきましょう。
【問3】
読み取った条件をもとに試行錯誤しながら、答えにたどり着く練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号の「条件にしたがう」の回では、複雑な条件のもと答えを推理する問題に挑戦します。
【問4】
多くの情報を効果的に使う練習をしておくとよいでしょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生9月号や1月号では、条件に合った駅やパビリオンの回り方を考える問題に挑戦します。
【問5】
あたえられた文章を正しく読み取り、自分の意見を表現できる練習をしておきましょう。
また、課題解決力については、Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生4月号では、「話し合い・説明する」というテーマで課題解決力をつける練習をします。
・適性検査Ⅱ
【問1】
複数の資料を読み取る問題を解いて、書くべきことをメモなどに整理する練習をしておきましょう。
整理したメモをもとに指定の字数に合わせて作文することで、だれが読んでも論理的にわかりやすい文章を作ることができます。
【問2】
資料や文章から必要な情報を読み取る練習や、正確に計算をする練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生7月号では、資料から情報を読み取ったり、計算を行ったりする問題に取り組みます。
【問3】
あたえられた条件をもとにひとつずつ順を追って考えていき、答えにたどり着く練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、では、条件からわかるところからひとつずつ整理して、答えにせまっていく問題に取り組みます。
【問4】
図形や立体の性質をよく理解し、条件に合うパターンを考察する練習をしておくとよいでしょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生5月号では、立体図形をとらえる問題に取り組みます。