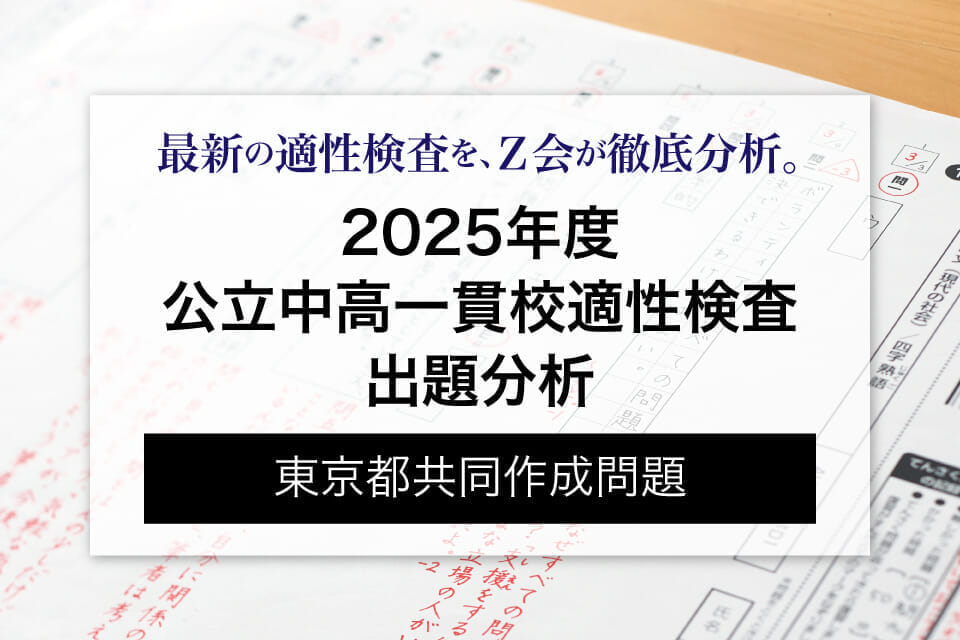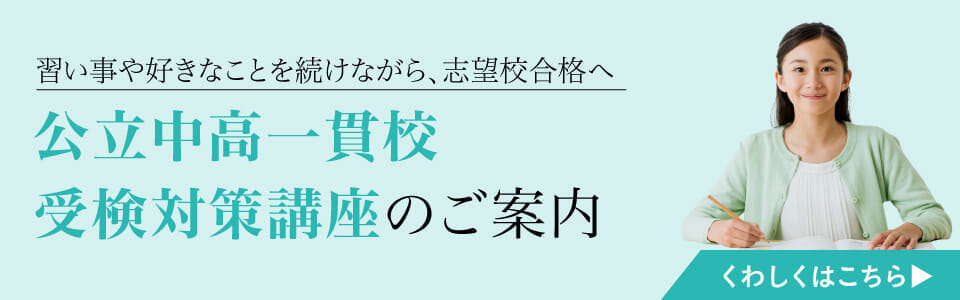出題校
東京都立の中高一貫校では、東京都の共同作成問題と、学校独自の問題を組み合わせて、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共同=東京都共同作成問題、独自=学校独自の問題)
※表は2024年度の問題です。
| 桜修館中等教育学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大泉高等学校附属中学校 | |||||
| 小石川中等教育学校 | |||||
| 立川国際中等教育学校 | |||||
| 白鷗高等学校附属中学校 | |||||
| 富士高等学校附属中学校 | |||||
| 三鷹中等教育学校 | |||||
| 南多摩中等教育学校 | |||||
| 武蔵高等学校附属中学校 | |||||
| 両国高等学校附属中学校 |
| 桜修館中等教育学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大泉高等学校附属中学校 | |||||
| 小石川中等教育学校 | |||||
| 立川国際中等教育学校 | |||||
| 白鷗高等学校附属中学校 | |||||
| 富士高等学校附属中学校 | |||||
| 三鷹中等教育学校 | |||||
| 南多摩中等教育学校 | |||||
| 武蔵高等学校附属中学校 | |||||
| 両国高等学校附属中学校 |
全体的な傾向
適性検査Ⅰ
例年通り、読解問題と作文が出題されました。作文は2つの文章から読み取った内容と自分の考えを適切に関連付けて書くことが重要でした。
問題の構成や傾向について、前年度からの大きな変化はありませんでした。
適性検査Ⅱ
例年通り大問が3つの構成で、大問1は立体図形の問題、大問2は循環利用率を高める取り組みについての問題、大問3はシャボン玉の実験問題が出題されました。
問題の構成や傾向について、前年度からの大きな変化はありませんでした。
問題ごとの分析
適性検査Ⅰ(45分)
共同作成問題(国語分野)
〇テーマ:
自分にとっての「謎」への向き合い方
〇出典:
【文章1】小島渉「カブトムシの謎をとく」(一部改変)による
【文章2】恩田陸「spring」による
〇内容
2つの文章とそれらをふまえた会話文の読み取り。作文(400字以上440字以内)。
◆概要
問題1
文章1の内容について述べた会話文の空欄に、文章1からぬき出した語を入れる問題です。
空欄がふくまれる会話文の内容、空欄の前後の内容、指定された字数に注意して、的確にぬき出しましょう。
問題2
文章2における登場人物の心情について述べた文の空欄に、文章2の中の表現をもとにして、指定された字数で語句を入れる問題です。
空欄をふくむ文が文章2のどの部分をふまえているのかを確実につかみ、指定された字数にも注意して、適切な語句を探し出す必要があります。
問題3
文章1、文章2で読解した内容や、それらについて述べた会話文をふまえて、自分にとっての「謎」への向き合い方を、400~440字で作文する問題です。
あたえられた条件に沿ったわかりやすい文章を書くことが重要です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題3
自分にとっての「謎」とは何か、それを解決するためにどのように取り組んでいきたいかを、400~440字で作文する問題です。
文章1・文章2・会話文の内容をふまえる、「謎」は一つにしぼる、という条件がついています。
文章1・文章2・会話文から読み取った内容を関連づけて書くことが必要ですが、「あなたの考え」が求められているので、自分の考えを論理的に説明することが大切です。
また「どのように」と問われているときは、できるだけ具体的に書く必要があります。
読み手があなたの取り組みを具体的にイメージできるように書くことが高得点のポイントです。
適性検査Ⅱ(45分)
共同作成問題(算数分野)
〇テーマ:
宝箱の展開図とブロックの組み立て
〇内容
宝箱の展開図の面積やブロックを組み立ててできる大きな立体について考える。
◆概要
問題1
宝箱の展開図の面積を言葉や図、式を用いて、計算で求める問題です。
解答のかき方の例を参考にしながら、解き方をまとめて説明する力が求められます。
問題2
2種類のブロックを組み立てて大きな立方体を作ったときの、一番上の段にある2種類のブロックの境界線を考える問題です。
途中まで組み立ててある立体に、2種類のブロックを追加してどのように組み立てていくと、大きな立方体ができるのか試行錯誤する必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題1
宝箱の展開図の面積を言葉や図、式を用いて計算する問題で、展開図の正方形の1辺の長さを求められるかが問題を解く鍵になります。
まず、あたえられた条件の「宝箱の底になる面の長方形の長い辺の長さは、短い辺の長さ(正方形の1辺の長さ)の2倍」に着目して、正方形の1辺の長さを求めます。
その際、正方形の1辺の長さ2つ分が、宝箱の底になる面の長方形の長い辺の長さと等しいと考えると、正方形の1辺の長さがすぐに求まります。
そして、「正方形の1辺の長さと、半円の直径の長さが等しいこと」と「宝箱のふたになる面の長方形の短い辺の長さは、半円の円周と等しいこと」に注意すると、展開図の面積を求めるために必要な辺の長さがすべてわかります。
この問題のように、言葉や図、式を用いながら説明する問題は出題されやすいので、答えを導くまでの説明を簡潔に記述する演習を積んでおきましょう。
共同作成問題(社会分野)
〇テーマ:
循環利用率を高める取り組み
〇内容
リユース・リサイクルなどの「循環利用」について、製品ごとの特徴を資料から読み取ったり、循環利用率を高めるための取り組みについて考えたりする。
◆概要
問題1
3つの製品についての循環利用の流れを表した図と統計数値を参照して、循環利用率の計算や、各製品の循環利用の特徴の比較・記述を行う問題です。
循環利用率の計算は難しくないので、正解することが必要です。資料の数値を正しく計算し、四捨五入の条件に沿って解答します。
記述問題では、「衣服とペットボトルの比較」または「衣服と紙の比較」を行います。それぞれの図を素早く読み取って、共通点・異なる点が明確にわかるように記述することが大切です。
問題2
3つの統計資料と会話文を参照して、循環利用率を高めるための取り組み事例から「消費者の意識や行動がどのように変化して循環利用率が高まるのか」を考察する問題です。
統計資料から読み取れることと、取り組み事例とをうまく結びつけて記述することが重要です。
2つの取り組み事例のうち、どちらか1つを選んで記述するので、自分にとって書きやすいのはどちらかを素早く判断することも大切です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題2
まず、「衣服の購入動機」「購入した衣服をほとんど着用しなかった理由」「まだ着られる衣服の処分方法」についての統計資料を参照して、循環利用率が低く留まっている要因や、循環利用を高めるためのヒントを読み取ります。
次に、読み取ったことを、2つの取り組み事例のうちどちらか1つ(回収ボックス利用によってポイントがたまる、または衣服を複数の利用者でシェアリングする)と結びつけて、消費者の意識・行動と循環利用率の関係性がわかるように記述すると、説得力のある解答となります。
なお、この問題では図や表だけでなく、会話文の中にも解答を作成するためのヒントが書かれています。
資料や会話文をもとに解答する問題では、情報の見落としがないように注意することが必要です。
共同作成問題(理科分野)
〇テーマ:
シャボン玉の実験問題
〇内容
シャボン玉の液に加えるさとうの量とシャボン玉の大きさの関係や、時間経過によるシャボン玉のまくの様子の変化について考える。
◆概要
実験の手順と結果をしっかりと読み、どのような実験が行われているかを正確に理解する必要があります。
実験1と実験2では、シャボン玉の液に加えるさとうの量と、作ることができるシャボン玉の大きさの関係を調べており、実験3と実験4では、針金のわくを用いてシャボン玉のまくがやぶれるまでの時間と様子を調べています。
問題1
水と食器用せんざいのみで作ったシャボン玉に比べて体積が2倍以上のシャボン玉を作ることができた液体を、液体B~液体Gの中から全て選び、その理由を説明する問題です。
実験結果の「ハンドルをおしきった数」が何を表しているのかを読み取ることができれば、条件を満たす液体を選ぶことは難しくありません。
問題2
わくにまくをつくって固定してから15秒後にわくを上下反対にして再び固定すると、まくがやぶれるまでの時間が長くなる理由を説明する問題です。
わくを固定してから15秒後のまくの様子から、時間がたつにつれてまくの上側がうすくなっていき、まくがやぶれることが読み取れるので、それらを実験4の結果と結びつけて説明する必要があります。
問題文や実験の手順、結果から読み取れることをまとめ、それらを論理的に説明する力は必要不可欠ですので、必ず身につけておきましょう。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題1
問題で問われている「シャボン玉の体積」と、実験結果の「ハンドルをおしきった数」の関係を論理的に説明できるかどうかが、この問題のポイントです。
手順2に、ハンドルを1回おすごとに同じ体積の空気がシャボン玉の中に入るとあるので、ハンドルをおす回数とシャボン玉の体積は比例の関係になっていることがわかります。
つまり「体積が2倍以上のシャボン玉を作ることができた液体」とは、「ハンドルを2倍以上おすことができた液体」ということになります。
実験1の結果から、水と食器用せんざいのみである液体Aは、ハンドルを4回おしきることができたため、4×2=8回以上おしきることができた液体は、体積が2倍以上のシャボン玉を作ることができた液体であるといえます。
実験2の結果についても同様に調べることで、条件を満たす液体を選ぶことができます。
とくに伸ばしておきたい力
東京都立では、「5つの力」をバランスよく伸ばすことが求められますが、より伸ばしておきたい力として、情報整理・運用力、論理的思考力、課題解決力、表現力が挙げられます。
・適性検査Ⅰ
論理的思考力、表現力が必要とされる問題です。
指定された字数の中で、あたえられた文章から読み取った内容をわかりやすく伝える力と、自分の考えを伝えられる表現力を伸ばしておきましょう。
・適性検査Ⅱ
【大問1】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。
問題文の条件を整理して、順序立てながら考察する力をつけておきましょう。
【大問2】
情報整理・運用力、課題解決力が必要な問題です。
資料を読み取る際には、共通点や変化、特徴的な値に着目できるようにしましょう。
また、社会的な課題に対する問題意識をもっておきましょう。
【大問3】
論理的思考力が必要な問題です。
実験の結果を正しく読み取り、考察できることを整理して、過不足のないように説明できる力を身につけておきましょう。
おすすめの学習法
教科知識をそのまま問う問題は出題されません。適性検査型の出題に慣れ、解き方を身につけておく必要があります。そのためには、適性検査型の問題にたくさん当たっておくことが大切です。
また、適性検査Ⅰだけでなく、適性検査Ⅱでも文章で説明することが求められます。そのため、簡潔に文章でまとめる練習、他者に伝える練習もしっかりしておくとよいでしょう。
問題ごとに、おすすめの学習法を紹介しますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査Ⅰ
読み取った内容や自分の意見の中で作文に必要なポイントをまとめ、全体の構成のメモをつくる練習をしましょう。
そのメモをもとに指定の字数に合わせて作文することで、だれが読んでも論理的にわかりやすい文章を作ることができます。
Z会の「公立中高一貫校作文」講座の9月号では、二つの課題文をふまえて作文を書くことを学びます。
・適性検査Ⅱ
【大問1】
図形や立体の性質をよく理解し、条件に合うパターンを考察する練習をしておくとよいでしょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生5月号では、立体図形をとらえる問題に取り組みます。
【大問2】
複数の資料から読み取った情報をもとに、問われている内容について説明するという問題形式に慣れておく必要があります。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生7月号では、同じ問題形式で練習ができます。時間を計り、スピード感をもって解く練習もできるとよいでしょう。
【大問3】
さまざまな実験・観察問題に取り組み、結果から考察する力を高めましょう。
また、身のまわりのものや現象が題材となることも多いので、普段の生活で疑問に思ったことは、積極的に調べてみるとよいでしょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生12月号、6年生8月号の「身のまわりの科学」の回では、身のまわりの現象がどういうしくみで起こるのか、実験を通して考える問題に挑戦します。