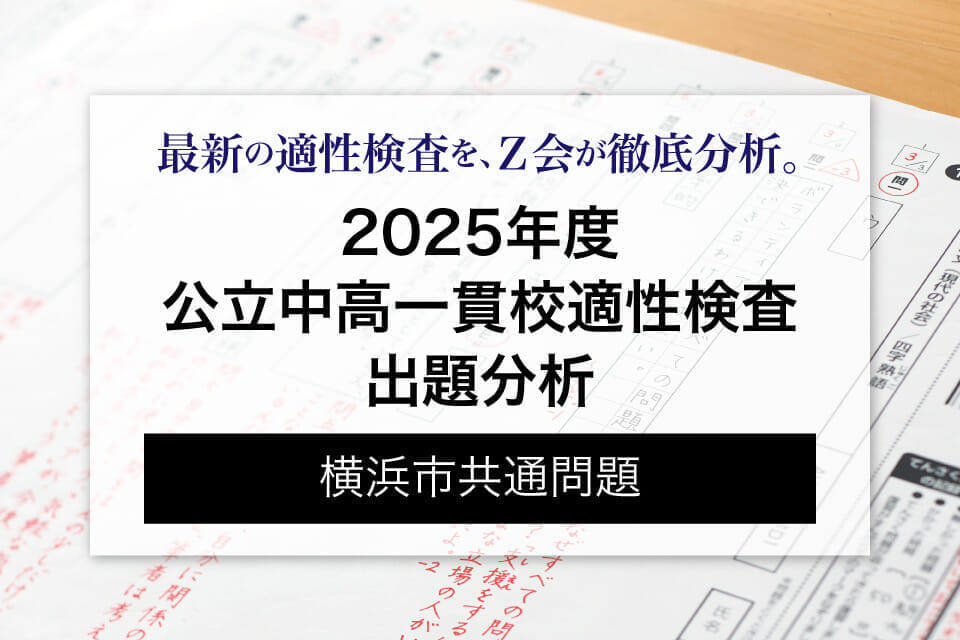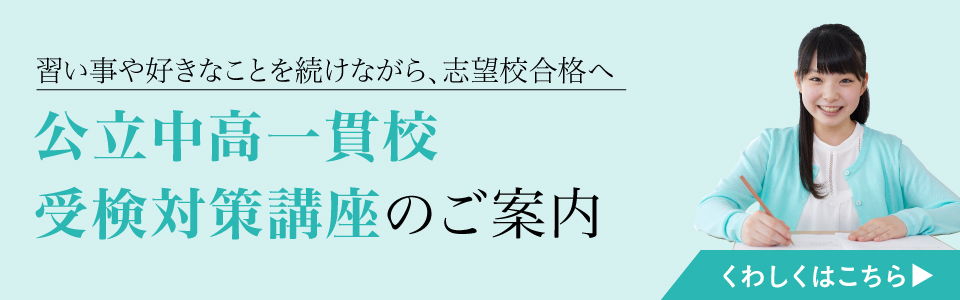出題校
横浜市の中高一貫校では、横浜市の共通問題と、学校独自の問題を組み合わせて、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共通=横浜市共通問題、独自=学校独自の問題)
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | ||
|---|---|---|
| 横浜市立南高等学校附属中学校 |
| 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア 高校附属中学校 |
||
|---|---|---|
| 横浜市立 南高校附属中学校 |
全体的な傾向
前年度と同様、問題の文章量が例年と比べて多かったですが、前年度と比べて大問1の難度がやや低くなっていました。
問題の構成は前年度とかわらず2問構成でした。毎年出題される作文の問題では、170字以上200字以内の作文を2つ書くという形式でした。
試験時間に対して文章量が多いため、あたえられた資料から必要な情報を素早く見つけ出す力が求められます。
問題ごとの分析
適性検査Ⅰ(45分)
共通問題(社会分野)
〇テーマ
お札と文化・歴史
〇内容
日本や外国のお札をテーマに、日本や外国の文化・歴史について考える。
◆概要
2024年に発行された日本の新しいお札について、えがかれた人物の功績や、ユニバーサルデザインの意義、浮世絵をめぐる歴史の問題などに答えます。
歴史の知識が必要となりますが、教科書レベルの基本知識があれば十分に解くことができます。
外国のお札については、描かれた絵についての人々の意図や願いなどを読み取る問題が出されています。
日本・外国ともに、お札に関連させて、地図の読み取りや、地理的知識を問う問題が出されるなど、あつかわれる分野は多岐にわたります。
それぞれの問題にはヒントとなる図や地図、絵・写真などの資料が示されており、それらを参照しながら考えることが大切です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題7
外国のお札である「ユーロ紙幣」に橋が描かれていることについて、どのような願いがこめられているかを考える問題です。
ユーロについての知識がなくても、掲載されている地図から、ユーロが多数の国で使われていることがわかります。そこから、橋が、国と国との間の友好関係の象徴として描かれていることが読み取れます。
自分がもっている知識と、資料から読み取れる情報を合わせて考えることが大切です。
なお、本問では「適切ではない」ものを選ぶことが求められています。選択問題では、設問文に下線を引くなどして、問われている内容を確認することが大切です。
共通問題(国語分野)
〇出典:
【資料1】茂木健一郎「シンプルで脳科学的に正しい読書法」
※一部変更あり
【資料2】ショーペンハウアー著 鈴木芳子訳「読書について」
※一部変更あり
〇内容
文章の読み取り。
◆概要
読書についての異なる見解を述べた2つの文章を読み、それぞれの内容を正しく読み取ることが求められています。
問題1
資料2の傍線部の内容として正しいものを選ぶ選択問題です。読解問題としては非常にやさしく、失点してはいけない問題です。
問題2
資料1と資料2それぞれの読書に対する考えを、あたえられた指示にしたがって、それぞれ170字以上200字以内で書く問題です。
自分の意見を述べるのではなく、二つの文章の内容を理解し要約する問題なので、書くべきことを過不足なく整理することが重要です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
問題2
資料1と資料2それぞれの読書に対する考えを、主張→理由の形で構成し、それぞれ170字以上200字以内で書く問題です。
2つの文章それぞれの中心的な内容を読み取り、それぞれが具体的にどのようなことを根拠としているかをまとめます。
まず「本はこのように読むべき。なぜなら、○○だからだ。」という骨格となるものを短くまとめ、字数の範囲内で理由の部分を肉付けしていくとよいでしょう。
とくに伸ばしておきたい力
横浜市の適性検査Ⅰは、文系分野からの出題です。
より伸ばしておきたい力として、教科基礎力、情報整理・運用力、表現力が挙げられます。問題の構成が変わっても対応できる力を身につけておくことが大切です。
・適性検査Ⅰ
【大問1】
教科基礎力、情報整理・運用力が必要な問題です。教科書レベルの基本的な知識を身につけ、複数の資料の中から解答に必要な情報を素早く読み取る練習をしておきましょう。
【大問2】
指定された字数でわかりやすくまとめる表現力が必要とされる問題です。自分の意見に限らず、書くべき内容を整理してわかりやすい文章にする力を伸ばしておきましょう。
おすすめの学習法
適性検査Ⅰでは、伝えたいことをわかりやすくまとめて書く表現力が必要とされます。
文章や資料を適切に読み取り、簡潔に文章でまとめる練習をしっかりしておくとよいでしょう。
また、時間内に問題を解くために、情報を素早く読み取る練習を積むことも大切です。
問題ごとに、おすすめの学習法を紹介しますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査Ⅰ
【大問1】
複数の資料から読み取った情報を、自分の知識と組み合わせて考える問題に取り組むとよいでしょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生9月号では、教科基礎力の確認と、資料から情報を読み取って自分の知識と結びつける演習を行います。
【大問2】
読み取った内容など作文に必要なポイントをまとめ、全体の構成のメモをつくる練習をしましょう。
そのメモをもとに指定の字数に合わせて作文することで、だれが読んでも論理的にわかりやすい文章を作ることができます。