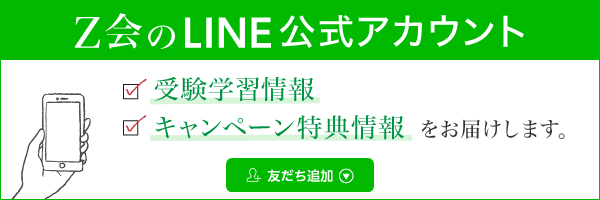制度が変更された大学入試とともに、高校入試も、単なる知識を問う問題から「思考力」「判断力」「表現力」を問う問題に変わってきています。特に、難関校をめざす場合はしっかりと情報収集を行い、対策をする必要があります。
今回の記事では、近年の公立高校入試(英数国)の出題傾向を、教科ごとに3つのポイントに絞って解説します。高校入試対策にお役立てください。
教科ごとの3つのポイント
英語
ポイント1:図表・資料読み取り問題の増加
学習指導要領で「資料の読み取り」が重点化されたためか、英文と一緒にグラフや図表などの資料を読み取る問題が増えています。資料の項目もすべて英語という場合がほとんどですので、読解スピードが重要になります。
ポイント2:自由英作文の出題は根強い
与えられたテーマに対して自分の意見や経験を述べる自由英作文の出題が、多くの都道府県で見られます。単に英文を書くだけでなく、採点者にわかりやすいように説明する力も必要です。英語での論の展開の仕方を身につけておくとよいでしょう。
ポイント3:リスニング問題の配点は増加傾向に
近年、リスニング問題の配点が高くなる傾向があります。英語を聞き取る力をつけるには、日頃から英語を聞く機会を増やすことに加え、実戦的な問題にも取り組んで、要点をつかんだり、効果的なメモを取る練習を積んだりしておくことが大切です。
数学
ポイント1:「資料問題」がバラエティに富んだ出題に
現行の学習指導要領から指導内容に加わった単元で、ここ数年の傾向として、問題の設定に工夫をこらしたものが多くなってきています。また、資料を使って説明をさせる問題も増えてきています。
ポイント2:数学で長文問題?
あらゆる問題において、問題文の長文化がここ数年の傾向として顕著です。高校入試は時間が限られているため、じっくり読んで問題を解くことはできません。数学においても速読が必要といっても過言ではありません。
ポイント3:記述問題イコール証明問題ではない!
ここ数年、「理由を書く」「間違いを述べる」などといった証明問題以外の記述問題が増加しています。数学でも、他人に自分の考えを伝える「表現力・記述力」が不可欠になってきていると言えるでしょう。
国語
ポイント1:幅広い分野から出題される
大問数が多く、知識・読解・作文・コミュニケーションに関するものなど、幅広い国語の力が試されます。偏りなくバランスよく勉強すること、速く読んで問題に答えられるように練習することが必要です。
ポイント2:複数の文章、図表や資料を読み取る問題の増加
本文にあわせて、図表・文字資料・対話文などを提示する出題が増えています。提示されたものどうしの関連性をとらえ、設問の求めに応じて必要な要素を抜き出すことが必要です。情報を整理し、すばやく対応する力が求められています。
ポイント3:文章や資料の読み取りを踏まえて書く作文問題の増加
文章や資料などを読み、与えられたテーマで〈自分の考え〉を書く作文問題が増えています。筆者の主張や資料が示す内容を理解したうえで、自分の意見を展開する必要があり、思考力が問われる出題といえます。
期間限定のお知らせ
自信をもって新学年を迎えよう!新中学1~3年生向け『春の新学年スタート応援キャンペーン』実施中!
▼キャンペーンの詳細はこちら
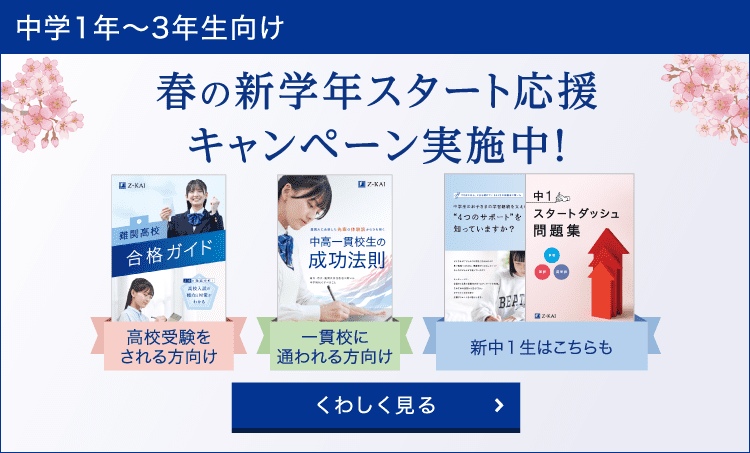
※本記事の内容やZ会のサービスは、投稿日時点の情報に基づいて執筆しています。
友だち追加でお役立ち情報を配信中!