「キャンパスレポーターに聞く 学び・大学生活の極意」2025年9月
様々な授業の中から、自分の興味関心に合ったものを選んで学べることも大学の魅力の一つ。その中でも、キャンパスレポーターたちが特に楽しみにしているのはどのような授業なのでしょうか?
ぜひこの記事を読んで、大学での学びをイメージしてみてくださいね。

▲軽井沢へゼミ合宿に行ったときに、ゼミが同じ友達と自然を感じながら撮った1枚です。
私の大学では、1年生から導入演習という科目でゼミ活動を行います。私は死刑制度の存廃や合憲・違憲について仲間とともに調査し、発表を行うゼミに所属しています。このゼミでは、合宿やグループワークで100分間の発表準備を行い、貴重な経験を積んでいます。また、春学期の終わりには大学内の法廷演習室でディベートも経験しました。法学を学ぶ学生として、理論と実践を結びつける機会が豊富にあり、日々充実した学びを得ています。ゼミ活動を通じて、法的思考力や議論のスキルを高めることができ、今後の学びに大いに役立つと感じています。本格的なゼミ活動は3年生から始まりますが、今からとても楽しみです。

▲同窓会誌のコピーです。色がレトロで時代を感じます。
私が今いちばん楽しみにしている授業は日本近現代史のゼミです。ゼミでは、約100年前の東京女子大学の同窓会誌を読んでいます。旧字体や筆者の置かれていた状況を読み解くのは難しいですが、わかったときの達成感は大きいです!
さらに、この授業は、同窓会に所属しているOGの方が授業を聴講しに来てくださいます。授業担当の先生も東京女子大学出身です。授業を通じて、先生方、OGの方から昔の東京女子大学を知ることができるため、毎週とても楽しみにしています。
授業を通じて、多くの同窓会誌を読むことになるので、研究を行ううえで必要なデータベースの使い方や、正しい論文の読み方、キーワードの見つけ方がわかります。内容はやや難しいですが、歴史学のおもしろさが詰まった授業です!

▲この授業の試験の準備をした日の、大学図書館です。
私が今いちばん楽しみにしているのは、一般教養科目の『アラビア語圏地域文化論』という授業です。この授業では、エジプト・シリアといった国々の映画を鑑賞しながら、イスラームの文化や慣習、内戦や宗教対立の現状を分析します。なじみの少ないアラブ圏について学ぶことは非常におもしろく、自分の偏見や先入観に気づくことも多いです。また、この授業は映画という媒体そのものに惹かれるきっかけにもなり、自分の世界が大きく広がったことを実感しています。大学の一般教養は、所属学部に関係なく、個人の純粋な興味に基づいてさまざまな分野を学ぶことができる貴重な機会です。あえて興味のなかった分野に挑戦してみると、思いがけない視点や関心が生まれることもあります。大学ならではの学びの魅力だと思います!
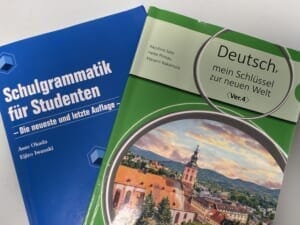
▲ドイツ語の授業で用いていた教科書2冊です。気に入っているのでこれからも何回も読みたいと思っています。
左:『岡田・岩﨑ドイツ文法』 岡田 朝雄 ・岩﨑 英二郎 著 朝日出版社
右:『Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt Ver.4』 佐藤 和弘・H ピナウ・中村 雅美 著 郁文堂
私は所属している学科の授業はもちろん楽しみにしていますが、第2外国語の授業も楽しみにしています。大学によって選べる言語は異なりますが、好きな言語を選択することができることが大学らしいなと思います。私はドイツ語を勉強していて、大学1年生の前期には文法の授業とグローバル理解という授業がありました。アルファベットを使うため英語と似ていますが、発音が異なったり、実は日本語と似ているところもあったりします! グローバル理解の授業では、ドイツ語のレシピを読んでみたり、ドイツの大学を調べてみたり、ドイツ旅行計画を立ててみたりし、とても楽しくドイツについて学べました。お金をためて、大学生のうちにドイツに行ってみたいと思っています!!

