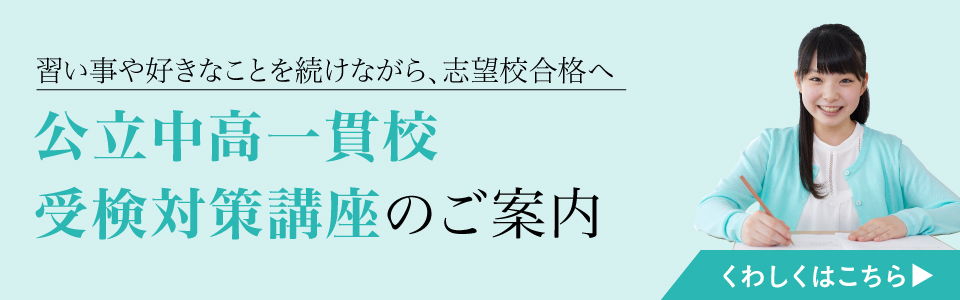出題校
愛知県の中高一貫校では、愛知県の共通問題を使用して、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共通=愛知県共通問題、独自=学校独自の問題)
Ⅰ1⃣ |
Ⅰ2⃣ |
Ⅰ3⃣ |
Ⅱ1⃣ |
Ⅱ2⃣ |
Ⅱ3⃣ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県立明和高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立津島高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立半田高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立刈谷高等学校附属中学校 |
Ⅰ1⃣ |
Ⅰ2⃣ |
Ⅰ3⃣ |
Ⅱ1⃣ |
Ⅱ2⃣ |
Ⅱ3⃣ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県立明和高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立津島高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立半田高等学校附属中学校 | ||||||
| 愛知県立刈谷高等学校附属中学校 |
全体的な傾向
適性検査では難しい問題が多く出る傾向がありますが、愛知県では、小学校で習う基礎的な知識が問われる問題も多く出題されました。
また、音楽や家庭科といった副教科の知識が必要な問題も出題されました。
適性検査Ⅰ、Ⅱともに大問3問構成で、すべて選択問題でした。
選択肢の数が多いので、当て推量で答えて正解することは少ないと考えられます。
大問ごとに1つの大きなテーマが設定され、その中でさまざまな教科の問題が出題されていました。
国語、算数、理科、社会はまんべんなく出題されていたため、苦手な教科をかかえたままだと、大量失点してしまうおそれがあります。
試験時間に対して問題量が多いため、問題文から情報を読み取る正確さだけでなくスピードも求められます。
問題を少し解いてみて時間がかかりそうだなと思った問題は、思い切って後回しにしてしまうのも一つの手です。
問題ごとの分析
※「ネットあいち」のサイトに移動します。移動先は予告なしに内容の変更または削除などがされる場合があります。
適性検査 Ⅰ(45分)
共通問題(国語・社会・音楽分野)
〇テーマ
年中行事
〇内容
年中行事をテーマに、平安時代の文化、各月の年中行事、楽譜の中に入るべき音符、古文とその訳の内容の正しい読み取り、長文とそのまとめとしての短文の正しい読み取りの問題が出題された。
◆概要
(1)
7つの選択肢の中から平安時代の文化について書かれたものを2つ選ぶ問題。
選択肢の内容は縄文時代~江戸時代までさまざまであり、各時代の文化についての正しい知識が求められています。
(2)
1月~12月までの年中行事を記した表の中の、2月・3月・7月・9月をうめる問題。
選択肢も4つで、ダミーの選択肢がないので、必ず全問正解すべき問題です。
(3)①
楽譜の中に2つある空欄を正しい音符で埋める問題。
国語、算数、理科、社会だけではなく、小学校で習うことすべてが試されています。
(3)②
枕草子とその現代語訳を読み、その内容に合う資料を選ぶ問題。
「葺く」という言葉の意味を知っているかどうかがポイントです。
(4)
年中行事について書かれた長文とそのまとめとしての短文を読み、短文についての説明として適当ではないものを4つの選択肢から選ぶ問題です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(4)
長文読解だけでなく、そのまとめとしての短文や、短文についての選択肢といったすべてに対する正しい読み取りが求められています。
まず、長文について、形式段落ごとの内容をおさえます。主張にあたる段落なのか、例示にあたる段落なのかを区別することがポイントです。
つぎに、短文の一文一文について、長文のどの形式段落をふまえて書かれているのかをおさえ、長文をどう再構成しているのかをつかみます。
短文のほうに、下線と長文の形式段落番号を付していくとわかりやすいでしょう。
最後に、選択肢それぞれについて、読点(「、」)で区切られた部分ごとに、短文の説明として正しいかを判断していきます。
そうすると、選択肢(エ)の「全ての段落から、筆者の考えが述べられている文をそれぞれぬき出すことで」という部分が誤りだとわかるでしょう。
共通問題(理科・算数・国語分野)
〇テーマ
メダカの飼育
〇内容
メダカの飼育をテーマに、スイッチの入れ方のちがいによるえさ箱のかたむき、メダカの体と誕生、立体の体積、外来生物がもともといる生物にあたえるえいきょうを考える問題が出題された。
◆概要
(1)
えさやり機の回路としくみを読み取り、結果の空欄にあてはまる記号と語句の組み合わせを答える問題です。
スイッチの入れ方によって、2つの乾電池が直列回路、または並列回路のどちらになるかを考える必要があります。
(2)
メダカの体のつくりや卵の成長についての問題です。
問われている内容はどれも小学校の理科で習う教科書レベルの知識なので、必ず正解しておきたい問題です。
(3)
水槽の中から、ぬかなければならない水の量を計算する問題です。
水槽をかたむけた状態の水の量を、三角柱の体積から求めることがポイントです。
(4)
会話文の空欄にあてはまる言葉を選ぶ問題です。
パンフレットにざっと目を通したうえで、会話の流れにそった言葉を選ぶ必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(1)
問題では〈えさやり機〉がテーマとなっていますが、その仕組みを理解していなくても問題を解くことができます。
適性検査は限られた時間の中で問題を解く必要があるので、問題を解くために必要な情報とそうでない情報を見極め、短時間で解けるようになることが重要です。
問題文が長いので、一見すると複雑そうな問題ですが、問われていることは、スイッチA~Cの入れ方によって、回路がどのようになるかということだけです。
まずはスイッチAのみを入れたときの回路を考えます。このとき電気の通り道をなぞっていくと、つながっている電池の個数や電池のつながり方を理解しやすいです。
同様に、スイッチB、Cをそれぞれ入れたとき、さらには、スイッチAとB、スイッチAとCを両方入れたときのかたむきを一つずつ調べます。
多数のパターンを調べる必要があるため、スイッチAを入れたときのかたむきを〇、それよりも大きいかたむきを◎として、結果を簡単な表にすると答えが一目でわかるうえ、見直しの時にも役立つでしょう。
共通問題(算数・国語・社会分野)
〇テーマ
リレー大会
〇内容
リレー大会をテーマに、レーンの位置や走る順番、合計タイムなどを求める問題、会話文の内容から適切な一文を当てはめる問題、日本の法律に関する知識をもとに考える問題が出題された。
◆概要
(1)
資料の説明を読んで、走るレーンのスタートラインの位置を考える問題で、ルールと円周の計算方法をふまえて解く必要があります。
(2)
資料や会話文、表であたえられた情報を整理して、走る順番や合計タイムを求める問題で、論理的思考力が求められる問題です。
(3)
バトンパスに関する会話文の穴うめ問題で、前後の文脈と選択肢の内容を照らし合わせながら解くことが大切です。
(4)
日本の法律ができるまでの内容として、適切な選択肢を選ぶ問題で、日本の法律に関する細かい知識が必要な問題です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(2)
資料や会話文であたえられた条件をもとに、6人の走る順番と合計タイムを考える問題です。
複数の条件を整理して論理的に考える力が求められます。
まず、「50m 走のタイムが最も速い人を第3走者に入れる」という条件と表1より、第3走者がきまります。
つぎに、残りの5人について、以下の条件を満たすように、走る順番の組み合わせを考えます。
つづいて、50m 走のタイムとテーク・オーバー・ゾーンに着目して、それぞれの人がどれくらいのきょりを走るかを考えます。
さいごに、50m 走のタイムをもとに、それぞれの区間を走るのに何秒かかるか求めて、合計します。
適性検査 Ⅱ(45分)
共通問題(国語・社会・家庭科分野)
〇テーマ
アサリをめぐる問題
〇内容
貝の一種であるアサリをテーマに、アサリの生態、料理の手順、学校から漁港までの経路、日本の漁業の課題など、幅広い事項について考える問題が出題された。
◆概要
(1)
アサリの生態などについて説明した文章をもとに、文法的知識や、内容を正確に読み取れているかを問う問題です。
テーマは理科的ですが、国語力を問うものといえます。
(2)
「アサリの酒蒸し」の作り方を記した文の並べかえ問題です。
家庭科の知識も少し必要ですが、それぞれの文が時系列的につながるように考えるという点では、国語力が重要となる問題です。
(3)
学校から漁港に行くために、さまざまな交通機関の時刻表を見ながら、問題文の条件に合わせて、到着時刻が早い経路、料金が安い経路を考える問題です。
(4)
日本の漁業に関する4種類の統計資料を参照して、日本の漁業の課題解決について答える問題です。
統計資料はそれほど複雑ではないため、必ず正解しておきたい問題です。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(4) B
日本の漁業の課題と、その解決についての発表原稿を読み、空欄に入る文を選ぶ問題です。
Bの空欄の直前に、「養しょく業の生産量を見ると」と書いてあることから、Bの空欄には、生産量に関する文が入ることがわかります。
であることから、正しいのは、「約98万tからあまり変わっていない」と書いてある選択肢(エ)となります。
養しょく業が「9%」が「23%」に増えていることをとらえて、「約2.5倍と大きく増えている」と書いてある選択肢がありますが(ウ)、これは生産量ではなく「割合」の変化について書いたものなので、誤りです。
問われているのが「生産量」なのか「割合」なのかなど、問題の条件をしっかり確認しましょう。
共通問題(理科・社会分野)
〇テーマ
国産ロケットの打ち上げ
〇内容
国産ロケットの打ち上げをテーマに、打ち上げる島の場所、酸素の特徴、酸素をふくむ気体を用いた実験、二酸化炭素の増加に関する資料の読み取りの問題が出題された。
◆概要
(1)
資料を参考に、ある島の場所を選ぶ問題です。
資料1は鉄砲伝来について書かれており、そこから答えを導くこともできますが、資料2の条件を読み解いて島の場所を特定することもできます。
(2)
酸素の説明として、正しい記述を選ぶ問題です。教科書レベルの知識なので、必ず正解しておきたい問題です。
(3)
実験結果からわかることを読み取る問題です。
いずれのびんも実験前後でちっ素の割合は変化しないこと、また、実験後の酸素が17%であることを表から読み取れれば、そこまで難しい問題ではありません。
(4) ①
三つのびんに入っている酸素の体積を求める問題です。
それぞれのびんのちっ素と酸素の体積の割合はわかっているので、一つ一つ計算します。
手順2で「びんの中に100mLは水が残るようにする」とあることに注意が必要です。
(4) ②
酸素1Lの重さを求め、空気と酸素の重さを比較する問題です。
酸素1Lの重さは、①で求めた酸素の体積と、実験前後の酸素ボンベの重さの差から求められます。
(5)
資料から読み取れる内容として最も適当なものを選ぶ問題です。
選択肢の内容と資料を見比べて、一つ一つ確認していく必要があります。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(5)
選択肢の内容を一つ一つ精査していく必要があるため、やや時間がかかる問題です。
選択肢を吟味するうえでのポイントは、以下の2つです。
共通問題(算数)
〇テーマ
プログラミング
〇内容
資料であたえられたルールのもと、プログラムが動くことができるマップについて考える問題が出題された。
◆概要
(1)
プログラムが動くことができるマップとして、あてはまるものを考える問題です。
あたえられたプログラムが、選択肢の各マップで動くことができるか、丁寧に調べることが大切です。
(2)
プログラムが動くことができるマップの縦と横のマス数の組み合わせを考える問題です。
実際に、プログラムによる移動の様子を書き出してみましょう。
(3)
プログラムが動くことができるマップの✕印が書かれたマスの数を考える問題です。
プログラムによる移動の様子を書き出す解き方だと、かなりの時間を要します。
◆問題ピックアップ!
※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します。
(3)
プログラムが動くことができるマップについて、✕印が書かれたマスの数を考える問題です。
(2)と同様に、プログラムによる移動の様子を一から書き出してみても解くことができますが、膨大な時間がかかってしまいます。
そこで、別の方針を考えると、資料の図 2 より、移動回数に 1 を加えた数は、✕印が書かれていないマスの数と等しいことがわかります。
(✕印が書かれたマスの数)=(全てのマスの数)-(✕印が書かれていないマスの数)で求まるので、移動回数に着目して✕印が書かれていないマスの数を求めることができれば、✕印が書かれたマスの数を計算で求めることができます。
このように、プログラムによる移動の様子を一から書き出さずに、移動回数を数えたうえで上記の関係式にあてはめて計算すると、より短い時間で解くことができます。
とくに伸ばしておきたい力
愛知県では、「5つの力」をバランスよく伸ばすことが求められますが、より伸ばしておきたい力として、教科基礎力、情報整理・運用力、論理的思考力が挙げられます。
・適性検査Ⅰ
【大問1】
主に教科基礎力が求められる問題です。
小学校で習うことはすべて、おろそかにしないようにしましょう。
【大問2】
教科基礎力が必要な問題です。
教科書の内容は完ぺきにしたうえで、あたえられた情報を効率的に処理する力も伸ばしていきましょう。
【大問3】
論理的思考力が求められる問題です。
複数の条件を整理しながら順序立てて考えていく力をつけましょう。
・適性検査Ⅱ
【大問1】
情報整理・運用力が必要な問題です。
表やグラフなどの統計資料から、何がいえるのかを素早く判断し、記述する練習を行いましょう。
【大問2】
教科基礎力、情報整理・運用力が必要な問題です。
グラフや表を正確に読み取る力をつけましょう。
【大問3】
論理的思考力が必要な問題です。
あたえられた条件を読みかえて、根気強く検討する力が必要です。
おすすめの学習法
まずは教科書の内容を完ぺきにしましょう。適性検査Ⅰでは、基礎的な知識が問われる問題が、全体の約3分の1をしめていました。
また、適性検査型の出題に慣れ、解き方を身につけておく必要があります。そのためには、適性検査型の問題にたくさん当たっておくことが大切です。
問題ごとに、おすすめの学習法を紹介しますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査Ⅰ
【大問1】
小学校で習うことすべてについて、知識にぬけやモレがないかをチェックしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座では、小学校で学習する教科知識を土台にした、思考力や分析力を試される問題に取り組みます。
【大問2】
教科書レベルの知識をしっかり身につけたうえで、それらを応用して考える練習をしていきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生8月号や6年生4月号では、教科書で習ったことを応用して考える問題に取り組みます。
【大問3】
あたえられた条件をもとにひとつずつ順を追って考えていき、答えにたどり着く練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、条件からわかるところからひとつずつ整理して、答えにせまっていく問題に取り組みます。
・適性検査Ⅱ
【大問1】
統計資料についての正誤問題や記述問題を、数多く解くようにしましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、さまざまな分野の統計資料を読み取り、記述する問題に取り組みます。
【大問2】
問題であたえられた実験結果や資料を素早くかつ正確に読み解く練習をしましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生10月号や6年生6月号では、グラフや表を読み取る問題に取り組みます。
【大問3】
複数の資料から必要な情報を読み取る練習や、表などを利用して順を追って考える練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生9月号では、複数の資料から読み取った情報をもとに、移動経路を考える問題にちょうせんします。