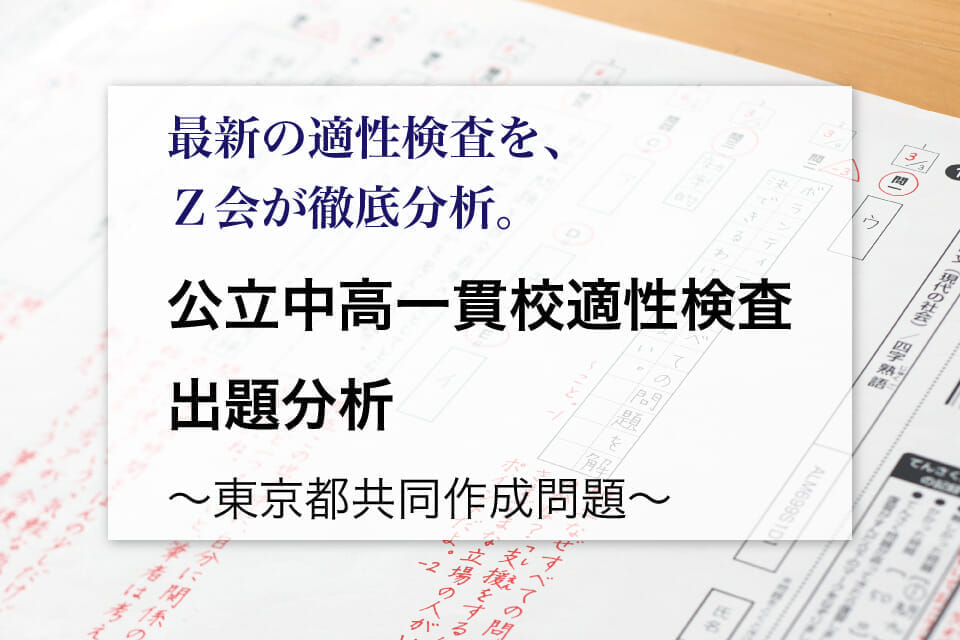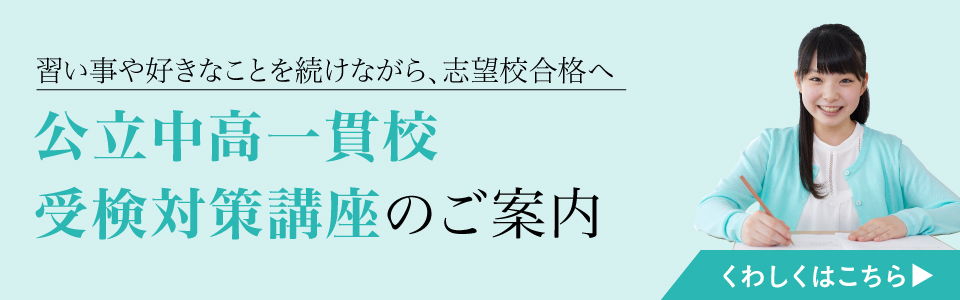出題校
東京都立の中高一貫校で出題される適性検査には、東京都の共同作成問題と、学校独自の問題があります。 適性検査Ⅲを実施する学校では全て、学校独自の問題が出ます。
(共同=東京都共同作成問題、独自=学校独自の問題)
| 令和5年度 出題情報 | 適性検査Ⅰ | 適性検査Ⅱ1⃣ | 適性検査Ⅱ2⃣ | 適性検査Ⅱ3⃣ | 適性検査Ⅲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜修館 中等教育学校 | 独自 | 独自 | 共同 | 共同 | 実施なし |
| 都立大泉 高等学校 附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 小石川 中等教育学校 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 |
| 立川国際 中等教育学校(※) | ー | ー | ー | ー | 実施なし |
| 都立白鷗 高等学校附属中学校 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 都立富士 高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 三鷹 中等教育学校(※) | ー | ー | ー | ー | 実施なし |
| 南多摩 中等教育学校 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | 実施なし |
| 都立武蔵 高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 |
| 都立両国 高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
※学校HPに令和5年の情報なし(2023/5/24時点)
| 令和5年度 出題情報 | 適性検査Ⅰ | 適性検査Ⅱ1⃣ | 適性検査Ⅱ2⃣ | 適性検査Ⅱ3⃣ | 適性検査Ⅲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜修館中等教育学校 | 独自 | 独自 | 共同 | 共同 | 実施なし |
| 都立大泉高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 小石川中等教育学校 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 |
| 立川国際中等教育学校(※) | ー | ー | ー | ー | 実施なし |
| 都立白鷗高等学校附属中学校 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 都立富士高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
| 三鷹中等教育学校(※) | ー | ー | ー | ー | 実施なし |
| 南多摩中等教育学校 | 独自 | 共同 | 共同 | 共同 | 実施なし |
| 都立武蔵高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 独自 | 共同 | 独自 |
| 都立両国高等学校附属中学校 | 共同 | 共同 | 共同 | 共同 | 独自 |
※学校HPに令和5年の情報なし(2023/5/24時点)
共同作成問題の全体的な傾向
問題の構成について、前年度からの大きな変化はありませんでした。
◆適性検査Ⅰ
例年通り、読解問題と作文が出題されました。 作文は2つの文章から読み取った内容と自分の考えを適切に関連付けて書くことが重要でした。
◆適性検査Ⅱ
3問構成で、大問1は速さと場合分けの問題、大問2は日本の産業に関する問題、大問3は水の吸収に関する問題が出題されました。
問題ごとの分析
適性検査Ⅰ(45分)
共同作成問題(国語分野)
〇出典 文章1 遠藤敏明「〈自然と生きる〉木でつくろう 手でつくろう」(一部改変)による 文章2 田口幹人「なぜ若い時に本を読むことが必要なのだろう」による
〇内容 2つの文章の読み取り。作文(400字程度)。
◆概要
〔問題1〕 文章1の傍線部について説明した文章の空欄に当てはまる言葉を本文中から書きぬく問題です。 あたえられた文章中の言葉に着目しながら、適切な言葉を探し出す必要があります。
〔問題2〕 文章2の傍線部の言葉について、指定された語句を用いて説明する問題です。 傍線部の前後の言葉に注目しながら、条件に従って自分の言葉でまとめましょう。
〔問題3〕 文章1、文章2の読解した内容をふまえて、これからの学校生活でどのように学んでいこうと思うかということについて、400~440字で作文する問題です。 あたえられた条件に沿ったわかりやすい文章を書くことが重要です。
◆問題ピックアップ!
(差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します)
〔問題3〕 これからの学校生活でどのように学んでいこうと思うかという課題に対して、2つの文章の内容や共通する考え方をふまえて自分の考えを400~440字以内で書く問題です。 昨年に続き段落構成の条件は無く、比較的自由度は高かったといえるでしょう。 また、テーマも自分の学校生活について考えるもので、書きやすいテーマだったといえますが、2つの文章から読み取った内容を上手に関連付けて書くことが重要な問題です。
適性検査Ⅱ(45分)
共同作成問題(算数分野)
〇テーマ 速さ、場合分け
〇内容 ブロックを運ぶロボットの動きや、電球とスイッチの関係を正しくとらえる
◆概要
〔問題1〕 ロボットの経路を考える問題です。 運んでいるブロックの個数によって速さが変わり、計算が複雑なので、どこから取りかかるべきか迷う人も多いでしょう。試しに経路を1つ決めて、かかる時間を計算したあと、条件に合うようにするにはどうしたらよいか考えていく必要があります。
〔問題2〕 電球とスイッチの関係をヒントをもとに見ぬく問題です。 あたえられたヒントだけでは電球とスイッチの関係が一通りに決まらないので、一通りに決まるよう自分でヒントを作る、というところに難しさがあります。
◆問題ピックアップ!
〔問題1〕 試しに経路を1つ決めて時間を計算することになりますが、やみくもに経路を決めてもうまくいきません。 試すべき経路をさっと見つけるセンスが問われ、まさに合否を分ける1問といえます。 経路の問題は適性検査でよく出題されており、ここに着目するべし!という「定石」があるものです。この問題では、次の点に気をつけて経路を考えるとよいでしょう。
① 道のりをなるべく短くする ② かかる時間をなるべく短くする ③ 変わった数値に注目する
論理的思考力・表現力が必要とされる問題です。指定された字数の中で、あたえられた文章から読み取った内容をわかりやすく伝える力と、自分の考えを伝えられる表現力をのばしておきましょう。 この問題では、「最短の道のりで」「最短の時間で」といった条件はありませんが、道のりや時間が長くなればそれだけ経路のパターンが増えるので、まずは、道のりや時間がなるべく短くなる経路を考えるとよいでしょう。 また、この問題ではかかる時間が48.8秒となることが条件です。ここで、「0.8秒」に注目すると、さらに経路がしぼられます。 こうしたポイントをもとに経路をしぼりこむことが大切です。難しく感じられるかもしれませんが、経路を題材にした問題にたくさん取り組めば、だんだん定石が見えてきます。
共同作成問題(社会分野)
〇テーマ 日本の産業
〇内容 日本の産業に関する資料の読み取り。6次産業化における利点を2つの立場から考える。
◆概要
〔問題1〕 産業別の就業者数に関する資料を見て、読み取れる変化の様子を説明する問題です。 資料から読み取れる情報を整理する力が必要となります。
〔問題2〕 「6次産業化」における利点を説明する問題です。 2つの事例に共通する利点を探すところに難しさがあります。
以上2問には、いくつかの項目から自らが選んだものについて説明するという共通点があります。 このような問題では、特徴が明確で書きやすいものを選ぶと、時間をかけずに解答をつくることができます。
◆問題ピックアップ!
〔問題2〕 それぞれの資料の事例から共通点を探し、2つの立場から説明するという、押さえるべき条件が多い問題です。 このような問題では、問題文の条件をしっかり整理したうえで解答を作成する必要があります。自分の解答がその条件を満たしているかに注意して、必ず見直しをしましょう。 また、教科の知識として「6次産業化」を理解していると、問題をスムーズに解くことができます。
共同作成問題(理科分野)
〇テーマ 水の吸収
〇内容 植物の種類や布の材質による水の吸収のちがいについて考える。
◆概要
身近な現象について実験で調べてみるという問題です。身近ではあるものの、その実験内容は初めて見る人も多いと思います。
〔問題1〕 (1)は水滴が転がりやすい葉と転がりにくい葉はどれかを考える問題で、(2)はそのちがいについて、どのように判断したのか説明する問題です。 実験結果や会話文の内容から、水滴が転がりやすい葉と転がりにくい葉を区別できるような特徴が何かを考える必要があります。
〔問題2〕 (1)は、ポリエステルのほうが木綿よりも水を多く吸収する理由を説明する問題で、(2)は、シャツの上にポリエステルのTシャツをかぶせるとシャツがよくかわく理由を答える問題です。 どちらも実験結果からわかることを整理し、問われていることを的確に説明する力が必要です。
◆問題ピックアップ!
〔問題2〕(1) 実験結果の写真から、水をより多く吸収するための特徴を読み取る必要があります。 問題文に「図3から考えられることと図4から考えられることをふまえて」とあるように、実験内容をしっかりと読み取り、それぞれの結果が何を意味しているのかを理解することがポイントです。 図3からは布の表面のつくりのちがい、図4からは布の厚みのちがいがそれぞれ読み取れます。それらを水の吸収と関連付けて考えることが重要です。 この問題は、ポリエステルや木綿の知識がなくても解くことはできますが、衣服やタオルなど身近なものと結び付けて考えることもできます。日ごろから身のまわりのものや現象に興味関心をもち、共通点を見出すことも大切です。
とくに伸ばしておきたい力
東京都立では、「5つの力」をバランスよく伸ばすことが求められますが、より伸ばしておきたい力として、情報整理・運用力、論理的思考力、表現力が挙げられます。
◆適性検査Ⅰ
論理的思考力・表現力が必要とされる問題です。 指定された字数の中で、あたえられた文章から読み取った内容をわかりやすく伝える力と、自分の考えを伝えられる表現力を伸ばしておきましょう。
◆適性検査Ⅱ 大問1
論理的思考力が必要とされる問題です。 問題全体の様子をとらえつつ、具体的に計算などをするのは論理的にしぼりこんだ最小限のパターンのみとすることで、効率的に取り組むことができます。
◆適性検査Ⅱ 大問2
情報整理・運用力が必要とされる問題です。 資料から読み取ったことをもとに、共通点や変化、特徴的な値に着目できるようにしましょう。
◆適性検査Ⅱ 大問3
情報整理・運用力や表現力が必要とされる問題です。 実験・観察の意図をくみ取ったうえで、結果から読み取れることを整理し、説明する力を身につけておきましょう。
おすすめの学習法
教科知識をそのまま問う問題は出題されません。適性検査型の出題に慣れ、解き方を身につけておく必要があります。 そのためには、適性検査型の問題にたくさん当たっておくことが大切です。 また、適性検査Ⅰだけでなく、適性検査Ⅱでも文章で説明することが求められます。そのため、簡潔に文章でまとめる練習、他者に伝える練習もしっかりしておくとよいでしょう。 問題ごとに、おすすめの学習法をしょうかいしますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
◆適性検査Ⅰ 読み取った内容や自分の意見の中で作文に必要なポイントをまとめ、全体の構成のメモをつくる練習をしましょう。 そのメモをもとに指定の字数に合わせて作文することで、だれが読んでも論理的にわかりやすい文章を作ることができます。
◆適性検査Ⅱ 大問1 条件に合う経路のパターンを手際よく検討する練習を積み、最適な経路の見当をさっとつけるためのセンスをみがきましょう。 Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生1月号では、遊園地やパビリオンを回るときに、条件に合う経路を考える問題に挑戦します。また、6年生6月号の「条件にしたがう」の回では、複雑な条件のもと答えを推理する問題に挑戦します。
◆適性検査Ⅱ 大問2 自分にとって説明しやすい項目を選んで解答するという問題形式に慣れておくことが必要です。 Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生7月号では、同じ問題形式で練習ができます。
◆適性検査Ⅱ 大問3 さまざまな実験・観察問題に取り組み、結果から考察する力を高めましょう。 また、身近なものや現象が問題のテーマとなることがあるので、普段の生活で疑問に思ったことは、理由や原理について調べてみるとよいでしょう。 Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生12月号、6年生8月号の「身のまわりの科学」の回では、身のまわりの現象がどのような原理によって起こるのかを考える問題に挑戦します。
Z会の公立中高一貫校受検対策をご紹介!
Z会では、自宅で合格に必要な力を最大限に磨き上げることができる、
「公立中高一貫校受検対策講座」をご用意。
Z会ならではの良質な問題・解説と、丁寧な添削指導で、合格レベルまで引き上げます。