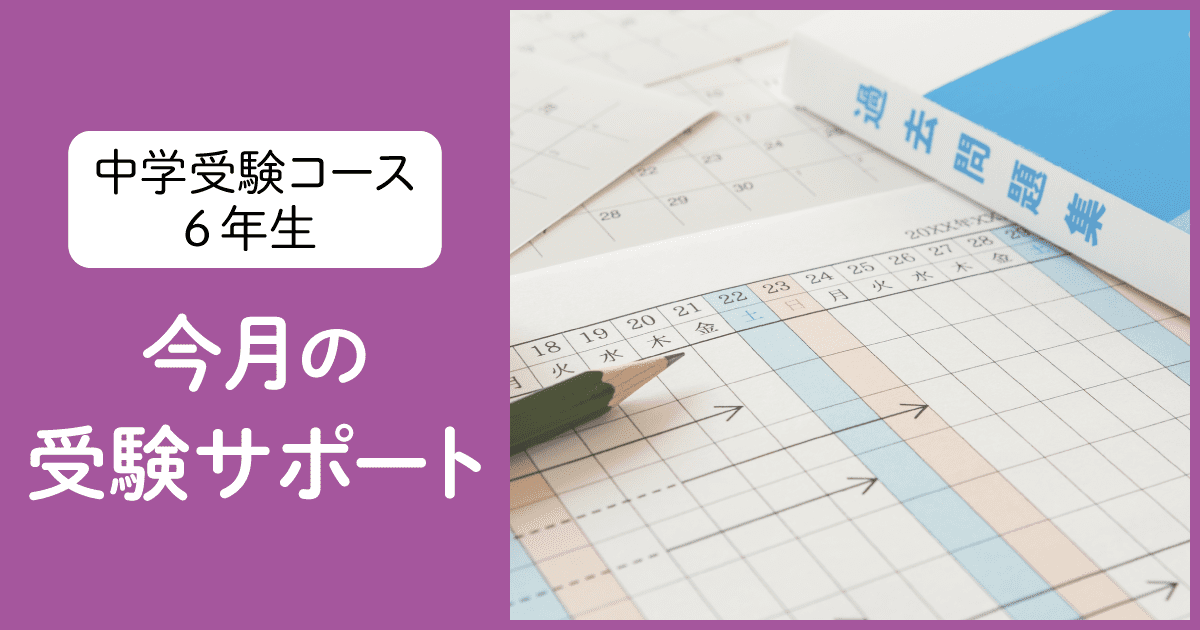4回にわたって合格を引き寄せる過去問活用法についてご紹介します。
過去問は入手しましたか?
第2回は、より効率的に合格に近づくための「出題傾向」のチェック方法についてお伝えします。出題傾向をチェックすると、今後お子さまが伸ばすべき力が見えてきます。
過去問攻略で合格をつかむ!中学受験「過去問活用法」 全4回
- ① 【中学受験】過去問はいつ・どう選ぶ?合格を引き寄せる過去問活用法
- ② 【中学受験】過去問から「合格に必要な力」を見抜く!効率的な出題傾向分析 ←本記事
- ③ 【中学受験】過去問の「解き方」は時期で変わる!合格力アップを目指す戦略 8月28日(木)更新予定
- ④ 【中学受験】学校説明会を「過去問攻略」に活かす!情報収集で差をつける 9月11日(木)更新予定
出題傾向チェックでわかる、お子さまに必要な力

 選択式の問題が多い
選択式の問題が多い
 語句を問われる問題が多い
語句を問われる問題が多い
 記述問題など、文章をたくさん書かせる問題が多い
記述問題など、文章をたくさん書かせる問題が多い
選択式の問題や、基本的な語句を問われる出題が多い学校では、比較的得点しやすい反面、合格最低点が高めになる傾向があります。抜け、漏れがあると、大きく失点してしまう可能性があるので、各教科まんべんなく基本事項を身につけておく必要があります。また、選択問題は「○○でないものを選びなさい」といったようなまちがえやすい問われ方をすることもあるので、問題文を丁寧に読むようにしましょう。
一方で、複数の分野の知識を組み合わせて考えたり、習ったことに自分の考えを加えて表現させたりするような記述中心の問題が多い学校は、合格最低点が低くなりがちです。こういった発展的な問題が多い学校に対しては、とにかく少しでも多く得点できるよう、ポイントを漏らさず書くための練習が必要です。
公式Webサイトで入試結果を公表している中学校の多くが合格最低点も公表していますので、実際に過去問題に取り組む前に「何割できていればよいのか」という点を調べておくとよいでしょう。
 長い文章を読んでから答える問題が多い
長い文章を読んでから答える問題が多い
 グラフや図などを使って答える問題が多い
グラフや図などを使って答える問題が多い
理科や社会で見られる長い文章を読んでから答える問題や、グラフや図を使って答えさせる問題は、文章やグラフ、図など、与えられた資料・題材を正確に読み取り、正解につながるヒントを探すことが求められます。
 途中の式や考えた過程などを書き残すよう指示があることが多い
途中の式や考えた過程などを書き残すよう指示があることが多い
 答えだけを書く問題が多い
答えだけを書く問題が多い
途中式を要求される場合には、採点者に伝わるように考えた過程を示す力や、答えにたどりつけなくてもわかるところまで書く力も必要です。答えだけを書く形式の場合には、時間に対して問題数が多いことがあるので、確実に解答できる問題を見分け、単位や漢字など、細かいミスをしないように気をつけながら限られた時間内に正確に解答する力が求められます。
 Z会のカリキュラムにある単元のなかで、まったく出題されていない内容がある
Z会のカリキュラムにある単元のなかで、まったく出題されていない内容がある
中学受験コースで学習する内容のなかには、出題する学校が非常に限られている単元があります。国語であれば文学史や短歌、算数であれば統計分野などは、ほかの学習内容と関係する部分も少ないため、例年の傾向から出題されないだろうと判断できる場合は取り組む優先順位を大幅に下げてもいいでしょう。
社会の時事問題についても同様で、例年どの程度出題されているかが今後の対策にかかわります。
8月が終了したら、過去問題を使った「実戦演習」にスイッチ!
夏の学習は、うまく進められていますか。今までの復習不足を実感し、「過去問題に取り組むのはもう少しあとにしよう」と判断されたご家庭もあるかもしれません。ただ、秋になってからは少しずつでもかまわないので、過去問題への取り組みを進めていただきたいと思います。
中学入試の範囲は膨大です。夏にしっかり復習していても、そこで確認した知識や解き方を模試や入試で自由自在に使いこなせるようになるには、もう少し時間をかけて演習を重ねる必要があります。
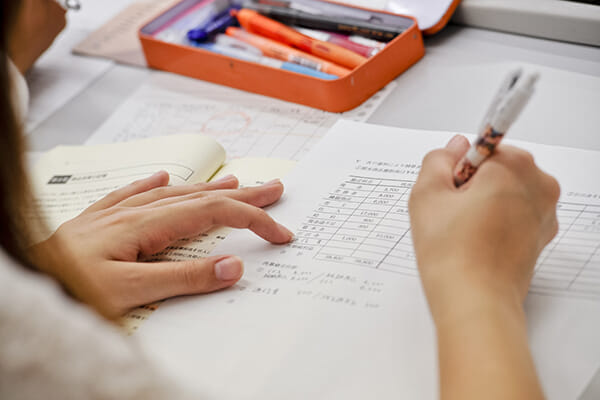
これから学習を進めるにあたっては、
1)実戦に近い演習を繰り返すこと
2)「この内容ができれば合格できる」という「ゴール」を見すえながら学習に臨むこと
が大切になるのですが、この両方の目的を担ってくれるのが過去問題なのです。
過去問題は、上手に使うとこれからの学習を進めていくうえで強力な味方となります。まず保護者の方が早めにチェックして、今後の学習内容を見直していきましょう。
入試必勝のための過去問題活用法・ここまでのまとめ
●過去問題集は特徴を理解して選ぼう
●夏のうちに過去問題の分析をしよう
●夏休みが終わったらいよいよ過去問題に本格的に取り組もう
次回の「今月の受験サポート」は8月28日(木)更新予定です。
過去問題について、夏以降、直前期までの時期に応じた具体的な取り組み方をご説明します。
中学受験コース6年生「今月の受験サポート」の記事一覧はこちら