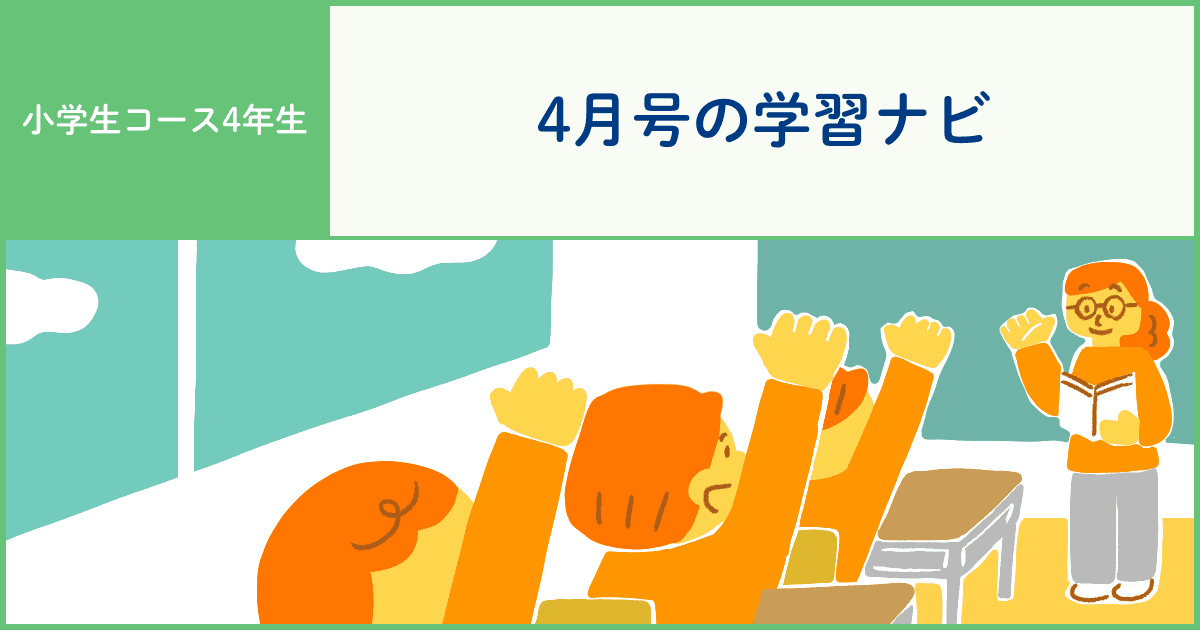今回は4年生の過ごし方と、主要4教科の重要な学習ポイントやおすすめ学習法をご紹介します。
目次
小学4年生とは?
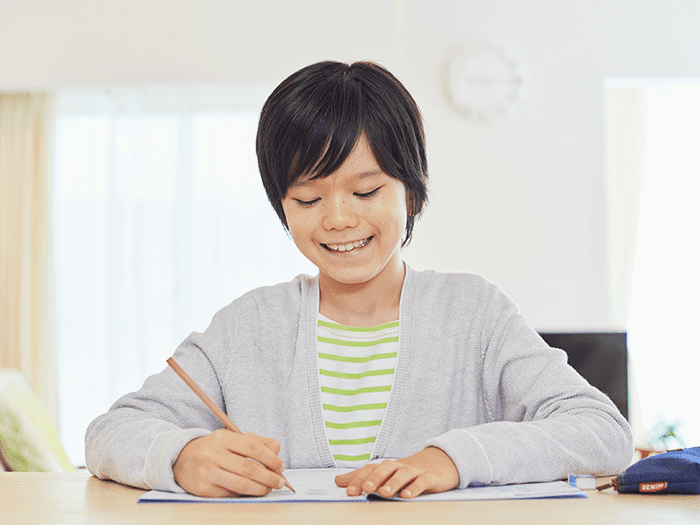
主要4教科の学習内容とアドバイス
- 文法
-
主語・述語・修飾語の関係や、接続語のはたらきなど、文や文章の構成を学びます。
文の組み立てを4年生のうちに理解しておくことで、今後複雑な文章を読み解く際の手助けになります。
おすすめ学習法
主語・述語・修飾語は5~6月号で、接続語は1~2月号で集中的に学習します。
問題演習を多く積むことで、知識の定着をはかります。
- 「段落の相互関係」の読解
-
4年生では文章の構成を意識して読むことが目標になるので、文章の部分的な読解から全体的な読解へとステップアップする必要があります。
そのためには、段落の相互関係を理解することが必須です。
おすすめ学習法
読解問題では、段落の関係を問う問題のほか、文章全体を俯瞰する必要のある問題を1年をとおして出題していきます。
問題文をしっかりと読む、『答えと考え方』を丁寧に読むなどじっくり取り組んでほしいと思います。
とくに「接続語」に注目して文章を読むことを心がけましょう。
- わり算の筆算(1けたでわるわり算、2けたのわり算)
- 学習が進むと、他の単元でもわり算の筆算ができることが当然として扱われます。
おすすめ学習法
教材では、
1.答えのたしかめ方
2.仮の商をたてて解く方法
について、繰り返し、丁寧に説明しています。まちがえた問題は、たとえうっかりミスだったとしても必ず解き直して、正確さ・速さを磨いていきましょう。
- 垂直・平行と四角形
- 5年生で学習する「平行四辺形の面積」や「図形の角」でも、ここで学習した知識を活用します。4年生のうちに、きちんと理解しておきたいところです。
おすすめ学習法
四角形の性質については、自分で平行四辺形やひし形などをかいて、本当にその性質が成り立つかを確認するようにしましょう。
実際に「かいて、調べて、考える」ことで、図形に対しての理解が深まります。
- 季節ごとの生き物や星のようす
- 4年生では、身近な自然の季節による移り変わりをとおして、観察の結果からその原因を考えたり、ものごとを関連づけたりできるようになることが目標です。
おすすめ学習法
『エブリスタディ』では、春、夏、秋、冬それぞれ学習回を設け、その季節の生き物や星のようすを、豊富な写真やイラストとともに紹介しています。
実際に外の様子を観察する機会をつくり、『エブリスタディ』を参考にしながら観察すると、より理解が深まるでしょう。
- 空気・水・金属の状態変化と熱
- 4年生では、身近な現象をとおして、実験の結果からその原因を考えたり、ものごとを関連づけたりできるようになることが目標です。

『エブリスタディ』では、実験の手順や結果を丁寧に説明しています。さらに、「ものの体積と力」と「もののあたたまり方」を関連づけて説明することで、より深い理解を促しています。
授業で実験が行われる際は、実験結果や気づいたことなどを書き留めておき、後で読み返すようにすると、内容が定着しやすくなります。
- 「県の様子」
- 4年生では、住んでいる都道府県へと学ぶ範囲が広がります。4年生の最初に、47都道府県と地方区分を学習し、様々な地図の読み取り方も学びます。
おすすめ学習法
4年生ではまず、47都道府県を正しく漢字で書けるようになることと、位置、8地方区分を覚えることが大切です。
小テストをくり返す学校も多いと聞きますので、目につくところに日本地図を貼ったり、白地図を活用したりして、正しく覚えるようにしましょう。
- 「くらしを支える・くらしを守る」
- 水道、ごみのしまつなどのしくみや、自然災害に備えた取り組みについて学びます。そのうえで、節水やリサイクル、家庭での災害への備えなど、自分たちにできることを考えていきます。
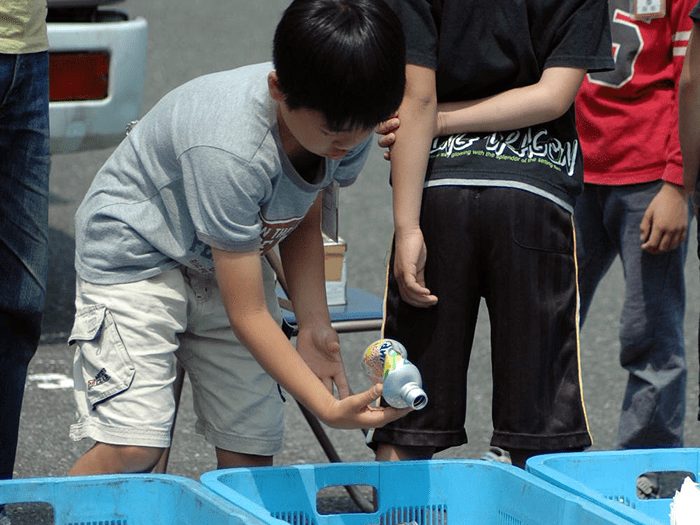
おすすめ学習法
県や市の取り組みだけでなく、住んでいる地域にはどのような取り組みがあるのか調べたり、市町村が作成したごみの分別ポスターやハザードマップなどを確認したりすると、より理解が深まります。
上記でご紹介した4年生の学習ポイントは、Z会でまんべんなく学習していれば確実に身につきます。まずは、Z会を使った学習サイクルに慣れていけるよう、保護者の方のサポートをお願いします。
次回の更新は4/23(水)です。「丸つけ」をテーマにご紹介予定です。ぜひご覧ください。