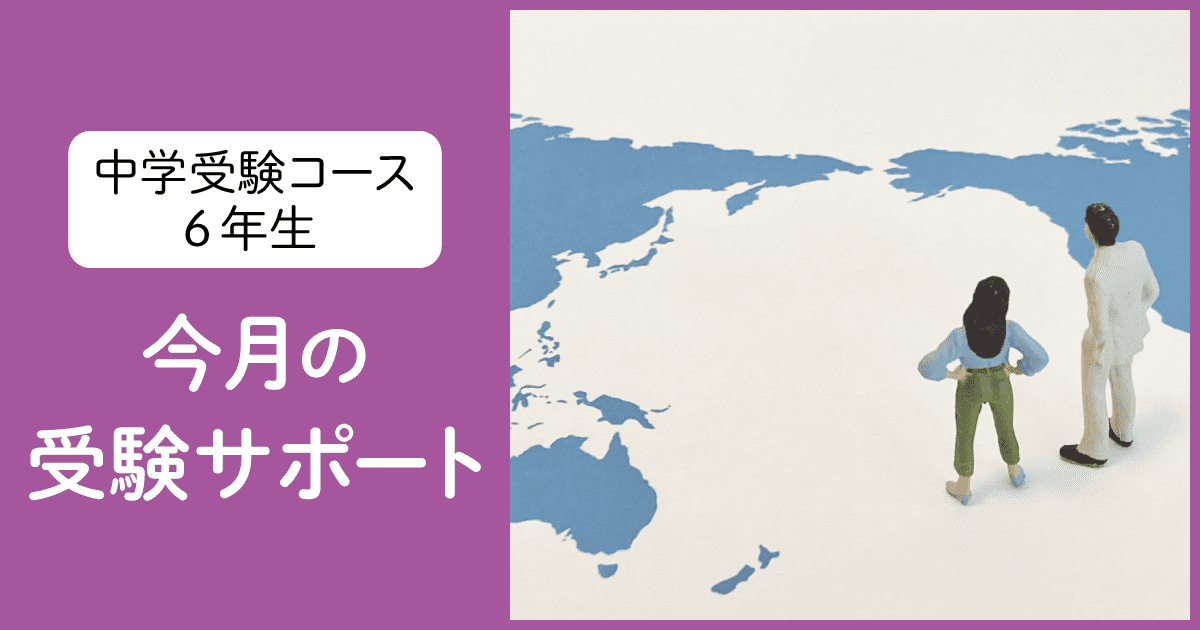入試において理科・社会で時事問題を出題する学校は多く、今後も出題が予想されます。受験直前にあわてることのないよう、ご家庭でのふだんの生活の中で今から時事問題対策をしていきましょう。
【理科】ニュースや新聞にふれよう!
ニュースを見たら復習を
時事問題に強くなるためには、まずは、ニュースにふれる習慣をつけることです。連日、大きく取り上げられているできごとほど、出題されやすいと考えてよいです。しっかりと目を通しておきましょう。そのとき、できごとのくわしい内容を理解することはもちろん大切ですが、そのできごとが理科のどの単元に対応するのか考えてみたり、時間があればその単元を復習したりすることが重要になります。
「なぜ復習が必要なの?」と思う方もいるかもしれません。入試の理科で時事問題が出題される場合、そのできごと自体を掘り下げる問題はめずらしく、むしろ、そのできごとに関連した理科の内容を問われることのほうが多いからです。
できごとに関連した知識を確認しよう
関連した内容の確認のしかたについて、2025年の天文現象を例に説明しましょう。
今年は9月8日に皆既月食が日本で観測できます。月食や日食は入試で出題されやすい話題です。月食や日食が起こる原理や、地球と月と太陽の大きさはどれくらいか等を確認しておくとよいでしょう。
また、過去の天文現象が入試で出題されることもありますので、大きな話題になったものは確認しておくとよいでしょう。天体については9月号で学習します。
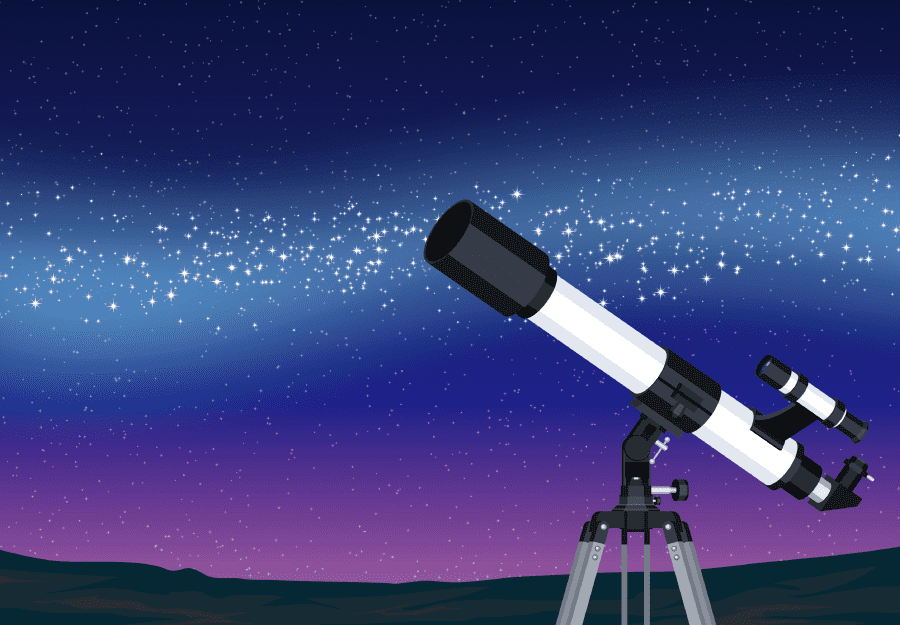
天文現象以外に、世界自然遺産、地震や火山噴火などの自然災害、マイクロプラスチックなどの環境問題、はやぶさ2のような探査機なども、理科の入試問題で取り上げられやすい時事問題です。ニュースに限らず、日々の生活や、博物館などに出かけたときに「なぜ?」と思ったことを調べていくと、ますます理科が楽しくなりますし、入試対策にも有効です。
(執筆:理科担当)
【社会】生活のなかには、社会の学習につながるものがたくさんあります
「時事問題」と聞くと、ニュースの内容そのものを問われるような問題を想像しがちです。実際そのような出題もありますが、実は、時事的な話題をもとにしながら社会科の一般的な知識を問う問題も少なくありません。
たとえば、2025年に参議院議員通常選挙が行われることに関連して、日本の選挙制度や国会のしくみについての出題が予想されます。また、歴史上の重要なできごとから節目となる年(例:2025年は第二次世界大戦が終結してから80年)には、そのできごとを軸にした出題が見られます。
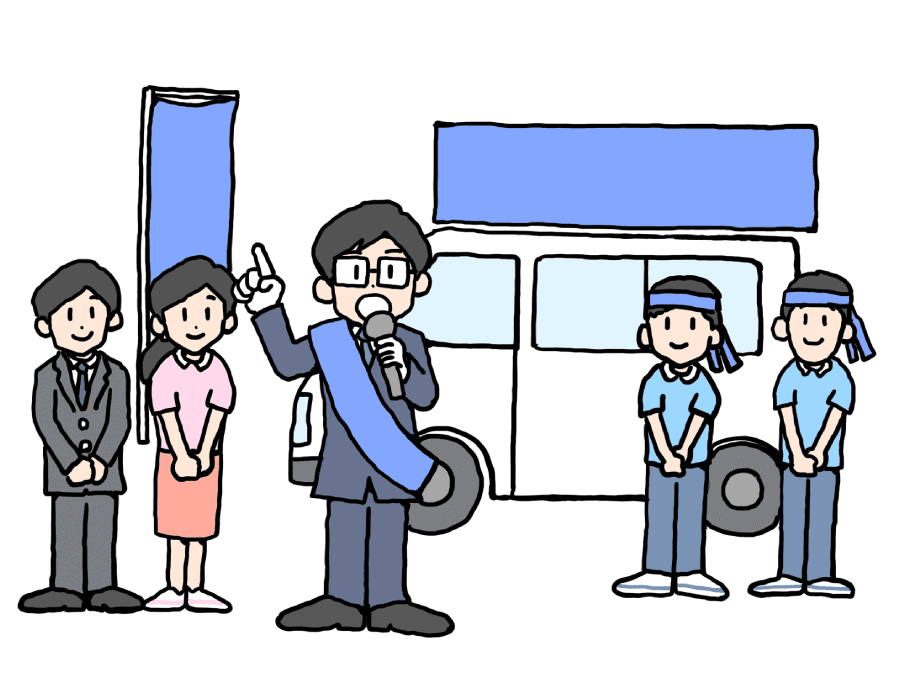
日々のニュースを見て逐一細かい知識を覚える必要はありませんが、どのような記事が新聞の一面で扱われているかを意識しておくことは時事問題対策に有効です。
政治や社会にまつわる話題は、ニュースでの扱いが大きく、多くの学校で出題されています。2025年度入試では、新紙幣の発行、佐渡島の金山の世界文化遺産登録、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)に関する出題が多く見られました。また、国外の話題では、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの軍事衝突、イギリスの政権交代やアメリカの大統領選挙なども出題されました。
公民の政治分野を学習し始めたのは6年生になってからですが、お子さまにとってはとっつきにくい分野です。早くから家庭で話題にするようにしておけば、「難しいけれどよく聞く言葉」が増えて、頭に残りやすくなるものです。お子さまと一緒に、ニュースや新聞などの報道に注目しながら、公民の知識も確実にしておきましょう。
ニュースを会話で取り上げるには
とはいえ、いざそういった話題についてお子さまと話をしてみようとしても、なかなか難しいものです。
そこで活用できるのが、小学生新聞や、ニュースを解説した子ども向けの雑誌です。これらは、大人でも興味深く読める記事がいろいろ載っていますので、あまりニュースなどにふれてこなかったご家庭は、お子さまに渡すだけではなく、まずは保護者の方がこういった話題や情報にふれることから始めましょう。各媒体のWebサイトでは、注目の話題の解説なども掲載されていることがありますので、それを見るだけでも参考になるはずです。下記「関連リンク」でご紹介しましたので、よろしければお子さまと一緒にご覧になってください。
また、気になるニュースについては、「あの話題はどうなったかな?」といったように、あとから追いかけて調べてみると、ニュースが変化することもよくわかり、より理解が深まるでしょう。
お子さまのニュースに対する興味・関心度合いや志望校の出題状況で、今後の対策方法は変わります。しかし、ご紹介したようなアイテムを上手に活用しながら、時事問題のテーマとして出題されやすい用語に慣れておくことや、自分なりにその問題について考えたり、ほかの人の意見を聞いたりすることが、のちの時事問題対策の基礎となり、大きな武器となるでしょう。
学習のきっかけは身近なところに
公民に限らず、地理・歴史を含めた社会科の学習全般にいえることですが、家庭や学校、地域などで見聞きする情報のなかには、社会科の学習につながるものがたくさんあります。
このことを保護者の方が意識なさっていると、よいタイミングでお子さまの知的好奇心を刺激することができますし、もちろん入試対策にも有効です。
1月号の教材では「社会時事関連」として時事問題対策を行う予定です。今のうちから、日ごろ目にするニュースやさまざまな情報から、意識的に社会科の学習につながるものを見つけ、お子さまと共有していってください。
(執筆:社会担当)
トータル指導プランの「月刊社会ニュース」
トータル指導プランの5・6年生社会をご受講の方には、身近な話題や時事問題を解説した「月刊社会ニュース」を毎月配信しています。Z会小学生アプリからご覧いただけます。
Z会おうち学習ナビ「ニュース検定にチャレンジ」
Z会おうち学習ナビでは、毎月1回「ニュース検定にチャレンジ」を更新しています。ニュース検定の問題に挑戦しながら、時事問題やニュースへのお子さまの興味関心を広げていくことから始めてみてはいかがでしょうか。
関連リンク
![]() 毎日小学生新聞
毎日小学生新聞
![]() 朝日小学生新聞
朝日小学生新聞
![]() 読売KODOMO新聞
読売KODOMO新聞
![]() 月刊「NEWSがわかる」
月刊「NEWSがわかる」
![]() 月刊「ジュニアエラ」
月刊「ジュニアエラ」
![]() 朝日新聞で学ぶ総合教材「今解き教室」
朝日新聞で学ぶ総合教材「今解き教室」
次回の「今月の受験サポート」は5月29日(木)更新予定です。
中学受験コース6年生学習Topicの記事一覧はこちら