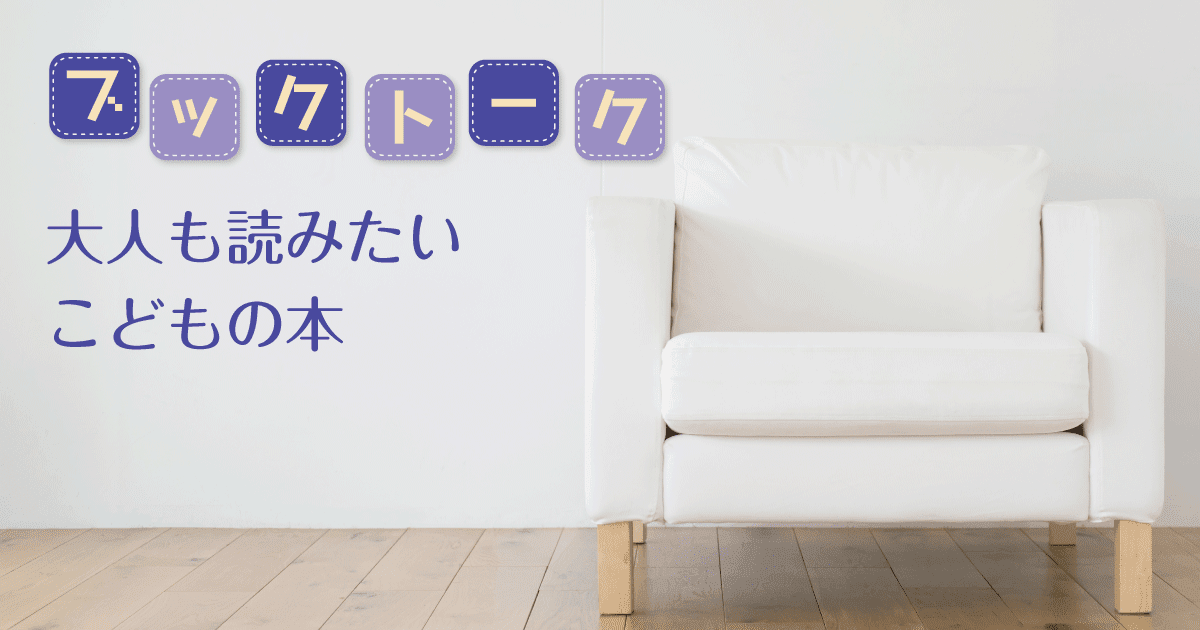世代を超えて読み継ぎたい、心に届く選りすぐりの子どもの本をご紹介いたします。
※本記事は、2021年5月13日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を再掲しています。
リズムで楽しむ昔話『ラン パン パン インドみんわ』

むかしむかしのインドのお話。クロドリのふうふが木のしげみに住んでいた。てい主のクロドリは、とてもいい声のもち主。
ある日のこと、王様が近くを通りかかった。
“あの声の主をつれてこい。わしの宮でんで鳴かせてみたい”
王様のめいれいで、家来たちが、クロドリをつかまえようとした。
ところが、大まちがい。つかまえたのは、にょうぼうのほう。
お話の冒頭部から歯切れよく軽快です。「いかりくるった」クロドリは、この後、完全武装で、「にょうぼう」を取り戻しに王宮を目指します。「ラン パン パン」と勇ましく太鼓を打ち鳴らしながら。道中、同様に王さまへの報復を望む者たちが次々に仲間に加わるのですが、その顔ぶれがまた奇妙です。なるほどと思えるのは「ネコ」だけで、アリの大群、木の枝、最後に名を連ねるのは、なんと「川」。こうしたメンバーが、クロドリの「耳のなか」に相次いで入りこんで待機するさまにも意表を突かれます。そして、いよいよのっぴきならない事態に陥ったクロドリの「耳のなか」。その満員御礼の様子を茶目っ気たっぷりに描きながら、一行は「ランパンパン ランパンパン ランパンパンパン」と進軍します……。
アルエゴとドウィ、二人の絵は、少々の毒気を孕(はら)みながらも朗らかで、この画家にしか出せない気ままで人懐こい画面を創りだしています。たとえば、王さまと戦う決意を固め、クロドリが行進を始めた冒頭部。黄色や橙色の不知なる植物がもりもりと生い茂る野山に青緑色のクジャクが数羽いて、クリーム色の小高い丘で太鼓を叩くクロドリをじっと見ています。「川」が仲間に加わる場面では、「川」で生きる魚や水鳥ごと大きくうねりながら、クロドリの「耳のなか」へと吸い込まれていくのですから、何ともシュールです。
「むかしむかしあるところに……」という日本民話の定型でしか昔話を捉えていなかった子どもたちは、この本に出合って驚き、さらにたくさんの他国の昔話を求めるでしょう。そして、王さまやお姫さま、勇者、妖精やトロルなどの立役者に触れ、さらに深いファンタジーの世界へと分け入っていくことになるのです。そういう意味で、こうした昔話絵本が果たす意味は大変大きいといえます。おもしろいお話なら、むろん出典など頓着しないものでしょうが、長い年月にわたって暗誦(あんしょう)に堪えてきた言葉のリズムは、弾むように読者を(聞き手を)、お話の舞台へと引き込むのです。
さて、幻獣も魔術師も登場しない『ランパンパン』。主人公は一貫して太鼓を叩いているだけなのに、ある種、壮大な展開を経て、ハッピーエンドを迎えます。軟体動物のようにフレキシブルに色や構図を転換させた絵が、この仇討ち話を、自由にのびやかに描きます。
吉田 真澄 (よしだ ますみ)
長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。