4月号では、最上級生としての過ごし方と、主要5教科のについて、6年次で登場する「重要な単元」についてご紹介します。
目次
小学6年生とは?
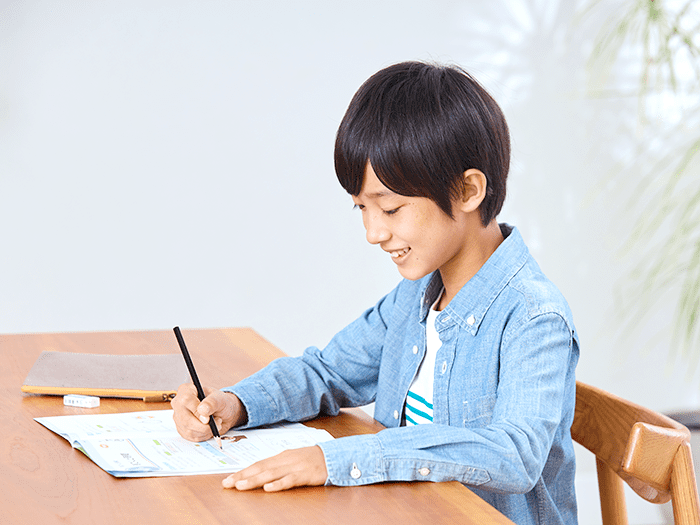
新学期スタート直後のこの時期から、「すきま時間を見つけて宿題やZ会をする」「スケジュールを立て、逆算して毎日の学習量を調整する」などといった経験を積んでいきましょう。その経験は、中学以降、お子さまを支える力となります。
なお今回は、主要5教科について、6年生で学ぶ重要ポイントとおすすめの学習法をご紹介しています。お子さまの学習サポートにお役立てください。
主要5教科の学習内容とアドバイス
- 敬語
- 小学校高学年の言葉の分野でもっともつまずきやすいのが「敬語」。
高校入試で頻出の重要単元ですので、6年生のうちに敬語の基礎を固めておきましょう。
おすすめ学習法
学校の授業やZ会の教材にプラスして、学校の先生や周囲の大人に対して敬語を使う場を設けてあげられるとよいですね。
電話や手紙などを通じて練習するのがおすすめです。
- 「因果関係」の読解
- 小学校6年間の集大成として、因果関係を軸に物事をとらえる論理的思考力が求められます。
説明文の「原因-結果」の関係や、物語の「できごと-心情-行動」のつながりを意識して読む必要があります。
おすすめ学習法
『答えと考え方』や「てんさく問題」への赤字指導では、各設問の解答について「なぜ、この答えになるのか」を丁寧に説明しています。
答え合わせにも丁寧に取り組み、解答の根拠を意識する習慣をつけることが何より大切になります。
- 文字と式
- 以前は、「文字と式」は中学校の学習内容でしたが、現在は一部を小学6年生で学習します。
中学校でスパイラル(反復)学習することで、つまずきを防ぎ、理解をスムーズにすることをねらいにしているためです。
中学以降の「数学」では、「文字式の計算」「1次方程式」「関数」など、文字式を自在に扱えることが基本になります。
おすすめ学習法
『エブリスタディ』では、文字式の扱いに慣れるために、問題に多種多様な場面を登場させています。
また、学校の教科書ではあまり扱われない問題でも、中学1年生の「1次方程式」に直結する応用問題は積極的に出題しています。
文字式を立てるときのコツは、
1.言葉を使った式を立てる
2.わからない数を文字でおく
の2ステップで考えることです。このコツを意識しながら学習しましょう。
- 比例
- 1個10円のお菓子をいくつも買うとき、買うお菓子の個数と合計の金額は比例の関係にあります。
このように、比例の関係を日常生活の中で探してみることで、算数への興味や理解をより深めることができます。
比例のようにともなって変わる2つの量の関係に注目することは、中学校で学習する「1次関数」「2乗に比例する関数」につながりますので、小学生のうちにマスターしておきましょう。
おすすめ学習法
比例の単元では、
- 比例の関係で成り立つ式 y=(きまった数)× x
- 比例のグラフ
を関連づけて理解することが大切です。比例の式の「きまった数」の求め方や、比例のグラフのかき方、特徴などを『エブリスタディ』で確かめておきましょう。
- 大地のつくり
- 日本は地震大国であり、同時に火山大国でもあります。天災に備えるためにも、地震や火山による大地の変化の知識は必須になります。
地層の堆積にかかる時間や火山灰の積もる範囲など、時間や空間のスケールが大きいことも特徴です。
おすすめ学習法
『エブリスタディ』では、地層や化石など多くの写真をもとにイメージをふくらませて説明しています。
身近な地域のハザードマップや、災害対策について調べてみると理解が深まります。
- 水溶液の性質
- 中学校で学ぶ化学分野の第一歩にあたる学習です。
耳慣れない物質(塩酸や水酸化ナトリウムなど)がどんどん出てきますので、ここで苦手意識をもたないようにしたいですね。

Z会では…
『エブリスタディ』では、水溶液に関する様々な実験について、たくさんの写真やイラストを用いて説明しています。
ふだんの生活のなかでも、サイダーや酢などいろいろな水溶液を目にする機会があるので、それぞれの性質に注目してみましょう。
- 公民
- 6年生になると、社会ではまず最初に政治全般について学習します。
「日本国憲法」の内容を学んだあとに、日本の国や地方の政治がどのように行われているかを勉強します。
また、歴史の学習が終わったあとには、世界のなかで日本がどのような役割を果たしているのかなど、国際関係についても勉強していきます。
おすすめ学習法
たとえばニュースを見たり、おうちの方と一緒に新聞を読んだりするなど、世の中への興味関心を広げるようにしましょう。
また、近代以降の日本の歴史の流れを知っておくと、大日本帝国憲法から日本国憲法への内容の変化をより深く理解することができます。
歴史まんがを読むなどして、第二次世界大戦前後の日本の大まかな歴史をつかんでおくことをおすすめします。
- 弥生時代の社会の変化
- 日本の歴史の流れのなかでもとくに重要です。むら同士の争いが行われ、くにができていく過程は教科書でも必出です。
昔の米づくりがどのように行われていたか、米づくりが当時の日本の社会にどのような影響を与えたかを理解できるかがポイントになります。

おすすめ学習法
『エブリスタディ』では、米づくりの流れやくにができる過程を写真やイラストを用いて解説しています。
毎号「今月のまとめ」に重要な単元の流れや語句がまとめられているので、必ずおさえましょう。
- 日本語と英語の語順の違い
- 英語は日本語とは大きく語順が異なります。
中学生になると「正確な英語で書いて伝える」ことが求められるので、小学生のうちに英文を「書き写す」練習をしながら、英語の語順に気づき慣れておくことが大切です。
おすすめ学習法
たとえばI play baseball.「私は野球をします。」という英文について、「聞く」ことや「言う」ことはできるのに、英作文となると日本語に引きずられてI baseball play.と書いてしまうことがあります。
学習した「音」をベースに「書く」練習を行うことが重要です。Z会の学習でも、音声とともに語順を意識しながら書くようにしましょう。
また、「てんさく問題」では、毎月、語順を理解して書けるかを問う出題をしています。
- 思い出を伝える「発表」―『過去』の表現
- 小学校の英語では、自分の体験を伝え、友だちの発表を聞くことをとおして、「行った」「見た」「食べた」など『過去』の表現を学習します。
おすすめ学習法
Z会では、自分のことを伝える練習をしたり、「発表」を想定した「てんさく問題」に取り組んだりすることで、中学での「スピーチ」の基礎を養うことができます。
似た表現を複数の月で扱いますので、go-went、see-saw のように暗記するのではなく、I went to~. という表現を丸ごと自然に覚えられます。
自分の体験を伝える手段として、自然と定着させることを目指しましょう。
上記でご紹介した6年生の学習ポイントは、Z会でまんべんなく学習していれば確実に身につきます。難しいと感じた単元は学校の授業で習ったあとでもよいので、必ず取り組むようにお声がけください。
次回の更新は4/23(水)です。「丸つけのポイント」についてお届け予定です。ぜひご覧ください。

