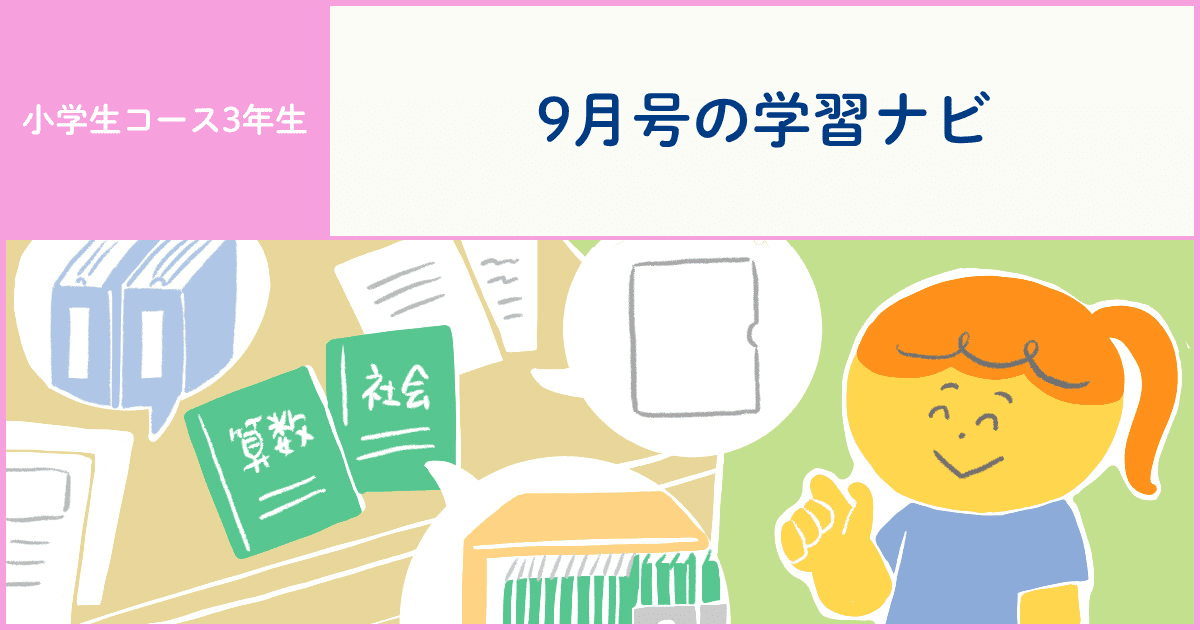目次
学習環境の整理ポイント
学習に取り組む前、あるいは取り組んでいる際に、お子さまが“ものを探している時間”が長いということはありませんか? 「宿題に取り組むことに集中してほしいのに、宿題で出されたプリントが埋もれて見つからない……」というようなことがよくあるようでしたら、一度お子さまと一緒に整理整頓の時間を設けるとよいでしょう。
ポイントとしては、「片づけなさい」と抽象的に声かけするのではなく、「『いつも使っているもの』と『使っていないもの』に分けてみよう」、あるいは「『大事にとっておきたいもの』と『それほど思い入れはないもの』に分けてみよう」というように、お子さまの「使用頻度」や「思い入れの強さ」で分類してみるのがおすすめです。
その後、「いつも使っているもの」をお子さまの手の届く範囲に置き、使用頻度が高くないものは出し入れしにくい机のいちばん下の引き出しに入れる、または思い切って捨ててしまいましょう。お子さまが「思い入れがあるもの」は常に見えるところに置くことでモチベーションアップにつながり、精神面での安定をもたらすこともあるかと思いますので、お子さまと一緒に置き場所を相談しながら整理整頓を進めていけるとよいですね。
ノート・プリント整理術
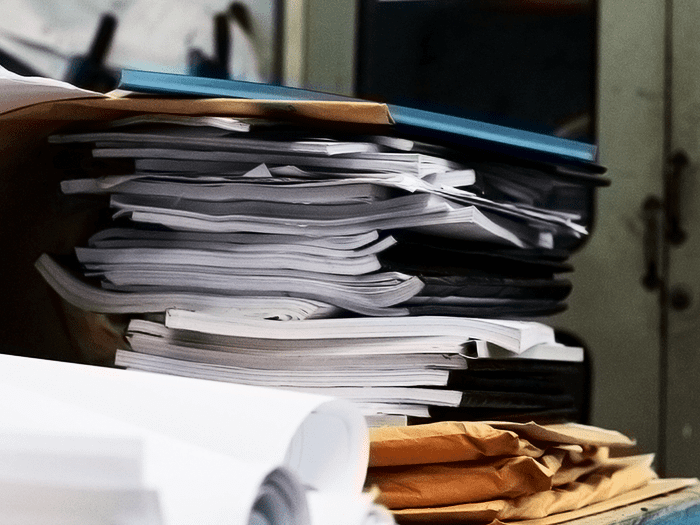
学校が始まってしばらく経つと、お子さまのノートやプリント類は、どうしても散らかってしまいがちです。ノートやプリント類は置き場所を定めて片づけることで、お子さまの家庭学習もはかどることでしょう。
“整理整頓は子どもの仕事”です。保護者の方が毎日片づけているご家庭もあるかもしれませんが、ルールを決めて、少しずつお子さまが自分でできるようにしていくとよいですね。
ここでは、お子さまが自分で整理整頓するためのアイデアをご紹介します。
ノートの整理術
❶ 学校のノートと家庭学習で使用するノートを分ける。
❷ 1の学校のノートは「使用中のノート」、「使い終わった今年のノート」、「前年度以前のノート」に分ける。
❸ 2の「使用中のノート」は、お子さまがいちばん取り出しやすい場所――たとえば“学習机の本棚のいちばん右”など――を常にしまう場所に定め、学校で使用しない日はそこに片づけるようにする。
❹ 2の「使い終わった今年のノート」と「前年度以前のノート」は、不要であれば捨ててしまい、いずれ使用するのであれば、学習の邪魔にならないようまとめてダンボールに入れるなどして保管する。
❺ 1の家庭学習で使用するノートは、一緒に使う教材類とひとまとめにしておく。
プリントの整理術
❶ 学校の宿題を入れるためのボックスまたはトレーを用意する。
❷ 保護者の方に渡さなくてはいけないプリント類を入れるためのボックスまたはトレーを用意する。または、“必ず保護者の方に手渡しする”というルールを決める。
❸ 1と2で用意したものを親子で決めた場所に設置する。
❹ 学校から帰ったら、1に宿題を、2に保護者の方向けプリントをすべて入れる。
❺ 終わった学校の宿題や、保護者の方から学校に持っていくように渡されたプリント類は、すぐにランドセルにしまうようにする。
後半期の学習も、Z会でばっちり!
今後の学習の土台となる部分を多く学習する3年生。Z会では今後の学習を見据えて教科書から一歩踏み込んだ発展的な問題を解く力まで身につけていきます。
10月号以降に学習する5教科の重要ポイントについて、下記の記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
新学期に向けて、お子さまと一緒にぜひ学習環境を見直してみてください。そして、お子さまが整理整頓できたらすかさず認めて、ほめることが継続への第一歩です。「自分はできる!」と前向きになれると、整理整頓が習慣になっていくでしょう。
次回は各教科の苦手になりやすいポイントと、その解決法についてご紹介します。9/24(水)の更新をお楽しみに!