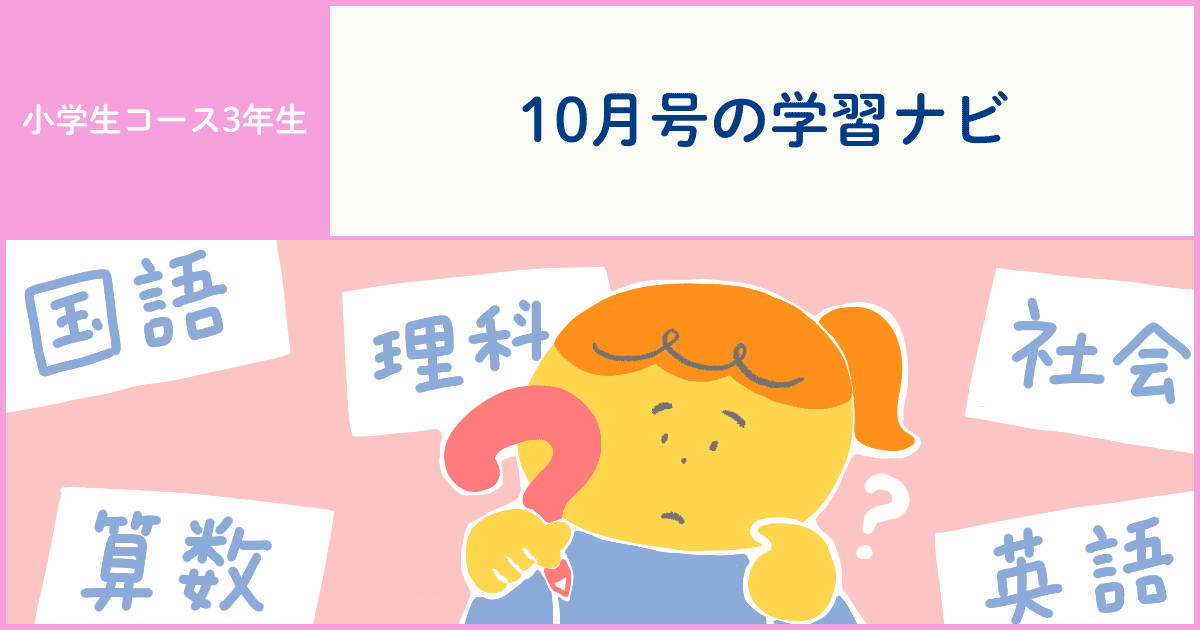目次
・国語:読解力をつけるためにはどうすればよいでしょうか。
・算数:ケアレスミスが多いのですが、どうすればミスが減るでしょうか。
・理科:どうやって学習すればよいかわかりません。
・社会:地図の読み取りに苦戦しています。
・英語:英語がなかなか上達しません。
5教科の学習 よくある質問に答えます!
これまでZ会に届いたなかで、多かった質問とその回答についてご紹介していきますので、苦手な教科の勉強をする際の参考にしてみてください。
国語
読解力をつけるためにはどうすればよいでしょうか。
国語の問題文として出される文章に限らず、「書かれている内容を正しく読み取る力」が読解力です。まず文章を読み取るときに必要なのは、言葉の知識です。小学生であれば知らない言葉はまだまだたくさんありますが、そこでつまずいてしまうと、文章を先に読み進めることができなくなってしまいます。知らない言葉が出てきたらそのままにしないで、辞書で調べる習慣をつけておきましょう。できれば、すぐに辞書を引くのではなく、前後の内容から意味を予測してから辞書を引いて確認するほうがより身につきます。
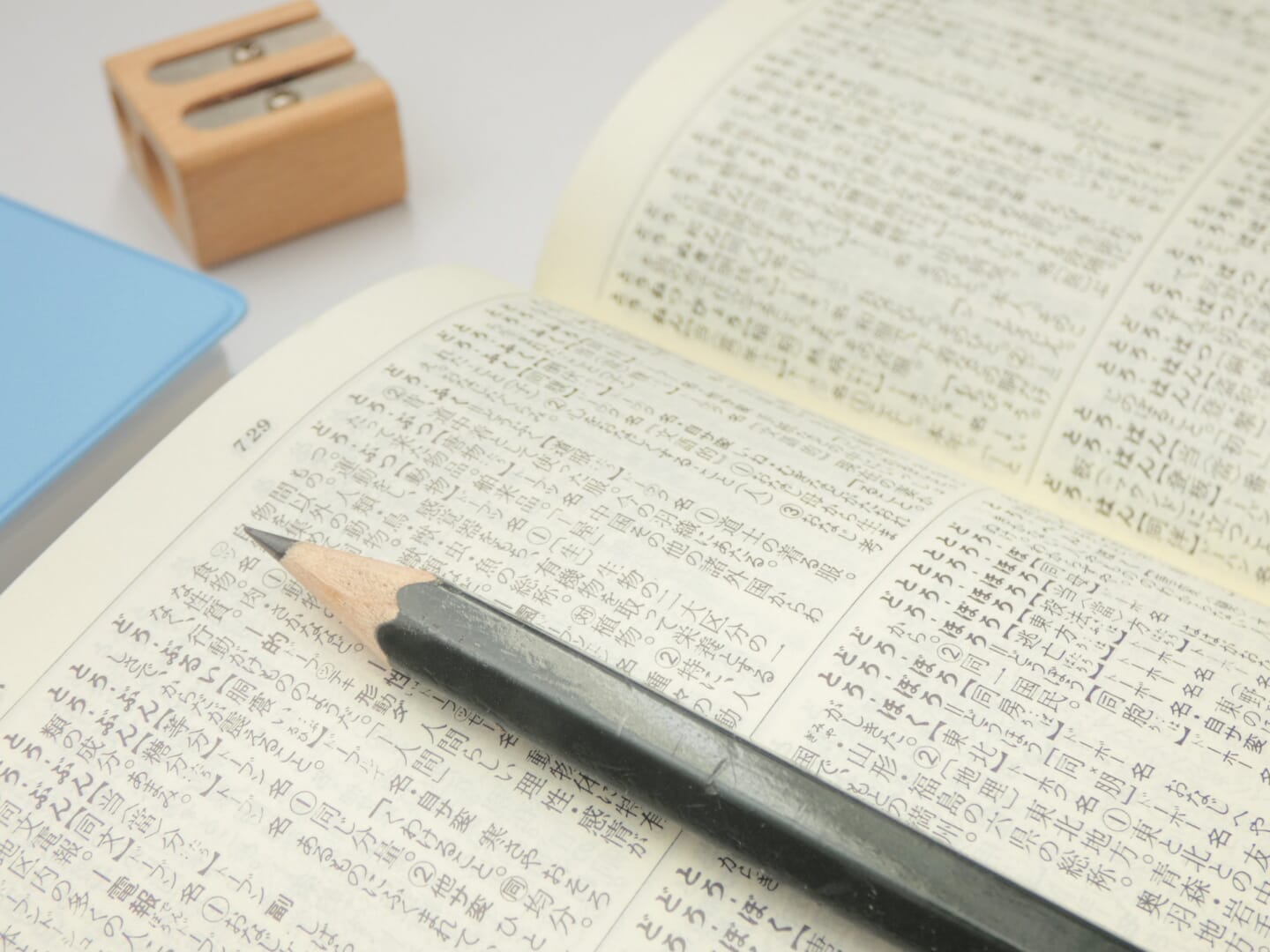
また、文章を読むのに慣れることも必要です。日ごろから本を読む習慣があるお子さまであれば、長い文章を読む力が自然とついていきますので心配はありませんが、勉強のとき以外本は読まないというお子さまの場合は、まずはZ会の教材で取り上げている文章をじっくり読むということから始めるとよいでしょう。その際には、「書かれている内容をしっかり理解できた」と思うまで、何度でも繰り返し読むようにすることが大切です。単に字面を追うだけでは十分ではありません。「わからない部分がなくなるまでしっかり読む」ということによって、読解力が養われるのです。ここで役立つのが、『エブリスタディ 答えと考え方』です。『エブリスタディ 答えと考え方』には、文章を理解するためのポイントが詳しく説明されています。問題文だけでなく、「考え方」をしっかり読むことによって、文章の理解が深まります。
このようにして、徐々に文章を読むことに慣れていくとよいでしょう。読解力は、短期間で簡単に身につくというものではありません。また、ほかの人から教えてもらって身につくものでもありません。お子さま自身がさまざまな文章に触れ、それを読み解く努力を繰り返し行うことによって、次第に身についていきます。
算数
ケアレスミスが多いのですが、どうすればミスが減るでしょうか。
まず、お子さまのミスしやすい箇所を知ることが、ミスをなくす第一歩です。問題文の読みまちがい、計算の手順のまちがい、暗算のまちがい、筆算のくり上がりやくり下がりのまちがいなど、これまでの答案などを見直して、お子さまのミスの傾向をつかみましょう。そのうえで、以下を参考にお子さまの傾向に合った対策を考えましょう。
●見直す習慣をつける
基本的なことですが、問題の読みまちがいや単位のつけ忘れなどのミスを発見するのに、見直しは大きな効果があります。「練習問題」や「てんさく問題」などは、解いた後に問題文や式、答えをざっと読み直すようにしましょう。
●検算をする
ひき算の結果はたし算で、わり算の結果はかけ算で検算すれば答えの確かめができます。くり上がりやくり下がりでまちがえやすい場合は、もう一度同じ計算をするよりは、検算で確かめたほうが確実でしょう。
●途中式を書く
途中式を書かない、書いた途中式を消してしまうといった傾向があり、計算ミスをしがちな場合は、計算部分の途中式を省略したり、消したりしないで書くようにしましょう。そうすると、見直すときにまちがえた場所を見つけやすくなります。また、計算に慣れるまではあまり暗算に頼らないほうがよいでしょう。
●筆算は位をそろえて書く
筆算のくり上がりやくり下がりの文字を大きく書きすぎたり、筆算全体を小さく書きすぎたり、位をまっすぐ縦にそろえて書かなかったりすると、位の勘ちがいによるミスが発生しやすくなります。位を縦にきちんとそろえて書くことで、こういった計算ミスを防ぐことができます。
理科
どうやって学習すればよいかわかりません。
理科は3年生から始まる教科なので、慣れるのに時間がかかるお子さまも多いかもしれません。生活科に比べて覚えることが非常に多いため、その違いに戸惑うお子さまも少なくないでしょう。
3年生の前半では、昆虫や植物の特徴を中心に学習してきました。これらの特徴を覚えるには、やはり本物に触れ、よく観察することが一番です。ですが、実際にすべての昆虫・植物を身のまわりで見られるとは限りません。見つけた昆虫・植物がなんの種類なのかを見極めるのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、いろいろな写真を観察したり、日常の会話のなかで話題に出したりすることでも、知識の定着を手助けすることができます。Z会の教材では、さまざまな種類の昆虫や植物について、各季節の様子の写真やイラストを掲載しています。教科書やお手持ちの図鑑とあわせて、ぜひご活用ください。
また、身のまわりの自然をきっかけに、昆虫や植物についての会話を広げていくこともおすすめです。「あそこに生えている草は、ショウリョウバッタが食べる草だね」「この花は、くきの先に花が咲いているから、ヒマワリと同じつき方だね」など、学習した内容を思い出す機会を増やすことで、知識が定着していきます。このとき、その場で正解がわからなくても構いません。カマキリを見かけたときに、「カマキリは何を食べるんだっけ?」と疑問に思ったら、家に帰ったあと、教科書やZ会の教材で確認しましょう。書いてあることを漠然と覚えるよりも、一度疑問に思って調べた内容の方がすっと頭のなかに入ってくるはずです。

3年生の後半では、磁石や電気のような目に見えないものの性質についての学習も始まります。抽象的な内容になるため、苦手意識をもってしまうお子さまも多いですが、たとえば、家のなかで磁石がつくものとつかないものを探してみる、「このコップはガラスでできているから電気を通さないね」というような会話を取り入れてみることによって、学習内容を身近に感じ、取り組みやすくなります。身のまわりのものや現象に疑問を感じ、その疑問を解決するために、調べたり、観察したり、実験したりすることは、理科(科学)の土台です。3年生である今のうちから、疑問を持つ→調べる→解決する、という学習の流れを身につけておくと、今後の理科の学習がスムーズになるでしょう。
社会
地図の読み取りに苦戦しています。
3年生からスタートする社会という教科の目標の一つは、「さまざまな資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめる技能を身につける」ことです。ですので、社会では、地図をはじめ、写真、グラフ、図表、記事など、さまざまな資料が登場し、これらを読み解いたり、使いこなしたりしていくことが求められます。地図については、次のことに注意して読み取るとよいでしょう。
●方位は確実に
それぞれの地図の方位は確実に理解しておきましょう。多くの場合、地図上に方位を示す方位記号が示されています。方位記号がない地図の多くは、上が北になっています。東西南北の関係性が定着するまでは、お子さまが地図を見ているときに、「北はどっちかな?」「東はどっちかな?」「南西はどっちかな?」とお声がけください。
●まぎらわしい地図記号はセットで覚える
交番と警察署、田と畑などは、地図記号が似通っていたり単純だったりするためか、混同しがちです。それぞれの地図記号の由来を確かめつつ、セットで覚えるようにするとよいでしょう。
●身近な地域の地図をベースに
教科書やZ会の教材には、見慣れない土地についての土地条件図(土地を山地や台地、低地などの地形ごとに分類した地図)や土地利用図(土地を森林、田畑、工場用地などの利用状態ごとに分類した地図)が登場します。こうした地図は、ふだんの生活で目にする機会が少ないので、難しく感じられるものです。学校では、副読本などを用いて自分の住んでいる地域の地図の読み取りを行うのが一般的ですので、まず、身近な地域の土地条件図・土地利用図の読み取りを積極的に行いましょう。そうすると、ほかの地域の土地条件図や土地利用図も比較的読み取りやすくなります。読み取ったあとは、インターネットの検索機能を利用して、地図の地域の画像・動画などに接すると、その土地のことがより身近に感じられるので、効果的です。また、3年生から配布される地図帳で、地図に登場する地域を探して確かめておくと、周辺地域との関係性の理解にも役立つので、取り組んでみるとよいでしょう。
英語
英語がなかなか上達しません。
まだ日本語の知識も完全でない小学生にとって、文字も発音もまったく新しい英語を学習するというのは、大人が想像する以上に難しいことです。話す、聞く、書くのすべてにおいて、まずは何度も練習することが必須です。一度だけで覚えられることはありません。そのことをお子さまに伝えながら、たくさんの単語や表現に触れ、それらを何度も口に出して練習することを根気強く続けてください。
そして、その際のポイントの1つは、アルファベットと音を結びつけることです。一般的に英語学習では「読んで正しく発音できる→意味がわかる→正しくつづることができる」という順番が理想とされています。小学校中学年で正しくつづる段階に到達する必要はありません。しかし今のうちに、どのアルファベットがどんな音になるのか注目する癖をつけておくと、新しい単語も発音しやすくなりますし、さらにつづりも覚えやすくなって、中学以降のあと伸び力につながります。
2つ目のポイントは、実際に英語を使う場面をイメージすることです。英語をただの文字の羅列ではなく、コミュニケーションツールとして捉えることで、やる気が続きやすくなります。
この機会に苦手をなくして、自信をもって新年度を迎えられるようにしたいですね。
次回の学習ナビでは「漢字の学習について」についてご紹介します。10/22(水)の更新をお楽しみに!