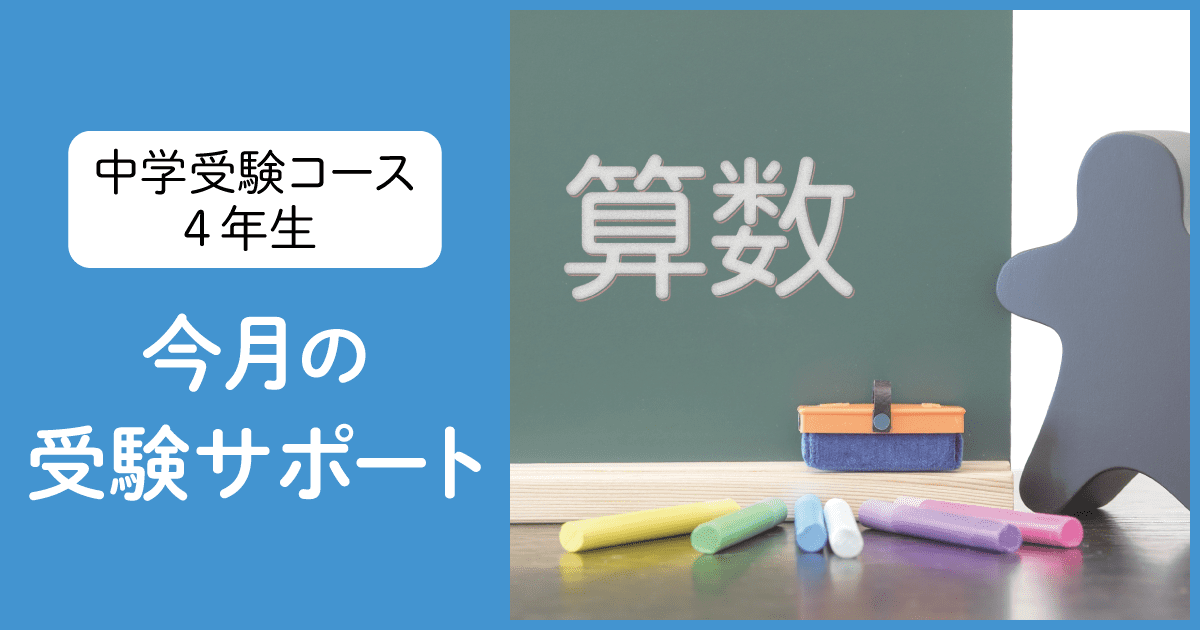中学受験に向けた勉強を進めるうえで、大きな差のつく教科の一つ、「算数」。これから難しい内容になるにつれて、新しい考え方・解き方についていけない、応用問題に対応できないといったケースが増えていきます。
今回は、中学受験の算数の学習のコツをご紹介します。
※今回の記事でご紹介している4年生の学習内容は、トータル指導プランをご受講いただいた場合のものです。
つまずいたときは一度前に戻る
受験算数で多くの子どもが頭を悩ませる文章題や図形問題には、解き方がいくつかある場合が多いものです。これから受験本番まで受験算数とうまくつきあっていくために、今の時期の学習で大事なことは、難しい問題でも下記のように試行錯誤しながら解く体験を何度も重ねることです。
- それまでに習った解き方・考え方を使って手を動かす
- ひとつの方法がダメなら、次の方法を考えてみる
こういった試行錯誤によって、問題の解き方をお子さま自身で体得していくことができます。
とくに難しい内容だと、「答えと考え方」を読んでもすぐには理解できないこともあるでしょう。そのようなときには、下記のような段階を踏んで、その問題の解き方を丁寧に見直してください。
- 解き方のどこまでがわかって、どこからがわからないのかをじっくり考える
- 関連する単元の要点や例題に戻って、解き方や考え方を確認する
こうした時間のかかる取り組みは遠回りのように思えますが、つまずきの原因を明らかにしたり、これまでの理解をより確かなものにしたりする効果があります。つまずいてしまったときこそ時間をかけて取り組み、これまでの内容を見直すことをおすすめします。
教材に「戻りやすく」する方法
① ノートを用意する
上でお話ししたように、算数の学習が進んでいくと、過去の教材に戻ることが多々出てきます。
練習問題に取り組む際に、『エブリスタディ アドバンスト』に式や答えを書き込んでしまうと、後で解きなおすときにそれが自然と目に入ってしまうため、なんとなくわかっている気になってしまうことがあります。練習問題用のノートを用意して、そちらに式や答えを書くようにすると、解きなおしたときにも解き方を一から思い出すことになりますので、きちんと確かめることができます。
② 練習問題に印をつける
まちがえてしまったり理解があやふやだったりした問題は、先の単元に進んだときにつまずきの元になる可能性があります。そういった問題には印をつけておいて、長期休暇などに復習する際の目印にしましょう。
「受験算数」の学習に関するQ&A
算数の学習に関してよく寄せられる相談とその回答をまとめました。これから学習を進めていく際に、参考にしてください。