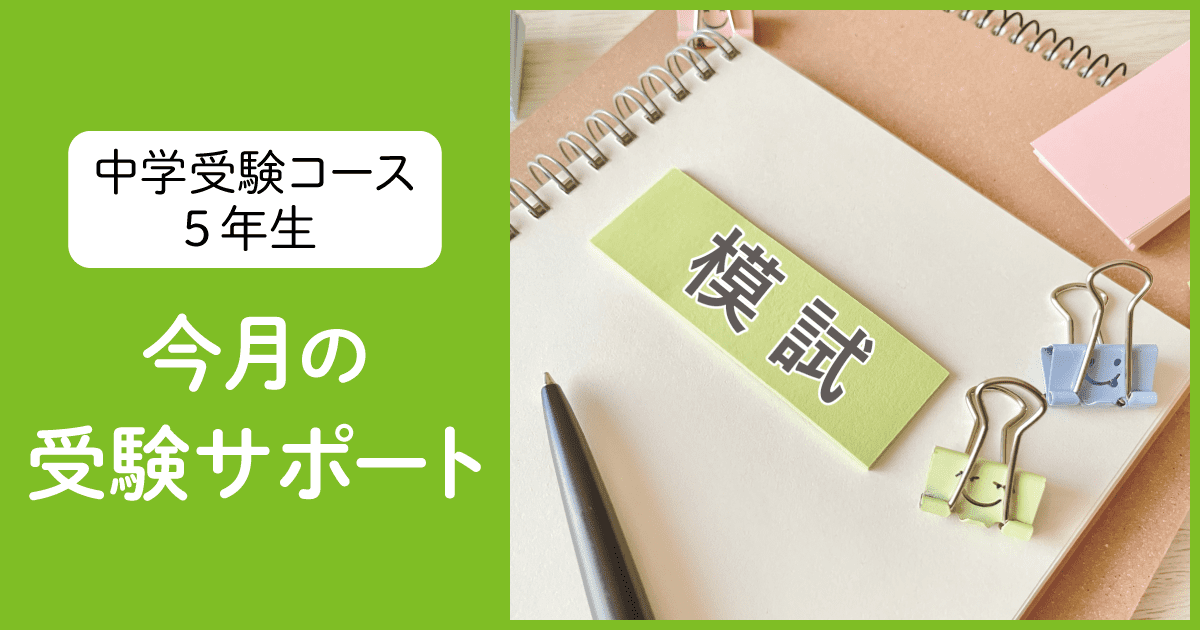Z会では、5年生の段階で夏と冬の計2回ほど、模試の受験をおすすめしています。
模試を効果的に今後の学習にいかすために、公開模試を受験する際に注意したい点をお話しいたします。
模試を効果的に利用するために
模試の受験で得られること
5年生での模試の受験目的は、自分の実力を試し、中学受験を目ざす子どもたちのなかでの位置を知ることです。この時期の模試の多くは、成績表の偏差値をもとに全受験生のなかでの位置を知ることができるものとなっています。また問題の正答率から、基礎事項がきちんと身についているかどうかが確認できます。
お子さまの学力がどこまで達しているのかを客観的に判断したり、お子さま自身がこれからがんばっていかなければならないことを実感したりと、早いうちに模試の受験に慣れ、活用していくことで、その後の学習を効果的に進めることができます。模試の結果をもとに今後の学習計画を見直していきましょう。
※自宅受験ができる模試もあります。最新の情報は、事前に主催者様のWebサイト等でご確認ください。
公開模試受験時に気をつけたいポイント
① (会場で受験する場合)会場には早めに到着する
知らない子どもたちがたくさんいる会場に入ると、どうしても緊張しがちです。早めに到着して、試験場の雰囲気に慣れておきましょう。
② 時間配分に注意
「わからない問題に時間をかけすぎてしまい、試験時間が足りなくなってしまった!」というのは模試で起こりがちな失敗です。受験前には、「試験が始まったら、まずは問題全体に目を通し、わかる問題から解いていく」など、時間配分に注意するよう確認しておくとよいでしょう。
③ わからなかった問題はメモしておいてすぐ解き直す
模試で大切なことは結果に一喜一憂することではなく、できなかった問題を見つけ、復習することです。保護者の方は冷静に結果を分析し、今後の学習につなげてください。
試験中にわからなかった問題には印をつけておくようにお子さまに伝えておき、その中で既習の単元については、できるだけ早く解き直すよう促しましょう。
模試を今後の学習にいかす
5年生の学習における課題は次の3つです。
- 「今学習していることをしっかり理解すること」
- 「定期的に模擬試験を受験して苦手を発見し、つぶしていくこと」
- 「志望校のことをよく知り、行きたいという気持ちを強くもつこと」
あまり多くのことに手をつけようとすると、理解が中途半端になりかねません。まずは基礎をしっかり固めることを目標に、模試などの結果をいかして、効率よく学習を進めましょう。
中学入試で使われる「偏差値」とは
さまざまな学校を「偏差値」で一覧にした表を目にされたことがあるかと思います。これらは模試を主催する団体などにより作成され、お子さまの模試の成績をもとに志望校や受験校を選定したり、合格判定が出る模試でどの中学校を登録するかを決めるときに参考にしたりするものです。
偏差値の表には、男子女子共学の別や入試日ごとに表にしてあるもの、その年の入試傾向を予想した「予想偏差値」、入試結果をもとに作成される「結果偏差値」など、さまざまな種類があります。しかし、こういった「偏差値表」を利用される際には、この「偏差値」の特性をきちんと理解していただく必要があります。
偏差値は、特定の母集団の平均を「50」とし、その集団の中での自分の位置を知る指標です。
首都圏の大手模試の多くは、主催模試の中での志望者の成績・動向をもとに、入試日別の合格可能性80%の予想偏差値の表を作成しています。たとえば、日能研の模試では合格可能性が80%の偏差値を「R4偏差値」として利用しています。首都圏以外の地域でも、「偏差値」をもとに学校ごとの合格基準を出す模試が多く、志望校選びの便利なツールとなっています。
ここで気をつけなければならないのは、偏差値は「その模試の受験者平均」からどの程度離れているかを表す数値にすぎないため、母集団である受験生の偏りによって、数字が変わってくるということです。
たとえば、同じ配点の模試で同じ得点をとったとしても、その模試の受験者全体の学力レベルが高く平均点が高ければ受験生の偏差値は低めに、学力レベルが低く平均点が低ければ受験生の偏差値は高めに出ます。
また、模試の出題レベルおよび母集団が大きく異なる場合、偏差値を単純に比較することはできません。たとえば、ある塾の模試の成績表で出てきた偏差値を、出題レベルも母集団の学力レベルも大きく異なる別の塾の偏差値表に当てはめて合格可能性を判断することは、適切ではありません。
各種の偏差値表は、これらの点に注意して活用してください。
次回の「受験サポート」は5月8日(木)更新予定です。