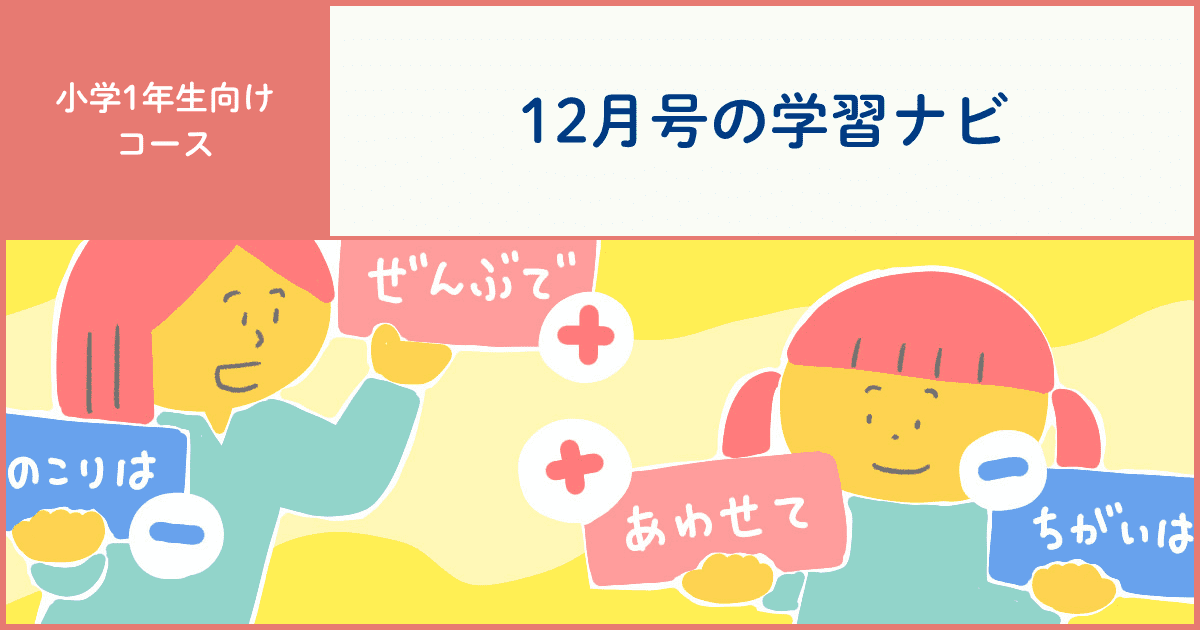学習内容が複雑になってくると、ケアレスミスも増えてきます。そこで今回は、「がんばっているのに失点する」そんな悔しい思いをしなくて済む方法を考えます。
国語:漢字で×になる
漢字の習得は、繰り返しお手本をなぞったり、お手本を見ながら書き写したりするのがいちばんですが、同じ漢字を何度も書くには忍耐が必要です。お子さまがあきてしまったり、保護者の方も反復練習につき合う時間が取れなかったりするようであれば、大きい字でゆっくり「ここははねる」「ここはとめる」と口に出しながら、お子さまが書くところを見てあげてください。×になってしまうポイントについては、時間をおいてときどきチェックするとよいですね。チェックのときは指で空に書かせるだけでも十分です。正しく書けたときにはぜひ、「いつもこの調子で書こうね」とほめてあげてください。
書き順もきっちり
新しい漢字が出てきたら、必ず正しい書き順とセットで覚えるのがコツです。2年生以上になるとさらに画数の多い漢字が出てきますが、書き順が正しければ字形も整います。1年生で習った漢字は「へん」など部首の部分で今後も繰り返し出てくることが多いので、今のうちから正しい書き順で書くことを習慣にしておきましょう。
算数:繰り上がりのあるたし算・繰り下がりのあるひき算でまちがえる
繰り上がりのあるたし算
10までの数の合成と分解をすばやくできるようになるまでおさらいしましょう。
日常の生活のなかでゲーム感覚で楽しく数字を探すなど、「たして10になる組み合わせ」が瞬時に浮かぶよう練習してみてください。これによって繰り上がりのあるたし算がスムーズにできるようになります。
繰り下がりのあるひき算
繰り下がりのあるひき算は「減加法」「減減法」という2つの方法で解くことができます。
【減加法】
13-7=(10+3)-7=(10-7)+3=3+3=6
【減減法】
13-7=13-(3+4)=(13-3)-4=10-4=6
ただし、必ず2つの方法をマスターしなくてはいけないというものではありません。どちらか1つの方法に絞って取り組んでいただいてもかまいません。その場合には、まずは減加法を教えてあげるとよいでしょう。比較的子どもが理解しやすく、多くの教科書では、減加法を中心に教えているためです。
算数:ひき算の文章題なのに、たしている……
問題文中に「あわせて」「ぜんぶで」「ふえると」などがあるときはたし算、「のこりは」「ちがいは」などがあるときはひき算、という具合にキーワードを頼りに文章題を読むようにしてみましょう。
1年生のうちは問題文中にこれらのキーワードが入っていることがほとんどなので、印をつけながら読むとよいでしょう。慣れてくると、キーワードが省略されていたりひっかけ問題(※)になっていたりする文章題でもたし算かひき算かを特定できるようになってきます。
※「ぜんぶで」が含まれた文章題なのにひき算で答えを求めたり、「のこりは」が含まれた文章題なのにたし算で答えを求めたりすることがあります。
ケアレスミスをなくすために「ちょっと気をつける」習慣は、上の学年に進んでからの助けになります。低学年の今のうちに習慣にしておきましょう。