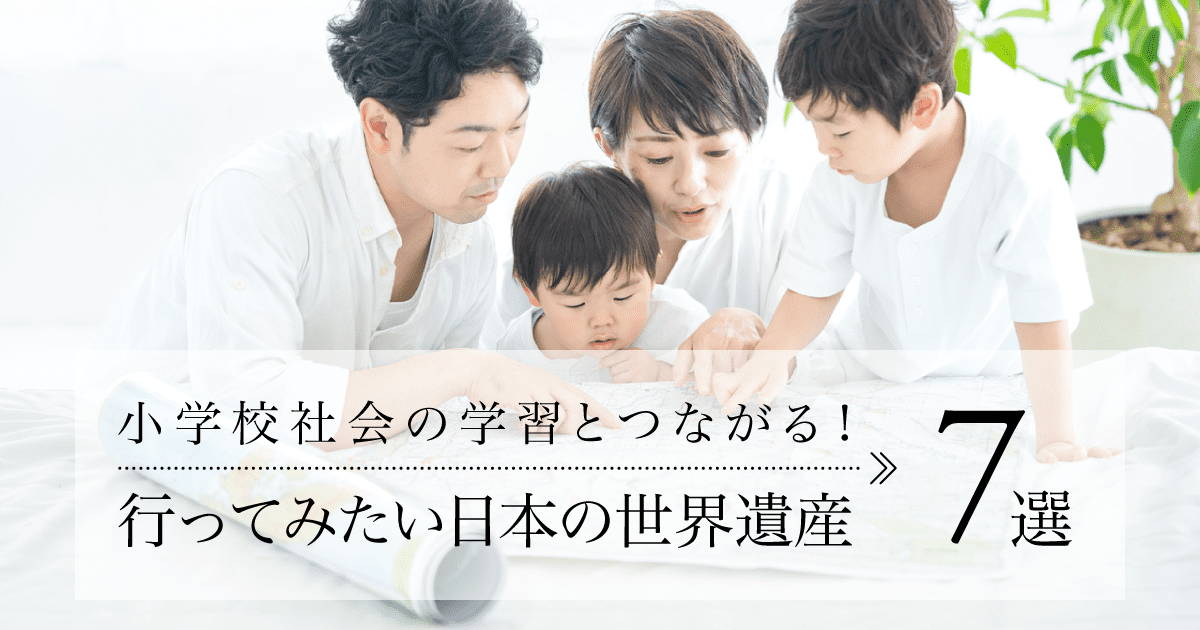国内旅行の行き先を考えるときに、お子さまの学習に役立つことも期待して計画するご家庭は多いのではないでしょうか。今回は、Z会の社会担当が、小学校社会の学習とかかわりの深い日本の世界遺産を選びました。
1 北海道‧北東北の縄文遺跡群

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
先史時代における農耕を伴わない定住社会及び複雑な精神文化、定住社会の発展段階や様々な環境変化への適応を示している点が評価されて、登録された考古遺跡群です。小学6年生の歴史学習では、最初に縄文時代について学びますが、教科書で大きく取り上げられている青森県にある三内丸山遺跡は、この世界遺産の構成資産の一つです。
歴史分野を学び始める“つかみ”に最適
北海道・青森県・岩手県・秋田県の1道3県に所在する17の遺跡で構成されています。
縄文時代を感じさせる景観が保全されているだけでなく、各遺跡の周辺には、発掘調査の状況や出土品を展示する施設があり、土器などのものづくりの各種体験プログラムも充実しています。
多くの遺跡で構成されている世界遺産ですので、気になった一つの遺跡だけを深掘りするパターン以外に、一つのエリアの複数の遺跡を巡るパターンや、離れた位置にある遺跡を巡りつつ、それぞれの遺跡の自然地形や出土品などを比べてみるパターン等、楽しみ方のバリエーションが豊富です。家族でプランを相談して決めるのもいいですね。
2 白川郷・五箇山の合掌造り集落

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
「合掌造り」は、傾きの急な屋根が特徴で、手を合掌したときの腕の形と似ていることからこのように呼ばれます。岐阜県と富山県の豪雪地帯にあるこの集落では、合掌造りをはじめとして、5年生で学習する「気候にあわせた生活のくふう」が多く見られます。
人が生活している珍しい世界遺産
3 日光の社寺

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
栃木県の日光山内にある二荒山神社、東照宮、輪王寺の建造物群と、建造物群を取り巻く遺跡(文化的景観)です。小学6年生の江戸時代の学習において、三代将軍徳川家光は、祖父家康がまつられている東照宮を、莫大な費用をかけて建て直したことを学習します。
日光を見ずして結構と言うなかれ
4 富士山‐信仰の対象と芸術の源泉‐

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
標高3776mの日本で最も高い山です。その神秘的な様子から、富士山は信仰の対象や、6年生の歴史で学習するさまざまな芸術作品の題材になっています。こうした点が評価され、富士山は世界文化遺産に登録されました。
登らなくても楽しめる日本の最高峰
5 姫路城

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
別名白鷺城。「日本の城」といえばこの姫路城の姿が思い浮かぶ方も多いでしょう。6年生の歴史で学習する安土桃山時代には城郭建築が発達し、城が領国支配の中心地となりました。
時代劇の中で目にしているかもしれません
6 厳島神社

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
広島県の宮島にある厳島神社は、1400年以上前に創建されたとされている神社です。小学6年生の歴史学習で、平安時代末期に平清盛は平氏の守り神としてこの神社を大切にして、瀬戸内海の海上交通の安全をいのったことを学びます。
満潮時に海に浮かぶ鳥居が印象的
7 屋久島

 小学社会とつながるポイント
小学社会とつながるポイント
樹齢数千年のヤクスギなど珍しい動植物が見られます。独特な地形により、5年生で学習する日本の気候のうち、寒い地域から暖かい地域まで、さまざまな気候と自然を1つの島の中で見ることができます。
世界遺産には「自然遺産」もあります!
今回は、家族旅行にオススメしたい日本の世界遺産を7つご紹介しました。
低学年のお子さまが社会科で習うのはまだ先ですが、勉強のためと身構えなくても、機会があれば訪問してみると、地形や気候、各地域の特性とともにお子さまの記憶に残ることでしょう。
参考リンク