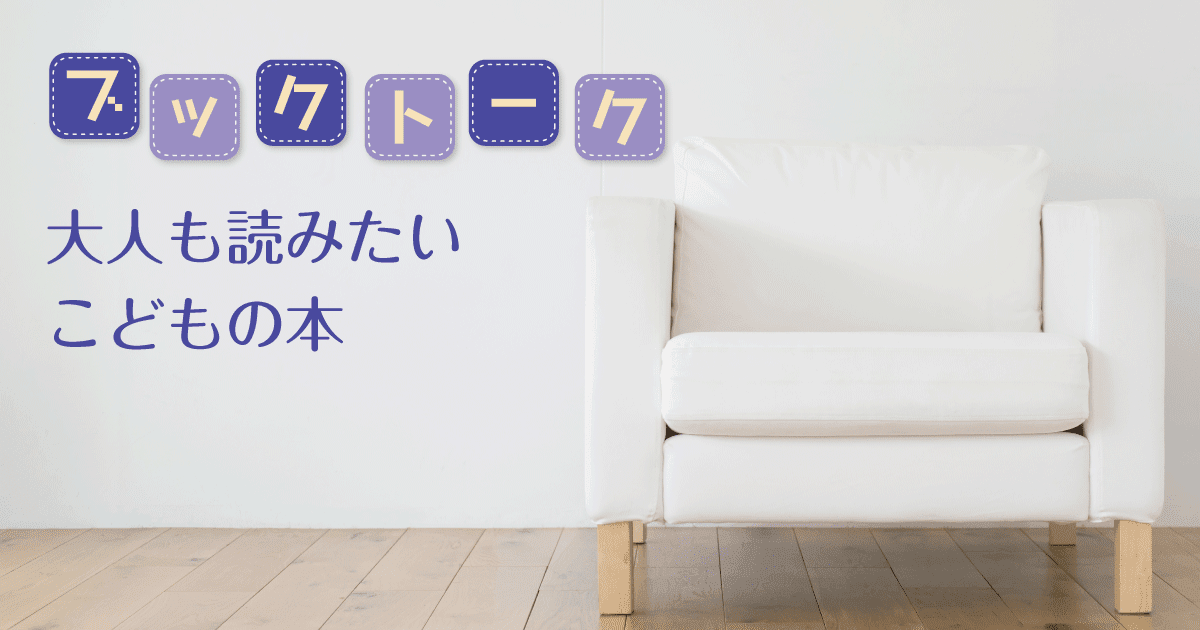世代を超えて読み継ぎたい、心に届く選りすぐりの子どもの本をご紹介いたします。
歩けるようになった魚と男の子の交流

さて、樹木や草花が茂る森や農場を舞台とした作品の多いベスコフですが、「しりたがりやのちいさな魚のお話」は、もちろん水辺のお話です。淡水と鹹水(塩分を含んだ水)がちょうど混じり合った湖には、カレイやコイ、カマスやカエルなどが共生しています。「しりたがりや」のスイスイは、小さなスズキの子どもです。スイスイは、カレイのおばさんが言う「二本足のカエルのオバケみたいな」ニンゲンというものを見てみたいと思っていましたが、その願いは、はからずもすぐに叶います。桟橋の下に泳ぎついたスイスイは、おいしそうな餌の誘惑に勝てず、あっという間に釣られてしまうのでした――。
異彩を放つのは、お腹あたりから生えた細い二本の足で地上を歩く魚の姿です。ベスコフの描く自然は写実的ですから、リアリスティックに描かれた魚に付けられた足は何ともシュール。大人には滑稽に見えてしまうかもしれません。しかし一方で、スイスイを釣り上げた男の子トーマスの小さな生きものに向ける朴訥なまなざしや、種族を越えて共に暮らす魚たちの睦まじさが、あるべき平和な世界を醸していて、心地好い安心感があります。私は、トーマスの姉シャスティンが、弟を思ってさりげなく手を貸す場面に、些事ながら、惹かれました。豊かな自然に触れて、のびやかにその環境を謳歌できる主人公の喜びの源を見たように感じたからです。
ベスコフの他の絵本と同様、悪い人や狡い人は出てきません。お話の起伏も少なく、淡々としています。それでも、長きに渡って子どもたちに支持されているのは、物語を統べる平穏な空気と、にもかかわらず必ず訪れる魔法、そして、愛らしくクラシカルな絵の力でしょう。今回のお話では、小人も妖精も出番がありませんでしたが、彼らを小さな生きものや植物と同等に描く確かな筆力が幼い読者を魅了しているに違いありません。
1933年にスウェーデンで出版されてから、およそ90年。一冊の本がたどる歴史を思って感嘆します。ベスコフは1890年代から創作を始めていますので、それでもかなり後の方の作品です。読者に媚びることなく、新しい時代にも生き残ってきたベスコフの絵本。素朴なストーリーは、迷う主人公を救うだけでなく、いつも思いがけない嬉しいハプニングへと展開します。ゆったりと身を任せられる心やさしい物語です。
吉田 真澄 (よしだ ますみ)
長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。