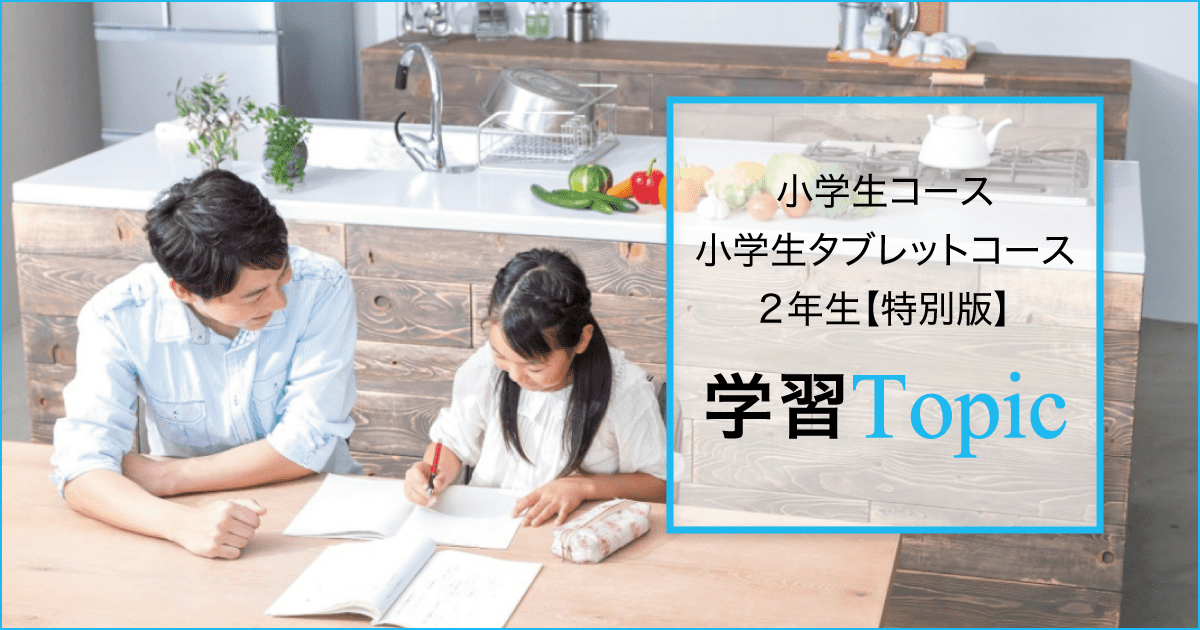3年生への進級を前に、そろそろ中学受験について考え始めるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、中学受験をお考えの保護者の方に向けて、学習Topic特別版をお届けします。今からおさえておきたい中学受験の基礎知識と2年生からできる準備について、「最難関中学受験プレミアム講座」責任者の鈴切秀敏がお話しします。
中学受験の基礎知識
国私立の中学校ってどんなところ?
――中学受験をして進学することになる国私立中学校には、どのような特徴があるのでしょうか?
まず、勉強面においてですが、多くの国私立中学校が中高一貫教育を採用していて高校受験がありません。その分、中学生のうちから高校の学習内容を先取りするなど、早めに中学・高校の履修範囲を終えて、余裕をもって大学受験に臨むことができる点が大きなメリットとしてあげられます。また、学校の教育理念に基づいて柔軟にカリキュラムを組んだり、少人数または習熟度別にクラスを作ったりして、生徒が学習しやすい形で授業を進める工夫もあるようです。
大学の附属校のなかには、併設大学の推薦を持ったまま他大学を受験できる学校もあるので、それもメリットの一つといえるでしょう。
――勉強以外の面についてはいかがですか?
学校行事やクラブ活動、キャリア教育、英語教育など、社会でリーダーシップを発揮できる人材を育てるための工夫を打ち出している学校が多かったり、校風の違いが学校ごとに顕著だったりします。学校によっては実験設備や図書館、食堂のメニューをはじめとした施設が充実しているところもあります。
それぞれに異なる教育理念や校風を持つ学校のなかから、お子さまに合った学校を選べることが、国私立中学校を選択する最大のメリットといえるでしょう。
――「その子に合った学校を選ぶ」ということが重要なのですね。
そうですね。学校ごとに教育理念や校風が異なりますから、お子さまに合った学校かどうかを慎重に見極める必要があります。
将来、お子さまにどんな大人になってほしいのか、あるいは、お子さま自身がどんな大人になりたいと考えているのかを踏まえて、そのイメージにあった教育理念・校風の学校を選んでいただきたいと思います。
中学受験に向けて、4教科をまんべんなく対策することが重要。
――中学入試本番では、どのようなことが問われるのでしょうか?
受験教科は、「4教科型(国語、算数、理科、社会)」が基本ですが、灘や甲陽学院など関西の上位校では「3教科型(国語、算数、理科)」の学校もあります。近年では、「算数1教科型」や、公立中高一貫校で採用している「適性検査型」、さらに部分的に「英語入試」を採用する学校も増えています。ただし、首都圏をはじめそのほかの上位校は4教科型がほとんどです。また、将来の受験校の選択肢を広げる意味でも、受験に向けた学習では、国語、算数、理科、社会の4教科をまんべんなく学習することが重要です。
とくに、理科と社会は経験から得た知識が得意・不得意に影響する教科ですし、この2教科の得点が低いと、いくら国語と算数ができていても不合格の要因になってしまいます。あとから追い込みが効くと思わず、今のうちから教科学習につながるさまざまな体験をしておくことが大事です。
2年生の今、やっておきたいこと
まずは2年生の学習内容を確実に。さらに「勉強って楽しい」と思える経験を重ねましょう。
――中学受験を意識したときに、2年生の今できることは何でしょうか?
まずは、2年生の学習にしっかり取り組んで、確実なものにすることです。2年生の内容が十分に理解できないまま、焦って3年生の内容を先取りしても身につきませんし、お子さま自身が勉強を楽しいと感じることはできません。
「勉強って楽しい!」と思えることは、受験勉強を進めるうえで非常に重要です。3年生から受験勉強を始めたとして、入試までの4年近くの間、スランプに陥らない人はいません。そのとき、「勉強って楽しい!」という意識がお子さまになければ、スランプから抜け出すことが難しくなります。
ですから、今からできることの一つとして保護者の方にお願いしたいのは、「勉強って楽しい!」と思えるよう、お子さまの学びをサポートしていただくことです。「問題に挑戦する→解ける→うれしい!楽しい!といった達成感を味わう→勉強が好きになる→中学受験の勉強も楽しく取り組める」という流れができるよう、ぜひお願いいたします。
もし、今の段階で学校の勉強が物足りなく感じているようでしたら、小学生コースのオプション講座「みらい思考ワーク」を追加受講したり、小学生タブレットコースのプラス学習に取り組んだり、Z会が販売している書籍『Z会グレードアップ問題集』に挑戦したりして、「粘り強く考える→解ける→うれしい!楽しい!といった達成感を味わう」という経験を重ねていただければと思います。
――ほかにも今からできることはありますか?
学習習慣や学習姿勢を身につけることですね。時間が来たら机に向かう、机に向かっている間は集中する、計画通りに勉強を進める、といった学習習慣と、問題を解いたら解きっぱなしにせずに丸つけをする、まちがえた問題は解説を読んで考え方を学ぶ、暗記をするときは書いて覚える、筆算を丁寧に書いてまちがえていても消さない、といった学習姿勢は、受験勉強をするうえで最も重要な土台となるものです。
――お子さまが学習習慣や学習姿勢を身につけるために、保護者の方はどのようにサポートするのがよいでしょうか?
学習習慣については、お子さまが自分に合った1カ月の学習スタイルを見つけられるよう、今お使いいただいている小学生コースの「がくしゅうカレンダー」、もしくは小学生タブレットコースのスケジュールを活用して「計画を立てる→実行する→進み具合を確認する→計画を修正する」というサイクルづくりをサポートしていただければと思います。
学習姿勢については、「丸つけをやってみようか」「まちがいの原因はどこにあったと思う?」「なんでまちがえたか解説で確認してみよう」などと、答え合わせをしてまちがいの原因を見つけて理解する手助けをすること、また、できたところをしっかりほめて達成感を与えてあげることを意識していただきたいですね。
3年生から始まる理科・社会のために、今からさまざまな経験を積んでおきましょう。
――理科と社会は、どちらも経験から得た知識が得意・不得意に影響するとのことですが、今から日常のなかで取り組めることはありますか?
最も手軽にできるのは、一例ですが、スーパーマーケットに一緒に買い物に行くことですね。店頭に並ぶ野菜から旬を知ったり、「なんでキャベツの値段が上がったのかな?」「最近雨の日が多かったからじゃない?」などと価格変動の要因を話し合ってみたり……。カゴに入れた商品の合計金額や、グラム当たりの単価を計算してもらえば、四則演算の訓練にもなります。いろいろと工夫のしがいがある場所だと思いますよ。
ほかにも、旅行に行く前に行き先や経路を地図で確認したり、その土地の歴史や特産物について調べたりするのもよいですし、動物園や植物園、水族館、プラネタリウム、博物館などに行って興味の幅を広げてあげるのもよいでしょう。
大事なのは、疑問や興味をもったものについてさらに調べてみること。調べて疑問が解決したり、より詳しく知ることができたりすれば、楽しさが増しますよね。もちろん、現時点では理解できなかったり、解決できなかったりすることもありますが、学年が上がるにつれて知識がついてわかるようになるので、最初から無理にすべてを理解させようとせず、そのままにしておいてかまいません。
小学生コースの経験学習や小学生タブレットコースのみらいたんけん学習も、3年生からの理科・社会につながっています。もし、うまく取り組めていない場合でも、お子さまが興味をもてる教材だけでもかまいませんので、ぜひ少しずつでも取り組んでみてください。