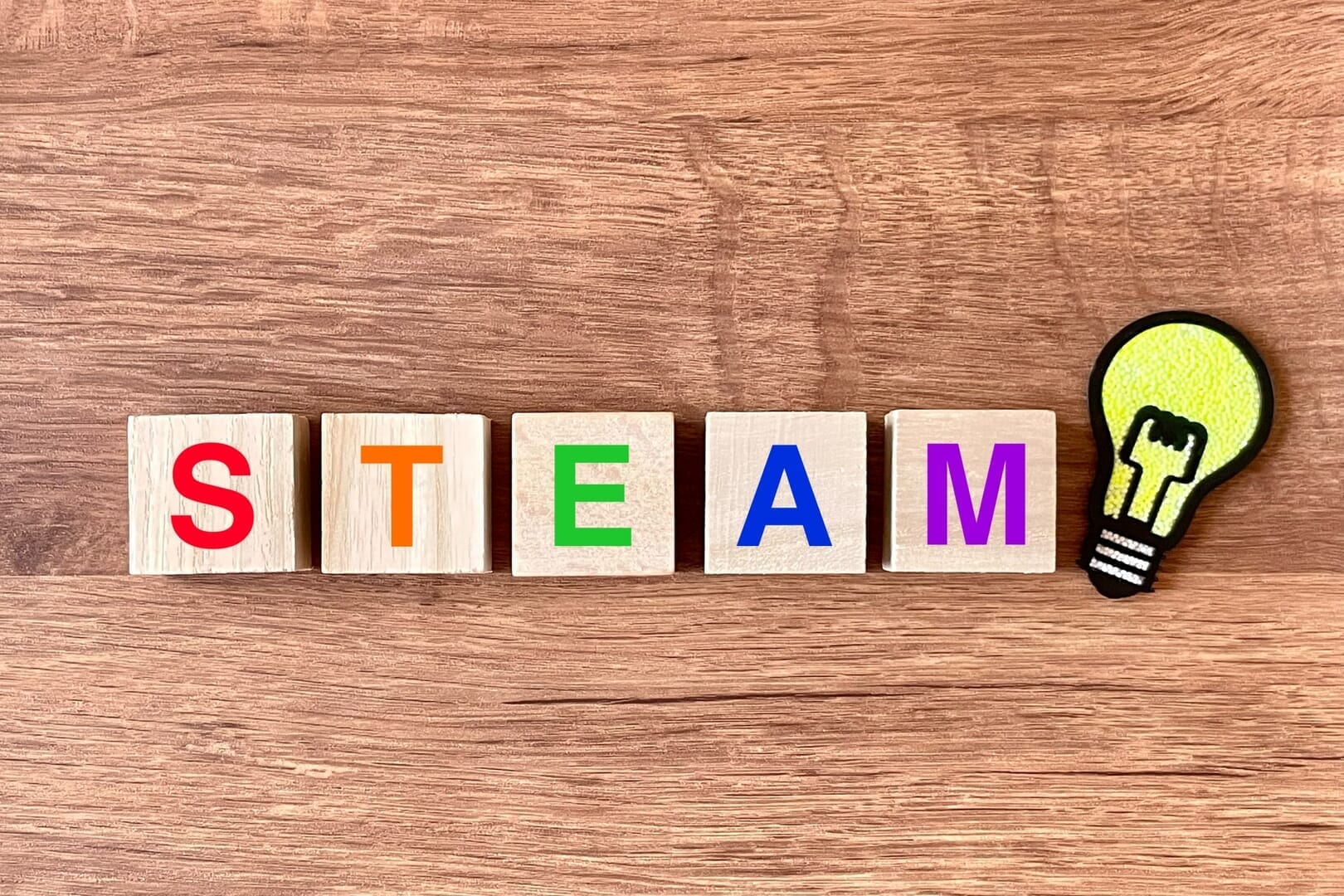前回(【第3回:STEAMの源流】)では、STEAMの「A」を Arts とする流儀と Art とする流儀があることを紹介しました。ただこれは、STEAM教育をする側の理論。受ける側はどのように考えておけばよいのでしょうか。
※本記事は、2021年2月10日に「Z会 STEAM・プログラミング教育情報サイト」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
関連しあっている
少し高校生の頃を思い出してみてください。文系であっても多くの場合、数学で微分・積分の基礎を学びます。数学を独立した教科だと思っていると、微積分の「よさ」はなかなか見えてきません。微積分が得意な方であればご承知の通り、微積分は物理現象を式で表すために生まれました。理系の大学に進学された方は、大学で学ぶ物理が微積分だらけだったことを覚えていらっしゃることでしょう。あるいは、化学で「モル」という概念を学んだことを覚えているでしょうか。モルの概念が理解できずに化学が苦手になる人は少なくありません。しかし、モルの基本は、小学校で学ぶ「比」です。いわゆる「理系教科」は独立しているようで、実は裏では互いに関連しあっているものが多いのです。
そして、学んだことを実社会に活かそうとすると、複数の「教科」がやはり関連しあっていることに気づきます。例えば第2次世界大戦中、イギリスはドイツの暗号を解読しようと必死になります。ここで活躍したのは数学者でした。様々な手法が使われましたが、主には統計学的な手法で読解を試みていたようです。そして暗号読解の際には、当然ながら、言語学的な知識も必要となります。数学だけでも、言語学だけでも足りないのです。
このように、複数の「教科」の内容が関連しあっていることを知り、他教科の観点から別の教科を眺めるという訓練は、知識を生かすためにもしておくべきものでしょう。また、関連しあっていることを知ることで、興味関心を高め、理解を助けることにもつながるはずです。これがまず、STEAMのAを「一般教養」と捉える立場の見方です。
飛び抜けるためには
少し話を飛躍させ、技術革新の例としてiPhoneを考えます。
いま、iPhoneという製品が「失敗作」であると考える人は、おそらくいないでしょう。しかし発表された当時は、「本当にこんなものが売れるのだろうか」と考えていた人は少なくありません。「キーボードがついていないのに、これでメールを打とうとするなど考えられない」「こんなものを買うくらいなら新しいiPod(音楽再生専用の端末)を買うよ」「電話としての出来が悪いから、そのうちに持ち歩かなくなるさ」。この「読み」が正しくなかったのは、今では明らかです。あとづけで考えれば、Appleには「IDEA」があったのでしょう。直感、デザイン、感情、アート、そしてアイディアが。
……でしょ?
このような例は枚挙にいとまありません。飛行機を開発したライト兄弟も「空を飛ぶなど絵空事だ」と言われていたそうですし、自動車が登場した際にも「自動車などを開発するよりも馬を早く走らせることを考えるべきだ」と酷評されたそうです。
このように、「イノベーション」を起こすためには、技術に対する理解だけではなく「IDEA」が必要です。エジソンの「99%の努力と1%のひらめき」という言葉にもあるように、努力だけではたどり着けない、ひらめきが必要な分野があるのです。「ひらめき」を得るためにも、まさにIDEAが必要なのでしょう。
つまり?
STEAM教育を受ける側はどのように考えていればよいのでしょうか。
「ArtsもArtも両方必要である!」
いわゆる「お勉強」をする際には、様々な知識が関連しあっていることを意識するべきです。どの教科も大事であることを忘れずに、教科間の関連を積極的に知るべきでしょう。
また、「IDEA」を鍛えることも必要です。「ひらめき」は、本当になんの脈絡もなくひらめくこともありますが、得てして過去の様々な経験が互いに影響しあってひらめくものです。「IDEA」は「ひらめき」を起こすための、そしてその「ひらめき」が単なる直感ではなく、何かしらの理論に裏打ちされたものであるためのよすがとなるものだと考えています。
このことは、「創作」をする人に共通する感覚ではないのでしょうか。例えば、生涯で1001編のショート・ショートを書いた作家の星新一は、エッセイで次のように書いています。
思いつきとは異質なものどうしの新しい組合わせのことだが、頭のなかで各種の組合わせがなされては消える。そのなかで見込みのありそうなのが、いくつか常識のフルイの目に残る。さらにそのなかから、自己の決断で最良と思われるものをつまみあげる一瞬のことである。分析すれば以上のごとくだが、理屈だけではここに到達できない。私にはやはり、神がかりという感じがぴったりする。
星新一『きまぐれ星のメモ』(角川文庫)「創作の経路」より
星新一のこの分析は、ジョン・マエダが「大学の至るところで毎日見られるなにかを作り出すスキルや批判的な思考」と書いたものと一致するように思えてなりません。
これからのSTEAM教育
これまで、「STEAM教育とはなにか」「STEAM教育をどのように受ければよいか」について考えてきました。今回はZ会の考えるSTEAM教育とその背景を紹介しましたが、さまざまな方が、さまざまな立場で「STEAM教育」について論じています。ぜひ、そうしたものもご覧ください。今後、STEAM教育は当たり前の教育として(名前は残らないかもしれませんが)根付くことでしょう。本記事が、お子さまの将来にとってよりよい形でSTEAM教育を受けられるよう、保護者のみなさまにも考えていただくヒントになったのであれば幸いです。
参考文献
- 新学習指導要領の趣旨の実現とSTEAM教育について ー「総合的な探究の時間」と「理数探究」を中心にー
https://www.mext.go.jp/content/1421972_2.pdf - Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf - Yakman, Georgette (2008) “STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education”
https://www.academia.edu/8113795 - Maeda, John (2013) “STEM + Art = STEAM,” The STEAM Journal: Vol. 1: Iss. 1, Article 34. DOI: 10.5642/steam.201301.34
https://scholarship.claremont.edu/steam/vol1/iss1/34 - 21世紀の教育・学習
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/pdf/001_09_00.pdf - Art(美術)の役割や位置付けを明確にしたSTEAM教育の在り方
https://www.jstage.jst.go.jp/article/artmanabi/1/3/1_202003/_pdf - レファレンス事例詳細「発明王エジソンは“天才とは1%のひらめきと99%の努力である”という名言を残しているが、この言葉の真意について知りたい。」
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000195344 - 星新一『きまぐれ星のメモ』(角川文庫)「創作の経路」
(「STEAM教育ってご存知ですか?」終わり)
バックナンバー
[STEAM教育ってご存知ですか?]バックナンバーは下記からお読みいただけます。
【第1回:蒸気じゃないよ、STEAMだよ】
【第2回:日本のSTEAMは?】
【第3回:STEAMの源流】
【第4回:みんな大事】
Z会サービスの紹介
学年やお子さまの興味に合わせた講座を展開中です。
- おうちで学べる通信教育 Z会のプログラミングシリーズ
https://www.zkai.co.jp/z-programming/ - Z会プログラミングシリーズ 資料のご請求【無料】
https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/