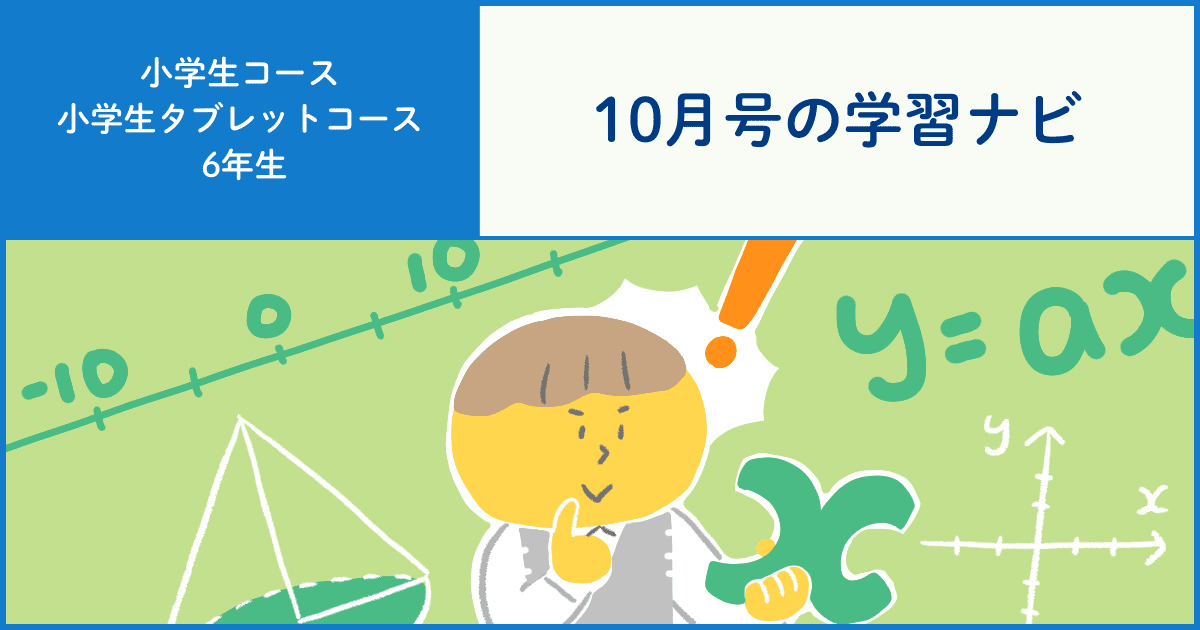前回は「中学生になると変わること」と中学での英語のポイントを解説しました。今回は国語・数学(算数)・理科・社会の4教科について、中学での学習ポイントと、今のうちから取り組んでおきたい学習のヒントをお伝えします。
中学校での学習ポイント
中学校での学習は、新しい概念にふれることの連続です。
たとえば、国語では扱う文章が難しくなり、古典の学習も始まります。算数は「数学」と名前を変え、負の数や文字で表す数など、新たな「数」と出合うことになります。

学校の授業を重視し、家庭では理解のフォローを
未知の概念を確実に理解するためには、学校の授業を大切にすることが重要です。しかし、中学校では国語・数学の授業時数は小学校のころよりも減少します。
短い時間で多くの内容を学習することになりますので、集中して授業に参加し、ノートの取り方も工夫するなど、先生の話を最大限吸収する姿勢を身につけましょう。
それでも、授業中にすべてを理解することは困難な場合があります。そのため、家庭での予習・復習で、「難しそうな箇所の見極め」や「授業中に理解できなかった箇所の確認」を行うことが大切です。
授業と家庭学習をうまく組み合わせることで、「わからないところを見つけ、その部分に時間をかける」という効率的な学習が可能になります。
高校受験に向けて、理科・社会の重要性がより高まる
一般的に、小学校では国語と算数に、中学校では数学と英語に比重を置いて学習を進める方が多くいらっしゃいます。しかし、公立高校入試では、大半の学校で英語・数学・国語・理科・社会の5教科入試が行われ、どの教科も同じように重要視されます。ですから、理科・社会を軽視せず、「5教科すべて取りこぼさない総合力」が大切になります。
また、高校入試は60〜70%が中1・中2で学んだ内容からの出題です。積み上げ学習を行う英数国とは異なり、理科・社会は分野別に学習を行う教科のため、習った後すぐに忘れてしまったり、高校受験間際に初めて苦手に気づいたりといったことが起こりがちです。
とくに公立上位校を志望するお子さまの場合、中1の内容に取りこぼしがないよう、早期から英数国と同様のウエイトで理科・社会の対策をするように心がけてください。
教科別・中学で成績を伸ばすヒケツ

Z会中学生向けコースの学習アドバイザーより、国語・数学(算数)・理科・社会について、小学生のうちに押さえておきたいポイントや、中学でよい成績を取るための学習法の秘訣をご紹介します。
中学で国語の成績を伸ばすヒケツ
<国語はすべての教科学習の源。言葉の力と論理的思考力を磨こう>
小学校では、おもに身近なモノ・人がテーマの文章を読んできましたが、中学からは、言語・社会・科学など、問題文として取り上げられる範囲が一気に広がり、内容も難しくなります。こういった文章に対応できるようになるには、小学生のうちから、次の2点を意識して勉強を進めることが大切です。
①言葉の力をつけること
文章が難しいと感じるのは、意味のわからない言葉が多いことが原因です。今のうちから、意味のわからない言葉は辞書で調べるクセをつけましょう。
②段落ごとに何が書かれているのかを考えながら読む習慣をつけること
考えながら読むことで、文章の構成を意識することができるようになり、「論理的にものごとを考える力」が養われます。
中学で数学の成績を伸ばすヒケツ
<夏ごろの「方程式」の単元を乗り切るために理由をもって式をつくる練習を>
中学生になって最初に学習する単元が「正の数・負の数」です。ここで習う「負の数」というのが、算数と数学の大きな違いになります。負の数を学習することで計算も複雑になるので、小学生のうちに、「ていねいに計算する習慣」を身につけておきましょう。
また、中学1年生の会員の様子を見ていますと、夏ごろに学習する「方程式」の単元でつまずく会員が多いです。中でも、自分で式をつくることに苦労している会員が多く見受けられます。方程式でつまずかないためには、小学生のうちに、「なんとなく」で式をつくらず「理由をもって式をつくる」練習をすることが大切です。これを意識することで、中学生での学習がスムーズに進むようになります。
中学で理科の成績を伸ばすヒケツ
<身近な現象の理解から、原理・法則の理解へ。意味が「腑に落ちる」まで学習しよう>
小学校では、身近な現象を題材に科学的に説明できることを認識できればよかったのですが、中学校の理科ではその現象の背景にある原理・法則までを深く学ぶことになります。
たとえば、小学6年生で習う「ものの燃え方と空気」では、何かが燃えるときに酸素が必要である、というところまでを理解できていればよかったのですが、中学2年生で習うときは「どのくらい酸素が使われるのか」、「燃やす物質の種類によって使われる酸素の量に違いがあるのか」など、実験から法則性を見出し、自分の言葉で説明できるようにならなければいけません。したがって、今は学校のテストで点数がよかったとしても、丸暗記方式で学習を進めていると、中学の理科にはまったくついていけなくなる可能性があります。「腑に落ちる」ところまで理解できているのか、という視点で復習を進めるようにしましょう。
中学で社会の成績を伸ばすヒケツ
<教科書だけではなく、地図や新聞などで「生きた知識」を身につけよう>
中学の社会では、地理的分野・歴史的分野・公民的分野の3つの分野についてくわしく学習していきます。地理では日本や世界の諸地域について学び、歴史では日本の歴史を中心に、世界の歴史や日本と世界の結びつきを学習します。そして公民では、政治や経済のしくみのほか、国際社会について学びます。
知識のインプットが不可欠な教科ですが、ただの暗記ではなく、思考力・表現力が求められる出題にも対応できるような知識を身につけていくことが大切です。そのためには、今のうちから、日本や世界の地図、歴史年表をこまめに見る習慣をつけておくと、都道府県や世界の国々の位置関係、また歴史の大まかな移り変わりがイメージしやすくなり、全体像をつかみながら知識を増やしていくことができます。
また、公民では現代の社会について学ぶので、ふだんからテレビのニュースを見たり、新聞を読んだりして、「生きた知識」にふれておくことが、得意になるヒケツです 。
親子で迎える中学生活、笑顔でスタートしましょう!
お子さまの中学校入学は、保護者の皆様にとっても大きな節目となることでしょう。この時期だからこそ、お子さまと一緒に中学生活への期待を膨らませ、新しい学びへの準備を始める絶好の機会です。お子さまが自信をもって中学生活をスタートできるよう、Z会はこれからもご家庭に寄り添い、応援してまいります。