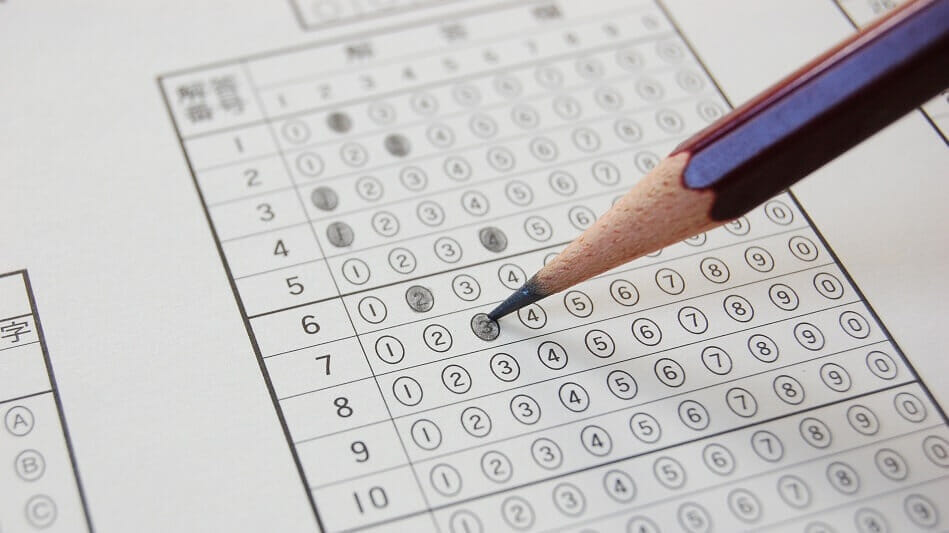2025年1月の大学入学共通テストから、「情報」が入試教科として加わります。来たるべき「情報」入試の内容と、情報入試・情報教育の未来予想図について、全6回にわたって解説いたします。
前回(【第4回:「情報」入試はマイナーデビュー?! いえ、プログラミングと同じくメジャーデビューの準備をしています。】)はこちらからご覧いただけます。
※本記事は、2021年09月09日に「Z会 STEAM・プログラミング教育情報サイト」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
入試にも流行が!
入試にも流行があります。2006年の医学部入試で京都大学、大阪大学をはじめ5つの大学で、大学入試センター試験(以下、センター試験)と2次試験をあわせて、理科が3科目(多くは、物理・化学・生物を選択)必要な時代がありました。その後、九州大学や岡山大学の医学部も理科3科目を課すようになりました。
これは、医学部生に必要な「生物」を受験せずに入学してくる学生に一石を投じたと言えます(また、ゆとり教育の揺り戻しも少し出てきた時期です)。
2011年まで、センター試験では理科3科目の受験が可能な時間割でしたが、それ以降は3科目受験ができなくなっています。……ここにも、【第4回】でふれた、時間割の影響が。
その後、理科3科目受験を必須とする大学は年々減り、九州大学を最後に今では医学部で3科目受験を課する大学はありません。
大学入学共通テストの影響力
このように、過去を振り返ると、時代の流れとともにセンター試験がかわり、その後、入試全体も大きくかわるのです。
今は、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)がそれを担っていると考えることができます。
少し前の、英語の民間試験活用や、記述式試験の導入も大きく取り上げられました。2021年1月は見送りとなりましたが、共通テストは、教育現場全体をかえるくらいの大きな影響力をもっていると言えます。
「情報」入試も、共通テストで1教科になり、情報で一つの試験時間帯となることから、少しずつ教育現場に浸透していっても不思議ではありません。
でも、「情報教育の重要性は認識されているけれど、うーん、まだ信じられないな…。」という方もたくさんいると思います!
ということで、もう1つのもっと身近な?例を……次回へ続く。
(【第6回:「情報」入試は過去の栄光の軌跡をたどれるのか!?…学習指導要領と試験が変わればかわっていきます。】につづく)
Z会サービスの紹介
学年やお子さまの興味に合わせた講座を展開中です。
- おうちで学べる通信教育 Z会のプログラミングシリーズ
https://www.zkai.co.jp/z-programming/ - Z会プログラミングシリーズ 資料のご請求【無料】
https://www.zkai.co.jp/z-programming/catalog/