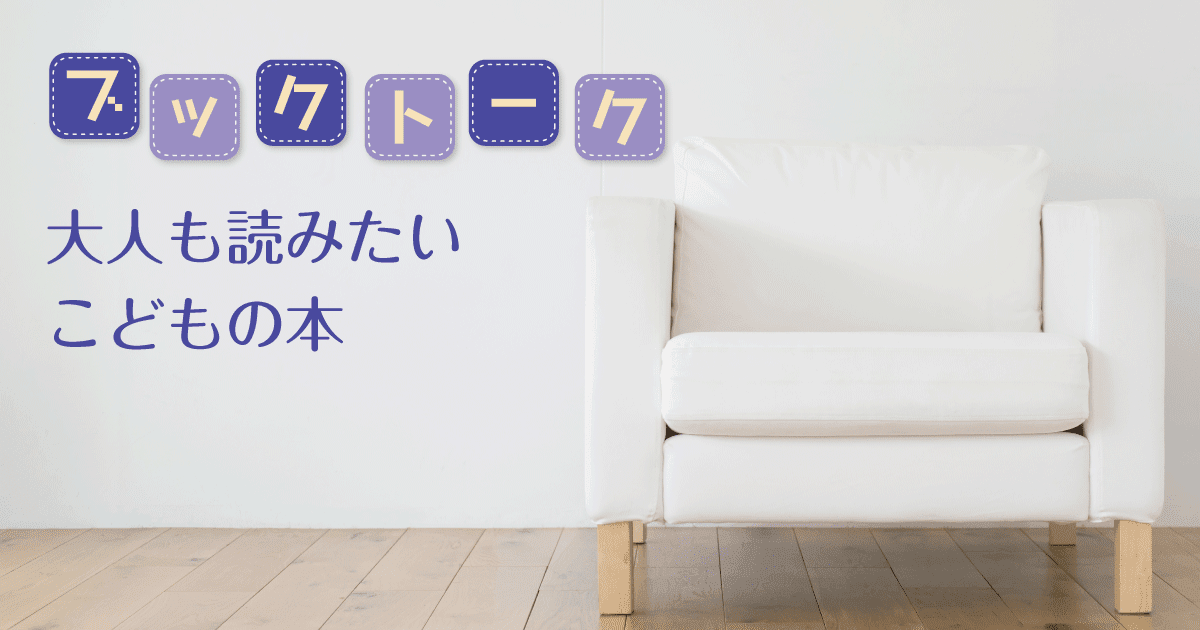世代を超えて読み継ぎたい、心に届く選りすぐりの子どもの本をご紹介いたします。
英国の詩人による短編集
 ジェイムズ・リーブズ 作/神宮 輝夫 訳/岩波書店
ジェイムズ・リーブズ 作/神宮 輝夫 訳/岩波書店
1909年に英国で生まれた作家ジェイムズ・リーブズは、20年ほど教師を務めたあと、昔話の再話や改作を通して伝承文学の魅力を紹介し続けました。また、マザーグースのような古い童謡にも影響を受け、子どもたちのためにユーモラスな詩を多く残しています。この「月曜日に来たふしぎな子」という短編集を読めば、確かに語りそのものは昔話風で、作者は、軽快なリズムでエピソードを積み上げています。6つの短編のなかには、明らかに英国の昔話をベースにしたとわかるお話もあるし、アイルランドに伝わるフェアリーテイルを彷彿とさせるものもありました。
表題にもなっている「月曜日に来たふしぎな子」は、特異な余味を残す短編です。それは、靴の底に入った小さな砂粒のような違和感ではあるけれど、とりわけ、無意識にテーマを探ろうとしてしまう大人の読者を迷わせるかもしれません。この子は何のためにこんないたずらを仕掛けるのだろう、事情があるのだろうか、あるに違いない、きっと改心するのだ、というように、自分なりの物差しを用いて読者は登場人物をはかります。しかし、終盤で、その物差しを取りあげられた時の心もとなさはどうでしょう?マザーグースの融通無碍な詩のごとく、謎は謎のまま。一方で、「ふしぎな子」を受け容れた家族が得られたのは僅かな心の成長だけ、という――ある意味では――潔いお話でもあるのです。
「水兵ランビローとブリタニア」は、アンデルセンの「ナマリの兵隊」と設定が似ています。自力では動けない人形たちが、時に全身をこめて願ったり、また時には偶然訪れた機会を利用したりしながら、自らの望みを叶えようと静かに奮闘します。英国の作家ルーマー・ゴッデンは、このシチュエーションで幾つもの名作を生み出しましたが、どのお話でも、人形の持ち主である少年や少女たちが人形の渾身の願いを受けとめ、動けない人形の味方となり行動するのです。「水兵ランビローとブリタニア」でも、(鑑賞用の置物として)ガラスに閉じ込められた2体の人形たちを援助する女の子が現れますが、その行為は自然で、ちっとも気張っていないので、人形たちと女の子、この3人を応援しながら私はお話を読み終えました。
「エルフィンストーンの石工」は、「トム・ティット・トット」や日本の昔話「大工と鬼六」と同様に、魔物の名前を当て、目当てのものを手中にした男の話です。めっぽう腕利きの石工なのに、怠け癖がどうしても抜けない主人公の人間臭さはもちろん、名前を知られた魔物の末路が昔話とは異なっていて(昔話では、魔物はパチンと消えてしまいます)、おもしろいところです。
最後のお話「11羽の白い鳩」は、おとぎ話とリアリズムが混じり合った風変わりなお話です。シェイクスピアの「リア王」のように子どもから手ひどい裏切りを受ける国王の物語かと思いきや、教訓めいた筋立てはどこにもなく、革命が起きて玉座を追われた王さまもひょうひょうとしています。そして、最終的には音楽が一翼を担い、ハッピーエンドを迎えるのです。
アーディゾーニの挿絵を見ていると、確かにそれぞれは民話を元にした創作物語なのだけれど、どれも人間が懸命に生きる物語であり、それは愛すべき姿なのだなあ、と感じます。文章だけなら、つい読み飛ばしてしまいそうな人形や子どもたちの些細な仕草にもしみじみと気付くことができました。この画家の他の作品と同様、彼の絵がお話に詩情を加え、より馴染みやすく味わい深い一冊にしています。
吉田 真澄 (よしだ ますみ)
長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。
ブックトークの記事一覧はこちら