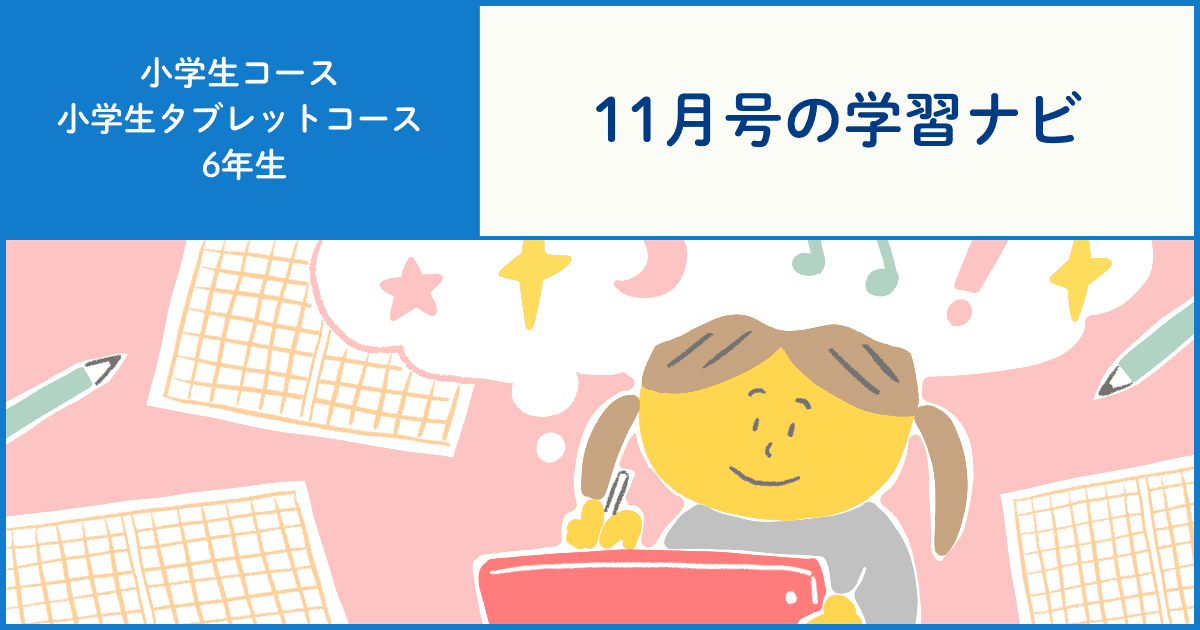今回は、小学生向けコースと中学生向けコースの違いや共通点について、それぞれのコースの代表者が対談形式でお話しします。前編となる今月号では、Z会が大切にする「考える力」や「学習習慣」、そして「書くこと」の重要性、さらに教材開発や添削指導のこだわりについて深く掘り下げていきます。
※本記事は、9月末に一部の方にお届けしたご案内に掲載した記事を再編集のうえ、再掲しています。ご案内には掲載していない内容もございますので、ぜひご覧ください。
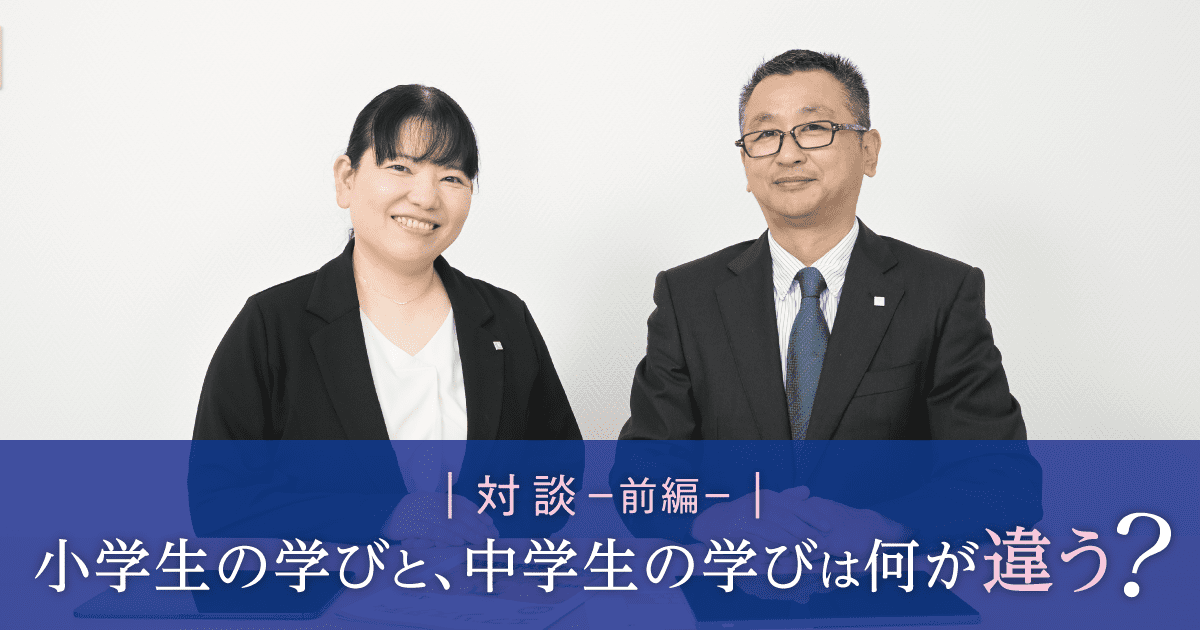

小学生向けコース代表者
鈴木 貴子(すずき たかこ)
株式会社Z会
通信教育事業本部
幼児・小学生事業部
事業部長
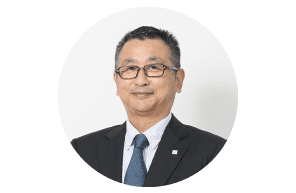
中学生向けコース代表者
祝部 憲孝(ほうり のりたか)
株式会社Z会
通信教育事業本部
中学生事業部
事業部長
「考える力」を育むことは、小学・中学でも大切にしている信念
──それぞれのコースで、コース設計や教材作成上工夫していることは何かありますか?
鈴木 Z会の教材は基礎知識を丁寧に理解できるよう工夫していますが、それだけでなく「考える力」をつけることを重視している点がZ会ならではです。
小学生向けコースでは、ドリルのように機械的に解ける問題ではなく、文章を読んで、「どういうふうに解くといいのかな?」と考えなければ解けない問題を多く出しています。例えば国語だと、小学校の単元テストでは理由を問う問題などは該当箇所を抜き書きで答えることも多いと思います。Z会では、学年が上がるとそのまま抜き書きするのではなく、2つの段落から少しずつ要素を引っ張ってきて自分でまとめ直して書くような問題を出しています。このような、じっくりと本質を考える問題によって、考える力を身につけられるようにしています。
祝部 中学生向けコースも同じです。特に添削問題では、単純な知識を問う問題は出さず、理由を問うような問題、例えば理科であれば、その現象の理由がわかっていなければ答えられないような問題を出します。知識の暗記ではなく、知識を知識として使える状態にもっていく出題をしています。
──小学生、中学生それぞれの時期に身につけてほしい姿勢とはどのようなものですか?
鈴木 小学生向けコースで身につけてほしいのは、家庭学習の習慣をつけることと、自ら学習計画を立てる習慣をつけることの二つです。例えば、タブレットコースの場合、モデルスケジュールからずれてしまった時に、自分でスケジュールを調整できるようにしています。また、紙の教材で学ぶコースの場合、その月の学習を1カ月間で完結させるにはどうすればいいかを考えてもらえるよう、Z会からお届けするカレンダーとシールを使って、自分で計画を立てることをやってもらっています。
祝部 中学生向けコースも同じです。中学生になると、計画を立てて勉強する場がZ会から学校にまで広がっていく、つまり、定期テストという学校でのイベントに向けて実践していく段階に移っていきます。
Z会では、「やるべきことの優先順位をつけながら計画を立てる」「計画どおりにいかない場合に臨機応変に対応して立て直す」という経験を積み、自主的に学習を進める姿勢に進化してほしいと思っています。
──小学生向けコースと中学生向けコースに通底する理念やこだわりについては、お互いにどのようにとらえていますか?

鈴木 先ほどお話しした通り、「考える力をつけること」は、小学生・中学生でも重視していますが、もう一つこだわっていることがあります。それは、「書くこと」です。
祝部 そうですね。書くことによってこそ、自分がどこまで理解できているのか・いないのかに気づくことができるので、アウトプットすることは最も重視すべきだと考えています。そして、足りない視点や知識に気づいていただくために添削指導があります。
鈴木 答案を書く際に盛り込むべき要素を理解しているつもりでも盛り込めていないことって結構あると思います。添削指導はそこをきちんと拾っています。また、算数や数学だと、そもそも問われていることが何かを理解していないと立式ができません。理解を深め、試行錯誤して立式し、解答を導くためにも書いて考えることはとても大事だと思います。
──アウトプットすることは、理解度の確認だけでなく、知識を使うトレーニングの側面もあるように思います。この点について、小学生向けコースから中学生向けコースで変化する面があれば教えてください。
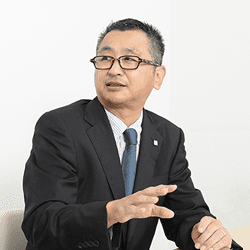
祝部 算数・数学を例に話すと、小学、中学、高校と進んでいくにつれて、扱う題材が数字でイメージする具体的なものから、記号などでイメージする概念的・抽象的なものに変化していきます。中学はちょうどその入り口で、XやYを使って表現・理解するものが出てきて、高校になると、具体がなくなり各種定理の中からどれを使って解答を導き出すかというところから考える概念的な世界になります。その理解の度合いや使い方を、アウトプットすることで確認していくことになります。
鈴木 確かに、国語や英語の素材文も、身近な題材から、だんだんと社会問題など大きな題材に移り、抽象度が上がっていくという点で、数学との共通点がありますね。
添削指導は、高校入試に向けて、教科専門性の高い指導へ
──学習指導要領は時代にあわせて変化してきていますが、その点についてはどう考えていますか?
鈴木 そのときどきの学習指導要領が育もうとしている資質・能力をふまえて問題をブラッシュアップしていますが、その際に、考える力をつけられる問題にする点はぶれないようにしています。例えば、社会では、一問一答の問題を出すのではなく、「この地図から読み取れることは何?」と問うような問題を昔から出しています。今の大学入学共通テストの社会科目(地歴・公民系の科目)で資料をたくさん読ませて読み取れる内容を回答させる問題に通ずるものがありますよね。
祝部 中学生向けコースも同じで、考える力をつけられる問題にすることを重視しています。ただ、一つ、小学生向けコースと異なるのは、高校入試をめざして学ぶ側面があるということです。高校入試の問題にも、流行や学習指導要領をふまえた傾向などがありますから、毎年、入試を分析した上で「こういう出題の仕方をすると、もっと考える力を問う問題になるよね」などと議論して中1から中3まで全学年の教材の見直しをかけています。
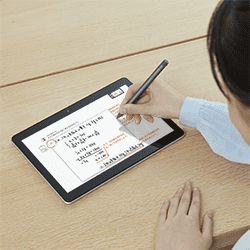
──添削指導では、何を重視して指導されていますか?
鈴木 担任指導者制をとっているコースでは、お子さまの変化や伸びを汲んで褒めるなどして一人ひとりの成長や身につけた力を認めるというスタンスで添削指導を行っています。もちろん、添削の質を維持するために、内部で添削者の先生たちの指導内容をチェックすることもしています。
祝部 中学生向けコースは、担任制ではなく教科専任制に変わるので、小学生向けコースから進級した際に違和感を覚えるところかもしれません。ただ、高校入試に向けて教科ごとに必要な力を養っていくために適した体制だと判断しています。
鈴木 小学生コースでは「ここはもう少しこういう要素もあるとよかったね」といった情緒的な指導をしていたところから、中学生向けコースでは、「この要素が足りていない」と明確に指摘するようになり、より教科専門性の高い指導になっていきますよね。それが、高校入試に必要な力を養うことにつながるということかと思います。
祝部 その通りです。あとは、先ほど話した高校入試の傾向をふまえて問題をメンテナンスした際には、その意図や問題を通じて問うている考え方が生徒さんにも伝わるように、「生徒さんにこういう気づきを与える朱筆を入れていただきたい」と添削者の先生にお願いしています。また、意図した解答を生徒さんが書けているか、書けていない場合は適切に添削指導が入っているか、また、その問題の後に出した問題の正答率にどのように影響したかなどを分析し、教材の設計が適切かどうかを検証しています。