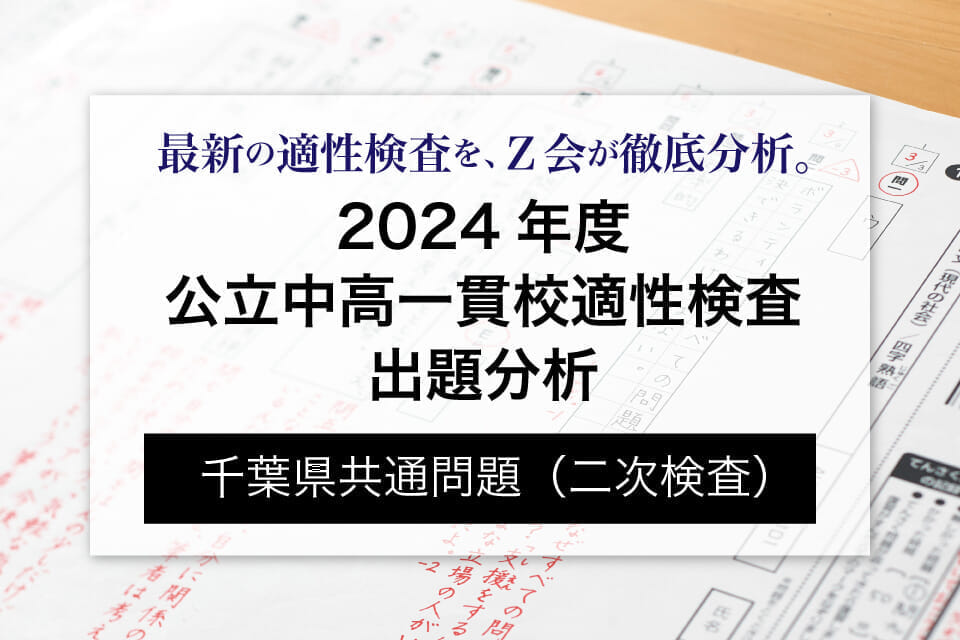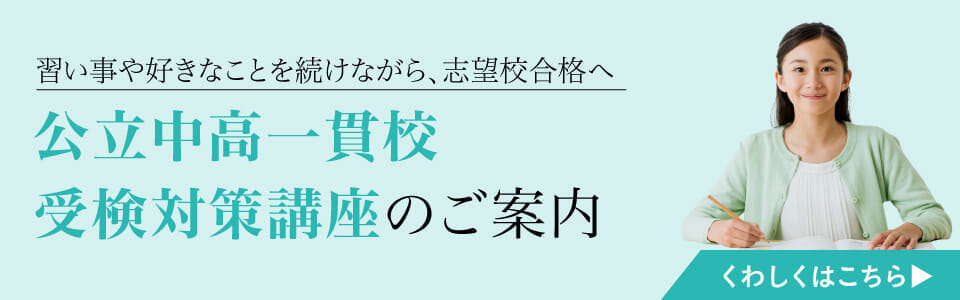出題校
千葉県の中高一貫校では、千葉県の共通問題を使用して、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共通=千葉県共通問題、独自=学校独自の問題)
1-1 |
1-2 |
2-1 |
2-2 |
|
|---|---|---|---|---|
| 千葉県立千葉中学校 | ||||
| 千葉県立東葛飾中学校 |
1-1 |
1-2 |
2-1 |
2-2 |
|
|---|---|---|---|---|
| 千葉県立千葉中学校 | ||||
| 千葉県立東葛飾中学校 |
※1-1・1-2が「一次検査」、2-1・2-2が「二次検査」となります。
全体的な傾向
問題の構成や傾向について、前年度からの大きな変化はありませんでした。
・適性検査2-1
2問構成で、大問1は鏡で反射する光の道すじを考える問題、大問2は渋滞の解消や電車の運行について考える問題が出題されました。
・適性検査2-2
3問構成で、会話文の聞き取りと文章の読み取り、作文が出題されました。
問題ごとの分析
適性検査 2-1(45分)
共通問題(理科分野)
〇テーマ
鏡、光の反射
〇内容
鏡で反射する光の道すじを考える。
◆概要
鏡に映るものから鏡を見る人の目に届く光の道すじを考える問題です。
(1)
2つの回転する鏡が、特定の角度になるまでにかかる時間を求める問題です。会話文の誘導に従って、空欄に当てはまる数を1つずつ考えていきましょう。
(2)
真正面から鏡を見たとき、全身が鏡のどの範囲に映るのかを考える問題です。鏡に物体が映るしくみについて、会話文からしっかりと読み取りましょう。特に「みかけの光の道すじ」について理解することが大切です。
(3)
2つの鏡を使って棒の像を見るとき、その像を見ることができる範囲を作図する問題です。下線部のとおり、2つのみかけの光の道すじをかくだけで範囲がわかります。
(4)
動く2つの鏡を使って棒の像を見るとき、その像が見え始めるまでにかかる時間や、像を見ることができる位置について考える問題です。条件が複雑であるため、1つずつ整理して考えていきましょう。
◆問題ピックアップ!
(※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します)
(4)
①
像が見え始めるまでにかかる時間を求める問題です。会話文の誘導に従って、1つずつ整理して考えましょう。特に「合同」や「拡大図と縮図の関係」などは問題を解くための大きなヒントです。
②
像を見ることができる位置のうち、点Aから最もはなれた位置を求める問題です。
問題文から、最もはなれた位置で像が見えるときの条件を読み取ることはできますが、①とちがい図が用意されていません。そのため、自分で簡単に作図してみるとよいでしょう。
三角形Q2HNと三角形Q2DLが拡大図と縮図の関係になることに注目すると、鏡が移動した長さを求めることができます。
共通問題(算数分野)
〇テーマ
渋滞の解消、速さ
〇内容
条件に合うように、車の移動や電車の運行の様子を考える。
◆概要
車の渋滞や電車の遅れの解消について、順を追って考える問題です。
(1)
示されている渋滞モデルのルールをもとに、車の流れる量や渋滞の解消について考える問題です。
(2)
反対方向に向かう電車がすれ違う場所や時刻について考える問題です。速さについての深い理解に加えて、問題で提示された思考の流れを読み取り、指示に従って答える力も求められます。
(3)
電車のダイヤを動かして遅れを解消する方法を考える問題です。たくさんの条件をすべて満たすようにダイヤを考えなければならない難しい問題です。
◆問題ピックアップ!
(3)
「回復運転のルール」の理解を試される問題です。まずは時間についての条件に特に気をつけながら、丁寧に読んでいきましょう。
条件を整理できたら、運行ダイヤにすでにかかれている直線をもとに、条件を満たすような出発時刻や到着時刻を考えて線を引いていきます。
また、この問題のように複数の条件を満たすような場合を考えるときは、条件を見落としやすいので、解き終わった後にすべての条件を満たしているか確かめることも大切です。
特に、快速電車のB駅の通過時刻は「何時何分ちょうど」にはならないので注意が必要です。前後の間かくが2分以上あることを計算でしっかりと確かめましょう。
適性検査 2-2(45分)
共通問題(国語分野)
〇放送音声
平田オリザ『わかりあえないことから』をもとに作成
◆概要
(1)
会話文の内容を簡単にまとめた図を見て、図の中の空欄にあてはまる言葉を入れる問題です。
聞き取りをしながら、重要なことを適切にメモに取っておくことが必要です。
(2)
会話の内容をふまえて、このあとの話し合いをどのように進めていくのかを書く問題です。
◆問題ピックアップ!
(2)
「りくさん」との話し合いがうまくいかなかった「はるさん」が、そのことについて「まきさん」と会話をしています。この会話が放送内容です。「まきさん」との会話の内容をふまえて、このあと「はるさん」が「りくさん」とどのように話し合いを進めていくかを作文します。
音声放送は一度だけで、問題を先に読んでおくことはできないため、音声を聞き取りながら、話している内容のポイントを確実にメモすることができるかが重要だといえるでしょう。
(1)の解答も参考にしながら、指定された範囲で文章をまとめましょう。
共通問題(国語分野)
〇出典
文章【1】橋本治『「わからない」という方法』より
文章【2】角幡唯介『そこにある山』より
〇内容
2つの文章の読み取り。作文5行程度。
◆概要
(1)
文章【1】についてまとめた文章の、空欄にあてはまる言葉を書く問題です。
いちばん長いもので20字以内と比較的短い言葉ですので、指定された字数に気をつけながら、それぞれの空欄にあてはまる言葉を考えましょう。
(2)
(1)をふまえて文章【2】を説明した文章の、空欄にあてはまる言葉を書く問題です。
(3)
文章【2】をふまえて具体例を挙げながら、文章【1】の文章中の「わかる」状態を説明する問題です。あたえられた三つの〔テーマ〕の中から一つ選んで説明します。
◆問題ピックアップ!
(3)
文章【1】の「わかる」状態について、文章【2】をふまえて自分の体験をもとに具体的に説明します。
文章【1】で述べられている、「わかる」ということを性急に求めるだけでは「なんにもわからない」ということを、文章【2】ではカーナビの例を使って具体的な話をしています。同じような具体例を自分の体験の中から探して書きましょう。
あたえられたテーマ三つのうちどれを選んでもかまいませんが、できるだけ自分が実際に体験したことを明確にできるテーマを選ぶとよいでしょう。
共通問題(国語分野)
〇出典
文章【1】今井むつみ『ことばの発達の謎を解く』より
文章【2】最果タヒ「巻末エッセイ」(谷川俊太郎『星空の谷川俊太郎質問箱』所収より)
〇内容
2つの文章の読み取り。問題2・3をふまえての読解と作文(15~20行)。
◆概要
(1)
文章の内容について整理した図を見て、空欄にあてはまる言葉を選んだり書いたりする問題です。
文章【1】【2】に共通する考え方を読み取りましょう。
(2)
文章【1】と【2】をふまえて、二人が話し合っている内容について考える問題です。
10~15字で自分の言葉を使って書くものが1か所と、【2】の文中からのぬき出しが2か所です。
会話の内容も考えながら適切な言葉を考えることが重要です。
(3)
問題2と問題3の共通点を整理した図に、あてはまる言葉を問題2の文章【2】からぬき出して入れる問題です。
(4)
他県の小学校との交流会に向けて作る、「学校の歌」の「歌詞作成チーム」の一員となったという設定で、その活動について考えを述べる作文問題です。
作文の内容は「自分が提案しようと考える取り組みを問題2【1】【2】の考えを取り入れて具体的に書く」「歌詞作成を進めるときに課題となると考えられることを問題3【2】をふまえて具体的に挙げる」といった条件があたえられています。
15~20行と字数にゆとりはありますが、あらかじめ書くことを整理して、論理的にわかりやすい文章を書くことが求められている問題です。
◆問題ピックアップ!
(4)
設定に沿って、15~20行の作文をする問題です。
自分の考えをただまとめるだけでなく、問題2・問題3の文章の考え方を取り入れて書くことに難しさがあります。
書き始める前に、それぞれの文章のどのような考え方に注目するのか、その考え方を自分の意見にどのように取り入れるのかということを考え、文章の構成を整理してから作文しましょう。
また、段落の構成と内容についても条件で指定されているので、それぞれの段落で書きたいことや文章の量のバランスなどもあらかじめ考えてから書き始められるとよいでしょう。
とくに伸ばしておきたい力
千葉県の二次検査では、「5つの力」をバランスよく伸ばすことが求められますが、とくに伸ばしておきたい力として、論理的思考力が挙げられます。
・適性検査問題2-1
【大問1】
教科基礎力、論理的思考力が必要な問題です。図形の基本的な知識が必要な問題はよく出題されるため、必ず身につけておきましょう。また、あたえられた条件でどうなるかを考える力も大切です。
【大問2】
論理的思考力、情報整理・運用力が必要な問題です。あたえられたルールをそれぞれの場合について適用して、答えにたどり着く力をつけておくことが大切です。
・適性検査問題2-2
【大問1】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。聞き取った内容や、資料から読み取ったことから重要なことを図やメモにまとめ、活用できるようにしましょう。
【大問2】
国語的な教科基礎力、論理的思考力が必要な問題です。読み取った資料について、文章の内容や筆者の主張を論理的にまとめられる力をつけておくことが重要です。
【大問3】
論理的思考力、表現力が必要な問題です。あたえられた条件に従って、自分の考えをだれが読んでもわかりやすい文章で書くことのできる表現力をのばしておきましょう。
おすすめの学習法
ルールやきまりを資料から読み取り、より複雑な条件でどうなるかを考える力を身につける必要があります。
難度がそれほど高くない問題もあるため、それらの問題で点を落とさないことが重要になります。
過去の適性検査を複数年研究して、どの問題を解くべきかを見極め、時間配分について考える練習を積んでおきましょう。
問題ごとに、おすすめの学習法をしょうかいしますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査問題2-1
【大問1】
問題文から物事のしくみやルールを理解し、あたえられた条件でどうなるかを論理的に考える練習をしましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生11月号では、初めて見るような物事や現象を題材に、論理的思考力をきたえる問題にちょうせんします。
【大問2】
読み取った条件をもとに試行錯誤しながら、答えにたどり着く練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、条件に従って答えを推理する問題にちょうせんします。
・適性検査問題2-2
【大問1】
聞き取った音声や資料をもとに重要なことをメモにまとめる練習をしておきましょう。矢印や図の使い方など自分なりのメモの取り方を決めておくと、短い時間でわかりやすいメモを作ることができます。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生9月号では、聞き取りの問題に取り組みます。
【大問2】
説明文や資料を読んで、内容や筆者の主張を図や文章に論理的にまとめる練習をしておきましょう。
【大問3】
読み取った内容や自分の意見の中で作文に必要なポイントをまとめ、全体の構成のメモをつくる練習をしましょう。
Z会の公立中高一貫校受検対策をご紹介!
Z会では、自宅で合格に必要な力を最大限に磨き上げることができる、
「公立中高一貫校受検対策講座」をご用意。
Z会ならではの良質な問題・解説と、丁寧な添削指導で、合格レベルまで引き上げます。