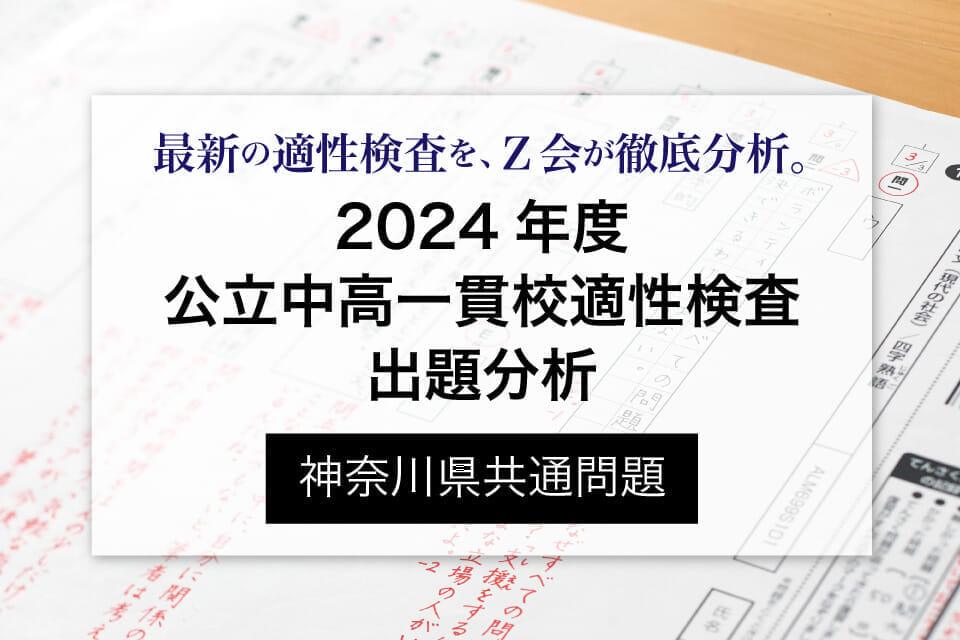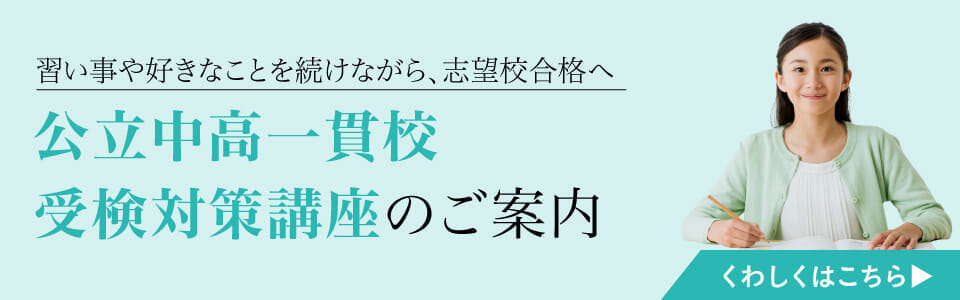出題校
神奈川県の中高一貫校では、神奈川県の共通問題を使用して、適性検査が実施されます。
各学校の問題は、次の表の通りです。
(共通=神奈川県共通問題、独自=学校独自の問題)
| 相模原中等教育学校 | ||
|---|---|---|
| 平塚中等教育学校 |
| 相模原中等教育学校 | ||
|---|---|---|
| 平塚中等教育学校 |
全体的な傾向
適性検査Ⅰの大問数が5問に増えましたが、全体の傾向に大きな変化はありませんでした。
また前年度と同様、マークシート方式による解答用紙が用いられ、マークシートで答える問題と語句や文章で記述する問題がありました。
適性検査Ⅰ、Ⅱはいずれも会話文や表・グラフなどの情報を読み取る問題で、あたえられた情報の中のどこに注目すればよいかを判断する必要がありました。
試験時間に対して問題量が多いため、問題文から正確に情報を読み取る力だけでなく、スピードも求められます。
問題ごとの分析
適性検査Ⅰ(45分)
共通問題(社会分野)
〇テーマ
「標石」による距離の測り方
〇内容
所定の装置を使って2地点間の距離を測る方法を、図や文から読み取り、実際に計算する。
◆概要
問題を解くためには、標石による距離の測定方法について、会話文や、図、文の資料を読み取り、素早く理解する必要があります。
標石という語や、それを使った距離の測定方法は、ほとんどの人にとって初めて知ることばかりだと思いますが、原理はそれほど難しくありませんので、あわてずに読み取れば、全問正解することが可能です。
◆問題ピックアップ!
(※差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題などをご紹介します)
(2)
所定の部品を用いた装置を「125回」動かしたときの距離を求める問題です。
装置を「10回」動かしたときの距離についての説明が資料の中にあり、その考え方を応用すれば解答できるということに素早く気づけるかがポイントとなります。
落ち着いて計算し、確実に正解しておきたい問題です。
共通問題(算数分野)
〇テーマ
候補をしぼって検討する
〇内容
ルールに従って箱を積み上げたときの高さについて考える。
◆概要
直方体や立方体の形をした箱を4人で分け合い、全員の高さが同じになるように積み上げるとき、積み上げた高さについて考える問題です。
同じ箱でも、積み上げる向きによって、高さは3通りの可能性があるため、いろいろなパターンを検討しなければなりません。
特に(2)は、高さが最大や最小にならない向きで積み上げる箱が出てくるため、時間をかけて試行錯誤する必要のある難しい問題でした。
◆問題ピックアップ!
(1)
アではすべての箱を積み上げたときの最大の高さを考え、それを4等分することで、4人で積み上げるときの最大の高さの候補を考えます。
イでは4人のうちで最も多くの箱を使う人の、箱の数を求めます。
どちらも答えを求めることはそれほど難しくありませんが、ここで用いた「最も高い場合を考えて候補をしぼる」考え方は、難問である(2)に取り組むうえでの重要なポイントとなります。ただ答えを出すだけでなく、答えにたどり着くまでの思考の流れも、問題文からしっかり読み取っておくことが大切です。
共通問題(理科分野)
〇テーマ
たんぱく質を含む食品
〇内容
食品に含まれるたんぱく質の量や、食品の生産に必要な水の量、穀物の量などを求める。
◆概要
たんぱく質についての会話文や表から、食品に含まれるたんぱく質や、その生産に必要なものについて、量や割合などを求めます。
会話文や表から、たんぱく質や食品の生産についての内容を読み取る問題です。計算ミスには気をつけましょう。
食品に含まれるたんぱく質の量が、1日に必要とするタンパク質の量の何%にあたるかを計算したり、各食品の生産に必要な水の量を比べたりする問題です。
算数の基礎的な知識が身についていれば簡単に解くことができます。
◆問題ピックアップ!
(2)
アは、ぶた肉と大豆に含まれるたんぱく質の量を、表であたえられた割合をもとにそれぞれ計算し、それらの和が、1人が1日に必要とする量の何%になるかを計算する問題です。
ぶた肉と大豆に含まれるたんぱく質の量の和を求めるだけでなく、それが1日に必要とする量の何%になるのか計算することを忘れないようにしましょう。
イは、アの考え方を使って、大豆の量を求めます。そのあとは、表2で示されている値から式を立てて、水の量を計算します。
共通問題(算数分野)
〇テーマ
ルールに従った考察、場合分け
〇内容
ゲームのルールを読み取って、得点について考える。
◆概要
1~5の数字が書かれたカードを使ったゲームを題材にした問題です。ルールが複雑なので、条件の読み落としや思いちがいがないように、丁寧に読むことが大切です。
カードの並べ方がわかっている状態で、ゲームの進行や得点を考えます。この問題を落ち着いて考えることで、ルールを理解できているか確認しましょう。
(1)でわかったことを利用して、条件に合うようなカードの並べ方の数を考えます。
◆問題ピックアップ!
(2)
(1)とはカードを取る順番が逆になるので、かなこさんがdとeの位置のカードを、たろうさんがaとbの位置のカードを取り、cの位置のカードが残ることになります。
このことをふまえて、a~dの位置へのカードの置き方それぞれについて、たろうさんとかなこさんの得点を調べましょう。
eの位置に5のカードを置くことが決まっているので、dの位置のカードから考えることで、かなこさんの取ったカードの数の和が決まり、検討がしやすくなります。
複数の場合を手際よく検討する必要があるので、うまく情報を整理しながら考えていくことが重要です。
共通問題(国語分野)
〇テーマ
児童会活動の提案
〇内容
全校児童集会をすることになった場合の活動の提案を70字以上80字以内で書く。
◆概要
児童会活動での取り組みについての話し合いを読み、「他学年の児童と交流をして楽しむことを目的とした全校児童集会」の活動を提案します。
話し合いの中での意見をふまえたうえで、どんな活動をするのか自分の意見をまとめます。「具体的な活動とその活動の中で他学年の児童と交流する場面がわかるように」とあるので、その活動に決めた理由などは書かずに、活動の具体的な内容を書きましょう。
適性検査Ⅱ(45分)
共通問題(国語分野)
〇テーマ
ローマ字について
〇出典:
【資料1】『楽しいローマ字』田中博史監修より
※一部表記を改めたところがある。
【資料2】『日本語のローマ字表記の推奨形式』東京大学教養学部英語部会/教養教育開発機構より
※一部表記を改めたところがある。
【資料3】『学校では教えてくれないゆかいな日本語』今野真二著より
※一部表記を改めたところがある。
◆概要
(1)
3つの資料から読み取れることとして正しいものをすべて選ぶ選択問題です。
(2)
3つの資料をふまえて「ヘボン式のローマ字表記」がどのようなものなのかをまとめ、70字以上90字以内で説明する問題です。
◆問題ピックアップ!
(2)
資料の内容をふまえ、「ヘボン式のローマ字表記」が、どの言語に近い表記なのか、どのような工夫によって、誰にとって何がしやすい表記なのかをまとめます。
資料は3つあるので、求められている内容がどの資料に書かれているのかを適切に判断し、わかりやすい文章にまとめましょう。
共通問題(算数分野)
〇テーマ
面積、表を利用した整理
〇内容
条件を満たすような畑の分け方や、各区画で育てる野菜の種類を決める。
◆概要
あたえられた条件をすべて満たすように、畑を4つの区画に分ける方法を考えます。
あたえられた条件をすべて満たすように、4つの区画で育てる野菜の種類を考えます。
どちらの問題でも、それぞれの資料にある複数の条件を考慮しながら、あてはまるものを考えていく必要があります。
◆問題ピックアップ!
(2)
4つの区画のそれぞれで、前期と後期に育てる野菜について考える問題です。アでは表がありませんが、イのような表を自分でかくと考えやすいでしょう。
表を準備できたら、問題であたえられた条件を丁寧に確認しながら、表の空いている部分にはそれぞれどの野菜を入れることができるかを考えていきます。
アでもイでも、育てることのできる野菜の候補が少ない部分から順に検討していくとよいでしょう。
共通問題(算数分野)
〇テーマ
条件に従った考察
〇内容
リーグ戦とトーナメント戦を組み合わせた対戦方式について、試合を行うチームの組み合わせや勝敗を考える。
◆概要
リーグ戦とトーナメント戦を組み合わせた対戦方式についての問題です。
行われる試合の数を考えます。ルールをきちんと理解したうえで、対戦表をきちんとかけば答えを出せるので、確実に正解しておきたい問題です。
リーグ戦の順位やトーナメント戦で試合を行うチームについて考えます。問題で問われている部分だけではなく、リーグ戦やトーナメント戦全体の対戦表を考える必要があります。
◆問題ピックアップ!
(2)
複数の資料であたえられた条件をもとに、リーグ戦の順位とトーナメント表を考える問題です。条件や考えるべきことが多いので、何から考え始めればよいか困った人も多かったかもしれません。
まずは「リーグ戦でどの組とどの組が同じグループだったか」を考えるなど、少しずつステップをふんで求めていきましょう。
また、トーナメント戦の組み合わせを考えるときは、「リーグ戦で試合をした相手とトーナメント戦で再び試合をするのは、準決勝か決勝である」ということに気づくと一気に解きやすくなります。
イでは※で示された順番で対戦カードを書き表す必要があります。このような細かい条件にも注意をはらいましょう。
共通問題(理科分野)
〇テーマ
文字や絵を数字に置き換える仕組み
〇内容
ある規則をもとに図を数字に置き換えたり、その逆のことをしたりする。
◆概要
コンピュータにも使用されている、図を数字へ置き換える規則について考えます。
会話文や資料から〔置き換え方〕を読み取り、指定された数字がどのような数字に置き換わるかを考える問題です。
数字から図を作成するという、(1)とは逆の作業をします。最終的には、方眼紙のマスが最も多くぬられている列を求めます。
◆問題ピックアップ!
(2)
アは、(1)のまとめのような内容になっています。一見複雑そうな〔置き換え方〕ですが、(1)で理解した作業を6行分正しく行えばよいだけなので、そこまで難しくありません。
イは、数字を図に変換する問題です。はじめに、〔パリティ〕として付けられた1番左の数字をひとまとまりの数字から取り除くと考えやすくなります。
続いて、〔圧縮〕とは逆の作業、つまり残った数字のまとまりを0と1に変換します。変換した数字が6個になったか、「1」の個数と〔パリティ〕が合っているかをチェックするとよいでしょう。
とくに伸ばしておきたい力
神奈川県では、より伸ばしておきたい力として、情報整理・運用力、論理的思考力が挙げられます。
あたえられた多くの情報の中から問題を解くために必要な情報を探し出したり、情報を読みかえたりする力が求められます。
・適性検査Ⅰ
【問1】
情報整理・運用力が必要な問題です。多数の資料を素早く読んで内容を理解し、解答に必要な情報を手際よく探し出せるようにしましょう。
【問2】
論理的思考力が必要な問題です。検討すべきパターンを最小限にしぼりこむ力と、しぼりこんだパターンを丁寧に検討して答えにたどり着く力をつけておきましょう。
【問3】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。各表から計算に必要な値を正確に選び、式を立てる力をつけておきましょう。
【問4】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。複雑なルールを理解する力が第一に求められます。また、様々な場合を適切に整理して、手際よく検討する力もつけておきましょう。
【問5】
課題解決力、表現力が必要な問題です。自分が考えた意見・提案について、他の人がわかるように適切な文章で表現する力をつけておきましょう。
・適性検査Ⅱ
【問1】
情報整理・運用力、表現力が必要です。複数の資料から必要な情報を探し出し、文章にまとめる力が求められます。限られた字数の中でわかりやすく伝えられるよう、書くべきことを整理する練習をしておきましょう。
【問2】
情報整理・運用力が必要な問題です。複数の資料を見比べて必要な情報を読み取る力と、読み取った情報を整理して順を追って考える力が求められます。
【問3】
論理的思考力が必要な問題です。あたえられた条件を読みかえて、順序だてて検討する力が必要です。
【問4】
情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。初めて見る規則を正確に読み取り、それをさらに使いこなす力が求められます。
おすすめの学習法
複数の資料の読み取りが必要なため、手がつけにくい印象を受けますが、比較的解きやすい問題もあります。
読み取った情報を文章や図などに整理する練習をしっかりしておくとよいでしょう。
問題ごとに、おすすめの学習法をしょうかいしますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。
・適性検査Ⅰ
【問1】
複数の資料から必要な情報を読み取る練習を行っておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生11月号では、長い文章や、複数の資料から、問題のポイントを読み取り、記述を行う練習ができます。
【問2】
条件を利用して調べるべきパターンをしぼる練習と、しぼりこんだパターンを一つ一つ丁寧に検討する経験を積んでおきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生1月号では、遊園地のパビリオンを回る順番を題材に、絶対に見ることができない展示について考えてパターンをしぼり、条件を満たす回り方を見つけ出すことにちょうせんします。
【問3】
複数の資料から必要な情報を読み取る練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生10月号では、表やグラフから必要な情報を読み取る問題に取り組みます。
【問4】
複雑なルールを正しく読み取って検討を行う練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生12月号では、複雑なルールのゲームを題材にした問題に取り組みます。
【問5】
あたえられた文章を正しく読み取り、自分の意見を表現する練習をしておきましょう。
また、課題解決力については、Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生4月号で、「話し合い・説明す、「話し合い・説明する」というテーマで練習します。
・適性検査Ⅱ
【問1】
複数の資料を読み取る問題を解いて、書くべきことをメモなどに整理する練習をしておきましょう。
整理したメモをもとに指定の字数に合わせて作文することで、だれが読んでも論理的にわかりやすい文章を作ることができます。
【問2】
複数の資料から必要な情報を読み取る練習や、表などを利用して順を追って考える練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座5年生9月号では、複数の資料から読み取った情報をもとに、移動経路を考える問題にちょうせんします。
【問3】
あたえられた条件をもとにひとつずつ順を追って考えていき、答えにたどり着く練習をしておきましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、条件からわかるところからひとつずつ整理して、答えにせまっていく問題に取り組みます。
【問4】
あたえられた規則に従って、会話文や資料などから読み取れることをひとつずつ整理する習慣をつけましょう。
Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生6月号では、資料からわかることを順に整理する問題に取り組みます。
Z会の公立中高一貫校受検対策をご紹介!
Z会では、自宅で合格に必要な力を最大限に磨き上げることができる、
「公立中高一貫校受検対策講座」をご用意。
Z会ならではの良質な問題・解説と、丁寧な添削指導で、合格レベルまで引き上げます。