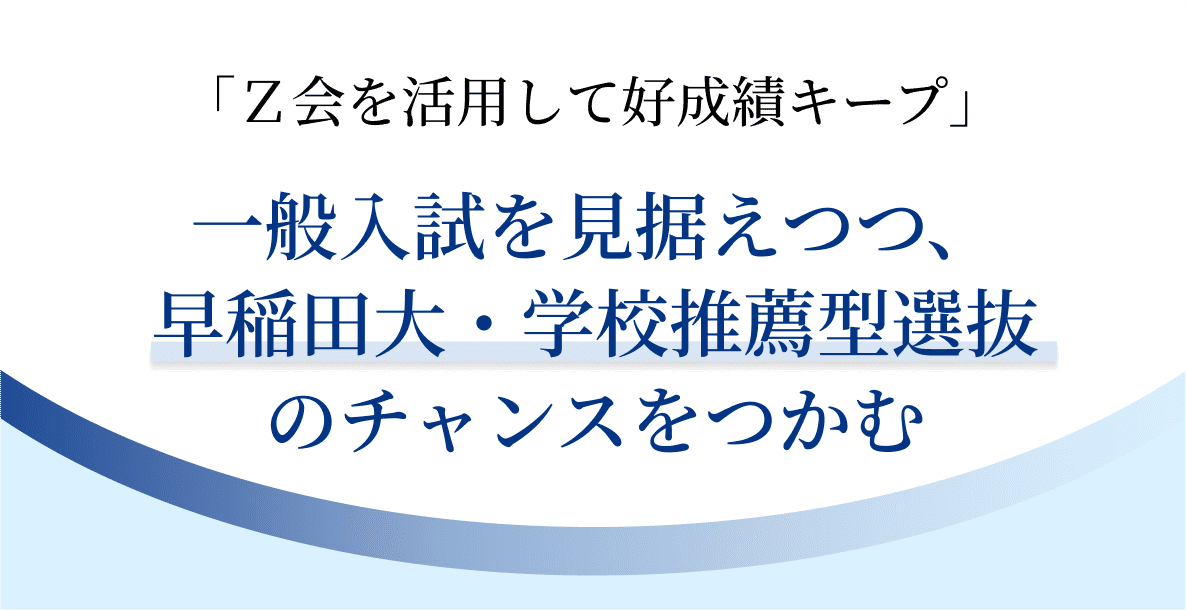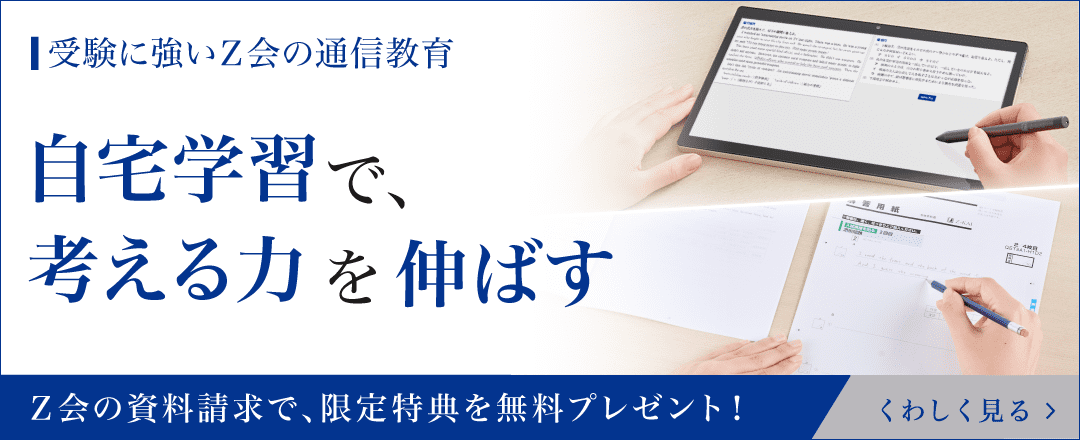多様化する入試方式。高校3年間、一般入試受験を見据えてZ会を活用し、定期テスト対策と応用力の養成に努めた結果、学校で好成績を修め、早稲田大学法学部の学校推薦型選抜・指定校推薦入試のチャンスをつかんだ先輩の学習法を紹介します。
2025年、早稲田大学法学部に学校推薦型選抜(指定校推薦入試)で合格・入学。高校時代はZ会を定期テスト対策にも活用しながら基礎力と応用力を強化。学校では生徒会執行部に所属し、高3時には生徒会長も務めた。
早稲田大学法学部をめざしたきっかけ
Z会:早稲田大学法学部への合格、おめでとうございます! どのような経緯から志望されたのですか?
Sさん:私は高校3年間で志望校をすごく変えたのですが、最終的にたどり着いたのが早稲田大学法学部でした。
Z会:志望校はどんなふうに変わっていったのですか?
Sさん:高校入学当初は国公立大志望で、医療系の学部を考えていました。ただ、医療系は学部を選択した時点で将来の職業が決まってしまう面があるので、それよりも自分の視野を広げたいと思うようになり、高2の文理選択では文系を選択しました。当時興味を持っていたのは経済学です。
その後、大学を調べていくうちに私立大特有の特徴的な科目を大学では受講したいと思うようになりました。そんなとき、面白そうだと思って行った裁判傍聴で興味を持ったのが法学です。法学を学べて自分に合いそうな大学を探した結果、早稲田大学法学部が候補の一つになりました。
Z会:指定校推薦入試で合格されましたが、いつごろから指定校推薦での受験を意識されていましたか?
Sさん:自分の高校に推薦枠があることを知ったのが高3の8月末ごろで、それまではずっと一般入試を見据えて勉強していました。推薦枠の存在を知って、アドミッション・ポリシーなどを調べていくうちに行きたい気持ちが強くなり、学校に希望を出したところ、評定平均の基準を満たしていたことなどから推薦してもらえることになりました。
高1・高2の学習法
Z会:指定校推薦の基準をクリアできる評定を得るには、高1から継続的に学校の勉強に取り組むことが重要かと思います。日々どのように勉強していましたか?
Sさん:まずは授業の内容は授業内で理解することを徹底していました。ただ、苦手な科目は授業内だけでは理解できないことも多かったので、わからない点は先生に質問しに行って教わっていました。宿題がなく、予習や復習も任意で、自分で必要な勉強をするよう言われる高校だったので、定期テストを見据えて学校から配布されているワークに取り組んだり、単元の理解がある程度進んだら復習のためにZ会に取り組んだりしていました。大事にしていたのは、定期テストでしっかりと得点して、評定をとっておくことです。
Z会:それはなぜですか?
Sさん:高校入試の際、当日の学力試験であまり得点できず、評定に助けられて合格したからです。高校でも評定をとっておけば何かにつながるかもしれないと思い、定期テスト対策には手を抜かず、Z会も科目を満遍なく受講して定期テスト対策に活用しました。負けず嫌いな性格も影響していたと思います。
Z会:勉強時間はどのように作っていましたか?
Sさん:片道1時間の電車通学をしていたので、行きの電車の1時間と帰宅後が主な勉強時間でした。電車では30分ずつ計2科目勉強することにして、たとえば数学なら単元の始まりの時期には学校のワークを解き、単元が進んできたらZ会の問題を30分で1問解いたりしていました。帰宅後はその日の体力に応じて、30分だけ勉強したり、集中できたときは2時間くらい勉強したりしていました。
Z会:Z会に取り組む日は決めていましたか?
Sさん:計画をみっちり立てて取り組むというよりは、常に通学カバンの中にZ会の教材を携帯して、状況や心境に応じて科目や問題を選んでやっていました。たとえば、「気分が乗らないけれどさすがにそろそろやらないと添削問題が溜まってしまうから今日は得意科目をやろう」とか、「今日は頑張れそうだから苦手科目と向き合おう」という感じです。
定期テスト対策とZ会
Z会:定期テスト対策には、Z会をどのように活用されていましたか?
Sさん:主に数学と英語で使っていました。まず数学は、定期テストの最後に出題される発展的な問題がZ会の問題と似ていることが多かったので、その対策として定期テスト前にテスト範囲の添削問題を解くようにしていました。また、苦手な単元や、解説を読んだだけではわからなかったところは映像授業を見たりもしました。
英語も、定期テストに出る初見の長文に対応するために、テスト前に添削問題をいくつかピックアップして解いていました。初見の長文を自力で見つけるのは大変ですが、Z会は哲学的な文章や小説など、様々なテーマやジャンルの文章が出るので役立ちました。
Z会:苦手科目はどのように活用されていましたか?
Sさん:国語が苦手だったので、毎日触れて文章や問題に慣れるようにしていました。定期テストのためというよりは、受験のためという意識で取り組んでいました。
数学の苦手意識を克服。得意科目に
Z会:Sさんは、苦手意識のあった数学を高校3年間で得意科目に変えられたそうですね。
Sさん:はい。高校受験で得点できなかった原因が数学で、高校入学後も高校数学を勉強してみて「嫌い」と思いました。
でも、取り組んでいくうちに、勉強すればいちばん点数が伸びる科目だと感じて。当時は国公立大志望で理系や経済学部を進路に考えていたのでなおさら数学は必要ですし、文系に進むにしても、文系で数学が苦手な人は多いので自分は得意にした方がいいかもしれないと考え、とりあえず数学を極めようと決めました。苦手な単元もありつつ勉強を続けていたら、最終的にはいちばん得点できる科目になりました。
Z会:どんなふうにZ会を活用されましたか?
Sさん:まず、教科書と学校のワークで基礎を固め、Z会のAI速効トレーニングで繰り返し復習しました。さらに、苦手な単元は青チャートで演習し、その上で応用問題の演習としてZ会の添削問題に取り組みました。これは高1からいろんな方法を試した結果、高2で確立した数学の学習サイクルです。基礎を固めないと得点は伸びないので、簡単な問題もちゃんと解けるようになることを重視しました。
Z会:AI速効トレーニングは、どのように活用しましたか?
Sさん:タブレットを毎日持ち歩き、電車での移動中や、学校で取り組んでいました。難しい問題も出てきますが、最初はわからなくても演習していけば解けるようになるかなという気持ちで淡々と解いていました。
Z会:添削問題は、数学の力を伸ばす上でどのように役立ちましたか?
Sさん:高1・高2の添削問題が、そのまま応用的な問題の解答を組み立てるプロセスになっているんですよね。具体的には、(1)、(2)、(3)…という小問の出題順が、その大問を完答するためのプロセスになっています。
だから、たとえば「(3)までは解き切れなかったけれど、(1)は解けたし、(2)も悩んだけど解けた」という問題であれば、(3)がなぜ解けなかったのか、どう考えれば解けるのかを復習して最後まで解き切れる状態にしました。そうやって演習と復習を積み重ねていくと、大問を解くプロセスがわかるようになってきます。すると、高3で真っ白な答案用紙に記述答案を書くことを求められたときにも、高1・高2でずっとやってきた小問を解き進めるプロセスを発展させて答案を組み立てることができました。数学の記述問題の得点を最大化できるようになる上で、このプロセスを踏めたことがよかったと思います。
Z会で自然と受験を見据えた学習ができた
Z会:3年間コツコツと勉強されて、定期テストでしっかり得点できる力と、一般入試にも対応できる力をつけていかれたのですね!改めて、Z会を受講して良かった点を教えてください。
Sさん:入学当初から大学受験を意識して学校の勉強に取り組んでいたので、Z会で演習した問題の類似問題が学校の定期テストや模試で出題されたときに、Z会でいろいろな問題に触れていてよかったと思いました。
Z会には、将来、個別試験で得点を重ねるためのプロセスや要素が高1から含まれていて、高3になって過去問などに取り組むときに戸惑わないような教材が揃っています。高1から意識的に受験を見据えなくても自然と見据えた勉強ができるので、コツコツやっておくのはすごく大事だと思います。
Z会:本日は貴重なお話をありがとうございました!
Z会公式おすすめアカウント
ぜひフォロー・友だち登録をお願いいたします