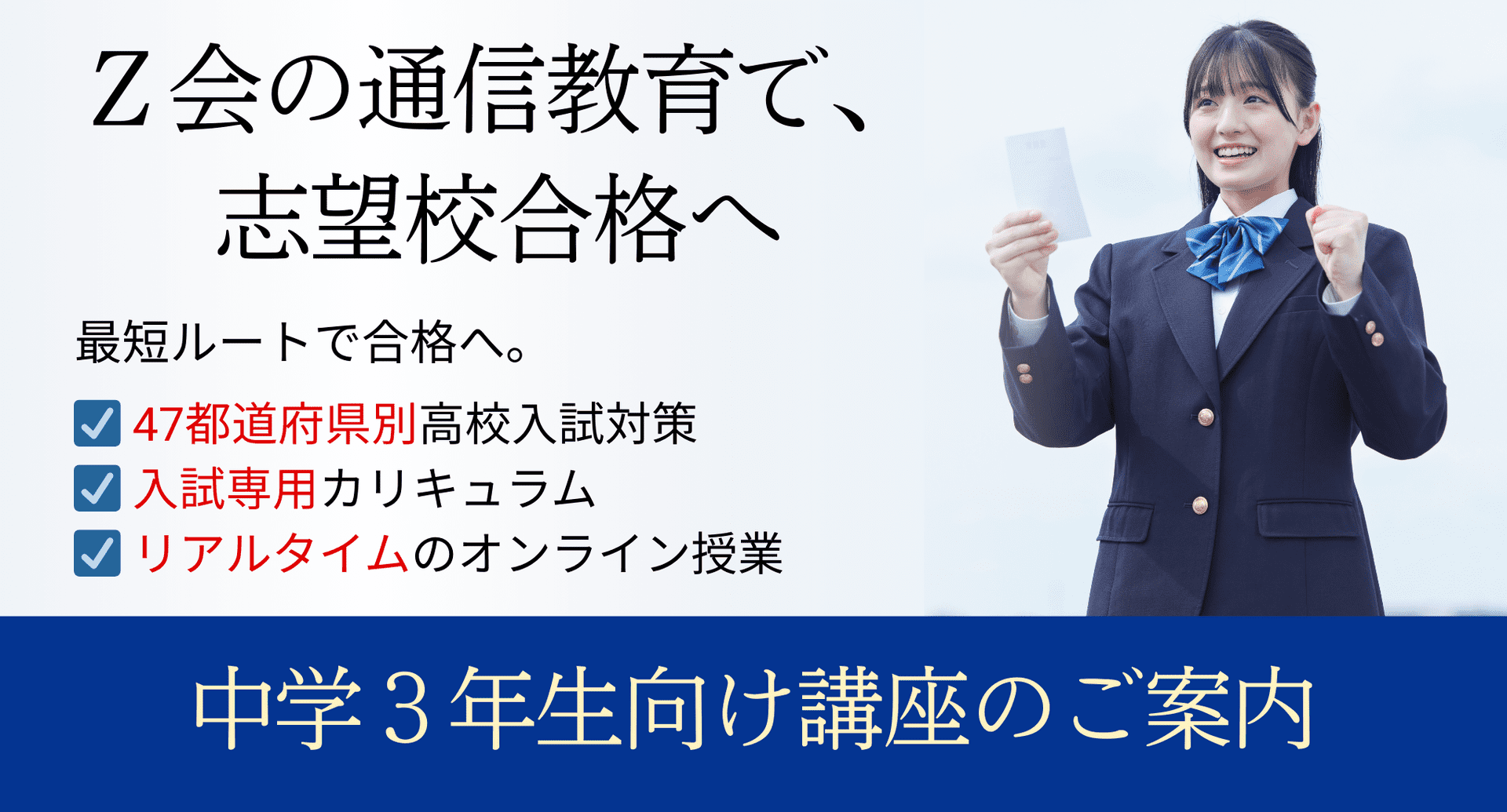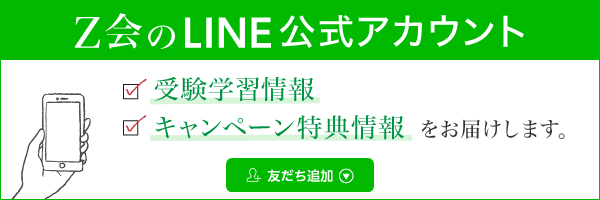高校受験生や保護者のみなさんは、「過去問」についてこんな疑問をお持ちではないでしょうか?
・いつから始めればいいの?
・何年分を、何回繰り返すべき?
・ただ解くだけじゃなく、どうすれば効果的?
この記事では、これらの疑問に明確に答え、最短で合格をつかむための過去問活用ロードマップを徹底解説します。
入試問題を入手して「相手」を知ろう!
まず、大前提として入試問題は確認しましたか?入試問題をまだ見ていない方は、まず入手しましょう。
①入試問題の入手方法
・公立高校
多くの都道府県では、各教育委員会のWebサイトから過去問を閲覧・ダウンロードできます。
また、「○○県学力検査問題」で検索するのも有効です。
・私立高校
各学校のWebサイト上で過去問が公開されている場合と、そうでない場合とがあります。事前に確認しておきましょう。
Webサイト上にない場合は、書店などで販売されていないか確認するのもいいでしょう。
②入試問題の種類と注意点
公立高校の入試問題は原則どの高校も同じ出題ですが、都道府県によっては特定の高校だけが別問題になっているケースがあります。
・「自校作成問題」「学校選択問題」「裁量問題」
・「A問題・B問題・C問題」からの選択制
事前に教育委員会のWebサイトで確認しておきましょう。
また、公立高校の入試問題は時間内に解き終えることが難しい分量が出題される傾向があるため、制限時間も一緒に調べておきましょう。
③過去問題集の選び方
購入する場合は、複数年分の収録があり、出題分野や単元の表記があるものがおすすめです。
出題傾向や頻出分野が丁寧にまとめられているので、入試問題全体の構成をつかむのに役立ちます。
過去問演習開始時期の「3段階」ロードマップ
過去問演習は、やみくもに始めるのではなく、目的別に3つの段階に分けて取り組むのが効果的です。
【9月〜10月】傾向把握と苦手分野を「知る」(1年分でOK)
目的
志望校の出題傾向(形式、配点、頻出単元)を把握し、自分の弱点を見つける。
やるべきこと
・時間を測らずに過去問に目を通す。
・「この形式は慣れが必要だ」「この単元はまだ習ってない」など、気づいたことをメモする。
・とくに英語のリスニングや国語の長文読解など、時間がかかる問題に早めに慣れておく。
ポイント
この段階では「点数」は気にしなくてOKです。あくまで志望校の入試問題という「相手」を知り、
自分の弱点という「地図」を作る時期だと考えてください。
【11月〜12月】実戦形式で「時間配分」の特訓(複数年分解こう)
目的
本番と同じ時間配分で問題を解く練習を重ねる。
やるべきこと
・本番と同じ制限時間(+解答用紙を用意し)の実戦形式で解く。
・「どの科目から解くか」「難問は後回しにするか」といった戦略を立てる。
・ 解き終えたら徹底的に復習する。
ポイント
この段階では解く前の戦略と解き終わった後の復習が何より重要です。
時間配分についての試行錯誤をして、自分なりの「道筋」を確立してください。
間違えた理由については、パターン(知識不足や計算ミスなど)に分類し、1つずつ克服していきましょう。
【1月〜2月】入試直前の「自信」をかためる時期
目的
過去問の解き直しと苦手分野の最終確認で、本番への自信をかためる。
やるべきこと
・新しい問題集には手を出さず、過去問の解き直しと復習に集中する。
・間違えた問題や、時間がかかった問題を再度解き、確実に正解できるようになるまで繰り返す。
・本番で合格点が取れることを確認し、自信を持って試験に臨む。
ポイント
この段階では「本番でこの問題が出たら解ける」という自信を積み重ねることが重要です。
新しい問題集に手を出すと、中途半端な知識が増え、かえって不安や焦りが増す可能性があるため、解き直しに力を注ぎましょう。
合格を左右する過去問活用「3つの秘訣」
ただ過去問を解いて答え合わせをするだけでは、効果は半減します。以下の3つの秘訣を意識しましょう。
①とくに11月以降は、時間を測って本番をシミュレーションする
入試は時間との勝負です。時間を測って解くことで、本番の緊張感に慣れ、時間配分の感覚を養うことが何より重要です。
また、5教科を通しで解く際は、科目間の休憩時間も入試本番の時間割に合わせて取るようにします。
これにより、集中力の維持や切り替えの練習にもなります。
②丸付け後の「復習」を徹底する
過去問の価値は「解くこと」よりも「復習すること」にあります。
間違えた問題はもちろん、正解した問題でも自信がなかったものや時間がかかったものは必ず見直しましょう。
「なぜ間違えたのか」、「どうすれば解けたのか」をノートにまとめ、弱点克服に特化した自分だけの参考書を作りましょう。
③優先順位をつけながら、複数年分取り組む
同じ学校でも、出題傾向は同じ都道府県や同じ学校でも毎年少しずつ変わります。複数年分解くことで、より深い傾向をつかむことができます。第1志望は最低でも3年分、できれば5年分を解きましょう。
一度解いた問題でも、数週間後に時間を置いてから解き直すことで、知識が本当に定着しているかを確認できます。
また、併願校については、時間が許す限り1~3年分程度解くと大まかな傾向をつかむことができます。
過去問演習と並行してやるべき3選
過去問はあくまで「本番形式の演習」です。過去問だけでは補えない部分にも目を向けましょう。
①基礎学力の定着
過去問で「基本的な知識が抜けている」と感じたら、一度立ち止まって教科書や基礎問題集に戻りましょう。
応用問題は基礎の土台の上に成り立っています。
②苦手分野の集中演習
過去問で見つかった苦手単元は、その分野に特化した問題集を使い、集中的に演習を重ねましょう。
過去問の復習で解けなかった問題やその周辺知識を理解し、関連事項をノートにまとめるのも有効です。
③体調管理
受験勉強は長期戦です。無理なスケジュールは避け、十分な睡眠と栄養を確保し、万全の体調で本番に臨むことが何よりも大切です。時にはリフレッシュをして気持ちを整えていきましょう。
過去問は、志望校合格への強力な武器です。
時期と活用法を正しく理解し、計画的に取り組むことで、合格をぐっと引き寄せることができます。
☑高校受験 過去問活用チェックリスト
このチェックリストを活用して、過去問演習を効果的に進めましょう。
□志望校の過去問(1年分でOK)を入手した
□制限時間を気にせず、まず問題全体に目を通した
□出題形式(リスニングの有無、長文の長さなど)を把握した
□まだ習っていない単元や、苦手だと感じた分野を特定した
□苦手分野を克服するための学習計画を立てた
【11月〜12月】実戦演習と時間配分の時期
□本番と同じ制限時間を測って過去問を解いた
□解き終わった後、すぐに答え合わせと見直しをした
□偶然正解した問題も含め、わからなかった問題を明確にした。
□なぜ間違えたのか(知識不足、計算ミス、読み間違いなど)を分析した
□時間配分に問題がなかったか確認し、次の改善点をメモした
【1月〜2月】最終仕上げと自信をかためる時期
□新しい問題集には手を出さず、過去問の解き直しに集中した
□過去問で間違えた問題や苦手分野を再度解き、完全に理解できた
□過去問で合格点(または目標点)が取れることを確認できた
□毎日十分な睡眠を取り、体調管理を徹底した
□入試直前は新しい情報に振り回されず、自信をもって取り組めた
Z会で過去問演習をさらに効率化しよう!
過去問を解いてみて、苦手な単元や、入試で差がつく問題がわからず困っていませんか?
そんなときは、Z会の高校受験コースがおすすめです。
『入試特訓カリキュラム』により、中学3年間の入試重要ポイントを効率的に学べるため、限られた時間で成果を出せます。さらに、47都道府県の入試傾向に合わせて厳選された実戦問題と、丁寧な個別添削指導が、あなたの課題を「解ける!」に変え、合格に直結する得点力を伸ばします。
効率的かつ確実に志望校合格をめざすなら、以下をご確認ください。
期間限定のお知らせ
自信をもって新学年を迎えよう!新中学1~3年生向け『春の新学年スタート応援キャンペーン』実施中!
▼キャンペーンの詳細はこちら
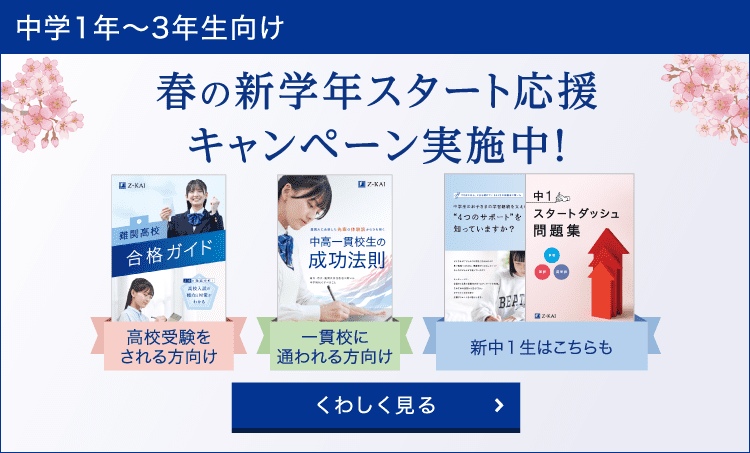
友だち追加でお役立ち情報を配信中!