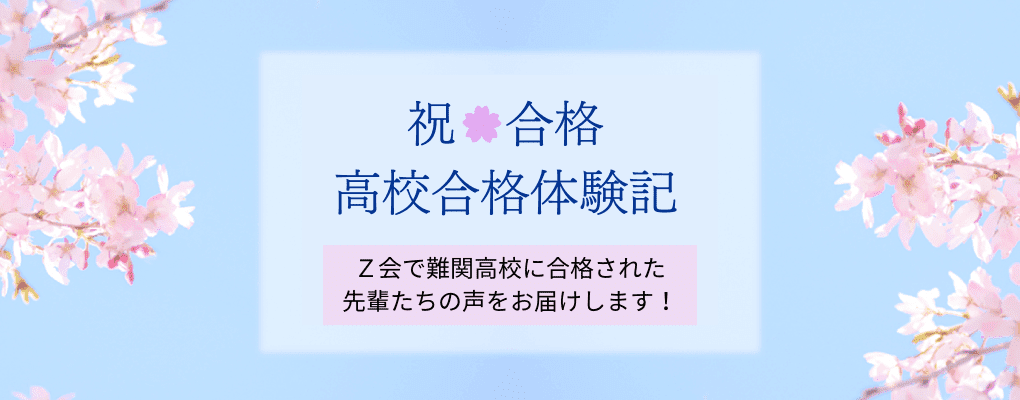
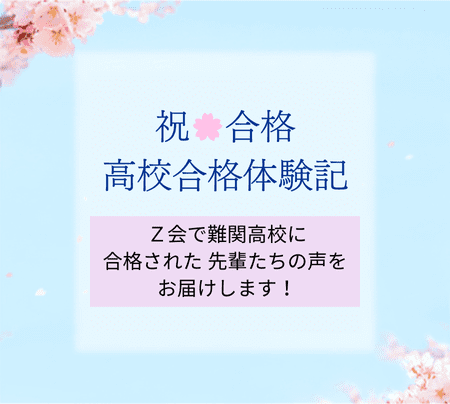
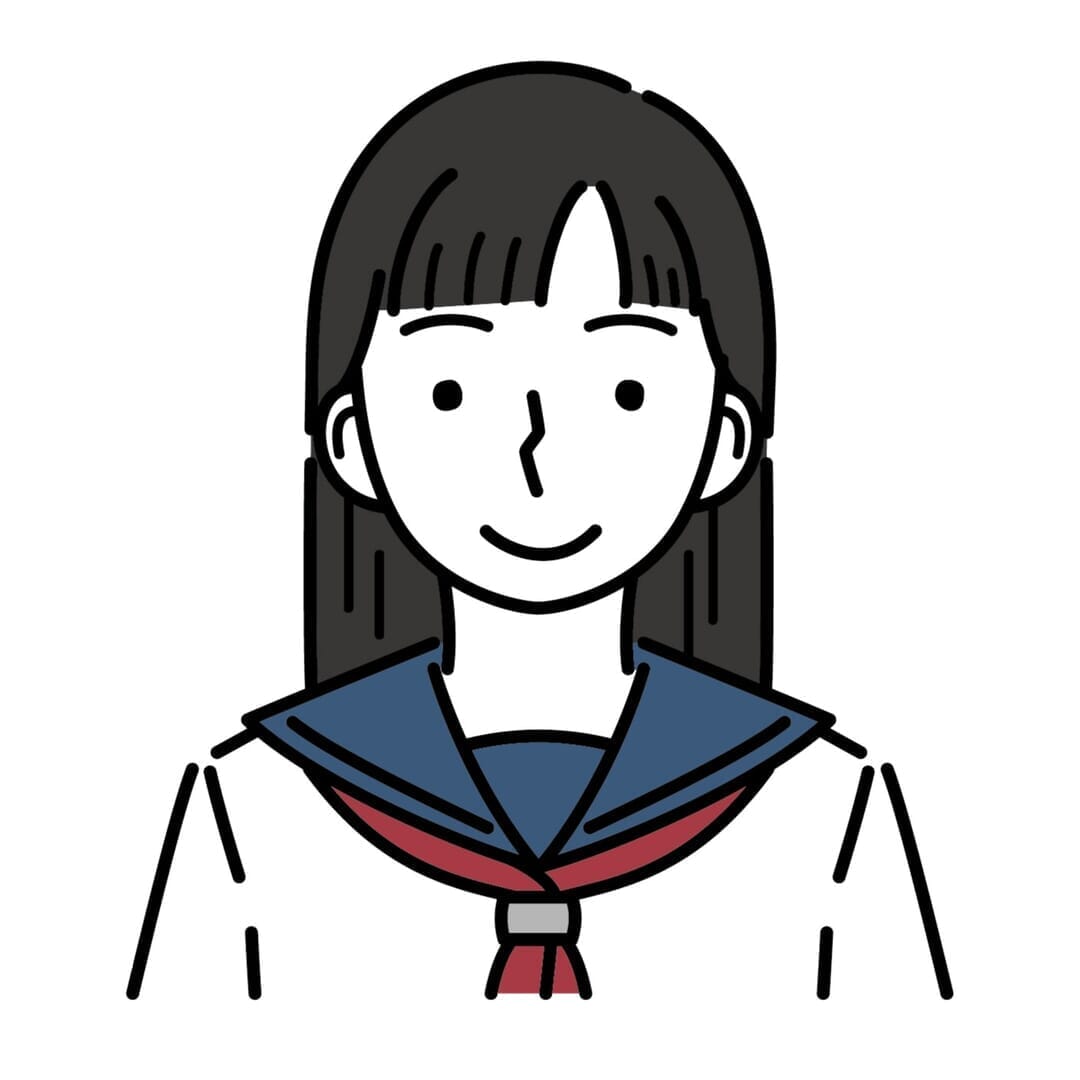
2025年度
東京都立
日比谷高等学校
Y.M.先輩
Z会の学習を通して、入試で求められる「自分で考える力」がつきました。
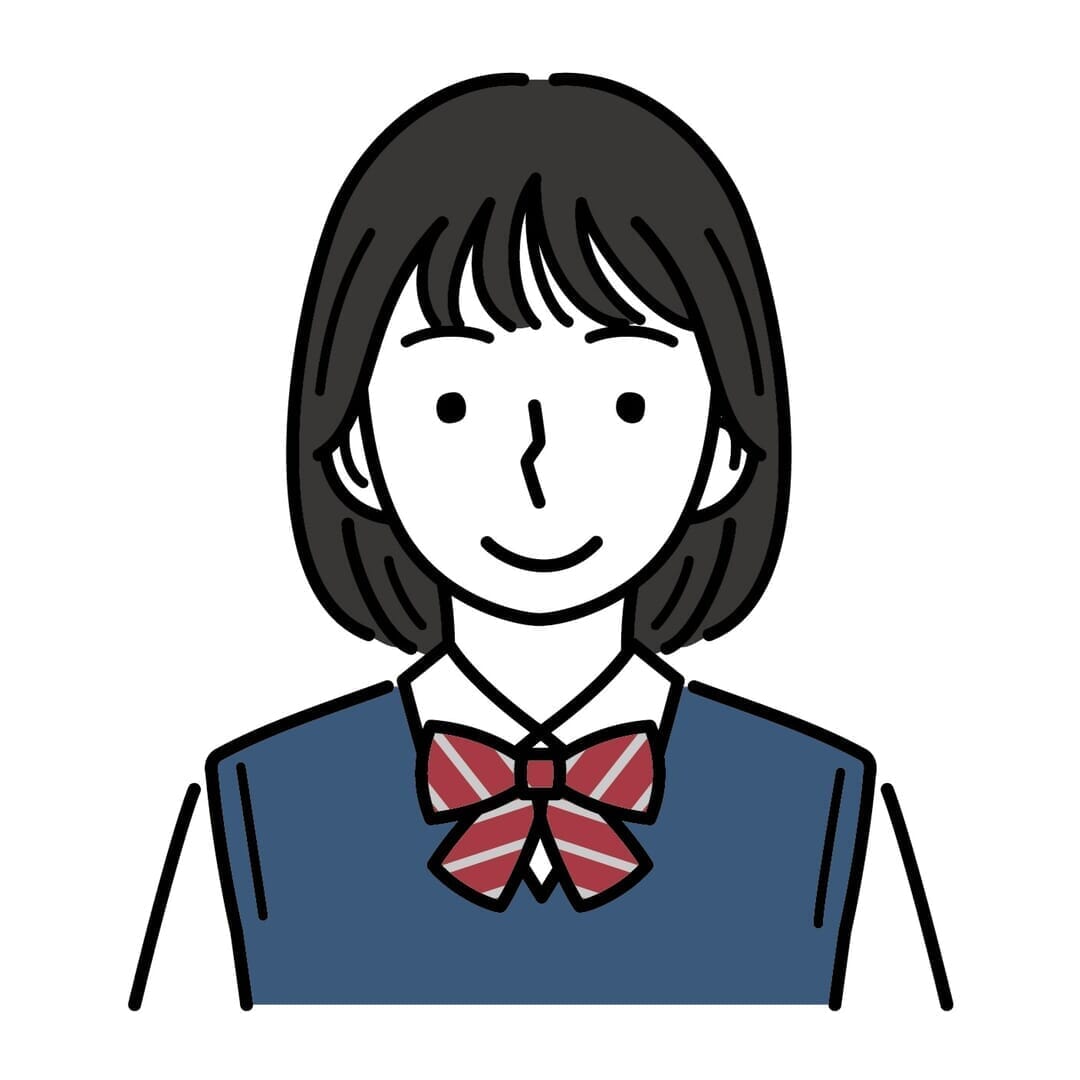
2025年度
東京都立
西高等学校
F.N.先輩
Z会を信じて楽しんで学習していけば、希望の進路はきっと叶えられます。
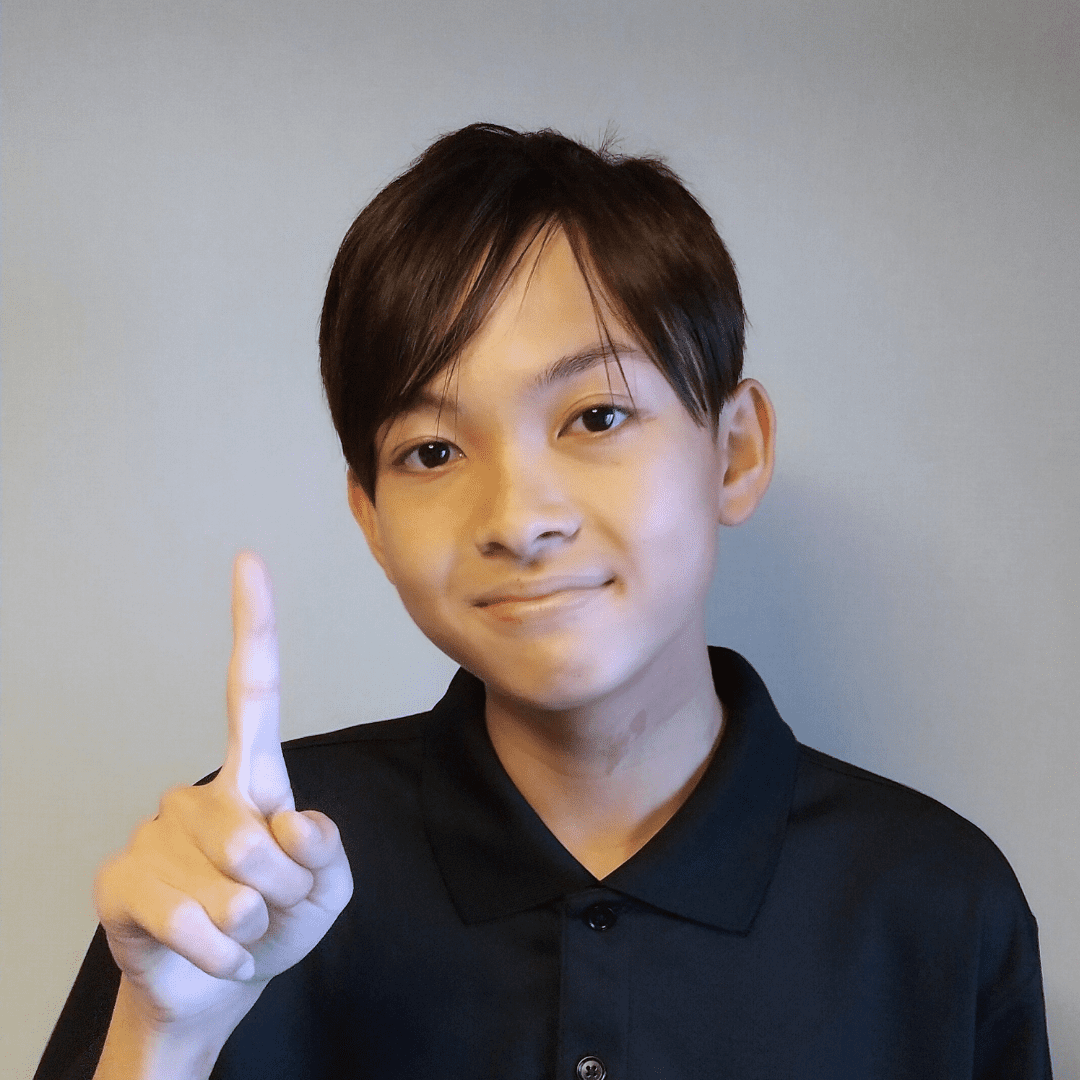
2025年度
神奈川県立
光陵高等学校
S.S.先輩
はじめは難しかったけれど、続けるうちに面白いと感じられるようになりました。
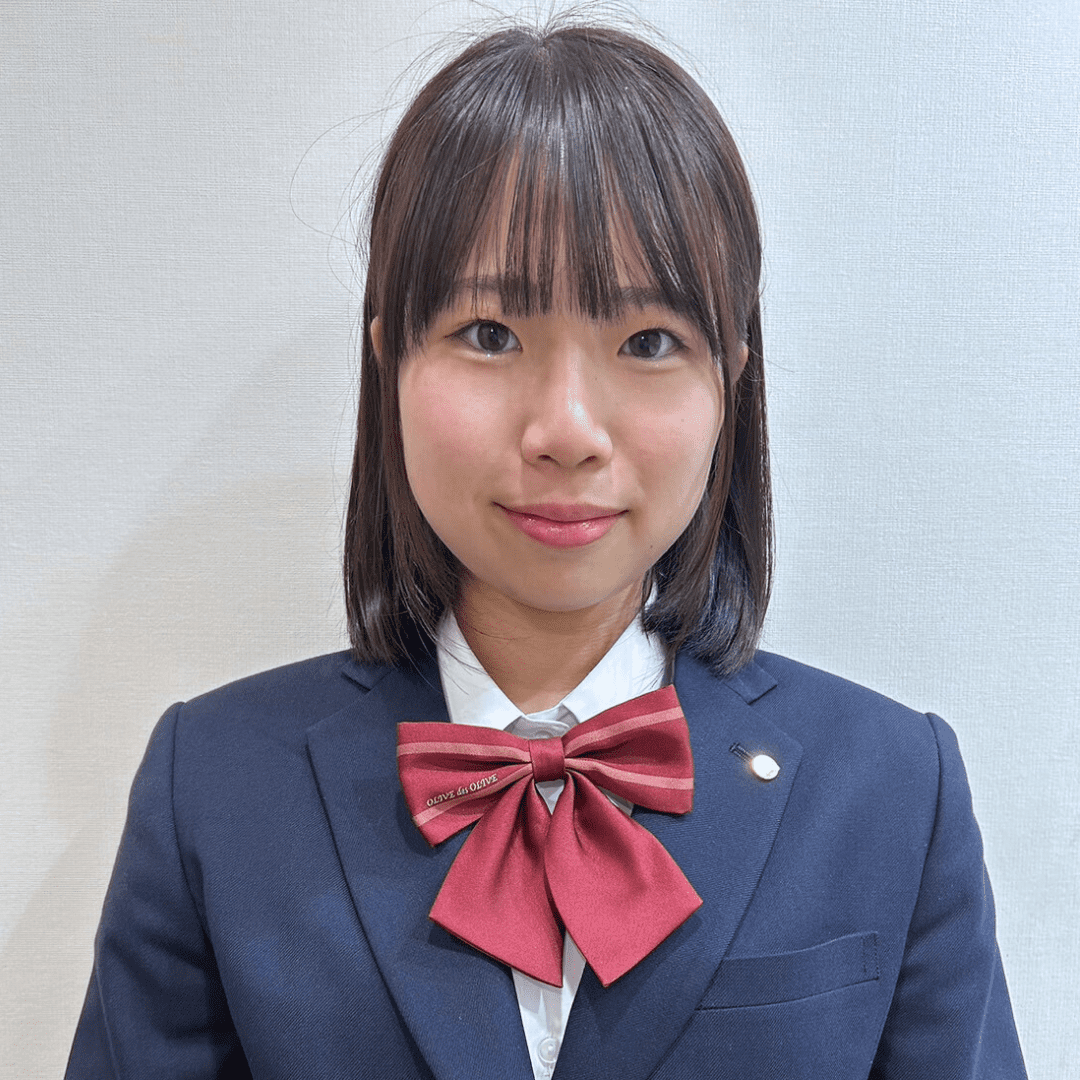
2025年度
愛知県立
明和高等学校
O.S.先輩
自分のペースで学べるから、部活や生徒会などの自分のやりたいことと両立できました。

2025年度
大阪教育大学附属高等学校池田校舎
O.K.先輩
どれくらい頑張っているかが目に見えて分かるから、学習習慣がつくきっかけになりました。
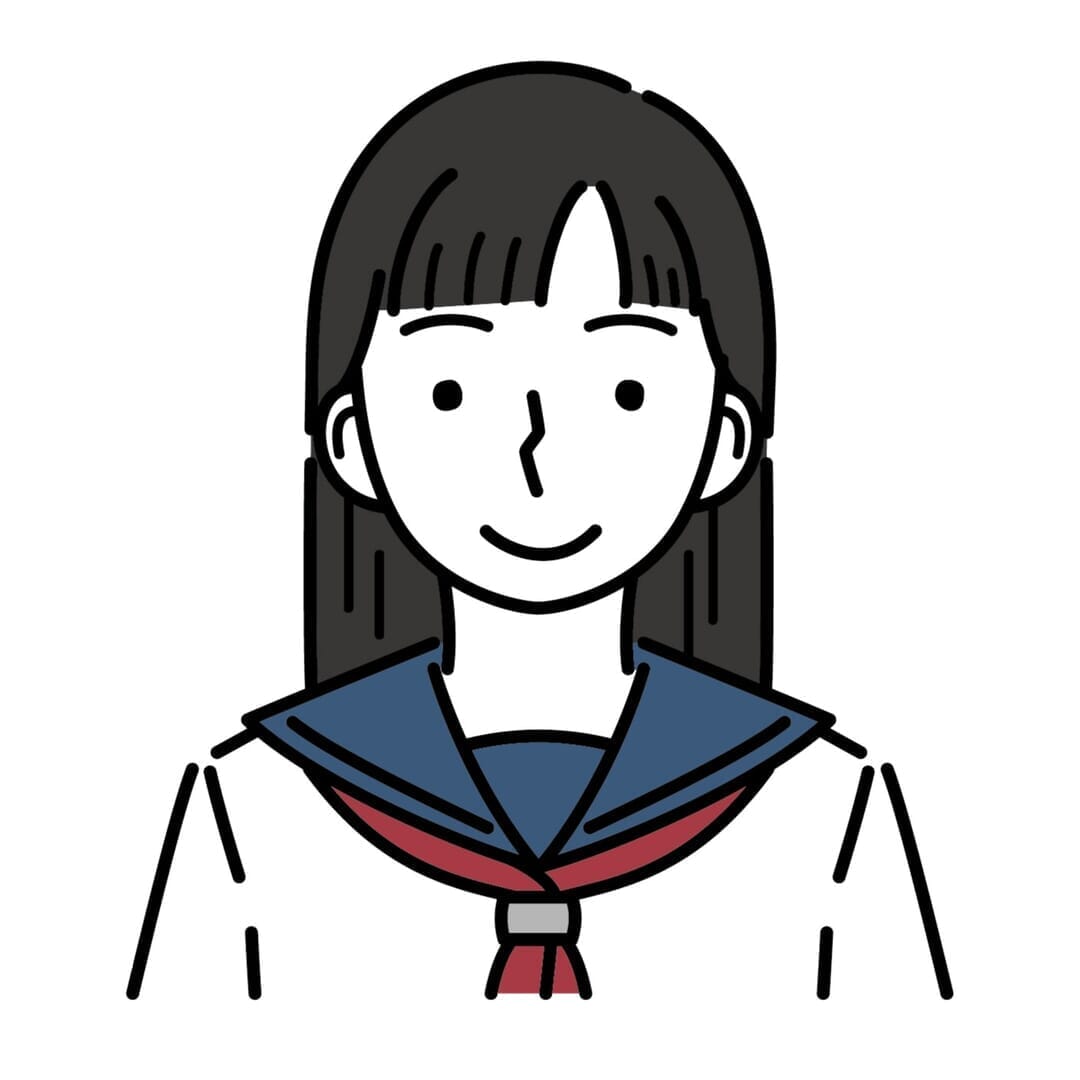
2025年度
東京都立日比谷高等学校合格
Y.M.先輩
東京都立日比谷高等学校合格
Y.M.先輩
Z会の考える学習が力に
忙しくなる中学校では自分の好きなタイミングで取り組める教材が良いと考え、Z会を始めました。ほかにも様々な教材を併用していたのですが、中でもZ会は発展的な問題が充実しているなという印象です。たとえば、他に使っている教材では公式をそのまま当てはめるような問題が多いのに対し、Z会ではどうすればその公式を使えるかという部分から考えることが求められました。
高校入試では中学3年生の単元が大事だと思われがちですが、実際には中学1、2年生で学んだことをきちんと理解していないと解けない問題がすごく多いんです。中学1、2年生のうちにZ会でしっかりと知識を定着させることができていたおかげで、中学3年生の学習内容や入試問題に対応することができ、本番の自信にも繋がりました。こうしてZ会で日々学習していたことが実際の入試でも役立ち、合格に繋がったと実感しています。
高校入試では中学3年生の単元が大事だと思われがちですが、実際には中学1、2年生で学んだことをきちんと理解していないと解けない問題がすごく多いんです。中学1、2年生のうちにZ会でしっかりと知識を定着させることができていたおかげで、中学3年生の学習内容や入試問題に対応することができ、本番の自信にも繋がりました。こうしてZ会で日々学習していたことが実際の入試でも役立ち、合格に繋がったと実感しています。
予習や定期テスト対策に活用
Z会の自分のペースで進められる点を生かし、主に予習として活用していました。学校の授業は予習をしておくと内容の定着度が大きく変わるので、土日や長期休みなどのまとまった時間を使ってZ会のコマを進めておき、さらに平日も毎日少しずつ続けることで、常に学校の授業よりも先に進めるようにしていました。
定期テスト前は、Z会の『AI速効トレーニング』を活用していました。苦手だな、不安だなと思う単元に絞って、AIが提示してくれる問題を解き、学習アプリに表示される理解度が100%になるまで繰り返し解いていました。実技の問題がまとまっている教材も重宝しました。他の教材だと暗記ばかりになりがちですが、Z会は問題演習がついているのがありがたかったです。自分で解かないと、覚えたつもりでも本番では書けないことがあるので、日ごろからインプットだけでなく、アウトプットの練習をすることが、テストに役立つなと感じていました。
定期テスト前は、Z会の『AI速効トレーニング』を活用していました。苦手だな、不安だなと思う単元に絞って、AIが提示してくれる問題を解き、学習アプリに表示される理解度が100%になるまで繰り返し解いていました。実技の問題がまとまっている教材も重宝しました。他の教材だと暗記ばかりになりがちですが、Z会は問題演習がついているのがありがたかったです。自分で解かないと、覚えたつもりでも本番では書けないことがあるので、日ごろからインプットだけでなく、アウトプットの練習をすることが、テストに役立つなと感じていました。
高いレベルを目指す人におすすめ
Z会は、基礎学習はもちろんのこと、それを使った応用問題や発展問題が充実しているので、高いレベルをめざしている人に特におすすめできる教材だと思います。日比谷高校の入試では、論理的な思考力や考察力、自分の意見を的確に表現する能力が求められますが、Z会ではこうした力を伸ばすような問題に多く取り組むことができました。Z会に日々取り組むことが、そのまま入試対策になったと思っています。
これからの高校生活では、楽しみにしていた理数探究の授業や、弓道部での活動などを通して、自分のやりたいことをどんどん見つけていきたいです。
これからの高校生活では、楽しみにしていた理数探究の授業や、弓道部での活動などを通して、自分のやりたいことをどんどん見つけていきたいです。
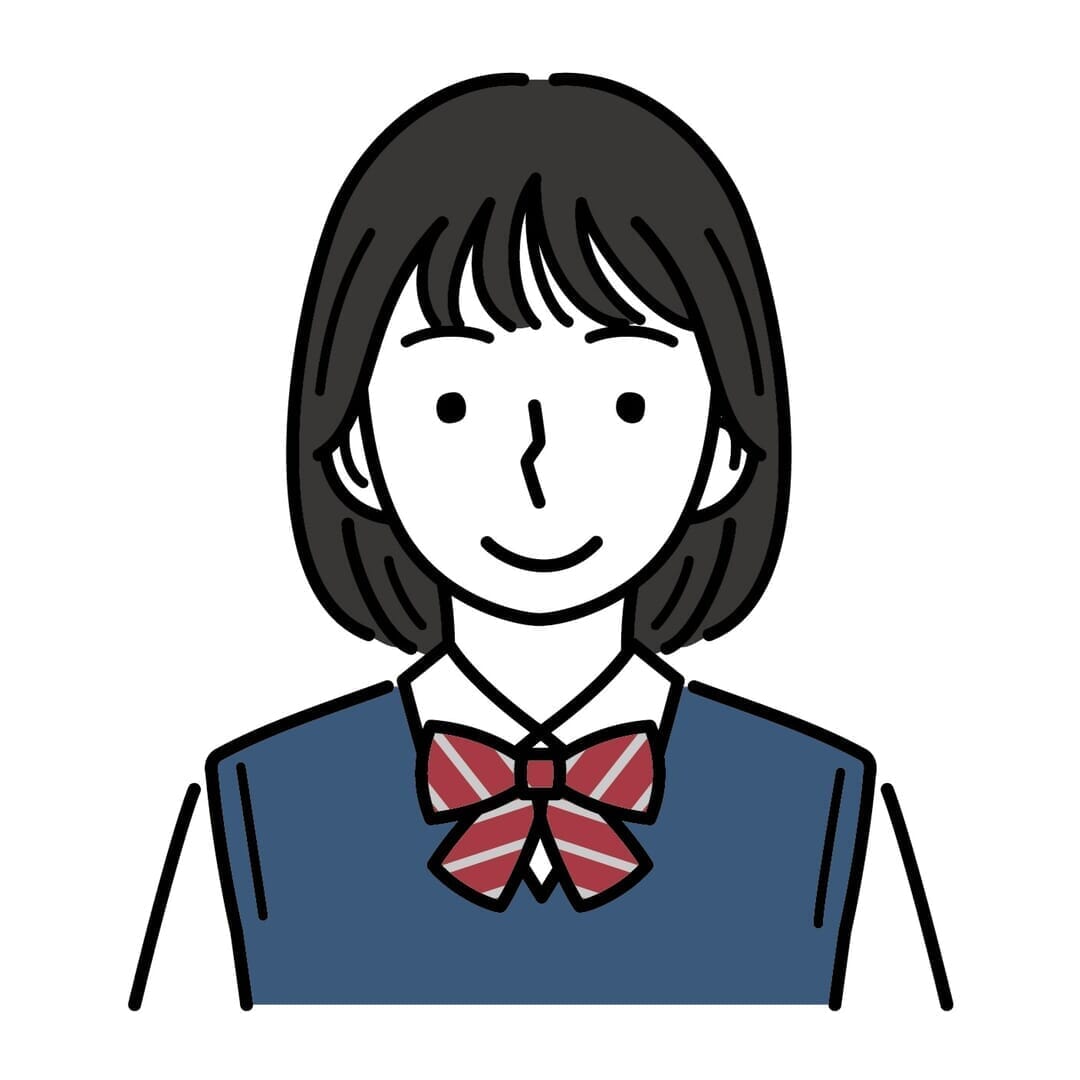
2025年度
東京都立西高等学校合格
F.N.先輩
東京都立西高等学校合格
F.N.先輩
自信を持って入試本番に臨めた
私は小学生の頃から通信教育でZ会を受講していたのですが、そこで勉強が楽しいものだと気づき、中学でもZ会を続けることを決めました。特に添削指導に魅力を感じていたので、部活動と両立しながらZ会を中心に学習を進めることを選びました。
添削指導や問題演習を通してしっかりとした実力を、模試や入試特訓で多くの類題を解いた経験によって大きな自信を付けることができました。入試本番で、予想外に難しい国語の問題が出て焦ったんですが、そこで「私が解けないなら、他の子も解けないだろう」とポジティブに切り替えることができたのは、Z会で培った実力と自信のおかげです。
添削指導や問題演習を通してしっかりとした実力を、模試や入試特訓で多くの類題を解いた経験によって大きな自信を付けることができました。入試本番で、予想外に難しい国語の問題が出て焦ったんですが、そこで「私が解けないなら、他の子も解けないだろう」とポジティブに切り替えることができたのは、Z会で培った実力と自信のおかげです。
添削指導と学習管理で高得点をキープ
Z会の添削指導では、ただ解説を読むだけでは気が付くことができないような部分まで教えてもらうことができました。たとえば、理科の記述問題で、自分では正解だと思っていた解答が「言葉のニュアンスが違う」と指摘されたことがありました。こうした経験から、ただ答えを出すだけでなく、「どうしてその答えになるのか」という解き方や考え方まで意識して取り組めるようになりました。
Z会のタブレットでは、学習状況がグラフで可視化されるので、苦手な教科の進捗も一目で把握でき、得意な教科ばかりにかたよることなく取り組めました。部活と両立するために、「Z会で予習→授業で復習→テスト前にZ会の教材でテスト勉強」というサイクルで学習し、効率よく知識を定着させ、常に高得点をキープできました
Z会のタブレットでは、学習状況がグラフで可視化されるので、苦手な教科の進捗も一目で把握でき、得意な教科ばかりにかたよることなく取り組めました。部活と両立するために、「Z会で予習→授業で復習→テスト前にZ会の教材でテスト勉強」というサイクルで学習し、効率よく知識を定着させ、常に高得点をキープできました
学びは自分の世界を広げてくれる
勉強は知識を得るだけでなく、自分の世界を広げてくれるものだと感じています。私自身も、日常の事柄や好きなことと学んだ内容との関連を見つけることで、学びがどんどん楽しくなっていきました。
Z会は、やる気のある人がどんどん伸びていける教材だと思います。Z会を信じて楽しんで学習していけば、希望の進路はきっと叶えられます。ぜひ意欲的に、楽しみながら勉強していってほしいです。
Z会は、やる気のある人がどんどん伸びていける教材だと思います。Z会を信じて楽しんで学習していけば、希望の進路はきっと叶えられます。ぜひ意欲的に、楽しみながら勉強していってほしいです。
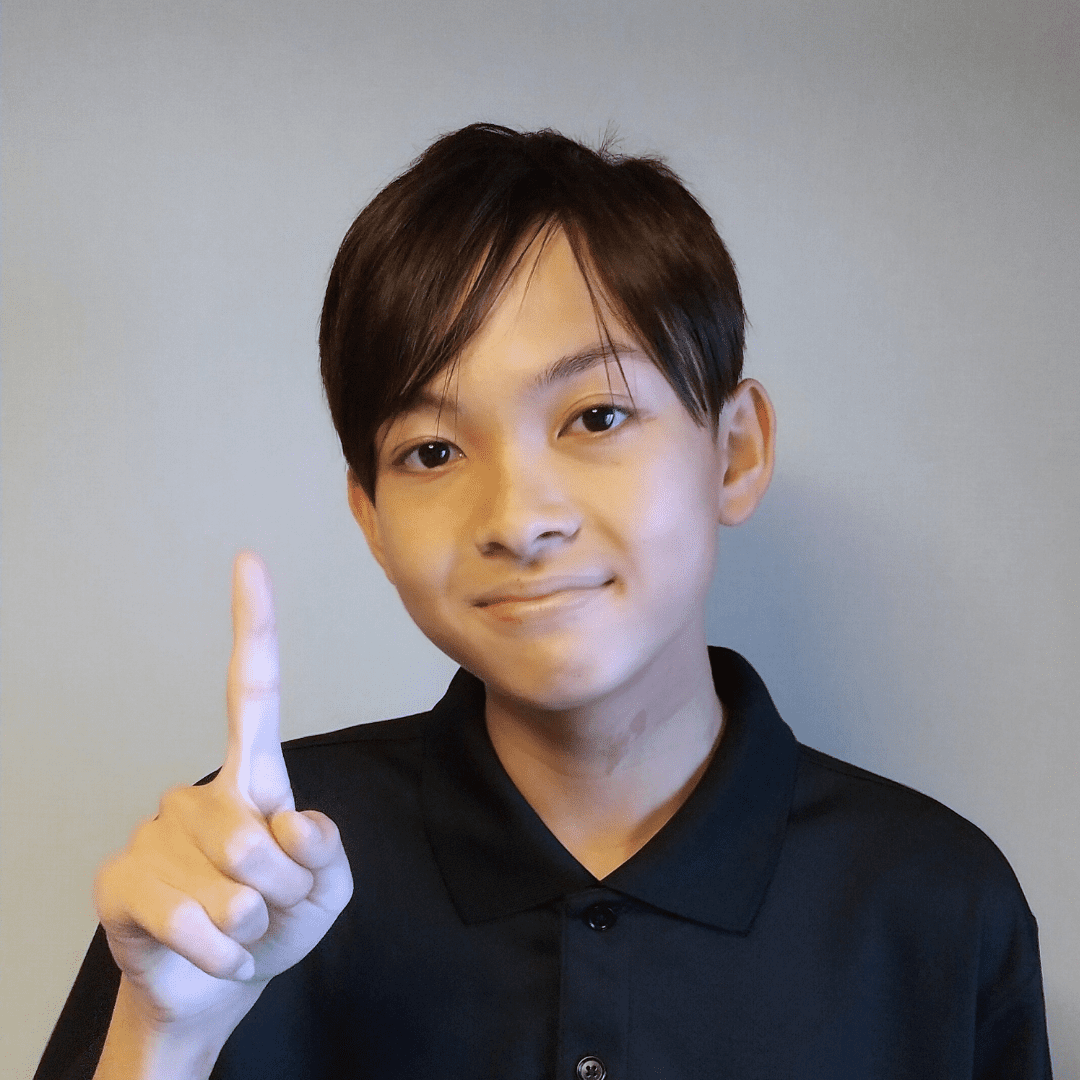
2025年度
神奈川県立光陵高等学校合格
S.S.先輩
神奈川県立光陵高等学校合格
S.S.先輩
Z会の学習でつかんだ合格
Z会を使った日々の学習の積み重ねがあったからこそ、志望校に合格することができたと感じています。私がZ会を始めたのは中学1年生の後期でした。それまでは別の通信教育を受講していたのですが、より高みを目指したいという気持ちが強くなり、Z会に挑戦することにしたんです。
最初のうちは、問題が難しくて戸惑うこともありました。でも、だんだんと手応えがあって面白いと感じるようになり、いつしかZ会で勉強するのが好きになっていきました。自分の持てる知識をすべて使って解くZ会の問題は、大変なだけあって解けた時の快感はたまりません。
最初のうちは、問題が難しくて戸惑うこともありました。でも、だんだんと手応えがあって面白いと感じるようになり、いつしかZ会で勉強するのが好きになっていきました。自分の持てる知識をすべて使って解くZ会の問題は、大変なだけあって解けた時の快感はたまりません。
良質な学習をコツコツと
私がZ会の学習で一番魅力的だと感じているのは「問題の質」です。Z会の問題は、単なる知識や解法の暗記だけでは解けず、思考力が試される良問ばかりです。そうした問題を解くことで、高校入試に必要な初めて見る問題に対応する力が身につきました。
実際の毎日の学習では、毎日夜8時から10時までと時間を決めて、コツコツZ会を進めていました。きちんと学習習慣が身につけられたので、中学3年ではスムーズに受験勉強に入ることができたと感じています。その他にも、定期テスト前には応用問題を解いてどんな問題が出ても対応できるようにしたり、基礎問題も重点的にやったりすることで理解を深めるといった工夫もしていました。
タブレットの機能も学習に役立ちました。学習時間が自動で計測されるので、頑張りが目に見えてモチベーションになりましたし、苦手な単元がグラフで表示される機能も、何を重点的に勉強すれば良いのかが分かりやすかったです。自宅で受けられる外国人の先生とのオンラインスピーキングや、分からないことを質問できる「教えて!Z会」もよかったです。
実際の毎日の学習では、毎日夜8時から10時までと時間を決めて、コツコツZ会を進めていました。きちんと学習習慣が身につけられたので、中学3年ではスムーズに受験勉強に入ることができたと感じています。その他にも、定期テスト前には応用問題を解いてどんな問題が出ても対応できるようにしたり、基礎問題も重点的にやったりすることで理解を深めるといった工夫もしていました。
タブレットの機能も学習に役立ちました。学習時間が自動で計測されるので、頑張りが目に見えてモチベーションになりましたし、苦手な単元がグラフで表示される機能も、何を重点的に勉強すれば良いのかが分かりやすかったです。自宅で受けられる外国人の先生とのオンラインスピーキングや、分からないことを質問できる「教えて!Z会」もよかったです。
将来の夢の実現に向けてこれからも
高校に合格した今も中学時代に培った学習習慣を維持しており、Z会での学習も続けています。海外の人と英語でコミュニケーションをとりたいと思い、英語部にも所属しました。社会の地理で先住民族について学び、興味を持ったニュージーランドにもいつか行ってみたいと思っています。
私の将来の夢、「世のため、人のために働く公務員になる」ことを実現するために、まずは高校で学びを深め、この先の大学受験に向けても頑張っていきます。
私の将来の夢、「世のため、人のために働く公務員になる」ことを実現するために、まずは高校で学びを深め、この先の大学受験に向けても頑張っていきます。
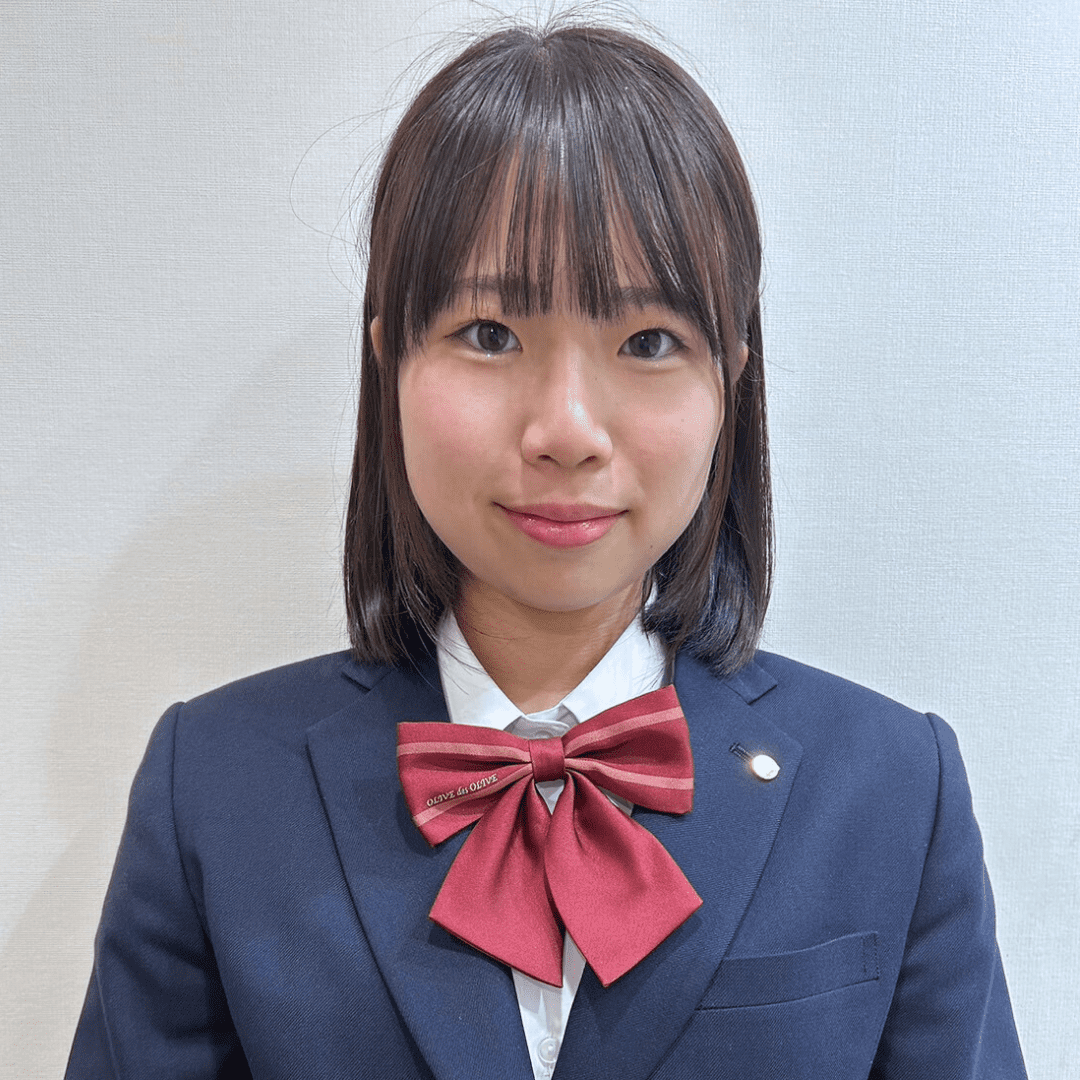
2025年度
愛知県立明和高等学校合格
O.S.先輩
愛知県立明和高等学校合格
O.S.先輩
入試本番に通用する力が身につけられた
中学生になると周りの友だちが塾に通い始め、塾で定期テスト対策もしっかり行っている様子を聞いて少し不安になりました。でも、私は部活や生徒会活動があり忙しかったので、塾に通うよりも自宅で自分のスケジュールで勉強できるZ会のほうが合っていると思いました。Z会なら通塾のための時間も不要だったので、その分、毎日2時間程度の学習時間を確保することができました。おかげで、自分のやりたいことと学習を両立することができたと思います。
Z会の教材は、ただ知識を問うだけではなく、思考力を必要とする問題が豊富です。難しいと感じる問題も多かったですが、そうした問題に日々取り組んでいたからこそ、テストや入試といった本番で通用する本物の実力を身につけられたのだと思っています。
Z会の教材は、ただ知識を問うだけではなく、思考力を必要とする問題が豊富です。難しいと感じる問題も多かったですが、そうした問題に日々取り組んでいたからこそ、テストや入試といった本番で通用する本物の実力を身につけられたのだと思っています。
得意科目はさらに得意に、苦手科目の克服もしっかりと
得意な英語については、無学年制で学べるAsteria英語を選択していました。月に2回のオンラインスピーキングで英会話の練習ができ、ネイティブの自然な表現をたくさん学ぶことができました。また、こうした実践の機会があったことで、もっと英語を頑張りたいという気持ちになり、更に力を伸ばすことができました。
苦手だった数学は、中学3年生の模試で点数が悪かったのがきっかけで、本格的に勉強を始めました。夏休みからはZ会のAI速効トレーニングや定期テスト攻略ワークの難しい問題を毎日解き続けたことで、夏と比べて偏差値が13もアップし、入試本番では満点を取ることができました。理科は特に苦手な科目でしたが、Z会には中学3年分の単元にいつでも取り組める機能である「オープンカリキュラム」があったので、前の学年の単元に戻って学習することで克服できました。
苦手だった数学は、中学3年生の模試で点数が悪かったのがきっかけで、本格的に勉強を始めました。夏休みからはZ会のAI速効トレーニングや定期テスト攻略ワークの難しい問題を毎日解き続けたことで、夏と比べて偏差値が13もアップし、入試本番では満点を取ることができました。理科は特に苦手な科目でしたが、Z会には中学3年分の単元にいつでも取り組める機能である「オープンカリキュラム」があったので、前の学年の単元に戻って学習することで克服できました。
自分のペースで学べるところが合っていた
学力が伸びたのが早い方ではなかったので、夏期講習で塾に行った際には、集団での学習だとペースについていけず不安になることもありました。その点、Z会は自分なりのスケジュールで学習に集中することができたので、私に合っていたのだと思います。
私は、忙しい中で取り組める時間を見つけて取り組んだり、その日何を勉強するかを自分で決めて学習したりしていました。Z会の受講を通して「自分の意志で勉強する」ことができるようになったのが一番の変化だと感じています。
私は、忙しい中で取り組める時間を見つけて取り組んだり、その日何を勉強するかを自分で決めて学習したりしていました。Z会の受講を通して「自分の意志で勉強する」ことができるようになったのが一番の変化だと感じています。

2025年度
大阪教育大学附属高等学校池田校舎合格
O.K.先輩
大阪教育大学附属高等学校池田校舎合格
O.K.先輩
Z会一本で掴んだ志望校合格
志望校については、兄が通っていたことに加え、自由な校風や行事に力を入れていることに強く惹かれて選びました。Z会は小学生の頃から続けていたのですが、中学生で部活に力を入れるようになってからは移動時間がないことの良さを改めて感じ、そのまま継続することにしました。
Z会の教材は、難しい問題もあれば基本的な問題もあって、基礎から応用まで幅広く色々なパターンが揃っています。特に「入試特訓」や「最難関攻略対策」といったレベルの高い問題が充実していたので、入試本番を意識した問題が多く解けて、とても役立ちました。AIが自動で問題を出してくれるAI速効トレーニングは、色々な分野からランダムに出題されるので、構えずに解く練習ができ、より実践的な力が身についたと感じています。
Z会の教材は、難しい問題もあれば基本的な問題もあって、基礎から応用まで幅広く色々なパターンが揃っています。特に「入試特訓」や「最難関攻略対策」といったレベルの高い問題が充実していたので、入試本番を意識した問題が多く解けて、とても役立ちました。AIが自動で問題を出してくれるAI速効トレーニングは、色々な分野からランダムに出題されるので、構えずに解く練習ができ、より実践的な力が身についたと感じています。
苦手克服と総復習を叶えた中3の夏
中学時代に打ち込んでいた野球部で培った粘り強さが、引退後の追い上げに活かされたと思います。中3の夏は、一日8時間勉強する目標を立て、特に苦手だった英語と、中1・中2の範囲で遅れていた理科・社会の克服に力を入れました。英語は模試で17点という点数を取ったこともあり、最初は長文を読むこと自体にやる気をなくしがちでした。でも、Z会のタブレットで毎日1題ずつ長文を読むことを続けたところ、少しずつ長文にも慣れていき、次第にやる気が湧いてくるようになりました。その結果、模試の点数が50点もアップしたときはとても嬉しく、自分の勉強法が間違っていなかったと確信できました。
添削指導も英語の克服にすごく役立ちました。特に作文では、inやatのような前置詞といった細かい間違いまで丁寧に指摘してくれたんです。自分の書いた文章への具体的なアドバイスをもらえたことで、解説をただ読むだけでは難しい知識がしっかりと身につきました。もちろん、父が分からない問題を一緒に解いてくれたり、解説を読んでくれたりしたことも、大きな支えになりました。
添削指導も英語の克服にすごく役立ちました。特に作文では、inやatのような前置詞といった細かい間違いまで丁寧に指摘してくれたんです。自分の書いた文章への具体的なアドバイスをもらえたことで、解説をただ読むだけでは難しい知識がしっかりと身につきました。もちろん、父が分からない問題を一緒に解いてくれたり、解説を読んでくれたりしたことも、大きな支えになりました。
タブレット学習で計画を立てて勉強できるように
Z会のタブレットは、自分のペースで着実に学習を進められるのが良かったです。特に中1、中2の範囲をさかのぼって学べる「オープンカリキュラム」で理科と社会の遅れを取り戻したときは、その膨大なコマ数を着実にこなすことで、自分が前に進んでいるという手応えを感じることができました。また、ご飯やお風呂の間のわずかな時間も数学の計算問題や英単語の暗記に有効活用できたので、そうした取り組み方もおすすめです。
学習時間グラフやコマ数といった機能で自分の勉強状況をいつでも確認できたことも、一人で勉強を進める上で大きな助けになりました。タブレットの機能によって、自分がどれくらい頑張っているかが目に見えて分かったので、それが学習習慣を身につけるきっかけになりました。受験勉強を通して、自然と計画を立てて勉強する力が身についたのが良かったです。
学習時間グラフやコマ数といった機能で自分の勉強状況をいつでも確認できたことも、一人で勉強を進める上で大きな助けになりました。タブレットの機能によって、自分がどれくらい頑張っているかが目に見えて分かったので、それが学習習慣を身につけるきっかけになりました。受験勉強を通して、自然と計画を立てて勉強する力が身についたのが良かったです。
※英検®は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。本サービスは独立した商品であり、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
