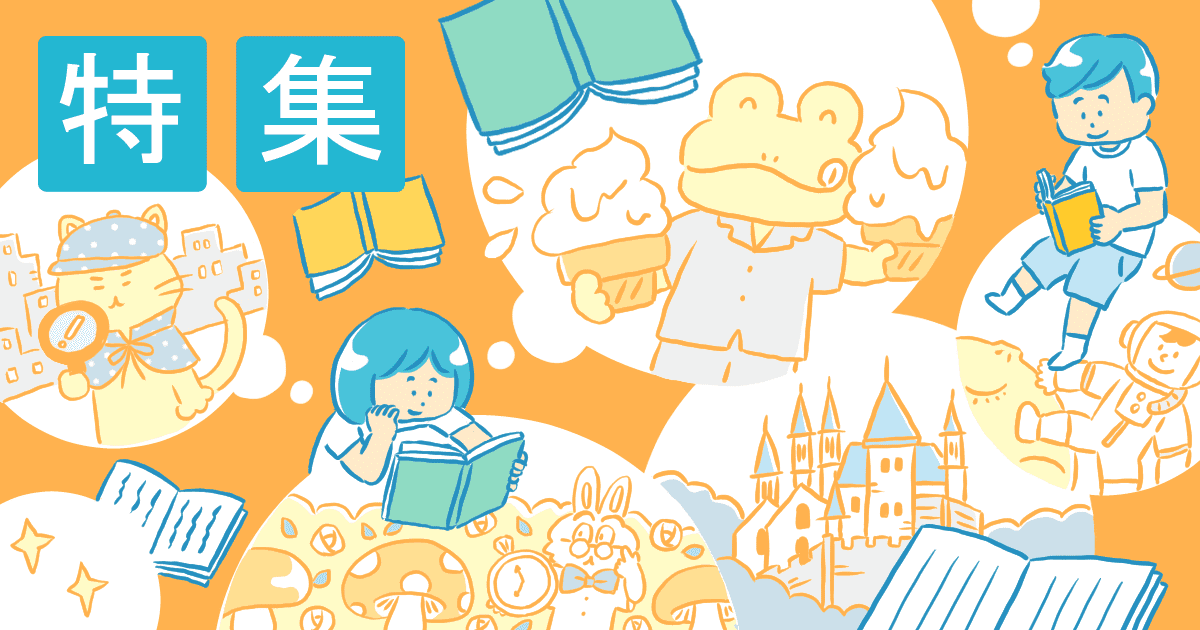「読解力を身につけよう」とよく言うけれど、そもそも「読解」とは何なのか、どうすればその力が身につくのか、よくわかっていない……という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、教育心理学や認知心理学を専門とされている犬塚美輪先生(東京学芸大学准教授)に、子どもの読解力にまつわるお話をうかがいました。家では母としての顔も持つ犬塚先生。大人の声かけ一つで、子どもの読む楽しさや意識は大きく変わると教えてくれました。
(取材・文 竹内 郁子)
※本記事は、2023年7月27日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
「読めれば、わかる」わけじゃない。読解は、頭をしっかり使う主体的な活動
――そもそも「読解」とは、何なのでしょうか?
私はよく「読解とは、理解することとほぼ同じです」と言っています。じゃあ、理解するって何? というと、心理学の用語で「表象を作ること」。ちょっと聞き慣れない言葉ですが、表象とは自分の外にある世界を頭の中に再現したもの、と思ってください。つまり読解とは、文章の内容を頭の中で再現すること、といえると思います。
――読みながら再現していく……頭の中ってすごいですね。
そうなんです。頭の中に表象を作るのは、けっこう難しくて大変なんですよ。はじめに、文字を音に変換し、単語の意味をイメージするところまでたどり着く必要があります。これだけでも大変ですが、そのうえで、単語と単語の関係を「命題」というかたまりにしなければなりません。命題とは、一つの述部(動詞や形容詞)を中心とした意味を表す単位です。たとえば、「行く」という動詞に「だれが」の情報や「どこへ」の情報が加わったものが一つの命題になります。一つの文に命題一つと決まっているわけではなく、多くの命題が含まれていることもあります。最終的に、文章全体でどう命題が関連しあっているかを理解してはじめて表象ができあがるので、しっかり頭を使って頑張らないと、「わかった!」とはならないんです。もし、文字を追うだけで情報がザーッと頭に入ってくるなら、誰も「読解力を鍛えよう」なんて言いませんよね。「読解は非常に主体的な活動である」という意識を持つことは、大事なポイントです。
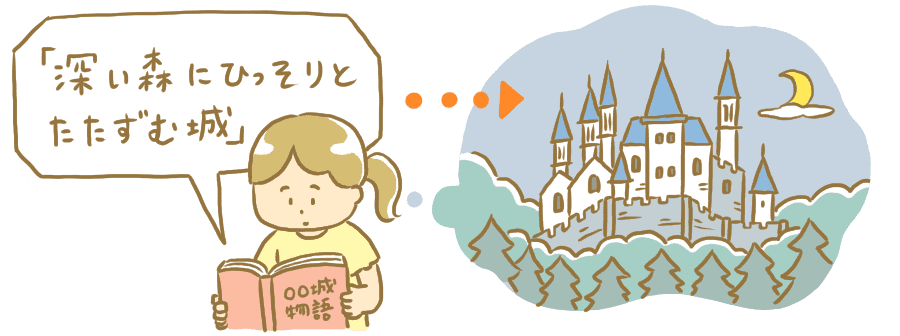
読解力は、知識を増やし、自分の世界を広げるために必要な力
――人はなぜ、読解力を身につける必要があるのでしょうか?
冒頭で、読解と理解はかなり近いとお話したのですが、読解力があると自分の知識をどんどん増やしていけるんですね。たとえば、学校の教科書に始まり、その先もさまざまな場面で本を読む機会は出てきます。勉強だけでなく、料理、育児、病気についてなど、生活の中でも新たに知りたいことはいっぱい出てくるはずです。そんなとき、説明文の読解力があるのは有利ですよね。こんな話をしていると、最近の小学生は「YouTube観ればいいし」って言うんですけれど(笑)。でも動画がフォローしてくれるのは、せいぜい中高生レベルまで。知りたい内容が高度になればなるほど動画の数は減りますから、いつまでも動画の視聴に頼るわけにはいかず、結局最後は「読む力」が必要になってくるんです。
つまり、「説明文の読解=知識を得るための読解」と言えると思います。
――小説など、物語文についてはいかがですか?
たとえば、文学作品を読んで「このセリフが心に刺さった」とか「あの登場人物の存在が私の支えになっている」みたいなことってありますよね? 物語の世界を頭の中に生き生きと描いてその中に入り込み、登場人物と気持ちを通わせるような感動の経験には知識獲得以上の意味があります。実際に体験できないことや現実とは違う世界にふれることで、自分の考え方が変わることもありますし、そこから生き方を考えることもあるでしょう。そうした意味での読解力も、子どもが自分の世界をつくり、広げていくためにはすごく大切だと思います。
無理強いは禁物。子どもに本の楽しさを伝えよう
――子どもの読解力を育てるために、親が気をつけるとよいことはありますか?
年齢に関係なく「まずここはクリアしておきたい」というポイントが、読むことに対する拒否反応を作らないこと。拒否反応が出てしまう原因はいくつかあると思うのですが、よくあるものとしては、親から「読書は大事だから読みなさい」「ほら、これも頑張って」みたいに無理強いされてしまうこと。やりなさい、と言われると、はじめは興味を持っていてもそれが消えてしまいます。同じ理由で、子どもが読んでいる本に文句を言うのもよくないですね。「そんな本ばっかり読んで。もっと難しいのも読まなきゃ」なんて言われたら、「親の薦める本だけは絶対に読まない」ってなりますから。
――「読解力をつけさせなくちゃ」という親の焦りが、逆効果になってしまうのですね。
そうなんです。じゃあどうしたらいいかというと、一緒に本を楽しむ経験がすごく重要かなと思います。自分が読んでいる本について、親が「いいね」と褒めてくれたとか、「どんな話なの?」と聞かれて話が盛り上がり、嬉しかったとか。とくに低学年の頃は大人の反応が大事な基準になってきますから、「読むことは楽しい活動なんだ」と思えるような声がけを心がけてください。
たまに学校の先生が、子ども同士で本の話ができるような機会をつくってくださることがありますが、あれはとてもよいと思います。 「先生が持ってきたあの本、読んだ?」「えっ、まだ」「面白かったよ!読んでみて」「あの場面、すごかったね」「誰派だった?」みたいな会話が友だちとできると、読書が楽しくなってきますよね。
ちなみに、この「楽しい」という感覚はとっても重要。さまざまな調査においても、「読んだ本の量」よりも「楽しんで本を読む習慣があるか」などの方が読解力を測る指標との関連性が高いと重視されています。本を無理やり読ませるのではなく、読んで楽しいという体験が読解力につながると考えましょう。
――はじめから本にまったく興味を示さない子どもの場合は……?
そんなときは、親御さんなど家庭内にいる人たちが日常的に本を読んでいるかな? と考えてほしいですね。大人がゲームやテレビばかりだったら、子どもだって「本ねぇ……」ってなりますから。雑誌でも何でもいいので、まずは大人が本に親しむ姿を見せ、さらに「こんなことが書いてあったよ」と子どもに教えてあげられるといいですね。すると子どもも「なるほど。本って面白いらしい」と興味を持ち始めるのではないでしょうか。あとは、図書館や書店に一緒に行くとか、家の中のすぐ手の届くところに子どもの本を並べるとか、本を身近に感じられるような環境づくりも大人の仕事かなと思います。
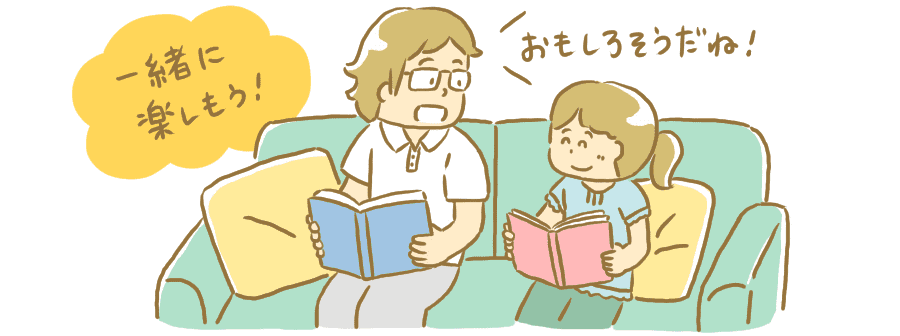
どうしたら難しい文章を理解できるの?助けてくれるのは、単語と知識のストック
――読んでも意味がわからず、「うーん……」と行き詰まるときは、どんなところにひっかかっているのですか?
表象をうまく作れない原因はいっぱい考えられるのですが、第一に単語ですね。これまでの研究から、私たちは「文中の単語の9割以上知っている」という状態になってはじめて文章を理解できるということがわかっています。ですが、とくに説明文を読むときというのは「知らないことについて理解しようとして」読むわけですから、知らない単語がたくさん出てきます。各分野の専門用語に加え、「およそ」「あるいは」「(~に)対する」「(~を)参照」など、日常生活ではあまり使わない言い回しも多いですよね。これらの単語は「学習用ボキャブラリー」といい、「新しいことば・概念を覚えるために重要なことば」なんです。こういったボキャブラリーは、ものごとの関係や範囲などを示すものとして、説明文ではなにげなく使われているものですが、これが基礎として身についていないと、さまざまなものを読むことが難しくなってしまいます。
――確かに、抽象概念の説明にはこうした言葉がよく使われますね。大人は気になりませんが、意識して接していかないと、子どもにはなじみがないものかもしれません。
そうですね。また、「学習用ボキャブラリー」だけでなく、トピックについて関連する知識も重要です。知識がもともと自分の中にあるかないかで、文章の理解度が大きく変わってくるからです。たとえば数学の文章を読むときに、私は数学の知識があまりないのですごく時間がかかりますが、数学者ならもっとスムーズに読めるでしょう。物語文で例を挙げると、『ハリー・ポッター』の中に「クィディッチ」と呼ばれる魔法界の架空のスポーツが出てくるのですが、ラグビーやサッカーなどの知識があれば、クィディッチがどんなスポーツなのかをよりよく理解し、いきいきとイメージすることができます。そんな風に、関連する知識をたくさん身につけることは読むスピードや的確さに直結し、本質的な読解対策になると思います。
国語の授業中にやる「アレ」は重要な方略だった!?
――「物語文は好きだけれど、説明文は苦手」という人も多いですよね。
そうですね。単語や内容の難しさに加え、説明文は構造も複雑なんです。物語文には「どこで、誰が、どんな問題に直面して、どう解決するか」という共通した型のようなものがあるので比較的読みやすいのですが、説明文の型はもっと不明確で数も多い。その分、より頑張って戦略的に読まないと内容が頭に入ってこないんです。この戦略的な読み方のことを心理学では「方略」と呼んでいます。
――実際、方略を使ってどんな風に読むのですか?
実はこの方略、小学生の早いうちから国語の授業で教わっているんですよ。たとえば「あれ?と思ったら何回かゆっくり読む(基本的な読み方コントロール)」「コレ、ソレなどが何を指しているのかはっきりさせる(明確化)」「大事そうなところを見つける(要点把握)」「わからないところはどこか考える(理解チェック)」「文章の段落構造に注意する(構造注目)」「知っている内容と結びつける(知識の活用)」など。これらは国語の授業中にのみやる作業だと思っている人が少なくないのですが、実は、子どもたちがこの先自分自身で使っていく方略の練習なんですね。
――とはいっても、本を読むたびに「方略を使うぞ!」と子どもが意識するのは大変ですよね?
うまく読めていないというときは、大人が方略を使って読めるように手助けしてあげるのもよいと思います。本が難しければマンガでもアニメでもいいのですが、子どもが読み終わった・見終わった後に「何の話だったの?」「1分くらいでまとめて教えて!」のように、ちょっとした問いかけをし、「大事なポイントはどこだったのかな?」と一緒に考えられるといいですね。子どもは質問に答えるとき、頭の中に作った表象を見直すことになります。すると「あれっ、話の前後がつながらない」とか「あの単語、読み飛ばしていたけれど大事だったのか。どんな意味だろう」など、きちんと読めていなかった部分に気づき、理解を深めるきっかけにもなります。こうした会話は食事中でもできるので、ぜひやってみてくださいね。「読むことは主体的な活動なんだ」ということを子ども自身が意識する、いい機会になるかなと思います。
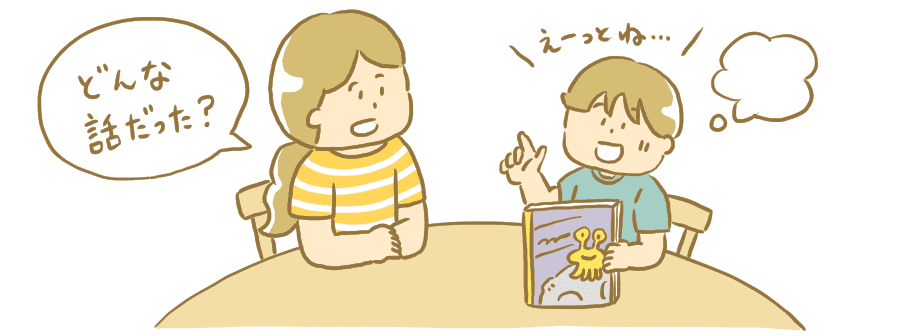
多様な読解力が求められる時代。大人も適切なサポートを
――最近は、メッセージアプリなどによる短い文でのやりとりを子どもが行うことも増えています。本などを読むときとはまた違ったポイントがあるでしょうか?
そうですね。究極に短い会話の例として、昭和のお父さんが「おい、あれ」と言ったら「はい」とお茶が出てくるような世界、あるじゃないですか。あれはなぜ成り立つのかといったら、「食後の飲み物といえば日本茶である」というような、お互いに共有している文脈、知識、価値観がいっぱいあるからですね。それと同じで、メッセージアプリなどの短い文の後ろには、省略されているものがいっぱいあることを忘れないでください。でも普通、友達同士だとそこまでいろいろ共有していません。省略されている部分のズレに気づかず、トラブルに発展することは大いにあると思います。私も自分の子どもにはそのことを伝えつつ「メッセージのやりとりでネガティブな感情が出てきたときは、そのままにしちゃダメ。話し合いの必要があるサインだよ」と話しています。そのあたりのサポートも、やっぱり大人の役目ですね。
――ネットを通じて、さまざまな文字情報にふれる機会が増えていますから、今後ますます、多様な読解力が求められますね。
そうですね。ネットの断片的な情報から、情報の背景や省略された部分を想像することなく「表象を作った」と満足してしまわないよう気をつけることも大切です。読んで「いや、おかしいんじゃないの?」と却下できる読解力を「批判的読解力」というのですが、こうした少しハイレベルな読解力も今後さらに必要になってくると思います。批判的読解力にも方略があって、「言葉が都合よく使われていないか」「省略や論理の飛躍で誘導されていないか」「他の情報と比べてどうか」「自分の知識との矛盾はないか」などがチェックポイント。インターネットや本に書いてあることを読解して表象を作るだけではなく、作った表象を多角的に見た上で「納得しない」「結論を保留する」など、自分なりに判断する力も大切な読解力といえます。
読むことは生きること、ふだんの生活と深くつながっています。会話や環境作りなど、無理のないやりかたで、子どもが読解力を伸ばしていくのを見守り、サポートしていけるとよいですね。

犬塚 美輪(いぬづか・みわ)
東京学芸大学 教育学部 教育心理学講座 准教授。博士(教育学)。東京大学大学院教育学研究科修了。日本学術振興会、東京大学先端科学技術研究センター、大正大学を経て、2017年より現職。専門は教育心理学、認知心理学。「文章を理解することについての心理学」に関心を持ち、文章理解のプロセスとその指導方法の開発に取り組んでいる。おもな著書に『認知心理学の視点―頭の働きの科学』(サイエンス社)、『論理的読み書きの理論と実践』(北大路書房)、『14歳からの読解力教室-生きる力を身につける』(笠間書院)など。