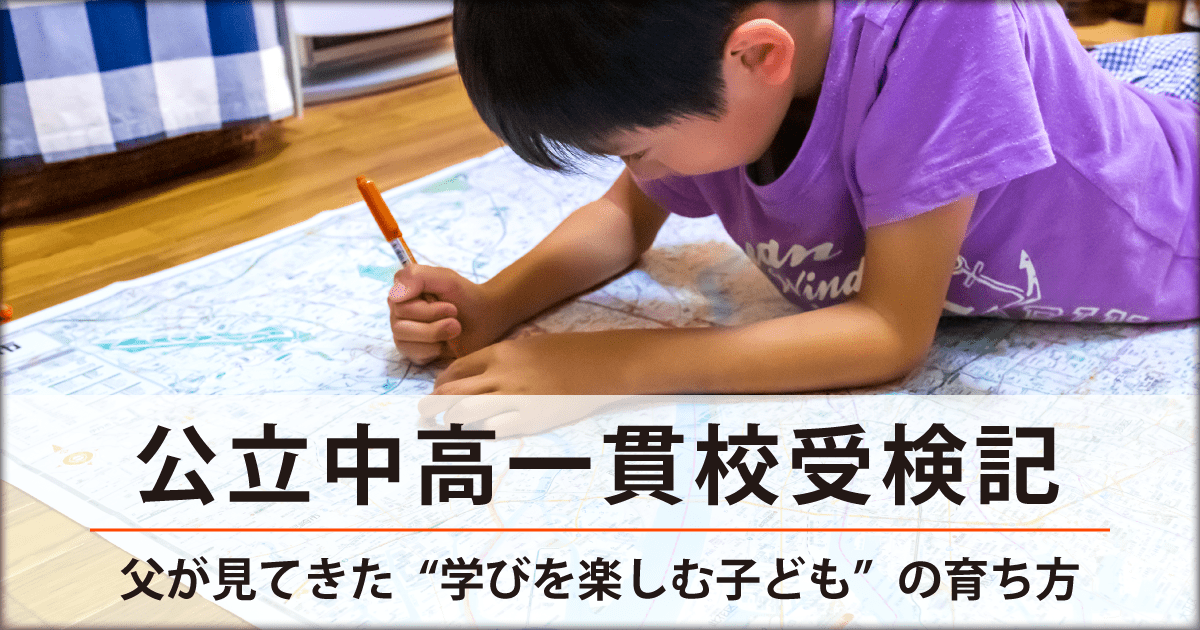旅は、日々の生活とは違うかたちで、子どもが生きた学びをする絶好の機会。子どもが自分で目標やプランを考えることで、それは達成感や自信となり、忘れられない思い出として、その後の人生をつくっていく基盤となるのかもしれません。
※本記事は、2023年11月9日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
教育系の記者として、公立中高一貫校への取材経験を多数おもちの著者・堤谷孝人さん。
父として、お子さんの中高一貫校受検をすぐそばで見てきたご経験を綴るエッセイの第8回です。
第7回まではこちら
RPG(ロールプレイングゲーム)で主人公がレベルアップする瞬間は、努力が報われて嬉しいものです。人生をRPG、自分自身がその主人公だと考えると、困難に挑戦して知識や能力を獲得し、レベルアップしていくこと自体に、生きてゆくことのおもしろみを感じられるようになるのかも…と思ったりします。
* * *
息子が幼稚園を卒園する直前の2月、日本全国でまれな大雪になりました。大阪でも珍しくたっぷり雪が積もり、息子は近所の公園で園の友だちと夢中になって雪遊びをしました。そこで週末、急きょ、息子の友だちのご家族と雪が積もった高原に出かけることに。子どもたちはソリ滑りに雪合戦、雪だるまやかまくら作りなど、本格的な雪遊びに浸りました。
息子はこの経験がよほど楽しかったらしく「もっと雪遊びをしたい」と言うように。そこで私たち家族は、大阪でいちばん標高が高い金剛山に登り、樹氷のトンネルをくぐったり、つららをかじったりしました。

雪や氷が楽しかったのか、「大阪でいちばん高い山」への挑戦をクリアしたのが嬉しかったのか、その両方なのかはわかりませんが、息子は下山しながらこう尋ねました。
「もっと高い山ないの?」
私が「富士山というのが日本一高い山やで」と答えると、息子は「登りたい!」とウキウキした声を上げました。
そこで私たち一家は、小1の夏休みに富士登山をすると決め、それまでに体力づくりをするため、毎月、生駒山や伊吹山など近隣の山を登りました。
* * *
7月の終わり、家族で富士登山へ。ふもとで前泊し、山小屋で仮眠後、ようやく山頂にたどり着いた息子は、下山中にはもう、「次はどんなチャレンジをしようかなぁ?」と言っていました。このとき、息子は自らチャレンジすることの楽しさや意義を体得したのだと、私は思いました。

当時、息子は生活科で習っている「地域」に興味をもっており、自分の身のまわりに何があるかを知りたがっていました。日頃から、息子と私は近隣のいろいろな場所を目標に設定してサイクリングに出かけていましたので、下山しながら次のような提案をしてみました。
「町を自転車で一周してみる?」
さっそく、私たちは市区より狭い範囲の町の境界を自転車でまわってみました。息子はカメラで気に入った風景を撮ったり、橋や建物に自分勝手に名前をつけたりしていました。私はというと、自分が住んでいる町の広さを実感したり、地形を把握したり、知らなかったお店や会社を発見したりと、新鮮な楽しさを味わいました。
その後まもなく、息子は「(自分が住んでいる)区を一周したい」と言い出し、これも達成。
小学2年生になるころには、「大阪市を一周したい」と言うようになりました。大阪市の市境が正確にはわからず、参考になるサイクリングモデルもないため、まずは大阪市の地図を購入。市境にマーカーでラインを引き、行きたいスポットや自転車が通れる道を確認しながら、一緒にコースを考えていきました。

小学2年生が普通の自転車で走行できる距離や体力を考えると、途中で1泊したほうがよいと判断。そして熱中症対策も考えて決行日は年末と決め、ついに大阪市一周のプランが完成しました。
当日は朝6時前に出発。無料の川下トンネルや渡船を使ったり、高い橋をいくつも渡ったり、美景にカメラを向けたりしました。道行く何人かの方に「その挑戦すごいね」などと温かい声をかけてもらい、嬉しかったのを覚えています。エリアごとにさまざまな顔があり、市全体が無料のアトラクションだな、と私も存分に楽しみました。
帰宅したのは大晦日前日。撮った写真を私がプリントアウトすると、息子はそれを地図に貼ったり、印象に残ったスポットや記憶していることを書き入れたりしていました。ゲーム的にいえば、オープンワールドゲームでマップを広げていくような喜びを感じていたのではないかなと思います。新年にその地図を見て驚く祖父母を前に、息子は笑顔を輝かせていました。



こうして、「年末の親子自転車旅」はわが家の恒例行事となりました。
◆3年生(2泊3日)
大阪府一周旅(実際は大阪府と和歌山県との境までを往復する大阪府ほぼ縦断旅)
◆4年生(2泊3日)
大阪湾と淀川が接する河口ゼロポイントから上流へさかのぼり、桂川・宇治川・木津川が合流する「三川合流地域」を経て、さらに宇治川・瀬田川をさかのぼって琵琶湖大橋を渡って折り返す淀川制覇旅
◆5年生(2泊3日)
自転車のみでさらに旅程を広げるのは難しかったため、青春18きっぷで琵琶湖・福井・朝来市の竹田城跡を巡り、姫路から帰ってくる関西エリア一周旅
※6年生のときは受検を控えていたため旅はお休み
このように毎年範囲を広げながら、自分で計画を練りそれを実践していくことには、もちろん苦労や失敗もたくさんありました。
たとえば、自転車では通れない道だとわかって遠回りするはめになったり、公園で遊んだり寄り道したりするうちに宿へ到着する時間が遅れたり、長時間自転車に乗るなかで(父が)お尻痛に悩まされたり、まさかのパンクで急きょ自転車店に寄ったりしたことなど。
逆に、思わぬ幸運もありました。年末の宿泊客は少ないらしく、宿の方が夕食を豪華にしてくれたり、寄ったダムの歴史などについて丁寧に説明してくれたりと、人の温かさを感じる場面の数々が息子ともども思い出に残っています。
* * *
こういった経験をとおして息子は、地図の読み方を理解したり、地図を見て距離感を体験から予測できたり、山や坂が多いエリアのたいへんさも計算して行程の時間の見通しを立てたりといったことができるようになりました。
何より、自分が住む町や大阪、関西の知らなかった価値、素晴らしさ、ポテンシャルに気づいたと思います。旅によって、こういった深い学びが得られたことが、挑戦することの楽しさと結びついたようです。



中学生になってからも、息子は、
◆関西国際空港往復日帰り旅(大阪府一周のときのルートを使った)
◆大阪市南端の大和川河口から遡り、源流の奈良まほろば湖まで往復100km日帰り旅
◆武庫川を遡って生瀬から六甲山を越えて有馬温泉でひとっ風呂浴びる日帰り旅
などの自転車旅のプランを自分で立て、一人で実行しています。そうやって、自分がレベルアップしていく感覚を味わっているのかもしれません。
ちなみに、大和川河口〜まほろば湖往復プランと、有馬温泉日帰りプランは、それぞれ2回目に私も連れていってくれましたが、相当厳しかったです。体力面で子どもが親を超えたと痛感した体験でした。

父「自転車旅が受検に役立ったのはどういうところ?」
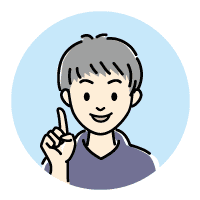
息子「最後まで挑戦すること! 目標だけ見ると難しそうでも、挑戦し続けることが大事だってわかったよ。」

堤谷 孝人 (つつみたに たかひと)
関西在住。2004年から子ども関連(保育・育児・教育)の取材、編集、制作をフリーランスで行う。職業柄、スーパーキッズや学校、教育機関などの取材をする機会多数。2008年、京都市立西京高等学校附属中学校を取材したことをきっかけに公立中高一貫校に強い興味をもつように。その後、長男が関西の公立一貫中学に合格。受検にあたりZ会小学生コース「公立中高一貫校適性検査」「公立中高一貫校作文」を利用した縁で、2023年4月よりこの連載をスタート。