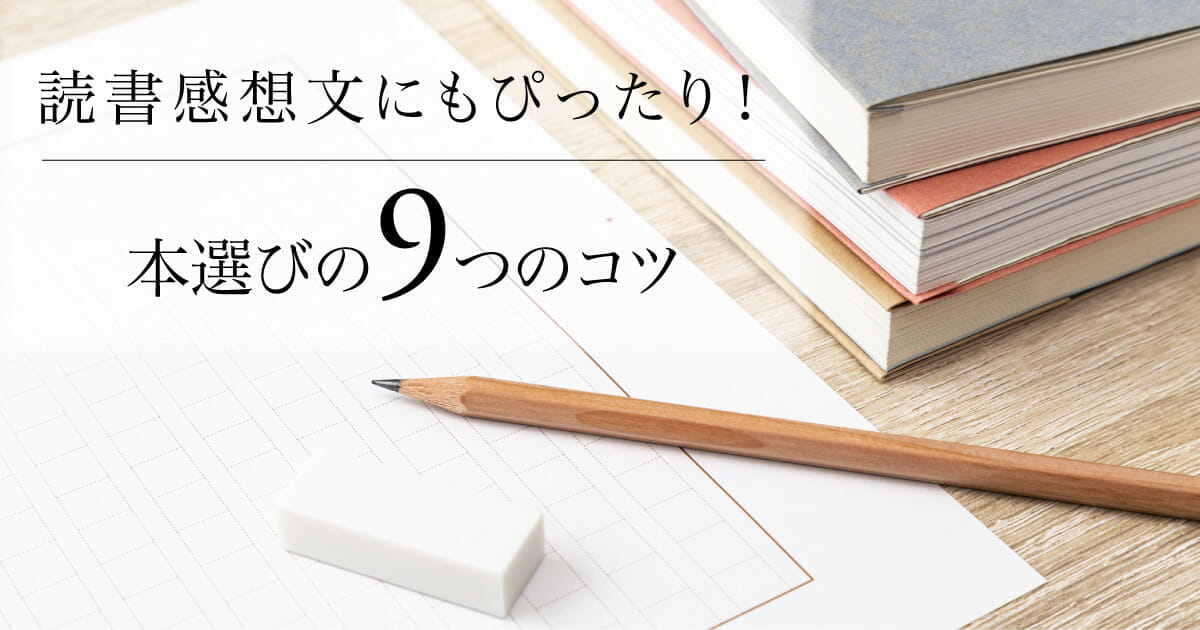そこで今回は、読書感想文を書くことを見据えた本選びのコツをご紹介します。
後半では、読書感想文が宿題にない場合でも使える本選びと読書をもっと楽しむコツを取り上げます。
読書感想文が書きやすいテーマから本を選ぶコツ
読書感想文は本の感想を書くものですが、単に「おもしろかった」「すごいと思った」ではなく、「自分はどう考えたのか」を書くことが大切です。自分がふだん考えていること・興味をもっていることに近い内容の本を選ぶことが、いざ読書感想文を書くときに苦労しないポイントです。
また、本を読みながら付箋を貼ったり、作文用のメモをとっておいたりすると、あとから読書感想文が書きやすくなります。今回は、おすすめのテーマと、そのテーマに沿った作文メモのポイントを紹介します。
<友だちとのつきあい方に興味・関心がある子なら>
コツ1 学校を舞台とした本や、習い事(スポーツ・音楽など)がテーマになった本
学校や友人関係、習い事などがテーマになっている本は、自分自身の経験と重ねて、主人公や登場人物の気持ちを想像することができます。
「自分だったらどういう気持ちになるだろう」「自分はあのときこんな行動をしたな」などと自分に置き換えながら読み進められるとともに、作文するときにも自分の言葉で表現しやすくなります。
例.涙が出そうになった、胸がきゅっとした、うれしかった、悲しくなった 等
・似たような経験がある場合、そのときの自分はどうしたか、どういう気持ちになったかを思い出して書く
・「もしも、自分が〇〇なら」と主人公や登場人物の視点に立って、自分ならどうするか、どう思うかを書く
このテーマを選ぶなら『わくわくワーク夏休み復習編』がおすすめ!
作文メモも一緒に作っていくので、書き方を知りたい方におすすめです。
・4年生:尾崎美紀『さよなら ごめんおばけ』(汐文社)
・5年生:芝田勝茂『ぼくらのサマーキャンプ』(国土社)
・6年生:梨屋アリエ『雲のはしご』(岩崎書店)
(※2024年現在)
<熱中しているもの、憧れや夢がある子なら>
コツ2 興味のある分野やその関係者を詳しく取り上げた本
熱中している分野や自分の好きなことについて書かれてる本は、自分の憧れや将来の夢と関連させて書くことができます。
夢中になっている物事について、その魅力を自分なりの視点で伝えることができ、「自分が将来どうなりたいのか」「夢を叶えるために今何をすべきか」など発展させて作文を書くこともできます。
<努力しているものがある子なら>
コツ3 尊敬できる人物が書いた、あるいは登場する本
その道の第一人者、研究者、歴史上の重要人物、ハンディを抱えながらも活躍している人、道を切り開いた人のことが書かれた本には、起承転結があり引き込まれやすいものが多くあります。困難をどう乗り越えたのか、そのときの思考や行動に着目することで、「自分だったらどう考えるだろう」と自分の意見を書きやすくなります。「困難を乗り越えるために大切なこと」に気づきやすいテーマです。
<社会について関心がある子なら>
コツ4 命の尊さ、他者へのいたわり、よりよい社会の実現、平和的な活動に関する本
医療や看護、動物のケアなどを通じて命の尊さや他者へのいたわりについて書かれている本や、よりよい社会の実現や平和について考えさせられる本も多くあります。
普段あまり意識しないような「課題」に気づくことも多いでしょう。「自分はその課題に対してどう考えるか」「読む前と読んだあとで意識はどう変わったか」を表現することで、自分ならではの深い感想文にすることができます。
<物語の世界に没頭することが好きな子なら>
コツ5 ハラハラドキドキする冒険ものやファンタジー
冒険ものやファンタジーは、小学生に人気のあるテーマです。どんどんページをめくり一気に読み進められるので、その分作文を書く時間を確保できるというメリットもあります。
ただし、作文を書くときのテーマ設定が難しく、あらすじを書くだけで終わってしまうこともあるので要注意です。
「おもしろい」と感じたところ、クライマックスでの主人公がどう問題を解決したか、作品を代表する名言などに注目すると、そこでの気づきや自分の考えにフォーカスしやすくなり、読みやすい作文になります。
<何に関心があるかわからない……そんなときは>
コツ6 青少年読書感想文全国コンクールの課題図書から選ぶ
お子さまが何に興味があるか、何が好きなのかはっきりしない場合もあるかと思います。テーマから選ぶのが難しい場合には、課題図書から選ぶのもおすすめです。青少年読書感想文全国コンクールの公式サイトには、みどころや選定理由・紹介動画も掲載されています。課題図書の中から親子で会話しながら選ぶのも、お子さまの興味を広げるきっかけになりますね。
本選びや読書をもっと楽しむためのコツ
読書感想文を書くときだけでなく、日頃から読書を楽しむためのコツをご紹介します。
コツ7 自分だけの読みたい本リストを作成する
気に入った本に出会うには、興味をもった作品と同じ作者、同じテーマなどでどんどん関心をつなげていくことが大切です。Z会の教材や学校の教科書で扱われている作品やその著者の他の本、あるいは、WebサイトやSNS上にある個人や団体がまとめた「おすすめ本リスト」を有効活用しましょう。気になるものはリストとしてまとめ、自分だけの「読みたい本リスト」を作成してみてください。読書感想文の課題に取り組むときには、そのリストの中から選んでもいいですね。ただし、他人のおすすめが必ずしもお子さまが興味を惹かれる本とは限りません。お子さまが楽しく読める本選びを心がけてください。
感想をしっかりメモしようとするとハードルが高いので、印象に残った一行(セリフなど)を書き写すだけでもいいですね。
あわせて読みたい「Z会おうち学習ナビ」おすすめ記事
「Z会おうち学習ナビ」では、メニュー「子育て・教育情報」から、幼児・小学生のお子さまをもつ保護者の方におすすめの記事を提供していきます。下記の連載ではお子さま向け・大人向けの絵本や本の紹介をしていますので、あわせてご覧ください。
コツ8 図書館や書店で実際に手に取って、中身を見てみる

最近は、通信販売による書籍購入や、サブスクリプションサービスによる電子書籍の閲覧などを利用することで、図書館や書店に行かずとも手軽に本を読めるようになりました。これらは非常に便利なサービスですが、実際に本を手にとってみてわかる本の魅力や、たくさん並ぶ本の中から選ぶ楽しみ、たまたま目にした1冊の本との出会いというのもありますので、「リアルな本選び体験」の機会もぜひ大切にしていただきたいと思います。