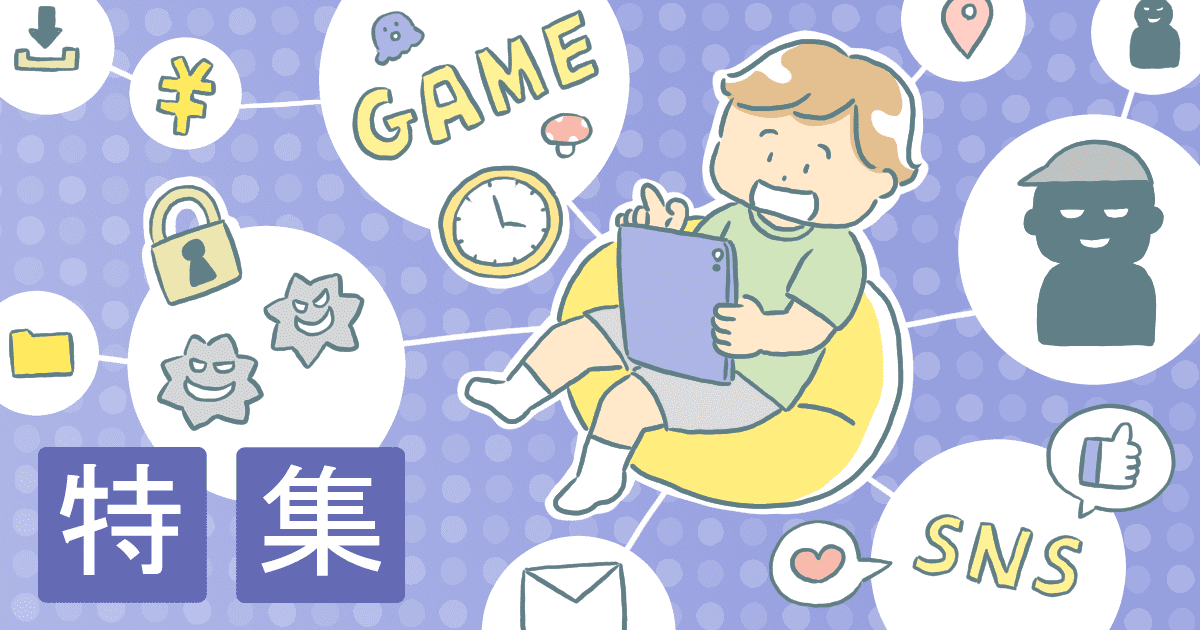今や、私たちの生活に欠かせないデジタル・デバイス。大人だけでなく小学生でもスマートフォンやタブレット、パソコンなどを愛用する時代になっています。これらは便利で楽しく魅力的である一方、使い方を間違えるとさまざまなトラブルに巻き込まれる危険性も。「子どもを守るには、使い方のルールが大事。わが家も親子でデジタル・デバイスを楽しみながら、日々ルール作りに試行錯誤しています」と笑顔を見せるのは、お茶の水女子大学理学部准教授の五十嵐悠紀先生。五十嵐家のエピソードも交えながら、ルールにまつわるお話をしてくださいました。
※本記事は、2023年8月24日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
デジタル・デバイスによって進化する学びの場
———子どもにとってデジタル・デバイスの魅力は何でしょうか?
親や友だちと連絡がとれて、動画も見ることができて、調べ物もゲームもできる。まるで玉手箱のように魅力的ですよね。デジタル・デバイスの普及によって、子どもたちの学びの場も変化しています。たとえば、生きた外国語に触れられたり、野生動物や微生物のリアルな映像が見られたりと、自分が未経験のことでも動画でわかりやすく理解できる機会が増えたと思います。最近は、放課後にグループ通話で友だちとつながって、勉強を教え合ったりもするようですね。
———小学校でもタブレットを使う授業が増えているようです。
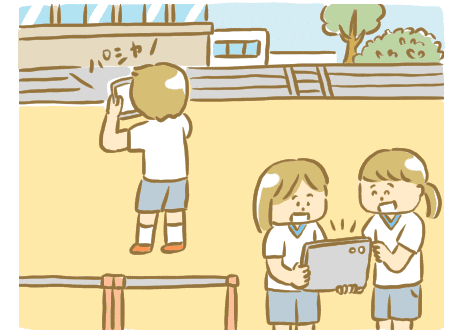
子どもがデジタル・デバイスを使うときに心得ておきたいこと
———デジタル・デバイスを使い始める年齢について、どのようにお考えですか?
「何歳からOK」というのは一概に言えないのですが、「話をしてわかる」「ルールを守ろうと思える」ことが一つの目安かなと思います。デジタル・デバイスは小型のパソコンであり、パソコンでできることはほぼできます。携帯型ということもあり、人の目の届きにくいところでインターネットにつながることのできる端末を持たせても大丈夫かどうかが判断の基準になってくると思います。
わが家には小中学生の3人の子どもがいるのですが、みんなスマホもタブレットもゲームも大好きです。私の仕事柄、自宅にはいろいろなデジタル・デバイスがあるので、子どもたちは幼いころから興味津々。一切触れさせないというのは難しかったので、使い方をきちんとレクチャーし、ことあるごとにルールも話し合いながら、デジタル・デバイスと付き合うという方法を取りました。
———どのように、お子さまたちにインターネットの基本的なルールや危険についてお話しされたのでしょうか。
最初に約束を決めてそれを守らせるという考え方とは少し違い、親も子どもと一緒にデジタル・デバイスを使いながら、基本的なルールや危険について話をするようにしてきました。「いつでも、親に見られていいように使ってね」ということは最初に伝えていましたので、「親に見られたらまずいような使い方はしない」というのが、基本ルールになっていったように思います。また、ネット犯罪に関するニュースを一緒に見ながら「こんな事件があるんだね」「あなたの周りでは大丈夫?」「どうしたらよいんだろうね」と問いかけ、子ども自身が「これはいいんだ」「これは危険なんだ」という判断基準を持てるような場を作るようにしています。
———具体的に、親子でどのような話をするとよいのでしょうか。
技術の進歩は著しい一方で、法律や規則の整備といった側面はなかなか追いつきません。何がきっかけでトラブルに巻き込まれてしまうかわからない部分もありますね。無料の新しいアプリを入れたいと言われたときには、「無料で提供する代わりにウイルスを仕込んだり個人情報を吸い上げたりするような仕組みになっているアプリもあるんだよ」ということを伝える必要があります。「個人情報が悪い人に知られてしまうと、迷惑メールや架空請求の被害者になったり、なりすましに使われてしまう恐れがあるので、やたらにダウンロードしてはいけないんだよ」と。
ただ、子どもと話し合って、アプリを入れようということになった場合、個人情報が流出しない入力の仕方をアドバイスするという方法もあります。たとえば、「友だちを作ろう!」みたいなアプリがあって「君の名前は?」「家はどこ?」といった質問をしてきた場合には、「名前はニックネームで十分なんじゃない?住んでいる場所も、住所ではなく『公園の横』『日本』とかなら特定できないよね 」とアドバイスすることはできます。「危ないからそんなアプリを使ってはダメ!」と言うことは簡単ですが、なぜ危ないのか、どうしたら危険を回避できるのかについてしっかりと教えていくことも大切なことだと考えます。これからの時代を生きていく子どもたちには、自分が初めて使う技術やアプリに接するとき、そして既存の技術であっても今までと違った使い方をするときには、メリットだけでなく、想定できるデメリットや危険の可能性にまで意識を向け、「これでいいのかな?」と立ち止まって考える力を持ってほしいと思うからです。
ルール作りのコツは「コソコソ使うような状況を作らせない」こと
———LINEの返信に追われたりゲームがやめられなかったりする場合は、どうしたらよいでしょうか。
デジタル・デバイスは「麻薬と一緒」と表現する専門家もいますが、つい夢中になってしまうのは子どもも大人も同じですよね。子どもは大人の背中を見ているので、私も子どもの前での使い過ぎには注意しています。子どもの使用時間が長引いたときは、頭ごなしに「やめなさい」と言うよりも「目や姿勢が悪くなるよ」「自分の頭でものを考える時間が減るよ」など、ダメな理由を伝えるほうが効果的。最近のデジタル・デバイスには「ペアレンタルコントロール」という機能があって子どもの利用時間の制限ができるので、ぜひ活用してみてください。
———使用時間の目安はありますか?
低学年のうちは30分以内が理想かと思いますが、モニターをただぼうっと見ているだけなのか、プログラミングなどのクリエイティブなことをしているのか、勉強に使っているのか、などの内容によって時間を調整してあげるといいですね。また、YouTubeなどはいったん見始めると次々におすすめの動画が出てきますが、そればかり見ていると新たな情報に出合いづらくなるデメリットがあります。一方、テレビや新聞からは、自分の好みに関わらず多彩な情報が入ってきますよね。ある意味、とてもいいメディアだと思うんです。いろいろな情報に触れる機会はとても大事なので、そうした観点も踏まえながら、ご家庭に合った時間のルールを考えられるといいですね。
———使用時間をルール化する際は、臨機応変さも必要ということですね。しかし、それだとルール決めが難しくないでしょうか。
そんなときは、まず「可視化」してみてください。目に見える形にするという意味ですが、1日の行動と時間を書き出して、勉強、遊び、ゲーム、仕事、家事などの項目ごとに色を塗ってみるんです。わが家でもやってみたのですが、私のグラフを見た子どもが「お母さん、家族のためにこんなに時間を使っていたの?」と驚いて、お手伝いを始めたんです。また「勉強時間に比べて、こんなにゲームをやっていたのか……」と、子どもなりにショックを受けたり。可視化して現状を知ることで、具体的にどのようなルールにしたらよいのか話し合いがしやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに、せっかく決めた時間のルールも、子ども部屋にこもるとつい……ということがあるかもしれません。そこでわが家は全員、デジタル・デバイスはリビングで充電し、リビングのみで使うと決めています。同じく子どもの好きなマンガもリビングのみ。コソコソ読むのではなく「読みたいなら、親の前で堂々と!」という方針です。
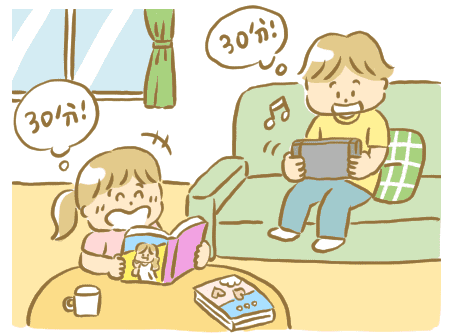
ルールは日々更新! 子どもと一緒に楽しみ、寄り添うことで、わかることがある
———決めたルールを子どもが守れないときは、どうしたらいいですか?
「ルールを破ったから、お小遣いなしね」というようなペナルティを与える方法も考えられますが、「ペナルティを受ければ、ルールを守らなくてもいいんだ」という発想につながってしまうのも違いますよね。守れないなら、なぜ守れないのか、子どもに理由を聞いてみるといいと思います。理由って意外と大事なんですよ。
———「言い訳」と思ってはいけないのですね。
たとえばうちの子どもたちはゲームが大好きで「1日30分」と決めているのですが、カートレースのゲームをやると決まって数分オーバーしてしまうんです。「なぜかな?」と思って私もやってみたら、コースやキャラクターなど事前に選ぶものがいっぱいあって、最短でも1回17分かかることがわかりました。「なるほど。それなら、17分×2回分の約35分までOKにしよう」と、延長することに。ほかにも、子どもたちが画面上で試行錯誤しながらコースを作っていくクリエイティブ系のゲームがあるのですが、30分という制限を守るために、紙に手書きでコースをかいていたんですね。それではゲーム本来のおもしろさが生かせていないと思い、「ちゃんとやるには、どのくらいの時間がかかるの?」と聞いたら「2時間」と言うので、「じゃあ土曜日ならいいよ。代わりに平日はなしね」とルール変更しました。子どもには「ルールを変えたいときは言ってね」と伝え、話し合いの機会を多く持つようにしています。
———ルールは絶対!ではなく、子どもの気持ちに寄り添って、柔軟に対応されているのですね。
子どもの気持ちに寄り添っていると、何か困ったことがあったとき、信頼して相談してくれると思うんです。逆に「ダメ」とばかり言っていると、子どもも隠れてコソコソやりかねません。それに、そもそも、大人の考えたルールは穴だらけですからね。「夜9時以降のデジタル禁止」と言えば、朝すごく早起きしてやっていたり、「YouTubeは30分まで」と決めれば「わかった」と言って、次々に違うアプリから動画にアクセスしていたり。思わず「賢い!」とほめたくなるほど、デジタル・ネイティブ世代の発想って違うんです。いっそのこと、子どもにルールを作らせるのもおもしろいと思います。ルールの穴を考えられる子は、ルールも考えられる子だと思いますから。「お母さんはこんなことが心配なのだけど、どうしたらいいと思う?」と、ぜひ聞いてみてください。
———これからの時代を生きていく子どもたちに、デジタル・デバイスとどう付き合っていってほしいとお考えですか?
デジタル・デバイスをを使いこなすことで、生活は間違いなく便利になります。これからの時代の子どもたちには使いこなすだけでなく、「私だったらこう使うけどな」「このアプリって実はこんな使い方ができるかも」「自分だったらこんな仕組みを作るのに」などの発想が子どもたち自身から出てくるようになるといいなと思います。そういった発想を育てるために、危険を知り、ルールを守りながらも積極的にデジタル・デバイスを使っていってくれることを望んでいます。一方で、野原でサッカーしたり手を動かして工作したりといった、生の体験もすごく大事だと思います。子どもたちにはさまざまな経験をして大人になってほしいですね。
———ありがとうございました。
五十嵐先生に聞く、インターネットQ&A

五十嵐 悠紀(いがらし ゆき)
お茶の水女子大学 理学部 情報科学科 准教授。2010年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。2018年より明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科准教授。2022年より現職。素人でも使えるインタラクティブなコンピュータグラフィックス(CG)や、そのためのユーザインタフェース(UI)などに興味をもって研究に取り組んでいる。著書に『スマホに振り回される子 スマホを使いこなす子 (ネット社会の子育て) 』 (ジアース教育新社)、『AI世代のデジタル教育 6歳までにきたえておきたい能力55』(河出書房新社)など。