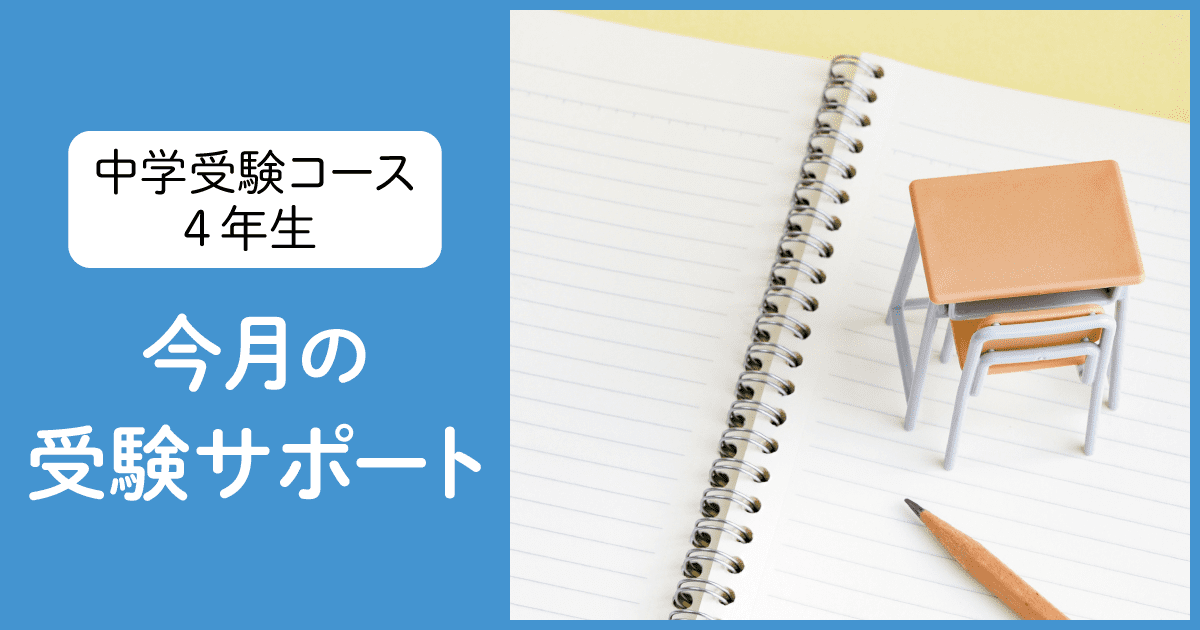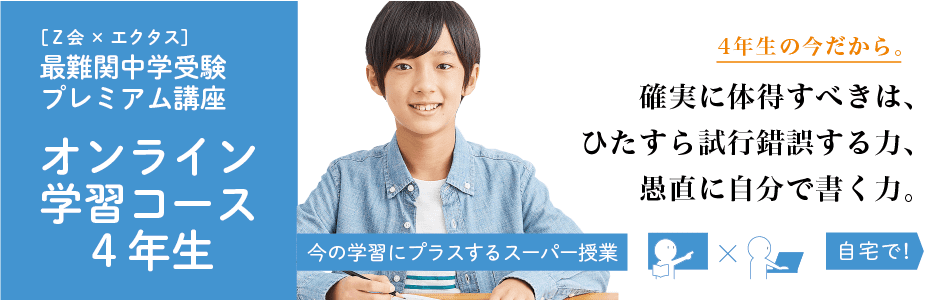中学受験コース4年生の学習も、残すところおよそ4カ月となりました。今回は、中学受験コースの教科担当者より、これから取り組む単元の学習ポイントをお伝えします。つい中だるみしてしまいがちな時期ですが、ぜひ参考にして、残りの単元も引き続き頑張っていきましょう。
国語
11月号では、詩やずい筆などを中心に取り上げます。志望校の入試でこれらが出題される場合は、4年生のうちからしっかり対策をしておきましょう。
12月号では「物語の読みとりのまとめ」として、「物語の場面」「登場人物の気持ち」「登場人物のせいかく」の読みとり方などを整理して学習します。入試問題の物語文では、とくに人物の気持ちに関する問題がよく出題されます。確実に基礎を身につけるようにしましょう。
1月号では「説明文の読みとりのまとめ」として、「話題をとらえる」「だん落の内ようとだん落どうしのつながりをとらえる」ことなどを学びます。文章の中心となる話題を意識しながら、具体例を示す段落、理由を示す段落など、文章の構成にも気をつけて読んでいくと、筆者の主張を読みとりやすくなるでしょう。
算数
10月号・11月号で分数の四則演算を学習します。通分や約分の問題を解くときに、9月号で学習した「倍数」「約数」などの用語がひんぱんに出てくるため、もし用語の意味を忘れていた場合は、必ず9月号に戻って内容を復習するようにしましょう。倍数・約数を題材にした入試問題は、倍数や約数をどう利用するかに気付きにくく、難問化しがちです。10月号・11月号を学習する中で「こういうときに倍数(約数)を使うんだな」と実感し、経験を積んでいきましょう。
また、1月号で学習する円周と円の面積では、小数・分数がまざった計算をたくさん行います。11月号で学習する分数の計算の途中で約分する方法や、2月号2回目第3回練習問題4で学習した分配法則について見直しておくとよいでしょう。
理科
10~11月号で学習する「水溶液の性質」では、物質が水に溶ける量の変化について学習します。水の量や温度、物質の種類によって溶ける量にどのような違いがあるのかを、実験の方法や結果とあわせて確実に身につけておきましょう。
12月号で学習する「電流のはたらき」や1月号で学習する「磁石と電磁石」といった電気の単元は、物理分野の中では、力学と並んで入試でよく出題されます。乾電池のつなぎ方と乾電池のはたらきの関係、電磁石の強さと電流の関係などを理解しておくとよいでしょう。
12月号で学習する「天気と気温」では、天気によって1日の気温の変化の仕方が違うこと、日本の天気は西から東に移りかわる傾向があることなどをおさえておきましょう。
社会
地理分野を体系的に学習していきます。
9月号と10月号では、「日本の気候」について学習しました。11月号と12月号では「農業」、1月号では「水産業」と「林業」を学習していきます。気候や産業の特徴をおさえるだけでなく、「太平洋側で夏に雨が多く降り、冬に晴れの日が多いのはどうしてなんだろう」「米づくりがさかんな場所にはどういう特徴があるのだろう」など、どうしてそうなるかを考えながら学習を進めていくとよいでしょう。学習内容をイメージしやすいように、アプリの要点に模式図や写真を掲載していますので、ぜひ見ておきましょう。また、入試でよく問われる社会の用語も多く出てきます。アプリに漢字練習のページがありますので、最初に学習したときに正確に漢字で書けるように練習しておきましょう。
次回の受験サポートは10月23日(木)更新予定です。