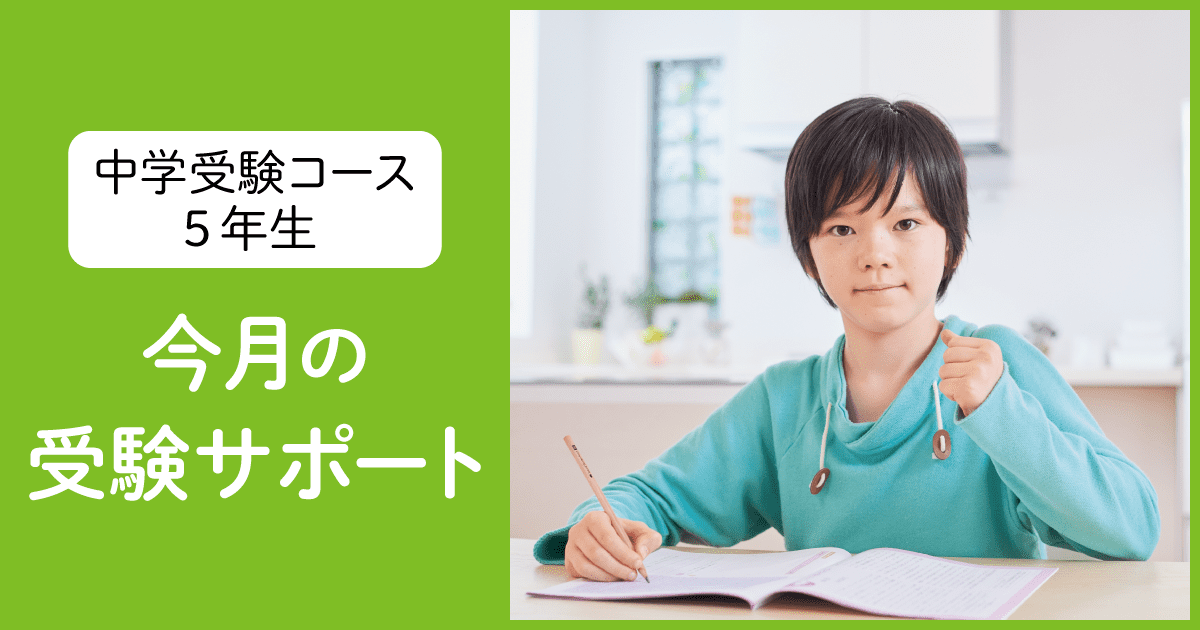10月に入り、小学5年生のお子さまがいらっしゃるご家庭では、中学受験への意思が固まってくる頃ではないでしょうか。
これまで模試を受験していなかったご家庭も、これからは定期的に模試を受け、お子さまが受験生全体の中でどのくらいの位置にいるのか、また志望校まであとどのくらい距離があるのかを把握していきましょう。そして、模試の結果を日々の学習にしっかりと活かしていくことが大切です。
模試の定期的な受験を
通信教育を中心に受験対策を進めていくにあたっては、模試を定期的に受験し、その結果を見すえながら学習を進めていくことが有効です。今まで積極的に模試を受験してこなかったご家庭もあるかと思いますが、学習状況を把握し、志望校・受験校の検討を本格的に進めるためにも、5年生の後半からは、無理のない範囲で少しずつ模試を受けるようにしていきましょう。
お子さまも、模試を受ける経験を通して、中学受験をより現実的にとらえられるようになり、「もっとがんばろう」「この弱点を克服しないと」といった自覚が生まれるはずです。結果を真摯に見つめ、「どうすればもっとできるようになるのか」と定期的かつ具体的に考える機会をもつことが、これからの学習には必要です。ぜひ、模試を上手に活用して、受験勉強を効率的に進めていきましょう。
6年生になったら、前半は目的にかなう模試を適宜選びながら、後半からはできるだけ毎月模試を受験するようにするとよいでしょう。
※模試を受験する際に気をつけたいことは、受験サポート「模試の受験を今後の学習にいかしましょう!」でご紹介しています。
模試活用のABC
Z会おうち学習ナビにて毎月第4週に更新している![]() 模試活用のABC では、模試を上手に活用するための模試受験の基本をご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
模試活用のABC では、模試を上手に活用するための模試受験の基本をご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
模試の反省を学習計画へ役立てるために
模試を受験した当日にしておくこと
模試の受験で大事なことの一つに、時間の使い方を身につけることがあります。模試は出題範囲が広いため、難しい問題やまだ学習していない内容が出題されることもあるかもしれません。しかし、本番の入試を想定し、「今、その問題に取り組むべき」なのか「あとで時間が余ったら取り組むべき」なのかといった判断をする練習の場ととらえましょう。
そして、多くの場合、模試の問題と解答冊子は持ち帰ることができますので、必ずその日のうちに、できたところ、できなかったところをお子さまと確認しておきましょう。
またそのときに、下記の点も合わせて確認をしておくとよいでしょう。
① 時間配分を考えながら取り組むことができたか
② 解ける問題から取り組んだか
③ 見直しはしたか
④ 解けなかった問題の理由は何か
(「未習分野だったから」、「学習していたけれど難しかったから」など)
とくに、①~③の問題を解く手順や時間配分については、日にちが経つと記憶があいまいになり、次もまた同じ失敗を繰り返してしまう場合もあります。そのため、記憶が薄れないうちに振り返って反省点をまとめ、次の模試にいかすことが大切です。
模試の結果が出たらしておくこと
試験が終わってしばらくすると、成績表と採点済み答案が郵送やWeb上で見られるようになります。結果が出たらすぐ、お子さまと一緒に確認しましょう。点数や順位にばかり注目しがちですが、どの教科・問題ができたか、また逆にどこができなかったのかを必ず確認するようにしてください。また、問題別の正答率も確認し、正答率が高い問題で失点していないかどうかもチェックしましょう。復習の際の参考になるはずです。
教科によって平均点がばらつくこともあるので、得点と偏差値をあわせて確認しましょう。できなかった教科があった場合は、どんな問題のためにふるわない結果になったのかを確認します。
原因の箇所がわかったら、その対策について具体的な話をする前にまず、できた問題について一通り触れるとよいでしょう。
「こんなに難しい問題もできたんだ」「算数は平均よりも高い得点が取れたね、がんばったね」という励ましが先にあると、子どもにとっては大きな力になり、弱点の補強にも前向きになれます。
模試で大切なことは、「成績の推移」を確認することです。大きく足を引っぱっている教科がある場合、その教科のできない分野・形式を克服するための課題を学習計画に組み込むなどして、補強していきます。
一方、得意な教科や分野があるのであれば、それらを得点源とすべく、偏差値や得点の目標ラインを決めることも、勉強に対するモチベーションアップには有効です。
そして、次の模試が近づいてきたら、問題を解く手順や時間配分について見直し、試験時間内に解ききるスキルも少しずつ磨いていきましょう。
次回の受験サポートは10月23日(木)更新予定です。