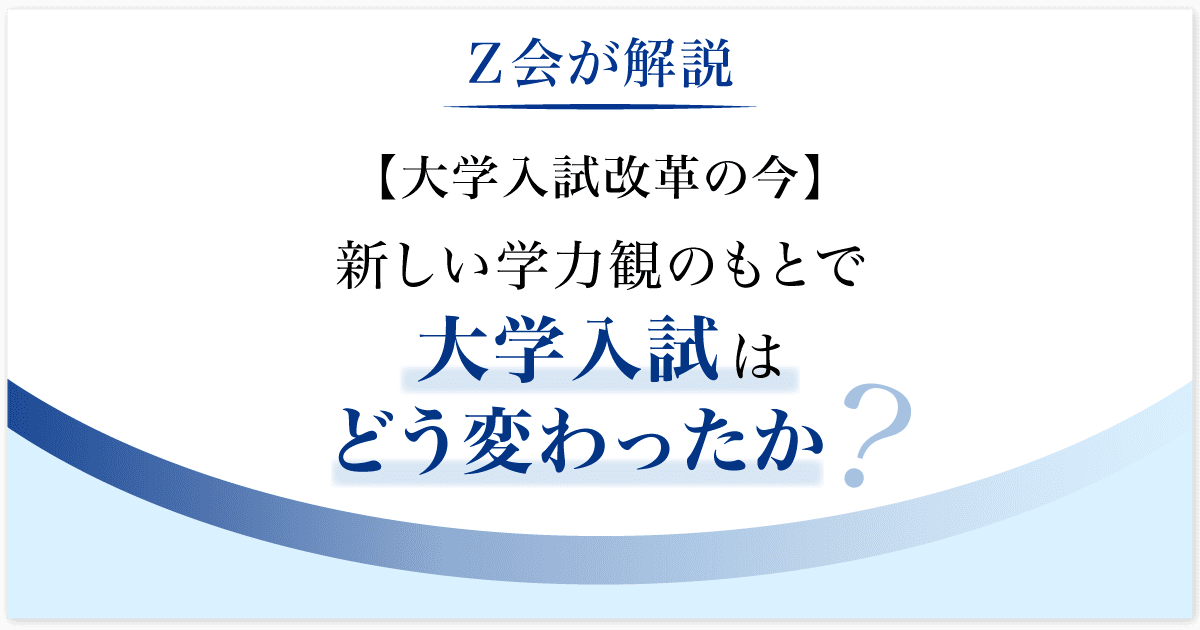長いあいだ、学力とは既存の知識・技能を身に着ける力だと考えられていました。
しかし、現代では社会環境の変化にともなって「学ぶべき知識・技能」自体が急速に変容し、解決すべき課題もより複雑・多様化しています。そのため、定型的な知識・技能の習得だけでなく、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ」力が非常に重視されるようになってきました。
そうした学力観の変化が大学入試に及ぼす影響についてまとめたのが、2018年に掲載された以下の記事です。
求められる「学力」が変わるって本当?主体性・多様性・協働性を問う出題とは(2018/05/12)
旧来の「知識・技能」に加えて「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を重視する新しい学習指導要領が高校で実施されたのは2022年度から。
また、現実の社会生活に即した思考力、課題解決力を測ろうとする「大学入学共通テスト」がスタートしたのはそれに先立つ2021年1月でした。
これらを経た2023年現在、大学入試はどうなっているのでしょうか。
総合型選抜による大学入学者が増加
「主体性・多様性・協働性」を重視する最新の学習指導要領の方向性とマッチした選抜方式としては総合型選抜(旧AO入試)が思い浮かびます。実際、総合型選抜での大学入学者は2018年度の約6万人から、2022年度には約8.5万人に増加しました。
国公立大学に限っても、総合型選抜の定員は2019年度入学者では約4,800名でしたが、最新の2023年度入学者では約7,700名。*1
国公立大学でも総合型選抜での入学はさらに広がるでしょう。
ただ、2023年度国公立大学入試の募集定員総数は約128,000名。そのうちの約7,700名ですから、総合型選抜での入学者が全体に占める割合は6%程度にとどまります。*1
いまのところ、入試制度そのものが一般選抜ではなく総合型選抜をメインとするかたちへ切り替わるといった事態には至っていません。
変わりつつある入試問題
それでは、一般選抜はどうなっているでしょうか。
「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」を評価しやすい試験科目と言えば小論文や面接ですが、国公立大学の一般選抜においては、小論文や面接を実施する割合は2019年度と2023年度ではほぼ横ばいです。*1
一方、「入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)」を明示し、「主体性・多様性・協働性」を個別試験で評価することや、出願時に書類(生徒自身が作成した志望理由書や学校の作成する調査書など)の提出を求めるケースは一般入試でも増えています。
小論文・面接という形式に限らず、「主体性・多様性・協働性」を評価していることが伺えます。
さらに注目すべきは、マーク式の出題で「知識や基礎力を測る試験」として認識されていたセンター試験が、大学入学共通テストに変更されたことです。
2021年1月より3度実施され、いずれも思考力を問う問題が出題されており、知識や解法だけでは得点できなくなりました。
入試全体を通して、「知識・技能」だけでなく「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を測ろうとしていることがわかります。
生成AIがもたらした衝撃
一方、入試での学力評価をめぐっては、5年前と異なる状況も生まれています。最大の問題はいわゆる生成AI(ChatGPTなど)の登場と急激な普及でしょう。
すでに大学教育の現場では、学生自身が書いた文章とAIに書かせた文章を区別することは難しく、レポート制作に際して生成AIの使用を禁止する案内を出す大学も増えています。
「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を重視する新しい学力観のもとで、大学入試でも自己推薦書やレポートの提出、受験者によるプレゼンテーションなどが広く導入されてきました。
これらにAIが生成した文章が使われる可能性があり、各種大学が「生成AIを踏まえた入試の内容と形態は急ぎ検討すべき課題である」と表明しています。文部科学省でも、教育現場における生成AIの利用に関するガイド作成に向けた方針を議論することを表明しています。*2
また、最近、国を挙げてデジタル人材育成を図る方針が明確に打ち出されたことも、今後の入試に一定の影響を及ぼすかもしれません。
ここ数年、多くの大学で全学生がデータサイエンスの基礎を学べるようにするカリキュラム改革が急ピッチで進められ、今後は文理融合型の学習環境の充実も進みそうです。
こうした動きにともない、入試でも数学的能力を重視する傾向が強まる可能性があります。
新しい学力を身につけるには
入試制度や出題形式が変化しても、「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を重視する学力観は揺るがないでしょう。
では、「主体性・多様性・協働性」を身につけるには、高校生のうちに何をすればよいのでしょうか。
一つは、読むこと・書くことを日々の生活の中に習慣づけること。
自ら主体的に行動し、多様な人々と協働する力はますます重要になってきていますが、その前提にはしっかりした「思考力・判断力・表現力」がなくてはなりません。自らの考えをわかりやすく周囲に伝えることができなければ、多様な人々とうまく協働することもできないからです。
だから、教科書や参考書でインプットし、よく理解したうえでアウトプットする訓練はやはり大切。そのプロセスを他人やAIに替わってもらうことはできません。
もう一つは、目的意識をもつことです。
今日のように先行き不透明な時代には、言われるままに知識を吸収するだけでは不十分。
学んだ知識をどんな課題に生かすのか、一人ひとりが問われます。
その意味で、高校生のうちにしっかり目的意識をもって学び、自らの意思で進学先や入試方法を選択することがとても重要になるでしょう。
過去の調査でも、目的意識を持って大学を入学した生徒ほど、入学後も高い学力を維持し、卒業していることがわかっています。学ぶ目的を明確にすることが、学びの質を高めるのです。
*1:文部科学省 国公立大学入学者選抜の概要より
平成31年度:https://www.mext.go.jp/content/1412102_001.pdf
令和5年度:https://www.mext.go.jp/content/20221014-mxt_daigakuc02-000025217_1.pdf
*2:文部科学省 大臣記者会見等より
永岡桂子文部科学大臣記者会見録(令和5年5月9日):https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00374.html
Z会の「良問×添削」で新しい時代の学力を身につける
自ら問題を読み解き、思考を書くZ会の通信教育は、思考力と主体性を身につける学習法です。
添削指導を通した採点者との対話では、自分では気づかなかった強みや弱点を発見できます。
新しい時代の学力はZ会の通信教育で身につけましょう。
◆Z会の通信教育
高校生・大学受験生
Z会の添削指導
Z会の小論文対策講座
Z会公式おすすめアカウント
ぜひフォロー・友だち登録をお願いいたします