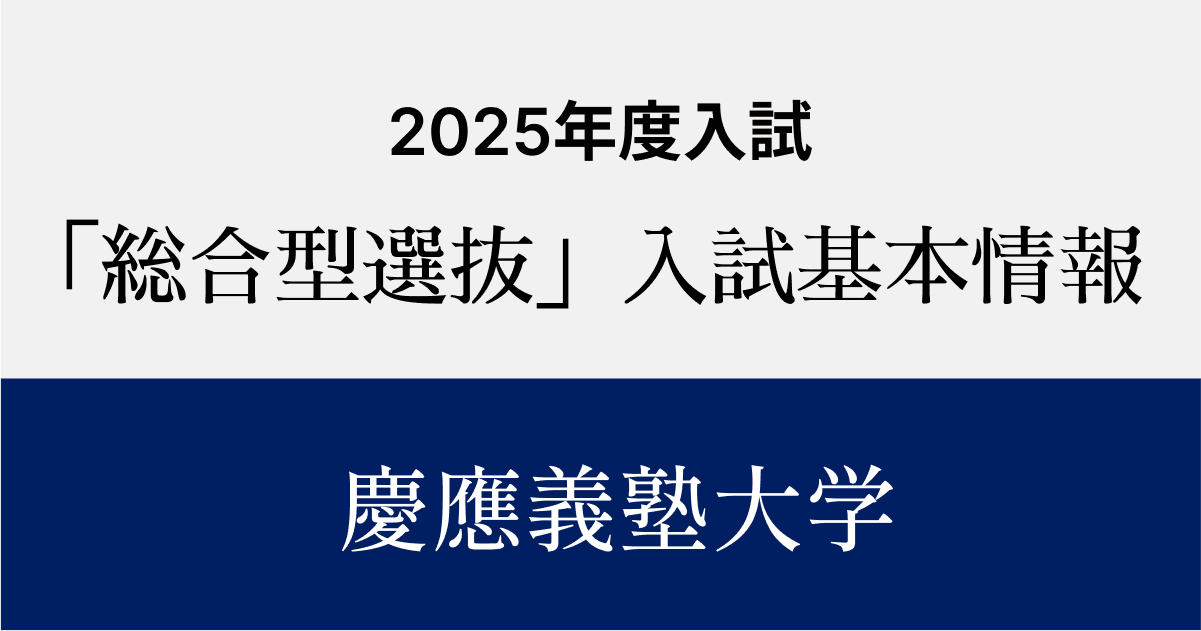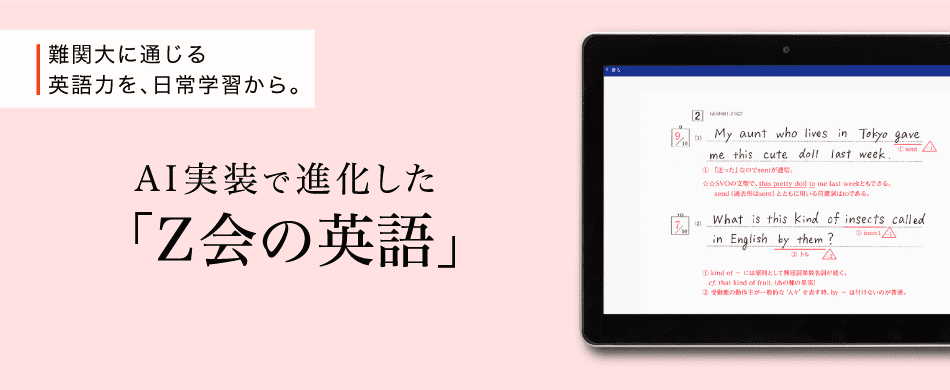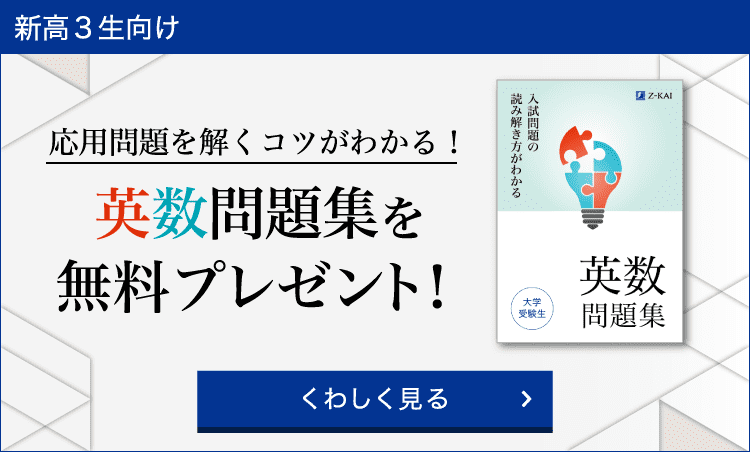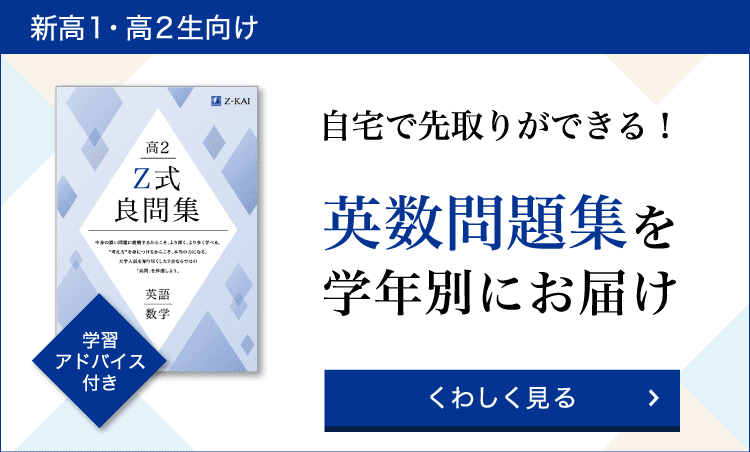入試制度が多様になる今、高校生活自体が評価対象になることも。高1・高2のうちから充実した学習・研究・課外活動を積むことも重要です。今回は慶應義塾大学の総合型選抜の制度を確認しながら、慶大をめざす高校生のみなさんが今なにをすべきかを解説します。
※本記事は慶應義塾大学より発表されている情報に基づいて作成しています(一部過年度の内容を含みます)。最新情報は、慶應義塾大学の公式ホームページにてご確認ください。
慶應義塾大学の「総合型選抜」とは
慶應義塾大学の入試制度は大きく分けると、以下のラインナップになっています。
- 一般選抜
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 帰国生・外国人留学生を対象とした入試
- 国際バカロレア入試(法学部のみ)
- PEARL入試(経済学部のみ)
慶大入試の特徴として、共通テスト利用入試はありません。また、国際バカロレア(IB)資格取得者を対象とした「国際バカロレア入試」、英語で経済学を学び国際的なリーダーをめざす「PEARL入試」は特定の学部のみでの実施となっています。
上記の入試ラインナップのうち、多くの学生が受験する一般選抜については、別の記事(慶應義塾大学入試基本情報)で触れています。今回の記事では「総合型選抜」を取り上げます。
試験の詳細は学部により異なりますが、以下の点はある程度共通しています。
- 従来の学力試験では測りにくい「志望動機」や「資質」「適性」などを評価する試験であること
- 高校時代の学習に対する姿勢や活動実績が重視されること
つまり、「志望学部のために、高校生活でなにをしてきたか」や「高校生活に真摯に取り組んでいるかどうか」などが評価されることになります。高1・高2生の段階から、志望学部を見据えて、日々の積み重ねを続けていくことが重要です。
慶應義塾大学各学部の「総合型選抜」の詳細
慶應義塾大学には多くの「総合型選抜」があります。今回はその中からいくつかを取り上げて、受験のポイントを確認していきましょう。
※その他の選抜制度、より詳しい試験内容は、慶應義塾公式サイト「入試制度」のページでご確認ください。
自主応募制による推薦入学者選考
<募集学部>
文学部
<試験内容>
- 出願書類(調査書、評価書、自己推薦書)による選考
- 「総合考査Ⅰ」「総合考査Ⅱ」による選考
<入試の特徴>
高校時代の自分自身の活動についてアピールし「自分自身を推薦する」入試制度です。
出願書類としては、学校側が志願者を推薦する「評価書」と志願者自身が高校での取り組みや文学部の志望理由を述べる「自己推薦書」などをもとに選考がおこなわれます。
「総合考査Ⅰ」は小論文形式、「総合考査Ⅱ」は与えられたテーマについての記述が課されます。文章構成・表現力、分析力等が総合的に評価されることになります。
<受験のポイント>
最大の壁は「総合考査」です。特に総合考査Ⅰは、各種資料を読解する必要があるうえに、外国語(英語・ドイツ語・フランス語のいずれか)による作文力も求められるため、非常に難度が高い内容になっています。
また、高校における「全体の学習成績の状況が4.1以上」が出願資格の1つとされています。1年次からの全期間の成績が対象になるので、高1から基本的な勉学を充実させ、そのうえで+αの取り組みをおこなうことが必要です。
なお、選考に合格した場合は必ず文学部に入学することを確約する必要があります。出願書類などでも「慶大に入りたい理由」ではなく「慶大文学部に入りたい理由」が問われます。他学部・他大学との併願を考えている場合は注意しましょう。
<2025年度入試の選考結果>
2025年度入試では、募集人員120名に対し、志願者は358名、最終合格者は127名、合格倍率は約2.82倍でした。
FIT入試
<募集学部>
法学部
<試験内容>
- A方式
第1次選考:提出書類を総合的に精査する選考
第2次選考:論述試験(教員による模擬講義含む)、口頭試問 - B方式(成績要件あり)
第1次選考:提出書類を総合的に精査する選考
第2次選考:総合考査(資料読解および小論文)、面接試験(個人)
<入試の特徴>
偏差値にとらわれない人物本位の選抜方法として、慶大法学部で学びたい学生の想いと「こんな学生を教えたい」という教員の想いを「fit」させることをめざした入試形式です。
高校時代の自分自身の活動についてアピールする「自己推薦」を軸とするA方式に加え、学業成績や学校からの評価を軸とするB方式が実施されており、両方の方式に出願することが可能です。
また、B方式では「地域ブロック」制度が導入されており、全国を7ブロックに分けブロックごとに合格枠が割り振られるため、志願者が少ない地方は合格確率が相対的に高くなる可能性があります。
<受験のポイント>
- A方式
第1次選考では「自己推薦書」が重要です。高校での活動報告と自己PRから成り、自己PRは書式内での自由な表現となっています。高校での充実した活動に加え、それらを最大限に表現する力も求められます。
第2次選考では、論述試験と口頭試問が課され、法律学ないしは政治学の修得に必要な力が問われます。理解力、考察力、表現力等が試されることになります。 - B方式
第1次選考では、学校に志願者を推薦してもらう「評価書」に加え、「高校における指定の各教科および全体の学習成績の状況が4.0以上」という要件が課されます。学業成績を含め、学校での取り組みにおける貢献・積極性が求められます。
第2次選考では、面接試験に加え、資料読解と小論文から成る総合考査が課されます。総合考査はいずれも400字程度でまとめる必要があり、限られた文字数で端的かつ過不足なくまとめる記述力が求められます。
なお、選考に合格した場合は必ず法学部に入学することを確約する必要があります。出願書類などでも「慶大に入りたい理由」ではなく「慶大法学部に入りたい理由」が問われます。他学部・他大学との併願を考えている場合は注意しましょう。
<2025年度入試の選考結果>
2025年度入試では、法律学科・政治学科の両学科合わせて881名が出願し、第1次合格者が282名、最終合格者が222名でした。合格倍率は、成績要件があるB方式の出願者数自体が少ないこともあり、A方式が5~6倍、B方式が2~3倍程度になっています。
特にA方式は第1次選考で一気に人数が絞られるため、第1次選考での自己推薦の内容が合格の大きなカギになるでしょう。
分野志向型入試
<募集学部>
理工学部
<試験内容>
第1次選考:提出書類による選考
第2次選考:論理的な思考を問う総合審査(化学科は実施しません)
第3次選考:面接試験
<入試の特徴>
慶大理工学部の分野志向型入試は、科学技術系コンテストや課外活動などにおける実績が出願要件となります。例えば、数学や物理・化学オリンピックへの出場・入賞、課外活動では全国大会での入賞などが該当します。
世界的・全国的なレベルでの大会に出場したうえで、高い評価を得る必要があるためハードルはかなり高くなっています。したがって、この入試のために頑張るというよりは、既に出場実績がある人がこの入試の利用を検討する…というのが現実的なところでしょう。
<受験のポイント>
出願書類では、慶大理工学部の志望理由や入学後の展望について述べる「志望理由書」が重要です。これまでの実績に触れつつ、入学後にどんなことをやりたいかを明確に述べる必要があります。
なお、志望理由書の文字数は、例年2,000字以内となっています。分量は多めですが「自筆」という制限があり、すべて手書きで記入する必要があります。普段パソコン・スマホなどの入力が主になっている場合には、読みやすい文字を書く練習もしておきましょう。
AO入試(総合政策学部・環境情報学部)
<募集学部>
総合政策学部、環境情報学部
<試験内容>
第1次選考:提出書類による選考
第2次選考:面接試験(個人)
<入試の特徴>
SFC(湘南藤沢キャンパス)の2つの学部で実施されている入試で、7月実施の「春AO」と10月実施の「夏秋AO」があります。両学部では「あなたは何を学びたいのか」という問題意識や学習意欲を重視しており、AO入試の内容もそれに即したものとなっています。
※グローバル選考として「冬AO」もありますが、募集要項から出願書類まですべて英語となっており、海外の高校に通う高校生が主な対象となっています。
<受験のポイント>
出願書類では、高校での「活動報告」は200字以内、「志望理由・入学後の学習計画・自己アピール」は2,000字以内の文章と自由記述でまとめる必要があります。文字数が少ない場合は過不足なく簡潔に、文字数が多い場合は全体構成がわかりやすいようにすることが重要で、記述力・表現力が求められます。
第2次選考の面接試験では使用する言語として英語と日本語を選ぶことができます。英語のリスニングおよびスピーキングに自信がある場合には、英語でのやり取りで自分自身をアピールすることができるので、英語4技能対策を進めることも合格への道です。
AO入試(看護医療学部)
<募集学部>
看護医療学部
<試験内容>
第1次選考:提出書類による選考
第2次選考:面接
<入試の特徴>
看護医療学部のアドミッション・ポリシーでは、コミュニケーション、異文化理解、課題解決などが重視されています。それらの資質・能力を、自己推薦を軸とする書類選考と面接試験によりはかる入試です。
高校時代の自分自身の活動についてアピールする「自己推薦」を軸とするA方式に加え、高校での学業成績を出願要件とするB方式が実施されています。
<受験のポイント>
A方式では、高校時代の特筆すべき活動をアピールする「活動報告書」が重要です。看護・医療・保健・福祉に関連する経験に加え、ボランティア活動や高校での探究活動なども取り上げることができます。分量は1,200字以内となっており、高校時代の活動を大学以降にどのように活かせるかを端的に述べる必要があります。
B方式では「高校における全体の学習成績の状況が4.5以上」という高いハードルが課されます。そのぶん出願書類では高校での取り組みよりも、大学以降で学びたい内容や将来展望などが重視されます。学部で学べる内容を把握し、自分自身がやりたいことと照らし合わせて記述するようにしましょう。
※その他の選抜制度、より詳しい試験内容は、慶應義塾公式サイト「入試制度」のページでご確認ください。
「総合型選抜」のために高校生がやるべきこと
ここまで慶應義塾大学の入試制度の情報を整理してきました。大学・学部の特色はありますが、総合型選抜試験の対策として、共通して大切なことも見えてきました。
最後に、高校生のみなさんが今なにをすべきかをまとめておきましょう。
- 高校での日々の勉強にしっかりと取り組む。
総合型選抜では、「高校での全体の評定平均値」を出願条件とするものも多く、日々の勉強にしっかりと取り組み、学校で好成績をとることは大前提となっています。高校での履修科目は入試で使わない科目も含めてバランスよく学習を進めておきましょう。 - 記述力を高める。
多くの総合型選抜では、レポートや論文試験が課されます。限られた文字数・限られた時間で、自分の経験や考えが伝わる文章を書くためには、高校の早い段階から記述対策を積んでおくことが必要です。学校の提出課題やZ会の添削指導などを活用して記述力を高めておくことは、一般選抜にも大いに役立ちます。 - 興味のある事柄について自分なりの意見を持ち、行動する。
授業や日常生活で興味をもった事柄については、積極的に探究活動に取り組んでみましょう。文献やインターネットで情報を集めたうえで、「こうしたらよりよくなる」や「自分ならこうする」など自分なりの意見をもつことで、思考力が身につきます。そして、考えたことを実際の行動に移すことができれば、入試でのアピール材料にもなりますし、その後の人生においても貴重な経験を積むことができるはずです。
これらの基本的対策は、学習習慣や学習姿勢の面において、総合型選抜だけでなく、一般入試に対しても有効です。
総合型選抜は各大学・各学部で特色のあるものが設定されます。基本的な対策に加え、オープンキャンパスに参加する、興味のある学問分野を調べるなどの進路活動も、早い時期から取り組むとよいでしょう。