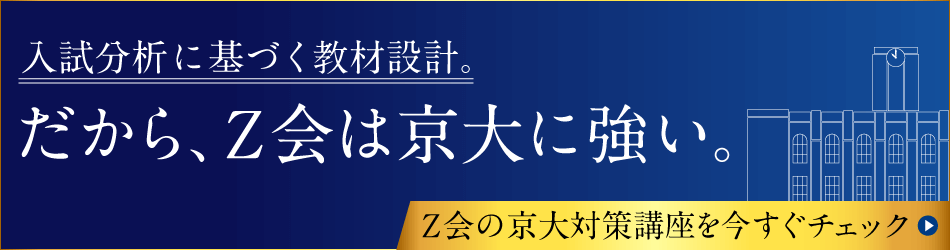Z会の大学受験担当者が、2022年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化(時間:文系120分)
2021年度と比較して全体の分量・難易度に大きな変化はなく、京大入試として標準的な難度の出題であった。
2022年度入試の特記事項
- 例年通り、現代文・現代文・古文の三題の出題。(一)の現代文のみ文理共通の文章からの出題。(理系は一問設問数が少ない)
- 2017~2021年度同様、(一)での漢字書き取り問題の出題はなかった。
- (二)は2020・2021年度と異なり旧仮名遣いの文章からの出題ではなかったが、昭和の小説家による随筆からの出題だった。
- (三)は近世の歌論からの出題。京大頻出ジャンルであり、正確に論理展開を追い逐語訳する力が求められた。
合否の分かれ目はここだ!
(三)の古文は江戸時代の歌論書からの出題。歌論は京大頻出のテーマであり、筆者は歌合や古歌を直すことについて非難している。指示語の指示内容をきちんと押さえ、一文一文丁寧に読解していくことがポイント。
本文の内容はとらえやすく、設問の難易度もそこまで高くないので十分取り組める出題だったと思われる。そのため古文では確実に点を確保する必要がある。そのうえで第一問・第二問でどこまで点を伸ばせるかで差がつく。
隙のない京大対策ができる!
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
(一):現代文 出典:岡本太郎『日本の伝統』
著名な芸術家による、伝統主義・権威主義への批判と新たな伝統創造への気概を主張する文章からの出題。主題は読み取りやすいが、解答のまとめ方に工夫を要する設問が多く、記述力が試される。
- 問一は傍線部周辺から解答要素を押さえればよく、比較的取り組みやすい設問。ここでの失点はできる限り避けたい。
- 問二・問三は、随筆らしい表現を問題文の主題を踏まえて説明する必要がある設問。解答の中心要素はつかみやすいが、行数に見合う形でわかりやすくまとめる記述力が必要となる。
- 問五は、問題文全体の主題を踏まえ「ほんとうの芸術家」について説明する全体のまとめとなる出題。傍線部自体の表現の説明と、問題文全体の内容を踏まえての説明が要求される難度の高い設問であった。
問題文中の表現の切り貼りでは解答を作成できず、自分なりに表現をふくらませて説明する必要がある京大らしい出題であった。取り組みやすい設問を見極めて確実に得点し、問題文全体の主題を踏まえて解答をまとめ上げる記述力が要求される出題で、京大型の演習経験を積んでいたかどうかで差がついただろう。
(二):現代文 出典:高橋和巳「〈邪読〉について」
作家・高橋和巳の随筆からの出題。筆者は自らの読書の在り方を「邪読」と呼んでいるが、決してそれを否定的に考えているわけではない。「こうあるべき」的な読書の在り方や、いわゆる即効性のある読書と対比しつつ、筆者の「邪読」にはどのような効能があるのかを読み取っていく。設問はいずれも文中に解答の根拠が求められるもので、解答の方向性自体に戸惑う、というものはない。
- 問一は平易。傍線部の前後をまとめればよい。
- 問二は「自分の読書の仕方」と友人のそれを対比することで、「後ろめたさ」が生じる理由を説明する。
- 問三は「これ」=筆者の読書の仕方を、直後に説明されている「べき論」的な読書の在り方と対比することで、「邪読」と表現した理由を説明する。
- 問四は「その〈忘却〉」の内容を説明し、続く二つの段落で説明される「忘却」の効能を示すことで、「意味がある」理由を説明する。
- 問五は全体のまとめとも言える設問である。設問に「筆者にとっての」とあることにも留意し、一般的な「読書の本質」ではなく、筆者にとっての「読書の本質」=「邪読」に絞ってまとめる。
(三):古文 出典:田安宗武『国歌八論余言』
江戸時代の歌論書からの出題。歌論は京大頻出のテーマである。指示語の指示内容に注意しながら一文ずつ丁寧に読み取っていけば、論旨をつかむことは難しくなかっただろう。
- 問一は、歌合せについて「いと浅ましきわざなり」という理由を説明する設問。傍線部直前の内容をまとめればよいので、ここは確実に得点したい。
- 問二は、指示語の指示内容を本文から適切に読み取り、丁寧に訳出することがポイント。(2)がやや難しく、「それ」が指す内容や「己にたよるにしもあらぬ人」の内容を理解できたかどうかで差が開く。
- 問三は、傍線部の内容説明。筆者の主張を「田子の浦ゆ……」の歌の例と合わせてきちんと読み取れたかが問われる。「ふりける」と「ふりつつ」の違いから説明すればよい。
- 問四は、「その人」が「古き歌」の詠み手を指すことを押さえて逐語訳していく必要がある。本文全体の内容が理解できていれば解きやすい設問なので、ここも確実に得点したい。
攻略のためのアドバイス
京大文系国語を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 基本的な語彙力
文学的・抽象的な表現を含む文章からの出題が多い京大国語では、読解力・記述力ともに高いレベルが要求される。その水準に達するためには、基本語彙の意味を正確に把握し、記述する際にも適切な語を選ぶことができる語彙の運用力が必要不可欠。Z会の書籍『現代文 キーワード読解』や『速読古文単語』などで、語彙力の基礎を固めよう。
●要求2● 幅広いジャンルに対応できる読解力
京大国語では、評論・随筆・小説など、普段受験生が読み慣れないであろうさまざまなジャンルの文章から出題されるため、京大で出題されそうな文章の読解経験の量がものをいう。問題文中に直接的に表現されていなくとも、文中の表現のニュアンスを汲み取り、筆者の主張や心情を正確に読み取る力が必要である。
要求3●大意をまとめなおす記述力
京大国語の設問は、すべてが記述式問題であり、求められる記述の分量もかなり多い。解答に必要な要素を見極める力と、必要な要素を正確に伝わる形で解答にまとめなおす力が求められる。問題文中の記述の寄せ集めではなく、適宜自分の言葉で言い換えたりふくらませたりすることができる確かな記述力が必要である。
対策の進め方
まずは、土台となる●要求1・2●を満たすことを目指そう。Z会では、さまざまなジャンルの問題文を出題するので、読解経験を積むことができる。語彙・文法事項といった知識事項の抜け漏れをつぶしていくと同時に、記述演習にも取り組むことで、第三者に伝わる解答の作成法を身につけよう。
その後は、さらに●要求2・3●を磨いていこう。Z会の通信教育では、受験生の9月からより実戦的な京大対応のオリジナル問題を出題する。第三者の客観的な視点からの添削指導を受けて、自分の解答に足りない要素やまとめ方のコツを把握し、解答の質を高めていこう。読解量・記述量ともに負担が重い京大国語に対応するために、制限時間内でうまく解答をまとめることを意識して問題演習を行おう。
入試直前期には、過去問演習に加えて予想問題にも取り組むことが大切だ。本番前の最終調整として、より本番に近い形での演習をするとよい。
Z会で京大対策をしよう
現代文は二題とも随筆からの出題で、受験生に文学的素養を求める京大らしい出題でした。単に問題文中の表現を切り貼りするだけでは対応できず、筆者の考え・問題文の主題を読み取り自分なりの表現でまとめ直す必要があります。京大に照準を合わせた演習を積んでいたかどうかで差がつく出題でした。
古文は近世の歌論からの出題。和歌について論じる文章は京大頻出です。文章展開を正確に押さえ、丁寧に逐語訳する演習を積んでいた受験生であれば、実力を発揮できたでしょう。
受験生がなかなか読み慣れないような文章から出題され、さらに広い解答欄に自分なりの言葉でわかりやすく解答をまとめていくことが要求される京大国語では、さまざまな文章の読解経験を積み、作成した解答を第三者に見てもらうことが非常に重要です。
Z会では、長年の入試分析をもとに、本科「京大コース」、専科「京大即応演習」、特講「過去問添削」など、京大合格までの道筋を支える講座を多数用意しています。良質な問題と添削指導を通じて盤石の実力を養成し、京大合格をつかみ取りましよう!