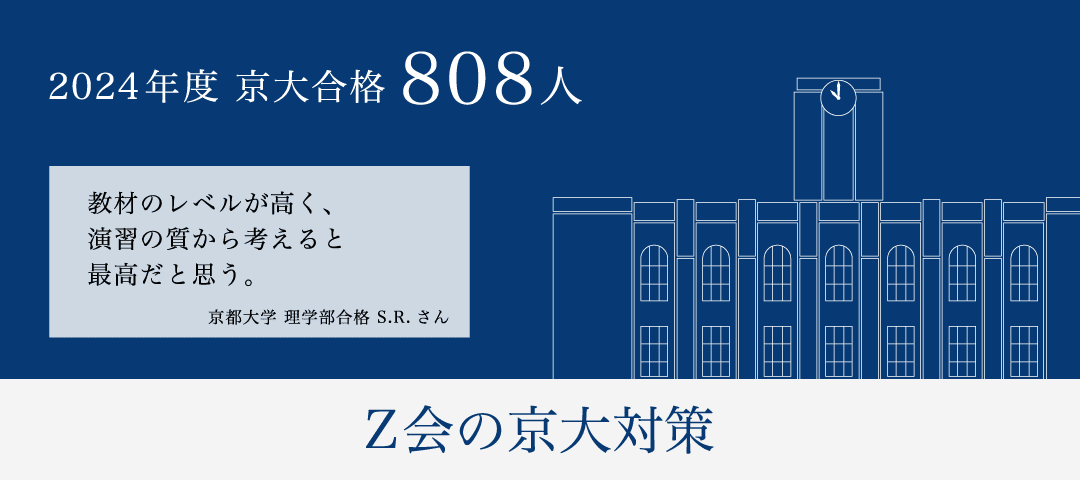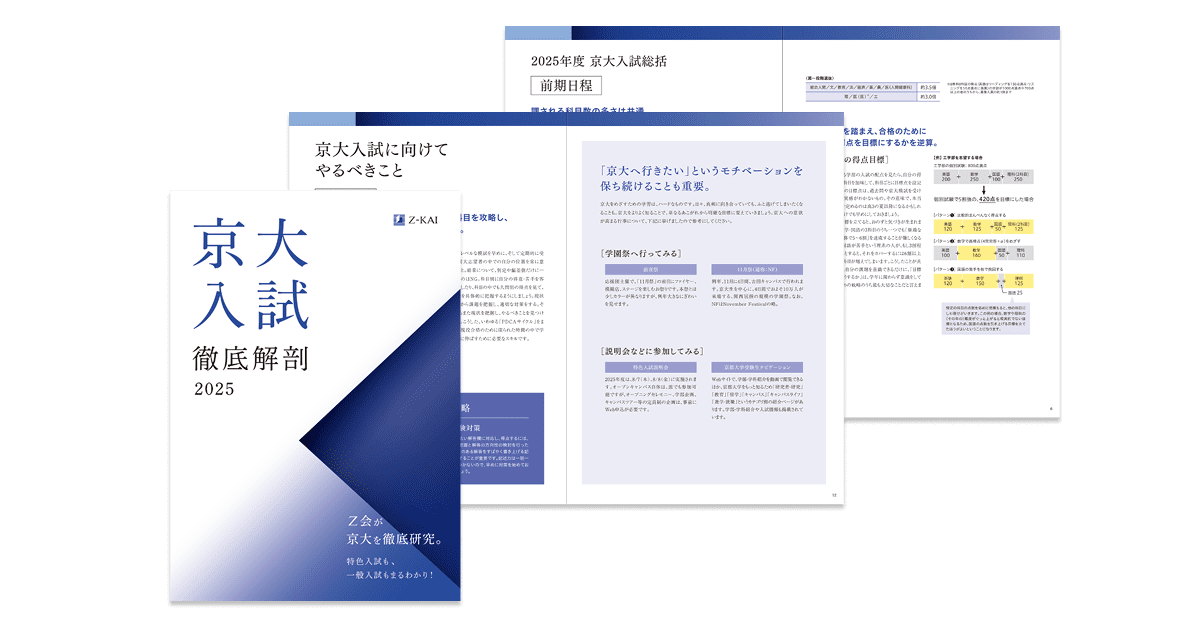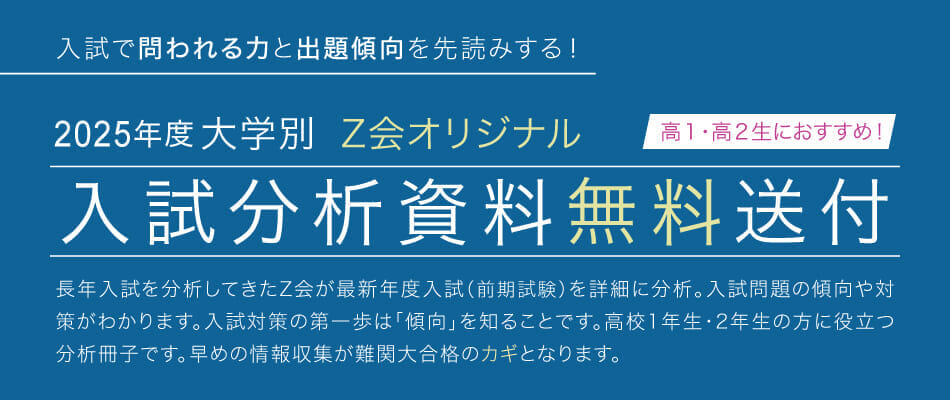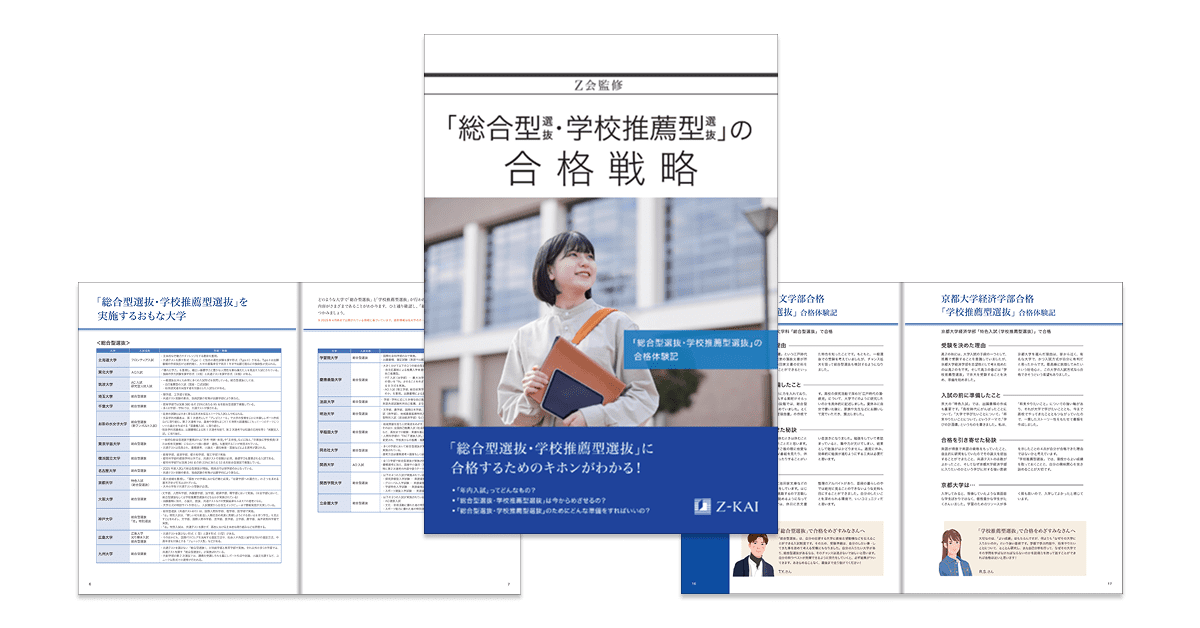Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会国語担当者からのメッセージ
京大理系国語は、さまざまな時代・ジャンルの文章が出題され、広い解答欄に自分なりの言葉でわかりやすく解答をまとめることが要求されます。合格水準に達するためには単に問題文中の表現を切り貼りするだけでは対応できず、筆者の考え・問題文の主題を読み取って自分なりの表現でまとめ直さなければなりません。このように理系に対しても高い国語の読解力・記述力を要求するのが京大の大きな特徴であり、合格のためには京大国語についても十分な対策が必須です。
Z会の「京大講座」では、京大入試本番で要求されるこうした力を養うために、京大国語に対応したジャンル・出題形式で問題演習の経験を数多く積み、作成した答案について、プロの添削者の目線からフィードバックを受けることで、盤石の実力を養成できます。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化(時間:理系90分)
- 分量は2024年度からやや減少
- 難易度は2024年度からやや易化
2025年度入試の特記事項
- すべて標準的な難度の大問で構成され、全体の負担感は2024年度よりも下がった。特に古文の難度が下がり、全体としてやや易化したと言えるだろう。
- 第一問に時間をかけすぎないよう、トータルの時間配分に留意が必要である。
- 第二問は感性的な随筆が出題され、理詰めで読み解けない文章を読まねばならない負担感があった。文学的文章の出題、広い解答欄は京大入試の特徴なので、京大に対応した演習を積むことが求められる。
- 第三問の古文は2024年度と同じ本居宣長の文章からの出題。
合否の分かれ目はここだ!
どの大問も、大きな解答欄にどこまで解答要素を盛り込むかといった京大特有の難しさはあるが、慌てる必要はない。落ち着いて得点できる所を確実に押さえ、トータルで合格点を確保するという意識を持つことが重要である。
第一問は標準的な出題だったので、文学的要素が強く、書かれたことの背後にある思いを読み解くことを求める第二問で確実に得点できたかどうかで差がつくだろう。また、第三問の問二は、設問要求を確実に満たせるように、解答要素を選定して記述する力で差がついたと思われる。出題傾向は一貫しているため、京大に照準をあわせて読解・記述演習をしっかり積んできた受験生であれば、実力を発揮できただろう。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
〔一〕:現代文(随筆) 出典:中井久夫「現代社会に生きること」 [標準]
「都市化」を題材として、人間と自然とのありかたについて論じた文章からの出題。どちらかといえば評論に近く、読みやすい文章だが、言いたいことをあえて直言せず読者の理解に委ねる表現も目立つので、いざ設問に答えようとすると難しく感じたかもしれない。
- 問一は、傍線部までで書かれたことのうち、「かわいらしい」と評しうる内容はどういうものかを考えてまとめる。
- 問二は「このように」の指示内容をもとに、「自然を『疎外』し」「自然から『疎外』された」の意味内容が明らかになるようにまとめる。
- 問三は、「正常さ」「大地の感覚」を鍵として傍線部の前の内容をまとめる。問一~問三はいずれも比較的解答要素が見つけやすく、取り組みやすい設問なので、時間をかけ過ぎずに得点を稼ぎたい。
- 問四は、どういうことに「同感」しているのかを的確に読み取り、筆者自身の考えはどういうものかをまとめる。設問要求を満たすように、わかりやすくまとめることが大切。
〔二〕:現代文(随筆) 出典:佐野洋子 『友だちは無駄である』 [標準]
出典は、絵本作家・エッセイスト佐野洋子の随筆。理路整然と理屈を積み上げて解説するタイプの文章ではなく、筆者の個人的な体験に基づく内面の思いを綴った感性的な文章なので、そうした文章を苦手とする人にとっては難しかったであろう。どの設問も、解答要素をどこまで盛り込むかの見極めが重要であった。
- 問一は、この一瞬に「了解」した内容を問うもの。傍線部直後の段落の内容を中心に、わかりやすくなるよう言葉を補ってまとめる。
- 問二は、「立派ではない」友だちとはどういう存在であるかを、ここまでの内容をもとに端的にまとめることが鍵となる。
- 問三は、本文全体の主眼にあたる箇所。友だちの見舞いを通じて筆者が得た気付きを、最後の五段落を中心に、本文全体にも目配りしてまとめる。「感謝したい気持ちになった」理由としてふさわしいものになるように、まとめ方にも注意が必要。
〔三〕:古文(随筆) 出典:本居宣長 『玉勝間』 [標準]
江戸時代(近世)の随筆からの出題。平易な用語・文体で読み取りやすく、設問も標準的なものだった。わずかなミスが合否を分ける可能性があるので、丁寧に解答したい。
- 問一は現代語訳。「心すめれば」「をさをさ……なき」の解釈がポイント。
- 問二は説明問題。「かへすがへす」とあるので、前にも述べた疑問を再び提示しているのだ、ととらえ、2行目の「又いかにぞや」にも注目してまとめる。「てにをはのととのへ」と対比せよ、という設問条件を満たせるよう、解答に必要な要素を整理しよう。
- 問三は現代語訳。「いれずては」「かたかんべき」の解釈がポイント。
2025年度の古文は標準的なものだったが、京大古文では和歌を含む難しい文章も出題される。どのような文章が出題されても対応できるよう、過去問を用いた演習でしっかりと対策をしておくことが重要だ。
攻略のためのアドバイス
京大理系国語を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 基本的な語彙力
文学的・抽象的な表現を含む文章からの出題が多い京大国語では、読解力・記述力ともに高いレベルが要求される。その水準に達するためには、基本語彙の意味を正確に把握し、記述する際にも適切な語を選ぶことができる語彙の運用力が必要不可欠。Z会の書籍『現代文 キーワード読解』、『速読古文単語』などを活用して、語彙力の基礎を固めよう。
◎『現代文 キーワード読解』の詳細はこちら
◎『速読古文単語』の詳細はこちら
●要求2● 幅広いジャンルに対応できる読解力
京大国語では、普段受験生が読み慣れないであろうさまざまなジャンルの文章から出題されるため、京大で出題されそうな文章の読解経験の量がものをいう。問題文中に直接的に表現されていなくとも、文中の表現のニュアンスを汲み取り、筆者の主張や心情を正確に読み取る力が必要である。
●要求3● 大意をまとめなおす記述力
京大国語の設問は、すべてが記述式問題であり、求められる記述の分量もかなり多い。解答に必要な要素を見極める力と、必要な要素を正確に伝わる形で解答にまとめなおす力が求められる。問題文中の記述の寄せ集めではなく、適宜自分の言葉で言い換えたりふくらませたりすることができる確かな記述力が必要である。
対策の進め方
読解力の練成
まずは、土台となる要求①②を満たすことを目指そう。Z会の通信教育の「京大講座」では、毎月さまざまなジャンルの問題文を通じて、京大入試に対応した読解・演習の経験を積むことができる。語彙・文法事項といった知識事項の抜け漏れをつぶしていくと同時に、記述演習にも取り組むことで、第三者に伝わる解答の作成法を身につけよう。
記述解答のブラッシュアップ
その後は、さらに要求②③を磨いていこう。9月以降のZ会「京大講座」では京大入試本番と同様、大問3題セットのオリジナル問題を出題する。第三者の客観的な視点からの添削指導を受けて、自分の解答に足りない要素やまとめ方のコツを把握し、解答の質を高めていこう。
京大レベルの演習
入試直前期には、本番前の最終調整として過去問や予想問題を活用しながら、より本番に近い形での演習をするとよい。読解量・記述量ともに負担が重い京大国語に対応するために、制限時間内でうまく解答をまとめることを意識して問題演習を行おう。
Z会でできる京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!