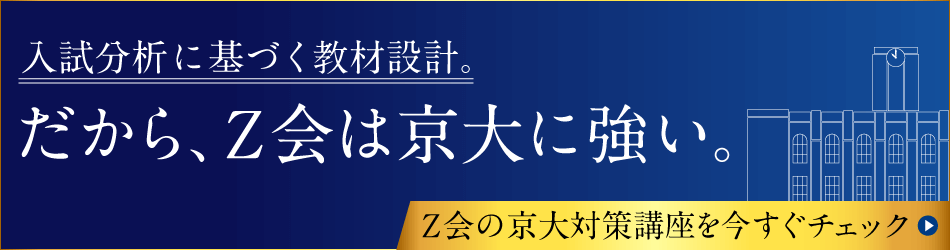Z会の大学受験担当者が、2023年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化
- 難易度は2022年度並み
- 分量は2022年度並み
2023年度入試の特記事項
- 第1問は中問に分かれて出題された。
- 「数学III」の要素を含む問題が3問と、多く出題された。
- 第1、2、4、5問は誘導となる小問がない単問構成であった。
- 第2問は文系と共通。また、文系で似た題材を用いた問題がいくつか出題されている。
- 命題の真偽を、判定したうえで証明させる形式の問題が出題された。
合否の分かれ目はここだ!
- 得点しやすい問題とそうでない問題で差が大きくついていた。そのため、問題の難易を見きわめてきちんと得点することが非常に重要である。
- 第1問 問1、第2問、第3問、第6問(1)は基本事項の確認といってよい問題。確実に得点しておきたい。
- 次に手を付けるのは第1問 問2、第4問がおすすめ。ともに、気づきを要する箇所があるが、確実に攻略できると合格がぐっと近づく。
- ここまでを確実に得点できるとよいが、もし第4問の解き筋が思いつかなかったら第5問へ。第5問は積分法の分野では頻繁に見かける題材であるため、解法のあらすじは読み取れるだろう。方針を書いて部分点をねらうところまでは進めておきたい。
- 第6問(2)は非常に難解。題材を同じくする類題の経験がないと太刀打ちできないだろう。これ以外で確実に点数を重ねるのがよい。
隙のない京大対策ができる!
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問
- 問1:積分の計算問題。部分積分法を用いて計算すればよい。基本的な計算手法を確認するもので、確実に得点しておきたい。
- 問2:整式の除法の問題。「xの2023乗」という、年度に絡めての出題となっている。(割る式)=0が実数解をもたないので、因数定理を用いると手間が多くなる。x5-1で割った余りを考える、x2023-1を因数分解する、などの工夫があるとよいだろう。
第2問
空間内の点について考察する問題。
- 1次独立な3ベクトルを用いて各ベクトルを表していけばよく、方針に迷うところは少ないだろう。京大志望者ならば落としたくない問題である。
第3問
さいころの目に関する確率の問題。
- 条件をみたす目の出方のルールが見抜ければ、余事象の考え方を用いてすぐに解決する。これも落とせない問題だった。
第4問
関数の最大値・最小値を求める問題。
- 微分法を用いて調べていくのはその通りなのだが、与えられた関数をそのまま微分するのはうまくない。式の形の特徴を見抜いて工夫が必要。
- 自然対数の底の大まかな値が与えられていることの意図も読み取りたい。
第5問
積分法を用いて体積を求める問題。
- 線分の通過領域の問題であるが、P、Qの動きをすべて同時に把握しようとすると破綻する。まずはPとQの位置を適切に“固定”し、その状態での動きを把握したあとで全体に拡張することでうまく求められる。
- 積分法の問題としてはよく見る型ではあるものの、きちんと論証および計算をやり遂げるのは大変である。
第6問
三角関数と整数の融合問題。
- (1)は易問といってよいだろう。基本事項の確認レベルなので、必ず押さえておきたい。
- 重要なのはこれが(2)につながっていると気づけるかどうかで、cos(nθ)とcosθの関係式に思い至れるかが重要。
- チェビシェフの多項式とよばれる有名な題材を背景にしており、この題材の問題に取り組んだことがあると有利だった。
攻略のためのアドバイス
京大理系数学を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 手早く正確に計算をする力
京大では煩雑な計算を行う出題は多くないが、着想、論理展開に時間を奪われる出題が多い。それだけに、方針が立ったあとの計算は手早く正確に行うことが重要で、計算時間を短縮できれば、ほかの問題を解く時間に使うことができる。
計算力は日々の計算練習で身につく。日々の問題演習において、最後まで計算し、確認する習慣をつけることが大切である。
●要求2● 問題の構造を捉える力
京大理系数学において頻出の分野として、図形問題がある。図形問題には、初等幾何、ベクトル、座標幾何などいろいろな解法があり、どの解法を取ればよいのかをまず考えてから解く必要があるものが多い。どの解法を使うのか、見方を変えてほかの問題に帰着させることができないかなどを発想できる力をつけることが、京大理系数学攻略の第2のポイントである。
発想力は、京大の過去問など発想力を鍛えられる問題を解き、考える訓練をすることで身につけられる。
●要求3● 採点者に自分の考えを伝える力
京大では、 証明問題だけでなく、 求値問題においても、 結論に至る過程を丁寧に説明する力が要求されるものが目立つ。記述式の試験においては、自分の頭の中では分かっていてもそれを採点者に伝えることができなければ、点数に結びつかない。論理的に無理なく、より簡潔に答案を書くための論証力をつけることが、京大理系数学攻略の第3のポイントである。
論証力は自分一人で勉強を進めても身につきにくい。 この力は、 Z会の通信教育で別の人に採点・添削をしてもらい、その結果を復習することで身につけられる。
対策の進め方
まずは、各分野の完成からである。京大入試では様々な考え方が必要とされるので、苦手分野があれば、遅くとも高3の夏休みまでには克服したい。Z会の通信教育では、入試に必要な考え方を幅広い分野の演習を通して身につけることができるようになっている。
高3の秋以降は、それまでに身につけた考え方を、実戦的な問題演習を通して使いこなせるようにしていこう。受験生用のZ会の講座では、微積分、図形、整数、確率といった京大頻出分野の問題を中心に、論証力も養成されるように学習を進めていく。
共通テストが終わったあとは、これまでの学習の総まとめである。京大入試に即応したZ会の問題で、入試に使える計算力・発想力・論証力を完成させよう。
Z会で京大対策をしよう
京大数学では数式処理力、発想力、観察力、論述力がバランスよく問われる出題構成が多い。今年度のように、全体的に易化した場合は高得点が要求されるので、予定していた戦略を、当日臨機応変に変えるという柔軟性も重要になります。また、受験生が苦手とする見方を敢えてつく出題も多く、これは「数学をきちんと勉強してきたか?」を見るのが狙いです。解法の暗記や、身についてないテクニックを用いるなどのうわべだけの学習に対する警鐘ともいえます。
Z会の京大講座は、京大数学で問われる頻出テーマや分野を網羅するだけでなく、添削指導や豊富な解説で真の理解と応用力を育むことができます。1問1問を味わい尽くすように1年間取り組むことで、1年後には想像以上の学力が身につきます。