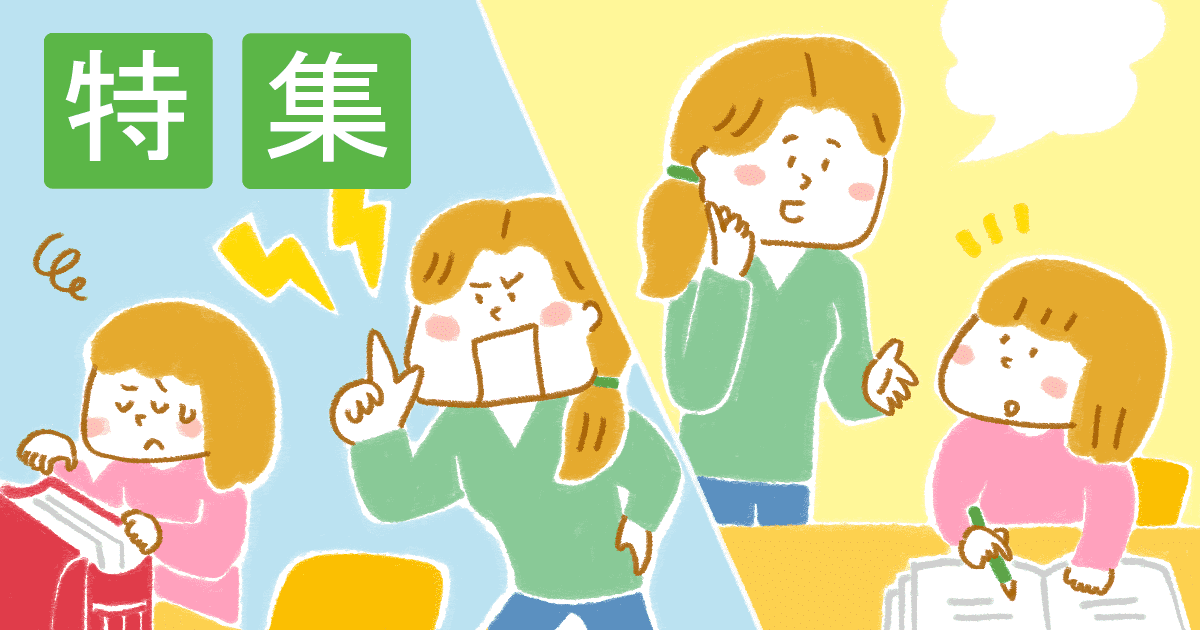怒らない子育てをしよう。そう思っていても、ついガミガミ、くどくど言ってしまい、あとで落ち込む……。多くの方が思い当たるのではないでしょうか。どうして親は子どもを怒ってしまうのでしょう。どうしたら怒らずに子どもを勇気づけ、勉強に遊びに自分から取り組む力をはぐくむことができるのでしょうか。近年、数々の教育メソッドに応用されている「アドラー心理学」の第一人者、向後千春先生に自立を促す実践的な子育て法を教えていただきました。
(取材・文 松田慶子)
※本記事は、2020年4月23日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
親と子どもは対等。その理解が脱ガミガミへの一歩
――笑顔で子育てをしたいと思っているけれど、“宿題はやったの?”“早くしなさい”など、気づくとガミガミ言っている――。そんな悩みをあちこちで耳にします。そもそも、どうして親は口うるさくなってしまうのでしょうか。
アドラー心理学的に言うと、親が子どもを対等に見ていないから。つまり「ペアレントトレーニング」ができていないから、ということになります。
――アドラー心理学とは?
19世紀末から20世紀前半にオーストリアとアメリカで活躍したアルフレッド・アドラーが打ち立てた心理学です。親と子、先生と生徒が対等な人間であるという考えを基本にして子どもを育てていくことが大事だとしています。そのアドラーの考えをベースに作られたのが、「ペアレントトレーニング」という親の教育プログラムで、アメリカでは広く用いられています。日本でも近年は子育ての悩み解決に役立つと、マスコミで数多く紹介されるようになっています。
――「早くしなさい」は、対等な言い方ではない?
「宿題はした?」と、宿題を思い出させることはいいのですが、「しなさい」は上からのもの言いですね。子どもはそれを命令だと受け止めてしまう。
――「早くやったほうがいいよ」とか、「〇〇ちゃんならすぐにできるよ、期待しているよ」では?
言葉を変えるのではなく、子どもは対等な人間だと考えることが大事なんです。
上から命令したり価値観を押しつけたりしてコントロールしようとすると、子どもは反発し、かえって親の言うことを聞かなくなってしまいます。
――でも宿題を早く終わらせたほうがいいのは事実です。教えることは必要では?
誰の「課題」なのか、分けて考えることが大切です。宿題をしないであとで困るのは子ども。つまりこれは子どもの課題です。子どもが早く宿題を終えないと落ち着かないというのは親の課題で、子どもに背負わせるのはまちがい。そして、「しなさい」は子どもの課題に対する「介入」です。

介入は2つの点で問題があります。
1つは、子どもが自分の行為の結末を見届けられないことです。宿題をしないと先生にしかられるという結末を見ることで「次は期限内に提出しよう」と学ぶわけです。自分の行為がどういう結果につながるのか、結末までを体験することで社会性が身に着く。その機会が失われます。
もう1つは、親を信頼しなくなることです。自分で解決すべき課題なのに親が介入してくると、「自分は親から信頼されていない」と感じます。
人間には、いいことをされたらいいことを、意地悪をされたら意地悪をし返すという、「互恵性」「返応性」が生来備わっています。信頼されていないと感じた子は、自分も親を信頼しなくなる。その結果、ますます言うことを聞かなくなる、またはいい子のふりをして親を欺くようになってしまいます。
親子の歩み寄りには家族会議がおすすめ
――宿題のように、行為の結果をすぐに体験できるものはいいかもしれませんが、勉強とかピアノの練習とか、結果が出るまでに長い時間がかかることがらに関しては、どうしたらいいでしょうか。
気になるところですよね。
アドラー心理学ではそういう問題の解決策として、親子で協力関係を築くことをすすめています。
――協力関係を築くとは、どうやって?
親子で目標を一致させることです。たとえば親は子に最難関の学校に入ってほしいと思い、子どもは勉強せずに入れる学校に進みたいと思っている場合。まず、子どもを説き伏せようとするのは間違いです。説得されると子どもは面倒だから従う。その結果親が希望する学校に入っても、大しておもしろくないとわかった途端に爆発します。暴力的になる子もいる。
そうではなく、双方が少しずつ歩み寄るようにします。たとえば、親は最難関の学校でなくてもよしとする、子どももこの程度まではがんばりたいなどといったように、お互いが納得できる点を探り、両者の目標を一致させることでようやく協力関係ができる。
これが確立したらアドバイスができます。「アドバイスさせてもらっていいかな?」とお願いしたうえで、「こんな勉強方法があるよ」「こういう学校があなたに合っていると思うよ」と提案すればいい。協力関係ができていなければ、アドバイスをしても子どもの耳には届きません。
――では、歩み寄るにはどうしたら?
話し合うことが大事です。私は家族会議をすすめています。
週1回、夕食の後にでも家族そろって30分程度の会議の時間をとり、「困ったことは」などと声をかけ、自由に議題を出してもらう。最初は「来年の家族旅行はどこに行こうか」など、楽しいことから始めるのもいいですね。習慣化すると「お父さんのお風呂の鼻歌がうるさい」など、議題がどんどん出るようになります。そうなったら、「あなたが勉強をしないと、私が心配なんです」と議題にする。「夕食前の時間なら勉強を見てあげられるよ」などと提案してもいいですね。
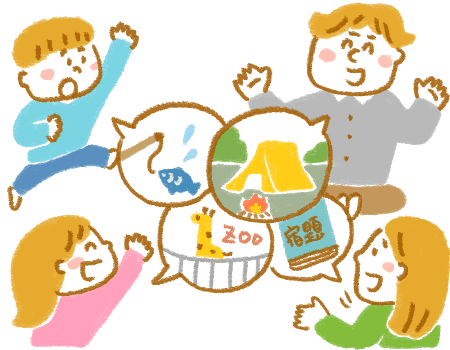
世界をどう解釈するか、選択肢を示すことで主体性をはぐくむ
――家族会議は、低学年でもできるものでしょうか。
もちろんです。むしろ低学年からそういう時間を持ちたいもの。
これも理由が2つあります。1つは習慣化しやすいから。もう1つは、アドラー心理学では子どもの性格は10歳くらいまでに確定すると考えているから。その性格形成の大切な時期に大人が子どもとたくさん話をして、「世界をどう解釈するかは自分次第なんだ」と伝えてあげたいからです。
――どういうことでしょうか。
家族会議で、「宿題をしなくてしかられた」と子どもがこぼしたとします。そういうとき、たいてい子どもは「自分はダメだ」と考えている。これを放っておくのではなく、「先生はあなたのことを気にかけているのかもしれない。よく見てくれるいい先生とも考えられるよね」「あなたに期待しているという見方もあるね」と、いろいろな見方を示してあげる。すると子どもは、世の中はいろいろなとらえ方ができて、自分で自由に選んでいいのだと学ぶことができる。そして自分が勇気づけられる(※アドラー心理学では「自分には価値がある・困難を克服していこうと思える」こと)方向を自分で見つけられるようになります。これは、主体性や折れない心を育てることにつながる。話し合う時間は、その機会にもなるんです。
――高学年では、もう遅い?
高学年は性格傾向がかなり一貫してくるので、なかなか話を聞かなくなりますが、遅いことはありませんよ。
急に家族会議をしようとか、「アドバイスしてもいいですか?」などと言うと、気持ち悪がられるかもしれません(笑)。そのときは「アドラー心理学について読んで、こうしようと思ったの」と種明かしをすればいいと思いますよ。「じゃあ、聞いてやってもいい」となるかもしれません。
ほめ方にはコツがある。子どもの勇気につながる言葉を
――よく「ほめて育てよう」といいますが、アドラー心理学ではほめることはすすめないのでしょうか。
ほめることは悪いことではありませんが、注意が必要です。コントロールしようとしてはダメ。相手が勇気づけられる言葉なら、どんどんかけてあげるといい。
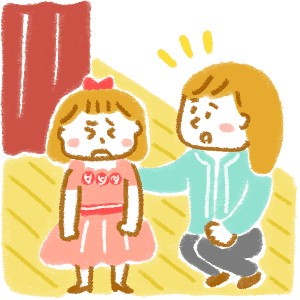
――具体的にどんな言葉ですか。
子どもの性格や状況、表情にもよるので、これだけ言えば大丈夫という魔法の言葉はない。ピアノの発表会で失敗した子に、「失敗もあったようだけど、上手だったよ」と言ったとき、「よかった。ずっと練習してきたかいがあった」と思ってもらえたらいいほめ言葉になりますが、失敗を指摘されたと思い泣き出す子もいるかもしれない。
今、目の前の子にはどの言葉がいいのか、親は必死で考えなくてはいけません。やったことがなければ難しいでしょうが、失敗して泣かれても、親の学びになります。繰り返すなかでうまくなりますよ。
――これまで、ほめてその気にさせるという接し方をしてきた人は多いと思いますが……。
実際のところ、子どもが低学年のうちはあまり言葉の裏を読まないので、「すごいね」「上手だね」で、コントロールできてしまうことも多いです。でも思春期を迎えると、「親はこういう意図で言っている」と、はっきり読み取るようになる。すると子どもは期待に添うことをやめる。真逆のことをするときもあります。
でもそれが当たり前なんですよ。親の期待に反抗することで子どもは自立していきます。反抗が見られたら自立の第一歩だと思い、コントロールしないように接し方を改めることが大切です。
人は観察から多くを学ぶ。親が挑戦を楽しもう
――子どもの社会的自立は教育の目標の1つだと言われます。アドラー心理学も、自立を目標にしているのでしょうか。
「自立」つまり自分で判断し行動できること、そして「調和」つまりほかの人とよい関係を築き協力し合えること、2つを目標にしています。
21世紀になり、計算や暗記力のような認知スキルより、こうした非認知スキルこそが社会で活躍していく上で大事だといわれるようになりましたが、アドラー派は100年前からそれを重要だと言ってきたのです。わが意を得たりという気持ちです(笑)。
――子どもを自立へ導くために、対等な立場で接すること、協力関係を築くこと以外に、親が何かできることはありますか。
「あなたにはいろいろな能力の芽がある。いろいろなことを試して、自分が生きていくための好きな道を見つけてね」と伝えることはできます。
子どもに人気のYouTuberだって、売れない時代にいろいろなことを勉強したはず。そんな例を出しつつ、「絵をかく、楽器を演奏する、歴史を勉強してみるなど、ひと通りやってみて、どれがおもしろいのか確認するといいね」と子どもに伝えれば、子どもも主体的になり、いろいろなことに挑戦するようになると思いますよ。
それには、親御さんが自分でも新しいことにチャレンジするといい。語学を習い始めるとか、テニスに挑戦するとか。新しいことを始める子どもの気持ちがわかって、意味のあるアドバイスができる。
それに、人は習うよりも観察するほうが、はるかに効果的に物ごとを習得します。親がおもしろいことをやっている姿から、子どもは多くを学ぶ。夢中になれるものを見つけ自立していきますよ。
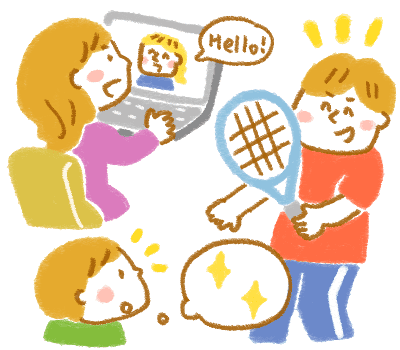
 向後千春(こうご・ちはる)
向後千春(こうご・ちはる)
1958年生まれ。早稲田大学人間科学学術院教授。博士(教育学)。専門は教育工学、教育心理学、アドラー心理学。1981年早稲田大学第一文学部卒業。日本タイムシエア株式会社、富山大学教育学部講師・助教授、早稲田大学人間科学部助教授等を経て、2012年より現職。『アドラー”実践”講義』(技術評論社)、『コミックでわかるアドラー心理学』(中経出版)、『200字の法則 伝わる文章を書く技術』(永岡書店)、『幸せな劣等感』(小学館新書)、『アドラー式「しない」子育て』(白泉社・吉田尚記氏との共著)他、著書多数。一般人、教育者、ビジネスパーソン等を対象にした講演やセミナーに登壇しアドラー心理学の実践法をわかりやすく説いている。