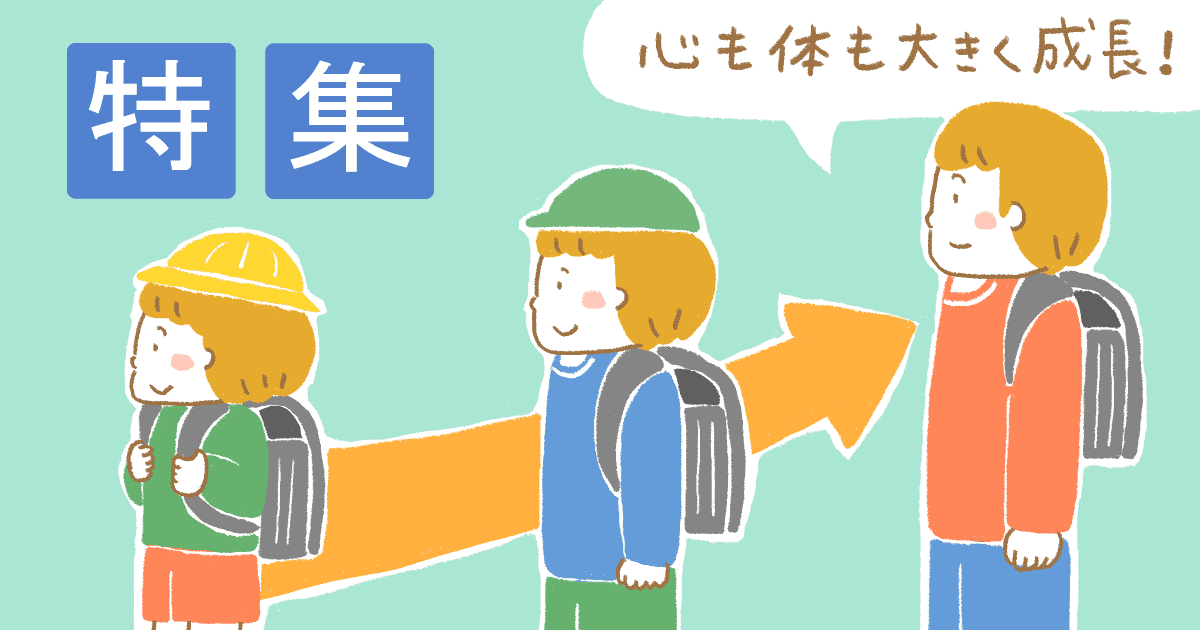大人びた6年生と幼い我が子を見比べて、「あと数年であんなふうになれるのかな」と心配になる。朗らかだった子がある時期から急に気難しくなって戸惑う――。子どもは小学校の6年間で大きく成長します。どう変化するのか見通しを持っておかないと、受け止め方に迷い、ときに親子関係がこじれてしまうこともあるようです。発達心理の専門家である渡辺弥生先生に、6年間の発達と親が心がけたい姿勢を教えてもらいました。高学年の保護者の皆さまもぜひご一読を。
(取材・文 松田慶子)
※本記事は、2021年1月28日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
時間や自己をとらえる力、横のつながりが増える小学生時代
――小学校の6年間というのは、子どもの発達においてどのような時期なのでしょうか。
小学校の6年間というのは、研究者の目から見ても、大きな変化が起きる興味深い時期です。
子どもは、いつかは独り立ち、自立をしないといけないですよね。それは決して1人で生きるということではなく、他者と協力しながらも自立した個人として生きていくということです。そのためには、自分の気持ちを相手に伝えたり、相手の気持ちを理解したり、感情をマネジメントしたりする力がまず必要です。
そういったいろいろな力を獲得していくのはもちろん幼児期から始まっていて、赤ちゃんのときのように感情のままに泣いたり怒ったりするのではなく、幼児なりに、我慢したり主張したりすることを覚えていきます。さらに小学生になると、学校という集団のなかで、自分をおさえたり、逆に自分らしさを発揮したりといった場面が増えていくわけです。
――自立するための土台を築くうえで、重要な時期ということですね。
小学校から中学校にかけて、特に大きく変化、成長することが3つあります。
第一に、「時間をとらえることができるようになる」という点。過去や未来を考える力がつくということです。幼児は「ママ、明日お出かけしようね」「ママ、昨日お散歩楽しかったね」ぐらいで、スケジュールを気にしませんが、1年生になれば1週間程度は頭に入ってきますよね。中学年・高学年になると、「ここで友だちと喧嘩したら2、3週間気まずいかも」などと未来を予測したり、「2年生のときはこうだったな」と過去を振り返ったりすることもできるようになります。
次に、「横のつながりが増える」という点。クラスのみんなとのかかわりが増えてきますよね。中学年や高学年になると、「この人は好きじゃないな」という好き嫌いも出てくる一方で、友だち関係を広い視野でとらえることができるようになります。さらには、地理や歴史を学ぶなかで、遠い国に暮らす人や歴史上の人物にまで思いを馳せる、想像できるようにもなってきます。
3つめが「メタ認知ができるようになる」という点。客観的に見る力ですね。「自分って、こんなこと言ってるけどその割にはこうだな……」などと、自分をモニターすることができるようになります。
時間というものに対する理解が深まり、横のつながりが増えて、メタ認知が発達してくるとどうなるか。それだけ賢くもなるけれど、実は悩みも深くなるわけです。だからこそ、この時期には人とのつき合い方、つまりソーシャルスキルや感情のマネジメントというものがとても重要になってきます。

近年は小学校の授業でも、アクティブ・ラーニングなどグループでの対話・交流をとおして学んでいく形式が増えていますよね。ということは、他者とかかわるスキルを小学校低学年のうちから身につけることが、そうした学びを積極的に楽しめるかどうかにもかかわってくると考えられます。つまり、学力にも影響する可能性があるということです。
対人スキルは「放っておけば勝手に成熟する」ものではなく、大人が教えることも必要
――グループワーク形式の授業が増えてきていますが、対人関係スキルの高さが学力に影響する可能性もあるのですね。昔に比べると、そうしたスキルを身につける必要性が高まってきているということでしょうか。
学ぶ必要があるのは昔も今も変わりませんが、昔は学ぶ機会が多かったので今ほど意識的にならなくても大丈夫だったということは言えると思います。今は、近所の子どもと公園で遊んだり、近所の人に叱られたりといった機会があまりないですよね。環境が変わったために、あえて教えないといけない時代になったということではないでしょうか。
というのも、先ほど言ったようなさまざまな能力は、放っておけば勝手に成熟するわけではなくて、周りにいる大人が教えることも必要なのです。勉強も、まったく教えていないことがいきなりできるようになる、なんてことはありえないですよね。よって、ソーシャルスキルを学ぶ機会をつくる必要がある。でも、それは先回りしてやってあげるということではないんです。
親は先回りしないこと。「応答性」をもってサポートを
――親はどのようにすれば子どもの社会性の発達をサポートできるのでしょうか。
まず第一に親に求められる態度は、「応答性」です。応答性というのは、子どもの求めていることを汲み取って受け止めるということです。子どもの様子に関心を向け、子どもが言おうとしていることをよく聞く。
ただし、「私はあなたにこんなに関心をもってあげてるんだから勉強しなさい」というのは違うんですよ。子どもを受け止めるよりも思いどおりに動かしたいという意図が強いと、それは子どもに伝わります。子どもは「親の喜ぶようなことを言わないといけないんだな」と悟って話したがらなくなり、親子間での対話が成り立たなくなってしまいます。
――心の中では子どもに「思いどおりであってほしい」と思っているのに、表面だけ応答的では受け止めたことにならないんですね。
そうです。たとえば、よく「ほめて伸ばすことが大事」などと言いますよね。でも本心から思っていないのに、「うまくできたね。こうしたらもっとよくできるのにね」なんて言ったら、やっぱりそれは本当に受容的・応答的な態度とはいえないわけです。自分ではほめているつもりでも、声とか言い方に出てしまうんですよ。
たとえば、「学校どうだった?」という声掛け一つとっても、本当に子どもの思いを汲み取ろうとしているのであれば、表情や声は応答的なものになっているはずです。でも、勉強をちゃんとしているのか問いただすような気持ちが先にあると、怒ったような言い方になってしまう。愛情をもって言っていたつもりでも、実は子どもにとって応答的でないという場合もあるわけです。
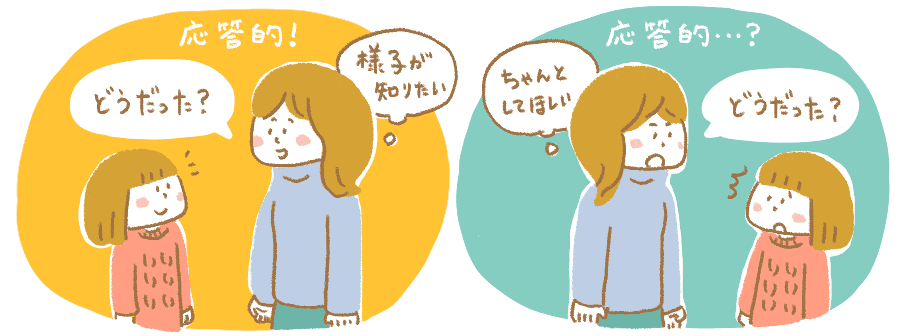
――わが子だからこそ、つい厳しい態度になってしまうのではないでしょうか。
子どもに対して「この子は乱暴だ」とか「引っ込み思案だ」などと悪い面が目についてしまっているのかもしれません。そういうときは、意識的に見方を変えてみるというのもいいですね。「リフレーミング」というやり方です。攻撃的な性格はパッションがある、引っ込み思案は慎重とも言えます。性格というのは一つの特徴の裏表なんですよ。見方を変えることで、嫌だと思っていたところがいいところでもあると気づけば、自然と受容的に接することができるかもしれません。
小学生は成長する時期、だからこそ葛藤が増える時期
――いま小学生の親には、この先の子どもの反抗期などを心配している方も多いと思うのですが、気をつけることは何かあるでしょうか。
応答性をもって、子どものいいところを見るようにして接していれば、そんなに反抗期を恐れることはありません。
ただ、反抗期の前から子どもの心は大きく変化しています。小学校の6年間で、子どもは過去を振り返ることも未来を想像することもできるようになり、対人関係も広がり、自分のことを客観的に見ることもできるようになるわけですから、悩みや葛藤がぐんと増えます。葛藤があるのだから、いつもニコニコはしていられないですよね。
大人と違うところは、葛藤が増える割には解決法がわからないということです。経験が浅いので、友だちと喧嘩しても仲直りの仕方がわからない。勉強がうまくいかなくてもどうしていいかわからない。でも、それをどう親に言っていいのかもわからない。
――そんなとき、親はどのようにサポートすればよいのでしょうか。
勉強もそうですが、そもそも、そういうときって「何がわからないかがわからない……」という場合が多いですよね。ですから、「仲直りしなさい」「頑張りなさい」や「わからないところがあったら言ってごらん」では、たぶん解決しません。それで解決できるんなら、そもそも悩まないですよね。
喧嘩して悩んでいるんだったら「お母さんがあなただったら、明日の朝、学校でこう言うかな」などと、具体的に、親身になって解決策を一緒に考える。勉強でつまずいている子には、おもしろくなくてもわからなくてもとにかく勉強しなさい、という接し方ではなくて、「ここでつまずいているんじゃない?」などと解決の糸口までは一緒に探してみる。
そもそも、メタ認知ができるようになってくると、自分のダメなところに気づくので誰でも劣等感が出てくるんです。それも葛藤が増える一因ですね。そこで自尊心が低くならないようにするためには、成功体験が大切です。とはいえ、失敗がダメというのではありません。子どもが失敗したら「それは悔しかったね」と共感したうえで、次に「自分で」成功体験をもてるようにさりげなくサポートするわけです。
いつもやってもらって成功しても、成長にはなりません。とはいえ放っておけばいいというのでもありません。本人の実力がどの程度で、どのくらい頑張ればうまくいくか、親も考えて、必要に応じて具体的なアドバイスをしてあげるといいですね。
そのように、物事を表面的ではなくきちんと教えてあげられれば、子どもはそういうものかと理解するので、単純に反発するということはあまりありません。
――応答的な態度をとっていると、子どもは葛藤を抱えずに済むのでしょうか。
いや、葛藤はすると思います。葛藤すること自体は悪いことではないんです。むしろ大事なことです。ただ、親のとらえ方が変わってくると、親も子も楽になります。
たとえばドアを子どもがバンッ!と荒っぽく閉めたとして、それを反抗している!と捉えるのか、なにか苦しんでいることがあるんだなと思って少し観察してみるのか、そうしたことでも親子のコミュニケーションは変わってきます。
問題が起きていないときの接し方が大切
――高学年になると学校でダメなものでもみんな持っているからほしがるとか、禁止されているところに遊びに行くといった行動が出てきます。どのように対処すればいいでしょうか。
そもそも、問題が起きてから子どもに注意を向ける、というのはあまりよくないんですね。むしろ、問題が起きているとき「以外」のふだんの生活で、子どもの言葉を聞き、いいところを見つけ、いいと思ったことは言葉に出してほめながら、子どもとの信頼関係をつくっていくことが大切です。ふだんほったらかしなのに注意だけしてくるというのでは、親の言葉は子どもの心に届きません。
親の考えを伝えたいのであれば、問題が起きていないときに、「こういうことをすると危ないね」「こういうことって大事だね」と話すのがいいですね。ニュースやドキュメンタリーなど、映像を一緒に見ながらそうやって親がガイダンス的に話すと、子どもはすごく学びますよ。
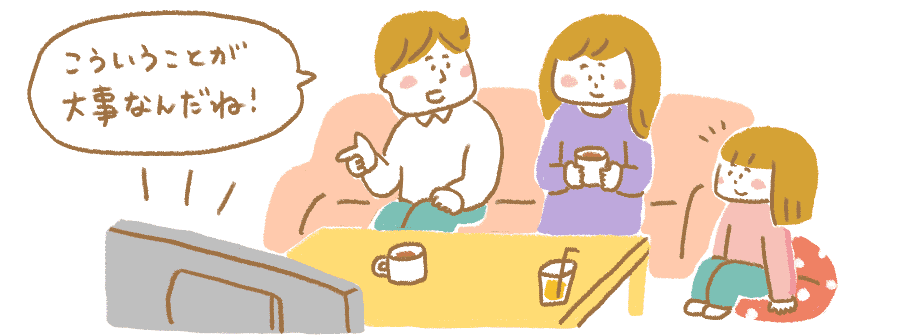
――子どもの行動や言葉にきちんと目と耳を傾けて受け止め、親の考えは子どもが受け止めやすい形で投げかけるのが大切ということですね。実は一番難しいことかもしれませんね。
そうですね。小学生の間に子どもはどんどん賢くなり、同時にさまざまな葛藤を抱えるようになります。それをしっかり見つめて会話をするというのは楽なものではありませんが、その変化に寄り添うことで、親も親になっていくのだと思います。突き放したらもったいない時期ですから、子どもと共に人生を楽しみましょう。
――ありがとうございました。
 渡辺 弥生 (わたなべ・やよい)
渡辺 弥生 (わたなべ・やよい)
法政大学文学部心理学科 教授。教育学博士。大阪府生まれ。1983年筑波大学卒業。同大学院博士課程で心理学を専攻した後、筑波大学助手心理学系、静岡大学教育学部助教授、ハーバード大学教育学研究科在外研究員を経て、2001年法政大学文学部心理学科助教授に。2004年より現職。『子どもの「10歳の壁」とは何か−乗り越えるための発達心理学』(光文社)、『親子のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)他、著書多数。