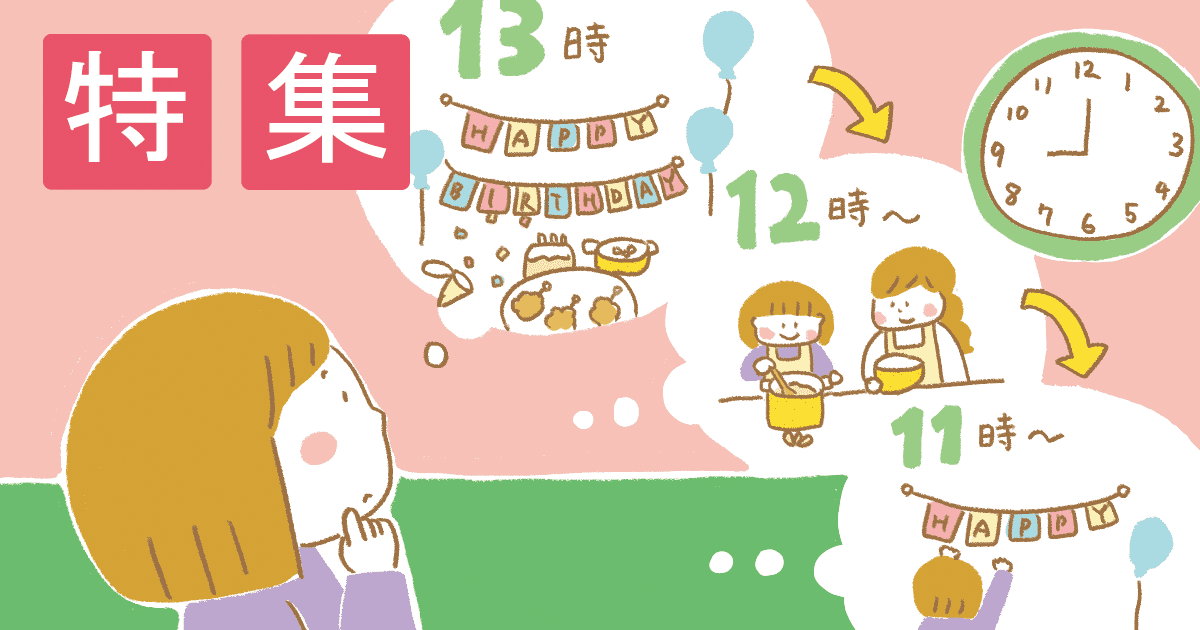ものごとを効率的に進めるために行う、「段取り」。生活でも勉強においても段取りができるようになると、時間をぐんと有効に活用できるようになります。段取りが上手にできるようになるには、どのような練習をするとよいのでしょうか。子どもの自立をうながすコミュニケーションプログラム「ことばキャンプ」を主宰し、時間の使い方に関する小学生向け書籍の執筆や監修にも取り組まれている高取しづかさんにお話をうかがいました。
(取材・文 浅田夕香)
※本記事は、2020年11月26日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
段取りとは? 段取りができるとどんないいことがある?
――高取さんは、「段取り」とはどのようなものだと考えていらっしゃいますか?
段取りは、時間管理の手段の一つだと考えています。
ビジネスを例にあげると、ものごとがうまく運ぶように先を読んで準備するということを皆さんやっていますよね。ゴールを見据えて、いつまでに何をするのか、方法やプロセスを考えて準備することは、「ものごとをトラブルなくスムーズに進めることができる」「無駄な時間なく、効率的に仕事を進めることができる」「あらかじめ準備しておくと、トラブルが起こっても対応できる」などのメリットがあり、仕事をするうえで絶対に必要なことですよね。
でも、子どもは、はじめから大人と同じように段取りができるわけではありません。子どもは経験が足りないからです。大人になる準備段階ととらえて、教えてあげ実際にやりながら、あせらず時間をかけて練習していってほしいですね。
段取り力をつける方法
――では、段取りの練習は、どんなふうにしていくとよいでしょうか?
具体的な方法を紹介する前に、保護者の方に心構えとして理解しておいてほしいことを2つお伝えします。
1つめは、当然ながら子どもは大人に比べると理解できていないことが格段に多いということ。大人は、自分が無意識に理解していることについて、子どもも同様にわかっているはずだと思いがちです。でも、子どもは経験が少なく、成長に応じて一つひとつ経験を積んで、知識と自身の感覚・経験が結びついてやっと「わかる」のです。仮に大人と同じように理解しているように見えても、本当はわかっていない可能性もあります。ですから、段取りもすぐにできるようになるとは思わず、あせらずに向き合ってくださいね。
もう1つは、段取りのトレーニングは、保護者が子どもを管理するためにするものではないということ。子どもたちが段取りできるようになること、そして、時間管理ができるようになることの目的は、子どもたち自身が、自分の時間を充実させることです。自分の時間を、自分でマネジメントして、自分が納得するように使えるようになる。それがゴールです。
――あせらない、目的をはき違えない、ということですね。
その通りです。子どもたち、とくに低学年の子どもたちは、段取りについて「ものごとには準備の時間が必要なことをわかっていない」「準備の内容にどんなものがあるか、把握していない」「どれを先にやると効率的か考えない」という3つの「ない」状態にあると思います。これらを、実体験をもって解消できるようにしていきましょう。
具体的な方法を、「寝る前の準備」を例にお話しします。
手順1.寝るために準備することをリストアップする
宿題をする、お風呂に入る、歯を磨く、パジャマを着る、明日の準備をする…など、一つずつ書き出します。このとき、保護者の方が先回りしてやることを挙げるのはやめてください。お子さん自身が言葉にして書き出せるよう、見守ったり、ヒントを出したりしましょう。
1枚の紙に思いつくままリストアップするのもいいのですが、本人ができそうであれば、一つずつ付箋に書き出していくと、あとで順番を考えたり、終えたことと、終えていないことを把握したりするのに便利です。

手順2.リストアップしたもの一つひとつの、所要時間を計る
歯を磨くのに何分かかるか、お風呂に入るのに何分かかるか…など、一つずつ時間を計って書き出し、電卓を使ってすべて足します。これもお子さんが自分でやるようにうながしてください。その結果、たとえば1時間かかったら「あ、1時間かかるんだ!」と子どもが「わかる」わけです。
このようにして、寝るためには準備が必要なことや、どれくらい時間がかかるか、また必要な時間から逆算して準備を始めないといけないことを、体で納得するのです。経験することが大事で、いくら保護者の方が口で言っても本当の意味で「わかる」ようにはならないのです。
手順3.どうすれば効率的に準備できるか考える
やるべきことと所要時間がわかれば、次は効率的に進められる順番を考えます。保護者の方から「何から始めればいいと思う?」「何を先にやったらいい?」などとお子さんに問いかけ、考えることをうながしましょう。これも、紙に書き出すのがおすすめです。
手順4.実際にやってみる
3で決めた順番でやってみます。ここで注意したいのは、失敗してもなんら問題ないということ。保護者の方が「うまくできるように導かなければ」なんて思う必要はありません。本人がやってみてうまくできれば一緒に喜び、うまくいかなければ「どうしたらいいと思う?」などと声をかけ、一緒に振り返る。そうしてトライアンドエラーを繰り返すことで、少しずつ段取りできるようになります。
この1〜4を生活のさまざまな場面でやってみて、小学校6年生くらいまでにある程度の段取りと時間内に終わらせることができるようになるといいのかなと思います。
子どもの段取り力を伸ばす、保護者のかかわり方
――子どもたちが段取りの練習をするにあたり、保護者はどのようにかかわっていくとよいでしょうか? かかわり方や適切な声かけについてアドバイスをお願いします。
何よりも大事なことは、子ども自身が考え、自分で納得して行動することですから、保護者の方は指図はしないと覚悟を決め、お子さんが自ら考えるようにうながす声かけや会話に徹してください。
あとは、失敗しても構わない、という意識でいること。そして、失敗してもガミガミ言わないことです。繰り返しになりますが、段取りする力をつけることのゴールは、自分の時間を、自分でマネジメントして、自分が納得して使えるようになること。そのためには、子どもたち自身が自分で考え、実践し、体で体得することに意味があります。なので、トライアンドエラーでも、時間がかかってもまったく問題ありません。
もう一つは、楽しくやること。たとえば、時間を計るときには「じゃあ時間計るね、よーい、スタート!」などと楽しく声かけしましょう。ゲーム感覚でやってもいいと思います。
保護者はあくまで伴走者である、という考えで、ぜひお子さんに寄り添ってあげてくださいね。
――声の掛け方について、どんな言葉がおすすめですか?
たとえば、寝る前にやることをリストアップした際にもれていることがあれば、「これ書いてないじゃない」などと頭ごなしに責めることはせず、「これはどう?」と提案するように話していただきたいですね。主体は、あくまで子どもなのですから。もれがあったとしても、リストアップできたなら、まずは「書けたね」「こんなにたくさん書けたんだ」などと、リストアップできたこと自体をほめてあげましょう。そのうえで、補足することがあったら、「これはどう?」と提案してみてください。
料理やおでかけなどでも段取りを練習できる
――寝る前の準備の段取りを例にお話しいただきましたが、ほかにどんな場面で段取りの練習をするのがオススメですか?
そうですね、3つ例を挙げますね。
1つめは、料理です。料理は、完成をゴールとして、必要な材料や効率的な手順を考えるという、段取り力を鍛えるのにうってつけのものです。
まず、必要な材料と完成までにやるべきことを書き出し、次に、手順を考えて書き出す、ということを一緒にやるといいと思います。もしくは、パンケーキなど簡単なおやつを一緒につくったり、保護者の方の段取りをなぞってもらったりすることで、「手順を決めてつくる」という行為を体感してもらうのも、最初のステップとしていいですね。
2つめは、おでかけのプランニングです。時節柄、遠出は難しいかもしれませんが、行き先を決める→行き方や所要時間、交通費を調べる→行き帰りに立ち寄りたい場所があるかどうか調べる→逆算して出発の時間や当日のタイムスケジュールを決める→持ち物を考える、という手順で1日の段取りを考えるのです。ここまでの規模でなくても、公園に行って帰ってくるまでの段取りを考え、実行するだけでも、十分な練習になるでしょう。
3つめは、だれかの誕生日会など、パーティーのプランニングです。いつ、何をするか、だれを呼ぶか、料理は何を用意していつだれがつくるか、ケーキはどこに頼むか、だれが取りに行くのか、飾りやプレゼントはどうするのか、だれが準備するのか、などを子どもに考えてもらうのです。
どれも、ポイントは楽しみながらやることと、出来の良し悪しを問わないことです。生活のなかに段取りをする場面はたくさんあるので、少しずつトライしてみてください。
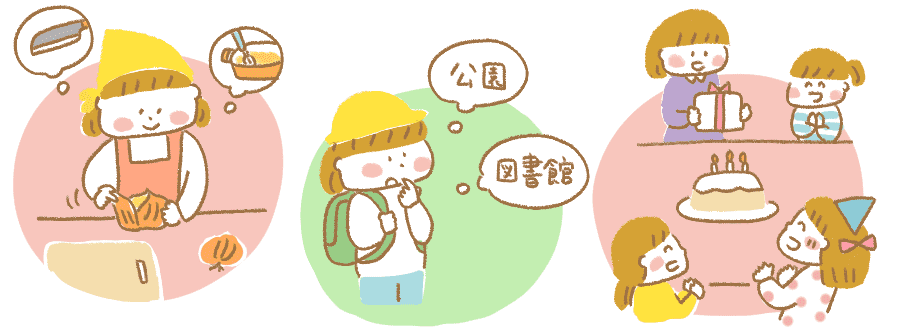
保護者による途中の軌道修正は不要
――練習するにあたっては、数時間の段取り、半日の段取り、1日の段取り、1週間先のことの段取り…などと、少しずつステップアップしていくのがいいのでしょうか?
ステップを踏むべきかどうかなどは、お子さんやご家庭の状況によって異なります。
お子さんが「やりたい」「おもしろい」と思ったことなら、どれだけ難しそうでもやってみてほしいと思います。保護者の方は大変ですが、本人ができそうなところだけやってみるなどして、できるだけお子さんの気持ちを大切にしてくださいね。
――保護者としては、なんとかうまくいくようにうながしたいという思いを持ったり、明らかに失敗しそうなことがわかれば軌道修正したいと思ってしまったりしそうですが、それらもしないほうがいいのでしょうか?
そこは見守ってほしいですね。失敗しても大丈夫です。たとえうまくいかなかったとしても、長い目で見るとたいしたことではないですから。保護者が軌道修正するよりも、子どもが自分で反省したり気づいたりすることの方が、子どもの生きる力になります。
ただ、保護者の方の気持ちはすごくよくわかります。ではどうすればいいかというと、子どもが段取りをすべて考えたあとに、保護者の方の意見を伝えてみてはどうでしょうか。「これだとほかのことをする時間がなくなっちゃうんじゃないかな?」「遊ぶ時間がちょっと長すぎないかな?」など……。
そうして保護者の意見を聞いて子どもがもう一度考えた結果、「段取りを変えずに進める」と決めたなら、尊重してあげてください。結果、失敗したとしても、小さな「できたこと」があるはずなので、まずはそれを認める声かけをする。そのうえで、「どうしてこうなったと思う?」「次はどうすればいいと思う?」などと考えるようにうながす。これを繰り返すことが、子どもの成長につながっていくのです。
――手順を決めて時間内に終わらせることはできるけれど、時間内に終わらせることが最優先になってしまい、一つひとつの「やるべきこと」の質が低いというか、おざなりになってしまう子の場合はどのようにサポートしていけばよいでしょうか?
時間内にやり遂げようとしたことや、こなせたことは素晴らしいことだと思います。まずは、そこをほめましょう。そのうえで、「一つひとつを丁寧にすると、もっといいね」とアドバイスするのはどうでしょうか。場合によっては、一度時間を意識することをやめて、一つひとつ丁寧にすることを重視する時期があってもいいと思います。これもトライアンドエラーで、社会人になるまでにできるようになればいいことなので、長い目で見てあげてくださいね。
――ありがとうございました。

高取しづか(たかとり・しづか)
ことばキャンプ教室主宰。NPO法人JAMネットワーク代表。「ことばキャンプ」の基本理念を考案し、全国のことばキャンプ教室普及につとめる。「子どもを自立に導く親子コミュニケーション」をテーマに、書籍の出版や新聞・雑誌コラムを執筆する。全国で1万人以上に講演・講座をおこなっている。
また、児童養護施設、里親家庭等で社会的養護の子どもたちへの社会貢献活動を行っている。神奈川県子ども・子育てアドバイザー、神奈川県青少年問題協議会委員を歴任。
主な著書に『時間のマネジメント』 (合同出版)など。『めちゃカワMAX!! 小学生のステキルール 夢をかなえる 時間の使い方BOOK』(監修、新星出版社)『「ことば力」のある子は必ず伸びる!』(青春出版社)他多数。