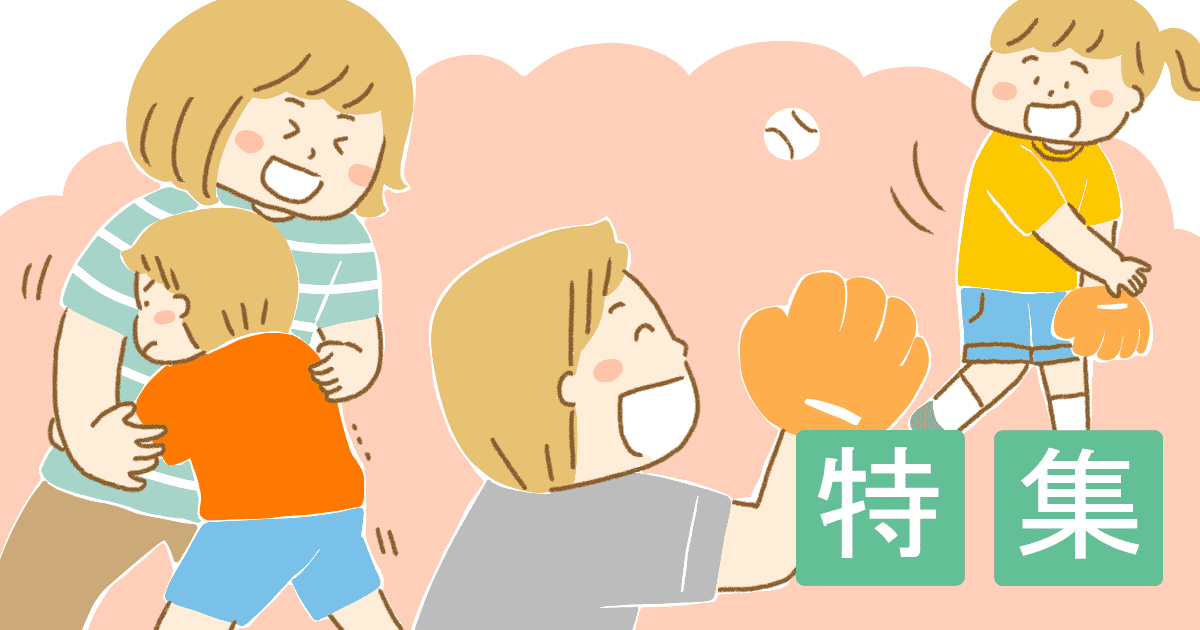小学校で取り組む機会が多い「走る」「縄跳び」「逆上がり」の3つの運動のコツについて、スポーツや身体運動を力学・生理学の観点から分析するスポーツバイオメカニクスを専門とし、運動の上達法に関する著書を多数執筆されている日本女子体育大学学長・深代千之先生にうかがいました。
※本記事は、2022年8月25日に「Z-SQUARE」上で掲載した記事を一部修正の上、再掲しています。
運動も勉強も、脳が記憶する仕組みは同じ
――深代先生は、体の動きを科学的に分析することを専門とされています。体を上手に動かせる仕組みは、どのようになっているのでしょうか?
運動ができる・できないは「脳が上手な動きを記憶しているかどうか」によります。この点で、運動は勉強と何ら変わりません。どちらも、練習して脳が記憶したかどうかによるのです。
例えば、九九や漢字は、練習して覚えなければできるようになりませんよね?体の動きも同じで、箸を使えるようになるのも、自転車に1回乗れるようになればしばらくの間乗っていなくてもまた乗れるのも、脳が動きを記憶しているからです。「体で覚えている」とよく表現されますが、その体とは、筋肉ではなく脳なんです。
――どのようなメカニズムで脳に記憶されるのでしょうか?
脳は発達に伴いたくさんの神経回路が張り巡らされます。その神経回路に電気を走らせることで、人はものを考えたり、体を動かしたりすることができます。そして、一度電気が走った道筋と同じところに再び電気が走ると、同じことが思い出せるというのが記憶の仕組みです。
神経回路は、都市部の電車の路線に例えることができます。ある駅からある駅に移動する際、複数の経路が選択肢に挙がる場合がありますよね?そして、それらをすべて試してみた結果、最適だと判断した経路を記憶しておけば、毎回乗り換え案内を調べなくても経路がわかる。このように、ある路線に乗ると最適な経路を思い出せるというのが記憶の仕組みで、その記憶を確固たるものにするのが練習です。
運動においては、「こうすればうまく体を動かせる」という動きを練習によって確固たるパックにして小脳に蓄えることで、いつでも引き出して使えるようになります。だからこそ、子どものころにさまざまな巧みな動作を蓄えておくと、成長したり、大人になったりしてから「ちょっと運動してみよう」となったときに、昔覚えた動作を引っ張り出して、その動きを応用してすぐにできるようになるのです。そして、練習すればうまくもなっていくので、楽しいんですよね。
運動や体を動かすことの根源には楽しさがあります。楽しさを感じるからこそ、結果として運動がうまくなる。ただ、その楽しさを味わうには、幼い頃に蓄積されたさまざまな巧みな動きがベースとして必要だと私は考えています。
――ということは、小学生で運動に上手・下手があるのは、その動きをしたことがあるかどうかに左右されるということでしょうか?
そうです。新しい動作がすぐにできる子は、昔覚えた動作のどれをもってくればいいかを即座に判断して、引っ張り出してくることができます。その器用さを、大人は「勘の良い子」で済ませてしまうことがありますが、決して勘ではありません。蓄え、すなわちさまざまな動作の基盤があるからです。
他方で、下手な子がなぜ下手かというと、やったことがない、すなわち、小脳に記憶がないから。もしくは、間違った下手な動作を記憶しているからです。
――では、上手な動きを脳に蓄えていくには、どうすればいいのでしょうか?
次の7つのポイントに気をつけて、上手な動作をそのとおりにできるまで練習しましょう。
- うまい人のイメージを思い描いて繰り返し練習する
- 目的意識を持って練習する
- 行き詰まったら休憩する
- うまくできたところで止めずに続ける
- 練習していないときも良い動きをイメージする
- 良い動作は他の動作に応用してみる
- フォームチェックなどをして、結果を見直す
こうして「上手にできた!」という体験が、記憶を強化していきます。これらのポイントは、大人が新しい動きを習得するときも同じです。子どもよりも時間はかかりますが、上手な動きを練習して小脳に蓄えることは、何歳になってもできることです。
「速く走る」ためのコツとは
――では、ここから、「走る」「縄跳び」「逆上がり」という具体的な動きのコツをうかがいたいと思います。まずは「走る」について、速く走るためには何に気をつけるといいのでしょうか?
速く走るコツは、股関節の動きにあります。具体的には、股関節を動かす筋肉を使って膝を速く前へ上げるのがポイントです。脚を前へ出すときは、背骨から大腿(もも)の骨に伸びる腸腰筋が縮んで股関節が曲がり、脚を引っ張り上げます。そして、前へ出た脚を下ろし、地面を後ろに蹴るときには、骨盤の後ろから太ももの後ろにつながる大殿筋や骨盤と脚の裏側をつなぐハムストリングスが縮み、股関節を伸ばします。これらの筋肉をタイミングよく、素早く順番に縮ませることで速く走ることができるのです。
ただ、このメカニズムを子どもたちが知っておく必要はありません。説明しても理解するのは難しいでしょうし、理屈抜きにできればそれでいいものですから。そこで、私が提案しているのは、「ドリル」です。ドリルに取り組むことで結果的に股関節が使われるようになれば、速く走ることができます。
――どんなドリルに取り組むとよいでしょうか?
脚を前に出すドリルとして「スキップ」を、前に出した脚を引き戻すときの地面を蹴る感覚を習得するドリルとして「競歩ドリル」を提案しています。この2つに取り組み、脚を前に出す動きと引き戻す動きが走りの中でできるようになれば、必ず速くなります。
――では、1つめの「スキップ」について教えてください。
これは、膝を素早く大きく前へ上げる動きを磨くことを目的としたドリルです。具体的には通常のスキップよりも大股でスキップをします。その際の動きのポイントは、次の2つです。
- 大きく腕を振って、リズムよく、遠くへ跳ぶつもりでスキップする
- 膝と足首の力を抜いて、脚を前に投げ出すように動かす
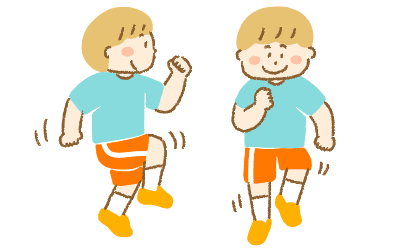
この動きがうまくできれば、股関節、膝関節、足首の順に力が伝わり、脚全体がムチのようにしなった動きになります。
――2つめの「競歩ドリル」とは、どのような動きでしょうか?
地面を後ろへ強く蹴る感覚を磨くことを目的としたドリルです。具体的には、次のポイントを意識して、速足で歩きます。
- 股関節を中心に動かして、できるだけ大股で速く歩く。走りそうな勢いになったら走り出してOK。
- 着地は足の指のつけ根付近を使う。かかとは一瞬だけ地面につく。
- 地面からの反力を利用して前に進む力にする

この「競歩ドリル」と「スキップ」を行ったあとに走ることまでを1セットにして繰り返すと、速く走れるようになります。注意点は、ドリルを繰り返すだけではなく、ドリルをしたらすぐに走って、ドリルが走る動作に結びついていることを実感すること。ドリルはあくまでドリルですから、走りでいかされないと意味がありません。
――ドリルで練習し、股関節を使って走っているときのフォームにはどのような特徴がありますか?
1つは、力を入れずに膝が曲がって前に出ていることです。力いっぱい膝を曲げる筋肉は使いません。大腿(もも)を速く上にあげていくと、膝は勝手に曲がるので、もし膝を曲げる力が働いてしまっているようなら、スキップドリルに戻り、脚を前に振り出すことに集中するようにしましょう。
あとは、ビデオを利用して、「少ない歩数でより大股で走れているか」「コマ送りにしたときに、1歩を何コマで走ったか」もチェックポイントになるでしょう。50メートルなど一定の距離を走る様子をスマートフォン等で映像に記録し、「何歩で走ったか」「1歩あたりのコマ」を練習前、1週間練習を重ねた後、2週間練習を重ねた後、と比較して、全体の歩数が減り、1歩あたりのコマ数が減っていれば、速さが増しています。
「縄跳び」を上手に跳ぶコツとは
――続いて、縄跳びを上手に跳ぶコツを教えてください。
次の9つのポイントに注意すると、上手に跳べます。
- 身長に合った長さの飛び縄を用意する。真ん中を踏んで伸ばすと持ち手が腕の高さになる長さがちょうどいい。
- 手のひらが上を向くように持つ。
- 連続ジャンプに手首の回転を合わせる感覚で跳ぶ。
- 「できるだけ高く跳ぶ」ことは必要ないのでジャンプは縄が通るスペースができればよい。
- かかとを地面につけず、ひざもほとんど曲げない。
- ジャンプのタイミングに合ったリズムで縄を回す。
- 腰の横にグリップを固定して手首で回す&脇をしめる(×腕全体で回す、腕を広げる)。
- 一定のリズムで、まっすぐ上へ、同じ場所で跳ぶ。体の各部はリラックスさせる。
- 下を向かず、まっすぐ前を見る。
――縄跳びがうまくできない原因には、どのようなものが多いでしょうか?
跳ぶことと縄を回すことを同時にするのがうまくできない場合が多いのではないでしょうか。「跳び縄を回して跳び越す」ではなく、「ジャンプした脚と地面とのすき間に跳び縄を通す」という感覚で、連続ジャンプをしているところにたまたま縄を回す動きが加わったという意識で練習するといいと思います。
練習の仕方としては、まっすぐ前を見て連続ジャンプができるようになったら縄を回すようにする、あるいは、自分のジャンプのペースに合う音楽に合わせて縄跳びの練習をするとよいですよ。
――跳んでいるうちに跳ぶ位置がずれていく場合、何に気をつけるといいのでしょうか?
片手ずつ別々の縄を持って空振りをさせながら、体の軸を動かさずに同じところでジャンプだけをする練習をするといいですよ。なぜ位置がずれるかというと、縄をくぐることに意識が集中してしまうからです。高くなくていいので、リズムよく、同じペースでジャンプできることがまずベースにあって、その上で、ジャンプのタイミングに合ったリズムで縄を回し(ポイント6)、ジャンプした脚と地面のすき間に跳び縄を通せる(ポイント3)ようになるとよいでしょう。
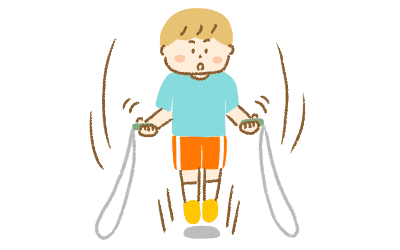
――あや跳びが上手にできない場合はどうすればいいでしょうか?
この場合も、跳ぶことと回すことを分けて練習するとよいでしょう。具体的には、縄を一つに束ねて持ち手を両手で持って八の字に回し、その動きにあわせてジャンプする練習をします。その動きに慣れれば、縄を通常の持ち方で持って、腕を交差して跳ぶことに移ると、あや跳びができるようになっていると思います。
――大縄跳びの跳び方のコツはいかがでしょうか?縄に上手に入っていくコツと、入ったあと上手に跳び続けるコツを教えてください。
縄に上手に入っていくには、自分の前を縄が通ったらすぐに入ることです。縄が地面についてから入るのでは遅いです。そして、入ったあと縄に合わせて跳び続けるには、周りの人とジャンプのタイミングを合わせるのが手っ取り早いと思います。
「逆上がり」のコツとは
逆上がりは、次の4つのポイントに注意しましょう。
- 上から鉄棒を持ち(順手)、親指はほかの指の上に置いてしっかり握る。逆手はNG。逆手で持つと、回ったあと鉄棒の上で止まるときに腕が伸びにくくなってしまいます。
- 脚を上げる方向は前ではなく上。脚と一緒におなかも鉄棒を越えるつもりで思い切り地面を蹴る。
- おなかを鉄棒にくっつけて回転する。上に蹴って腕を引きつければおなかが鉄棒にくっつき、あとは回るだけになる。
- あごを引く。あごを引くことで背中が丸まり、自然に鉄棒の上で回れる。逆に、あごが上がると体が反って失敗する。
――脚を蹴り上げたあと、腕を引きつけておなかを鉄棒にくっつけるのが難しい点だと思います。この動きのポイントを教えてください。
肘を曲げずに、手首を腰に引きつけるのがポイントです。肩の動きを使って腕を下に振り下ろす力が入れば、おなかを鉄棒に近づけることができます。
――鉄棒と腰が近づいたものの、脚が上がりきらなかったり、回りきれずに降りてしまったりする場合はどうすればいいでしょうか?
立った状態で鉄棒と腰を近づけて背中からバスタオルを巻き、両手で持って回る練習をしましょう。すると、腰が鉄棒から離れすぎず、腰を鉄棒に近づけるコツがわかってきます。コツがつかめてきたら、徐々にタオルを長くしていきましょう。そのうちタオルがなくてもできるようになります。
鉄棒と腰が離れてしまうことさえ改善できれば、逆上がりはできるようになりますよ。
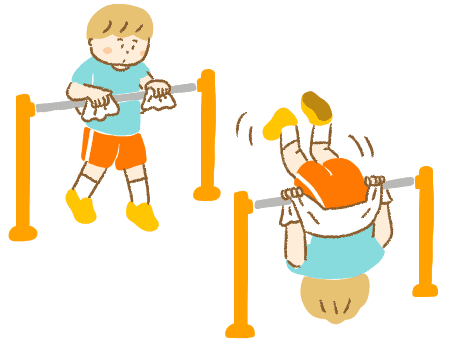
――では最後に、お子さんが少しでも運動を好きになったり、できる動作を増やせたりするために、保護者の方はどのようなかかわり方をするとよいでしょうか?アドバイスをお願いします。
いちばんは、保護者の方も一緒に体を動かすことです。保護者の方の運動の様子がおもしろそうに見えたり、自分の体を自在に動かせることは楽しいと伝わったりしたことで子どもたちもやる気になるというのが理想です。
親子で体を動かすのにおすすめなのが、キャッチボールと相撲です。キャッチボールは「投げる」という動作の基本になりますし、相撲は相手を押すときの体の動かし方や、押されたときのかわし方など、体の使い方がわかります。
いずれにしても、保護者のみなさんには、運動と勉強は別物ではなく、どちらもやればできるようになるものだということを理解していただきたいですね。教科学習と同じで、運動も練習すればするほどできるようになるもの。ぜひ子どもと一緒に楽しんでほしいと思います。
――ありがとうございました。

深代千之(ふかしろ・せんし)
1955年群馬県生まれ。日本女子体育大学学長。東京大学名誉教授。博士(教育学)。鹿屋体育大学、財団法人スポーツ医・科学研究所勤務から東京大学大学院総合文化研究科教授を経て、現職。スポーツバイオメカニクス研究の第一人者として、トップアスリートの動作解析から子どもの発育発達まで幅広く研究。著書に『すぐできる!かけっこ とびばこ さかあがり』(集英社)、『新・運動会で1番になる方法 増補改訂版』(ラウンドフラット)など多数。