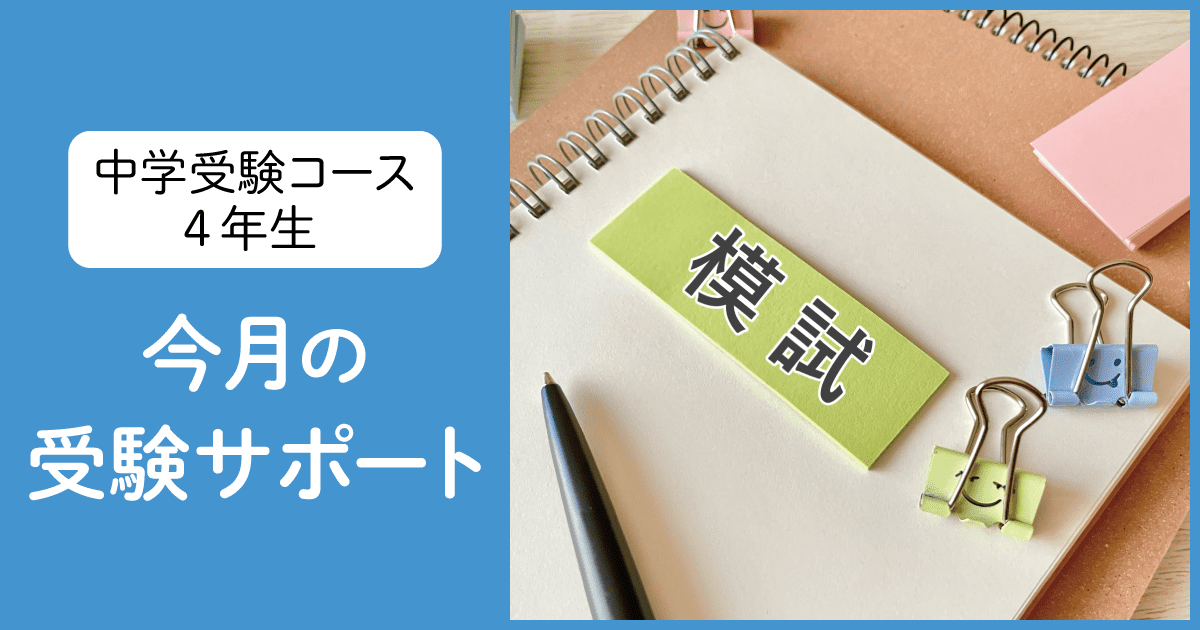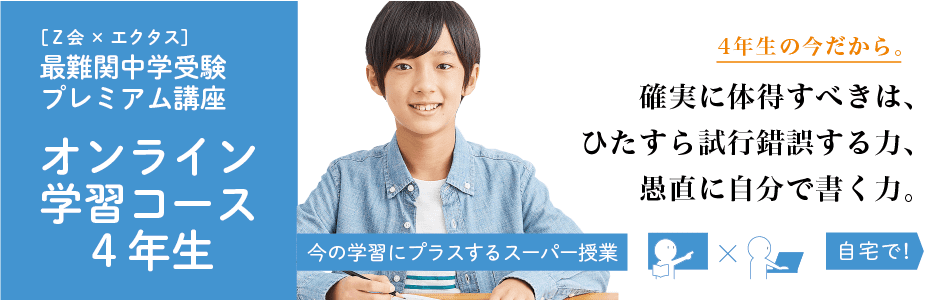Z会では、志望校合格に向けての学習計画を立てたり意欲を高めたりするためのツールとして、模擬試験(模試)の受験をおすすめしています。
今回は、その模試の基本的な知識から考え方・とらえ方について、ご説明いたします。
そもそも「模試」とは
模試とは、塾や模試主催団体などが実施する、いわゆる「公開模試」のことで、そのときの受験者のデータを収集して統計処理をし、学力偏差値を算出するものです。
中学受験の場合、5年生前半まではお子さま自身の「実力判定」や「苦手克服」のために受けることが多いのですが、受験者の意識が高まる5年生後半からは、実際の入試での合格可能性を測るために「偏差値」=「学力上での立ち位置」を知ることが目的になっていく傾向があります。
これまでの記事で、志望校を具体的に決めていく方法のいくつかをご説明しましたが、「模試」も志望校選定のためにとても役に立つツールです。できれば、6年生になる前に何度か受験しておくことをおすすめします。
「Z会おうち学習ナビ」の「模試活用のABC」では、模試を上手に活用するための模試受験の基本をご紹介しています。毎月第4木曜日に更新していますので、ぜひチェックしてみてください。
模試と偏差値
模試を受けると偏差値が算出されます。この偏差値は、志望校を決める際の指標として利用するため、お子さま・保護者の方ともに、その意味をきっちりと理解しておきましょう。
「偏差値」とは、特定の母集団(模試なら、受験者集団)の平均を「50」という数字として設定したときに、自分の位置が平均からどのくらい離れているかを知るものです。したがって、仮に80点をとったとしても、平均点が90点の場合は偏差値は50を下回ることになりますし、平均点が50点だった場合には、偏差値は高い数値になるでしょう。
また、偏差値は、学校の合格難易度を測ることにも使われます。合格難易度としては、例えば模試の偏差値から「〇〇中学校の合格可能性80%」のような指標を出す大手模試があります。これは、過去のデータから「この模試でこのくらいの偏差値が取れていれば、80%程度の合格可能性が期待できる」という一つの目安です。この合格可能性という指標で、志望校が合格圏内の「安全校」なのか、「実力相応校」なのか、もう少し頑張る必要がある「チャレンジ校」」なのかがわかりますから、実際の受験校を検討する際に参考にするとよいでしょう。
なお、合格可能性は過去のデータから導き出したものです。したがって、何らかの要因で受験者数、合格者数が大きく変わる場合や、受験科目数、難易度、試験日程の異なるものにはあてはまらない場合があります(むしろあてはまらないと考えるほうが自然です)。その点もふまえておきましょう。
4年生のうちは、結果に一喜一憂しすぎない
4年生から受けられる模試もありますので、今、お子さまが受験者のなかでどの立ち位置にいるのかを把握したり、試験の雰囲気に慣れたりするために受験するのはよいでしょう。しかし、この段階ではまだ学校ごとの志望者の層が流動的です。また、この時期は学習の進度も個々人によってばらつきがあります。4年生の模試の結果で、そのつど「この学校の合格は確実だ」「やっぱり志望校を変えたほうがいいのかもしれない……」などと一喜一憂するのは、意味のないことです。あくまで現状把握や慣れるためのものと捉え、冷静に結果を受け止めることが大切です。
5年生の後半あたりになれば、多くの受験生の実力がある程度固定されてくるため、合格可能性への信頼性が高まってくると考えてもよいでしょう。6年生になるとまわりの受験生たちも学習のペースを上げていきますので、偏差値を一気に大きくアップさせるのは難しくなるといわれています。
今後、模試を有効に利用していくためにも、模試を初めて受験するときから、
- 偏差値から、全体のなかでの自分の位置を客観的に把握して真摯に受け入れる
- 偏差値や点数に一喜一憂せず、「なぜ、この問題ができなかったのか」「次はどのようにすれば、解けるようになるか」ということを具体的に考える機会とする
という姿勢で臨むことが、受験でよい結果を迎えるために有効だといえるでしょう。
次回の「受験サポート」は11月13日(木)更新予定です。