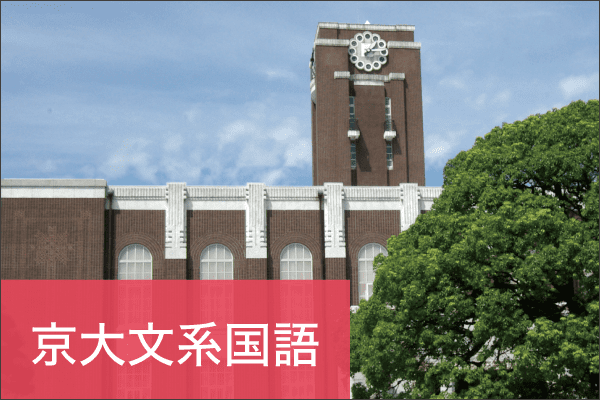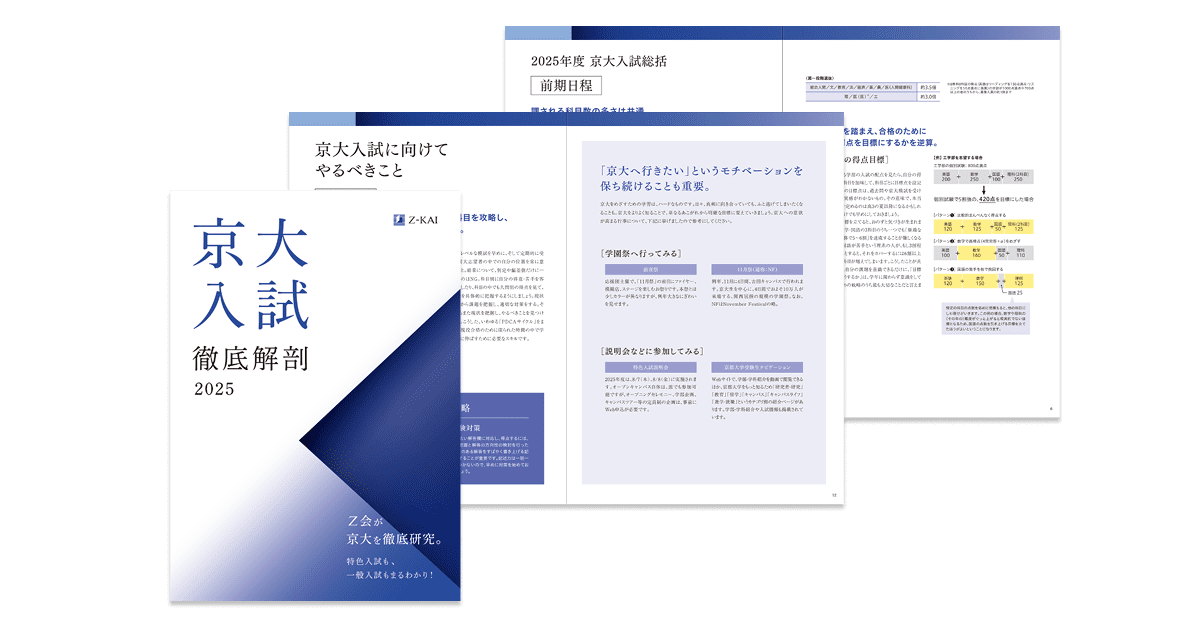Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化(時間:文系120分)
- 分量は2024年度からやや減少
- 難易度は2024年度からやや易化
2025年度入試の特記事項
- すべて標準的な難度の大問で構成され、全体の負担感は2024年度よりも下がった。特に古文の難度が下がり、全体としてやや易化したと言えるだろう。
- 現代文は、2024年度に出題された旧仮名遣いの芸術論のような、時代的にも文体的にもなじみの薄いものは出題されず、読みやすい文章からの出題となった。
- 極端に難度の高い設問もなく、分量も標準的であるため、一つ一つの設問での細かな取りこぼしが合否を分けかねない。設問要求と解答欄の大きさに応じた解答要素の見極めが、より重要になったと言えるだろう。
合否の分かれ目はここだ!
どの大問も、大きな解答欄にどこまで解答要素を盛り込むかといった京大特有の難しさはあるが、慌てる必要はない。落ち着いて得点できるところを確実に押さえ、トータルで合格点を確保するという意識を持つことが重要である。
第一問の問四・問五と、第二問の問五は、特に解答要素の選定に注意が必要。それぞれで問われている必要な要素を見極め、取りこぼしのないようにまとめることが重要だ。第三問の古文はオーソドックスな出題で、基本がしっかり押さえられていれば迷うところは少なく、それだけにわずかなミスが合否の分かれ目になりやすい。出題傾向は一貫しているため、京大に照準をあわせて読解・記述演習をしっかり積んできた受験生であれば、実力を発揮できただろう。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
〔一〕:現代文(随筆) 出典:中井久夫「現代社会に生きること」 [標準]
「都市化」を題材として、人間と自然とのありかたについて論じた文章からの出題。どちらかといえば評論に近く、読みやすい文章だが、言いたいことをあえて直言せず読者の理解に委ねる表現も目立つので、いざ設問に答えようとすると難しく感じたかもしれない。
- 問一は、傍線部までで書かれたことのうち、「かわいらしい」と評しうる内容はどういうものかを考えてまとめる。
- 問二は「このように」の指示内容をもとに、「自然を『疎外』し」「自然から『疎外』された」の意味内容が明らかになるようにまとめる。
- 問三は、「正常さ」「大地の感覚」を鍵として傍線部の前の内容をまとめる。問一~問三はいずれも比較的解答要素が見つけやすく、取り組みやすい設問なので、時間をかけ過ぎずに得点を稼ぎたい。
- 問四は、どういうことに「同感」しているのかを的確に読み取り、筆者自身の考えはどういうものかをまとめる。設問要求を満たすように、わかりやすくまとめることが大切。
- 問五は、京大では珍しい、傍線部のない全体読解。「人間と自然との関係」「人間と他の人間との関係」「都市化が与える影響」について整理し、解答要素の取りこぼしがないように、丁寧にまとめたい。
〔二〕:現代文(随筆) 出典:小津夜景『ロゴスと巻貝』 [標準]
俳人・エッセイスト小津夜景の、読書について語った随筆からの出題。筆者自身の体験に基づく思いを綴った、2024年度第一問と似たタイプの文章で、理路整然と理屈を積み上げて解説するタイプの文章ではない。京大らしい文章の出題と言えるだろう。
- 問一は、傍線部の比喩表現の意味するところをとらえ、前の段落の内容をもとにまとめる。
- 問二は、直前の内容をふまえて、「倫理をはぎとった」「対等に扱われる」の意味するところをまとめる。
- 問三は、「ことの次第が入れかわってしまう」という表現に留意して、傍線部の後の内容から筆者の考えをまとめる。
- 問四は、傍線部がどういうことについて述べたものかを読み取り、「特権階級的」「傲慢」という表現が示す内容を丁寧にまとめる。
- 問五は、筆者の強い思いが込められた箇所。傍線部の後の内容を中心に、言いたいことが明確になるように端的な表現でまとめたい。
〔三〕:古文(物語) 出典:『義経記』 [標準]
京大では珍しい軍記物語からの出題。わかりやすい文章だが、主語を明示していない箇所も多く、丁寧に文脈をたどる必要がある。難問はなく、全体としてオーソドックスな出題だった。
- 問一の現代語訳は傍線部が長く、文法的に重要な表現も多く含まれていた。一語一語丁寧に訳出し、人物関係や場面が明らかになるように言葉を補う必要がある。
- 問二・問三は、傍線部自体の意味はわかりやすいので、どのように言葉を補って説明するかの判断が重要であった。
- 問四は、「人」が誰を指すかの判断がやや難しく、文脈の慎重な吟味が必要である。
- 問五は和歌の現代語訳。高度な修辞は用いられていないので、北の方の思いが明らかになるように丁寧に訳出すればよい。
攻略のためのアドバイス
京大文系国語を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 基本的な語彙力
文学的・抽象的な表現を含む文章からの出題が多い京大国語では、読解力・記述力ともに高いレベルが要求される。その水準に達するためには、基本語彙の意味を正確に把握し、記述する際にも適切な語を選ぶことができる語彙の運用力が必要不可欠。Z会の書籍『現代文 キーワード読解』『速読古文単語』などを活用して、語彙力の基礎を固めよう。
◎『現代文 キーワード読解』の詳細はこちら
◎『速読古文単語』の詳細はこちら
●要求2● 幅広いジャンルに対応できる読解力
京大国語では、普段受験生が読み慣れないであろうさまざまなジャンルの文章から出題されるため、京大で出題されそうな文章の読解経験の量がものをいう。問題文中に直接的に表現されていなくとも、文中の表現のニュアンスを汲み取り、筆者の主張や心情を正確に読み取る力が必要である。
要求3●大意をまとめなおす記述力
京大国語の設問は、すべてが記述式問題であり、求められる記述の分量もかなり多い。解答に必要な要素を見極める力と、必要な要素を正確に伝わる形で解答にまとめなおす力が求められる。問題文中の記述の寄せ集めではなく、適宜自分の言葉で言い換えたりふくらませたりすることができる確かな記述力が必要である。
対策の進め方
読解力の練成
まずは、土台となる要求①②を満たすことを目指そう。Z会の通信教育の「京大講座」では、毎月さまざまなジャンルの問題文を通じて、京大入試に対応した読解・演習の経験を積むことができる。語彙・文法事項といった知識事項の抜け漏れをつぶしていくと同時に、記述演習にも取り組むことで、第三者に伝わる解答の作成法を身につけよう。
記述解答のブラッシュアップ
その後は、さらに要求②③を磨いていこう。9月以降のZ会「京大講座」では京大入試本番と同様、大問3題セットのオリジナル問題を出題する。第三者の客観的な視点からの添削指導を受けて、自分の解答に足りない要素やまとめ方のコツを把握し、解答の質を高めていこう。
京大レベルの演習
入試直前期には、本番前の最終調整として過去問や予想問題を活用しながら、より本番に近い形での演習をするとよい。読解量・記述量ともに負担が重い京大国語に対応するために、制限時間内でうまく解答をまとめることを意識して問題演習を行おう。
Z会でできる京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!