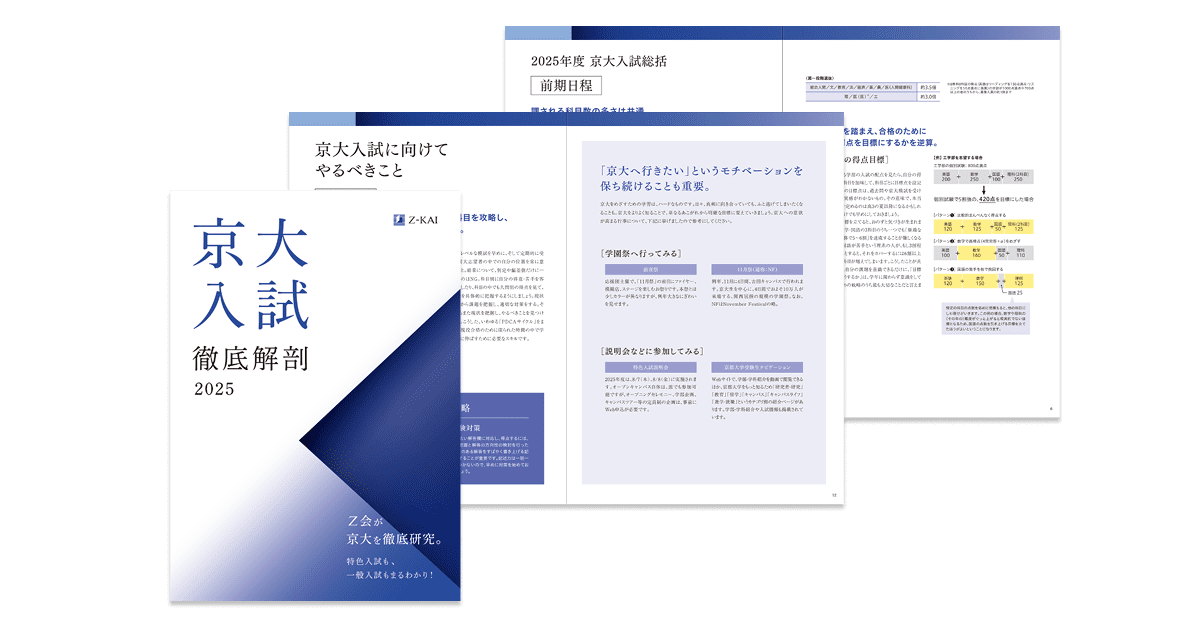Z会の大学受験担当者が、2024年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
「最難関講座」地理担当者からのメッセージ
京大地理は基礎的な内容が問われることが多いため、平易な問題でミスをすると他の受験生との差を広げられることになってしまいます。早めに高校地理の学習内容を押さえ、過去問を初めとする様々な演習問題に取り組むようにしましょう。
大問Ⅴの地形図の読図問題は、京大地理の定番といえます。新旧地形図の比較を含めて、様々な地形図に触れ、図から起伏や土地利用の特徴などを読み取る練習を積んでいれば、難なく対応できたでしょう。これらは資料問題の対策においても同様です。
本科「最難関講座 地理」では、京大地理攻略に役立つよう、図表の読み取りをもとにした論述問題や、基礎知識を確認する単答問題など、様々な形式の問題を、幅広い分野から多数出題しています。京大をめざすみなさん、Z会と一緒に頑張っていきましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:90分)
- 大問数は、2019年以降5題で定着している。解答数は、単答問題は38(うち空欄補充が17)で2023年度からやや増加した。論述は18出題され、2023年度からの問題数の変化はなかった。そのうち、字数指定のある問題が13で2023年度の14より減少し、総字数も415字で2023年度の510字より減少した。また字数指定のない問題は5で、2023年度の4より増加した。いずれも20〜30字程度で解答できる分量である。
- 論述問題の総字数が減少し、単答問題も基本的な用語が多く見られたが、短い字数でまとめにくい問題もあり、2023年度からの難度は変化なしである。
2024年度入試の特記事項
- 論述問題の指定字数の最大は40字(2023年度は60字)で、1問当たりの字数は少なくなっている。
- 2020年度に出題された作図問題、2020年度・2021年度と続いた画像の判読を必要とする問題は見られなかった。
- 地形図の読図問題は、2023年度と同様、大問Ⅴで出題された。
- 出題内容は自然環境・地誌・産業・都市・社会・地形図の読図であり、頻出のテーマからの出題であった。
合否の分かれ目はここだ!
- 基本的な用語を問うものが多い単答問題で、確実に解答できたか。
- 論述問題において、短い字数でまとめる対策を十分に行えたか。
- 問題全体を見渡し、時間配分を考えながら効率的に解答できたか。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
大問 I
インドの鉱工業に関する大問。(1)の空欄補充問題、(4)①の鉱産資源名など、基本的な問題が中心なので、確実に解答して得点につなげたい。
- (2) 都市名は迷うが、各地方の中心都市であるため落ち着いて解答したい。
- (4)② ジャムシェドプルの製鉄所立地の要因は、資源の産地であることだけでなく、鉄鋼業の立地の特徴についても触れたい。
- (5)「外国資本をひきつける要因となっているインドの人口構成上の特徴」とあるが、インドの人口ピラミッドの形なども思い出しながら考えたい。
大問 II
日本の都市の人口変化に関する大問。(1)の空欄補充、(4)〜(7)の単答問題は都市に関する基本用語であるため、確実に解答したい。
- (2) 「昼間人口が夜間人口を上回る」状態を示した都市を指摘するが、首都圏などへの通勤・通学による流入だけでなく、地方の中心都市における昼間の人口集中に気づけたかどうかがポイントである。
大問 III
世界の砂漠化に関する大問。(1)の空欄補充は基本的な用語が中心であるが、ウのオガララ帯水層は難度が高い。
- (2) アタカマ砂漠付近の砂漠化の原因について、自然条件の面から説明する問題。字数が短いため、要素となる用語を過不足なく使って説明できるかどうかがポイントであった。
- (4)② ミシシッピ川以西の植生について、「長草草原」だけでは10字に足りないため、具体的な特徴についても説明できたかどうかで点差を分ける問題であった。
大問 IV
日本の2019年度と2021年度の都道府県別の航空輸送に関する大問。航空輸送の基本的な知識だけでなく、新型コロナウイルス感染症の流行を境とした輸送の変化についても問われた。
- (1) グラフだけでなく、その後の問題文もヒントにして都道府県名を判定したい。
- (3) 国内旅客輸送が大きい理由について、B(北海道)・沖縄県から観光について考えがちであるが、問題文では「航空交通の特性」とあることから、その点に留意して解答したい。
大問 V
山梨県韮崎市・南アルプス市付近の新旧地形図の読図に関する大問。扇状地における農業的土地利用や人工的に建設された用水路など、幅広い分野からの出題となっている。
- (2) 旧地形図の「桑畑」の地図記号は、現在の2万5千分の1地形図では使用されなくなっている。
- (5) ①は「徳島堰」が人工の水路と判断する理由を答える問題。天井川であるA川の下を流れる箇所は地形図上では読み取りにくく解答しにくい。②は「地形と農業との観点」とあることから、扇状地の土壌の特徴を考えた上で、砂礫地では立地しにくい水田の土地利用から「灌漑」を連想して解答したい。
攻略のためのアドバイス
京大地理を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 幅広い分野についての知識力
京大地理は、自然(地形図の読図を含む)、産業、社会(都市・人口・民族など)、地誌といった幅広い分野から出題されるのが特徴である。細かい知識について問われることは少ないが、高校地理の全分野にわたって基本的な知識を押さえておく必要がある。
●要求2● 正確な資料読解力
京大地理では、多数の資料判読を必要とする論述問題が見られるので、正確な資料読解力が求められる。2024年度の大問Ⅰ・大問Ⅲのように、分布や位置関係など、地図上での理解を必要とする問題も頻出なので、日頃から地図を用いた学習を行いたい。
●要求3● 簡潔に論述する表現力
論述問題の1問当たりの指定字数は60字以内で、40字前後のものが最も多い。また、字数指定なしの論述問題に取り組む場合にも、解答欄に合わせて適切な分量を見極める必要がある(解答欄の大きさから20~60字程度と判断する)。
様々な角度から解答できるよう、基礎的な知識と簡潔にまとめる表現力が必要である。
Z会でできる京大対策
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!