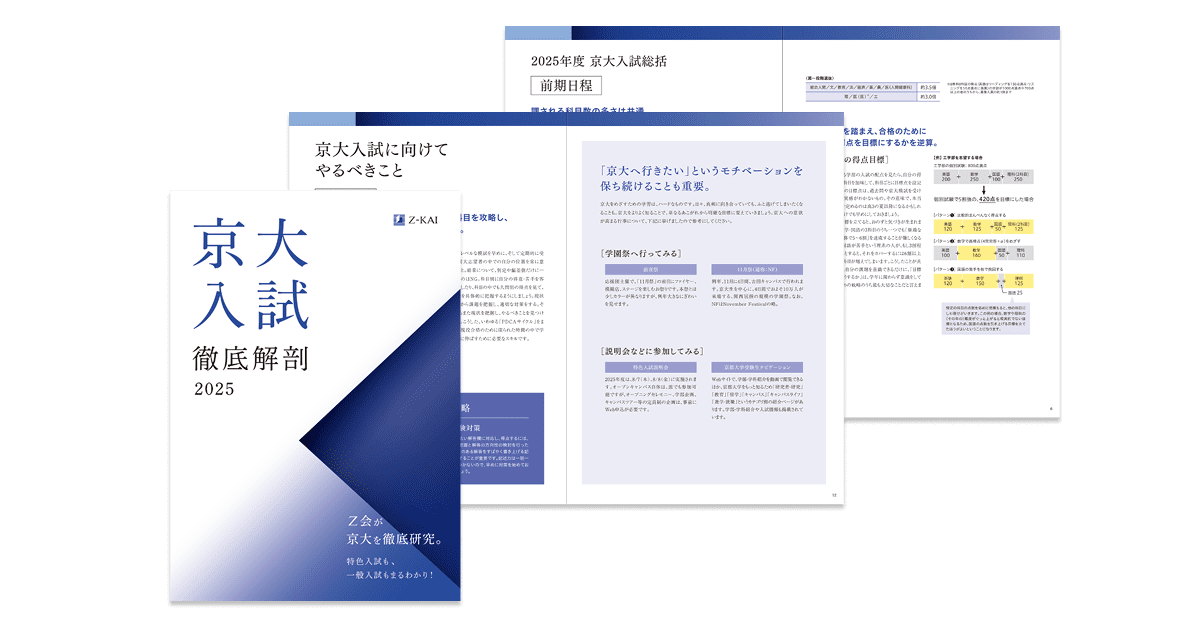Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会日本史担当者からのメッセージ
・2025年度も、試験時間90分で単答70問+200字論述2問という京大日本史の例年通りの出題スタイルが維持されました。Ⅰ〜Ⅲは標準的なレベルの知識問題が中心ですが、史料を読み解いたり、リード文の趣旨を踏まえて空欄の語句を考えたりする問題も見られます。一見難問のように思えても、注やリード文、他の問の設問文にヒントがあることも。出題の特徴に慣れておき、焦らず手際よく答えることを心掛けましょう。
・京大の特徴である“全時代・全分野”からの出題に対応するためには、教科書の脚注レベルも含め、知識の抜け漏れがないようにしておく必要があります。文化史も抜かりなく、「正しく書ける」ところまで仕上げておくことがマストです。
・2025年度の論述問題はオーソドックスで書きやすいテーマでしたが、それだけに、高得点勝負になったのではないかと思います。必要な要素を漏らさず盛り込んだ解答を作れるよう、テーマに沿って要素を書き出し、200字で文章にまとめる、という練習を積んでおきましょう。
・京大で求められる幅広い知識、史料問題への対応力、題意に即した解答をまとめる論述力を伸ばすためには、十分な問題演習が必要です。Z会の「京大講座」で、バランスよく知識、史料、論述の対策を行いましょう。論述対策では、自分の解答が設問の意図に沿ったものになっているか、要素に過不足はないか…などをZ会の丁寧な添削指導を通して確認し、論述力を伸ばしていきましょう。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:90分)
- 分量は2024年度から変化なし
- 難易度は2024年度からやや易化
2025年度入試の特記事項
- 例年〔Ⅰ〕や〔Ⅲ〕で数問出題されることがある短文記述問題について、2024年度は5問出題されたが、2025年度は出題がなかった。
- 〔Ⅲ〕Cで、表・グラフを提示した問題が初めて出題された。
- 〔Ⅳ〕の論述問題は⑴古代、⑵近・現代からの出題で、⑵では2014年度以来の昭和戦後史が出題された。
- 2024年度より易化したが、標準的なレベルの試験であった。
合否の分かれ目はここだ!
2025年度の〔Ⅰ〕~〔Ⅲ〕は、詳細な知識が必要となる問題は少なかった。基本的な知識で解答できる問題を取りこぼすことなく正解することができたか、一部のややひねった問い方をする問題でも史料・設問・リード文などから関連知識を想起して解答を導き出せたかどうかが、高得点を確保するための分かれ目であった。また、ほぼすべてが記述なので誤字で失点しないよう、正確な漢字で歴史用語を書けるようにしておくことも必須である。空欄補充問題では空欄の前後にも注意してケアレスミスを防ぎたい。
最も差がつくのは〔Ⅳ〕の論述問題である。2025年度は、⑴は平城京の特徴を、⑵は戦後の沖縄の変遷を述べることが求められ、いずれも題意に即して具体的な歴史的事象を取捨選択し、200字という字数に合わせて過不足のない解答を作成することが重要であった。京大型の論述問題の演習を十分に積み、完成度の高い解答を作ることができたかどうかで差がついただろう。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
〔Ⅰ〕
保元の乱(『兵範記』)/レザノフへの江戸幕府の対応(『通航一覧』)/斎藤隆夫の回顧録(『回顧七十年』) [標準]
史料A〜Cともに受験生には未見と思われる史料から出題されたが、内容は特定しやすいものであった。史料中の用語の他、出典・注記・設問文も参考にすれば解答が導ける問題が多かった。
- 問⑴は京都周辺の地理的把握を問う問題。京大受験生なら押さえておきたい。
- 問⑺は史料をよく読み、史料の登場人物や述べられている内容を把握して解答する必要がある。
- 問⑽は鎖国体制下での交易相手を想起すれば答えられる。
- 問⒇は空欄後の「犬養健君」「憲政擁護に生涯を終始した父君」から想起できるだろう。
〔Ⅱ〕
原始・古代~近・現代の雑題(空欄) [やや易]
短文の空欄補充形式の問題。原始から現代まで、政治・社会・外交・文化に関する知識が問われた。基本的な問題が多いため、確実に得点したい。文化や社会・経済なども抜け漏れなく学習し、用語を正確に記述できるようにしておくことが重要である。
〔Ⅲ〕
南北朝期〜室町時代の文化/江戸時代における「公儀」の意味/幕末と昭和初期の貿易 [標準]
3つのテーマを設定した空欄補充問題と単答問題であり、概ね標準的な問題であった。
- Aは文化史からの出題であるが基本事項が中心のため取り組みやすかった。
- Bの空欄オ〜クは、史料を含むリード文全体の趣旨を理解した上で解答を考える必要がある。
- Cでは表・グラフとその説明文という初めての形での出題となったが、幕末の輸出入品の割合は教科書等でも見る資料であり、説明文も踏まえて見ていけば品目の特定などは難しくない。
- ⒀の(あ)(い)は、輸出額変化の背景への理解を問う問題であった。
〔Ⅳ〕
平城京の特徴/第二次世界大戦末期から1970年代初めまでの沖縄 [標準]
(1)
平城京の特徴について、藤原京との差異、東アジアからの影響に触れながら述べる問題である。唐の長安に倣った計画的都市であった点、条坊制による区画などの特徴を軸に、構造・配置や内部の施設などについて説明すればよい。教科書レベルの記述で対応可能であり、要素の抜け漏れなく丁寧に記述できるかどうかがポイントである。
(2)
第二次世界大戦末期から1970年代初めの沖縄返還に至る時期の沖縄について、「人々がどのような政治状況の下に置かれ、どのようにそれに向きあったか」という面から述べることが求められた。沖縄の人々を取り巻く状況として、沖縄戦、戦後のアメリカ軍直接統治から日本独立後のアメリカ施政権下への流れ、米軍の基地利用などの動向を盛り込みつつ、住民による祖国復帰運動の活発化と沖縄返還協定締結による本土復帰について述べればよい。戦後の沖縄史について体系的に学習できていたかどうかで差がついただろう。
攻略のためのアドバイス
京大日本史を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 全時代・全分野にわたる知識
京大日本史では多くの単答記述問題が出題される。毎年幅広い時代・分野が満遍なく出題されるため、全時代・全分野にわたる知識と、それを正確に記述する力が必須である。学習が疎かになりがちな文化史などの出題も見られるので、漏れのないように学習してほしい。
●要求2● 史料の正確な読解
京大日本史では様々な時代の史料が出題されている。未見史料も必出なので、史料中のキーワードや出典・設問文をヒントに史料文を読解する力を身につける必要がある。
●要求3● 設問の要求に沿った論述
例年200字の論述問題が2問出題されている。リード文などヒントのない端的な設問で出題されるので、設問の意図を的確につかむ力と、知識を取捨選択して論理的に解答を組み立てる力が必要である。また、各時代・分野の重要テーマが出題されることもあるため、論述問題で出題されやすいテーマについては、一通り解いておくようにしたい。
対策アドバイス
基礎力の完成
まずは要求①を満たすことをめざそう。京大で出題される細かな知識問題に対応するためにも、教科書の基本事項は早めに身につけておきたい。また、既習分野については論述問題の対策も始めよう。
入試形式に合わせた対策
要求②・③を強化するためには、史料問題・論述問題の演習を繰り返すことが大切である。但し単答問題の多い京大日本史では、知識量の底上げも必要なので、バランスのよい演習をしていきたい。
実戦演習
ここまで演習を積み重ねれば、要求①~③の力は十分身についているはずだ。京大日本史は時間に比して出題数が多いので、実際の入試での時間配分を考えながら演習を行う必要がある。時間を計って解くなどして、より本番に近い答案作成を行おう。
Z会でできる京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!